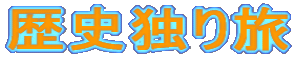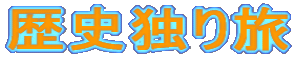
ニセモノの時代
英領時代の香港の繁華街のあちこちに、日本人観光客と見ると、「ニセモノ時計、ニセモノ時計」とたどたどしい日本語で話しかけてくる怪しげな商人たちの一団を大勢見かけたものだった。彼らの露店に並べられている商品は、ヨーロッパの一流メーカー製の腕時計のイミテーション、それを日本円で約1000円くらいで売っている。1000円くらいなら旅の記念に騙されてやるのもいいし、親しい間柄ならちょっとした土産にもなる。ただし日本へ買って帰った後で本物と偽ってン万円で売ったりすると犯罪になるが、最近の日本ならそれほどの目利きでなくてもニセモノとバレる程度のチャチな造りではあった。
こういうニセモノを「ニセモノ、ニセモノ」と連呼して安価で売っているようなことなら面白い話のネタにもなるが、最近の日本は笑うに笑えないニセモノばかりで、とんでもないニセモノの時代になったものである。
ニセモノの耐震強度計算書を作ってマンションやホテルの鉄筋使用量を減らして利潤を追及した事件は日本中を震撼させた。この件では違反発覚後も欠陥マンションを急いで売り抜けようとした悪質な業者だとか、これ以上事件を追及すると景気が悪くなるから止めておけなどと公言したアホウな政治家だとかが次々にマスコミを賑わわせて、日本そのものが骨抜きマンション同然のニセモノだらけの国になっていることを、改めて国民は認識させられた。
要するに金になりさえすれば良い、違法であってもバレさえしなければ金が動いて景気が保てる、それで政治家も経営者も万々歳、よくもまあ、こういうクズばっかりの国になったもんだ。
リコール隠しで問題になった自動車メーカーの子会社がトラックの積載量をごまかして不正に車検を通していたことも明るみに出た。法令に違反して無届けで改築を行なったホテルチェーンも露見した。今のところ国交省関連の不祥事が多いが、やがて農水省、厚労省、文科省などあらゆる省庁に飛び火して、日本中の土台が腐れきっている現実に国民は直面させられることになる。
私がこう断言する根拠は、小泉改革vs官僚勢力の軋轢が間もなく臨界点に達することである。永田町と霞が関のせめぎ合いは、ユーラシアプレートと太平洋プレートのように、地殻の奥深くで戦後日本の政界を支えてきたが、時々地殻にエネルギーが溜まると政界に激震が走った。その好例が平成元年の宇野宗佑首相の退陣である。
宇野首相の退陣というと、ほとんどの国民は女性スキャンダルが命取りになったスケベオヤジのイメージしかないであろうが、それは表向きの話。宇野首相は後の小泉首相と同じく、政治改革に不退転の決意を示したが、政治改革・構造改革と言えば霞が関の官僚勢力がなかなかウンと言うはずがない。私は宇野首相は女性スキャンダルで官僚から刺されたと思っている。そもそも宇野首相を刺したのは素人女性ではなく、男女の道のプロであった。彼女は霞が関官僚の手先の女刺客だったとしか考えられない。(後の小泉首相が宇野首相の仇を討つために女刺客を使ったのかどうかは定かでない。)
今回もまた霞が関官僚としては構造改革を叫ぶ小泉首相を狙い撃ちしたかっただろうが、おそらく小泉氏は宇野首相のようなスキを見せなかったのであろう。盟友の山崎氏のスキャンダル写真がすっぱ抜かれたりはしたが、その程度では小泉首相は倒せない。
つい最近まで官僚陣営が小泉改革に対して打つ手は無かった。せいぜいお年玉年賀ハガキの切手シートの当選番号を平成18年から2つに減らしたことくらいか。(それまでは3つあったが、これは郵政民営化を圧倒的に支持した日本国民へのイヤガラセではなかろうか。)
それはともかく、ここへ来て官僚側が勢いづいていることだけは確かだ。民営化したら欠陥マンションの偽造を見抜けなかった、という事実は国民受けする絶好の攻撃材料である。もっとも彼らは一部の官の検査機関も見抜けなかったということには知らん顔だ。
そこへ持ってきて小泉改革に乗った時代の寵児 ホリエモン(堀江貴文氏)が逮捕された。規制緩和に乗じて株券の取得や転売を繰り返して、ライブドアを額面だけは異様に大きな会社に成長させていったということだが、私は株式経済のことはよく判らない。要するにライブドア社は実質的価値に乏しい“ニセモノ”だったということだろう。総選挙で小泉サイドの応援を得て出馬したホリエモンが速やかに逮捕されたのも、霞が関陣営の差し金であった可能性が高い。
「我々官僚=“お上”がきちんと監督していないとこういうニセモノが出回ることになりますよ」という霞が関側のデモンストレーションは今後さらにエスカレートして、国民は日本国の土台があらゆる分野で腐れきっている現実を知らされることになろう。しかし最近の防衛施設庁の官製談合事件を見れば判るとおり、ニセモノを摘発する立場であるはずの官僚機構もまたニセモノの正義の味方だから困るのである。
欲の皮のつっぱった官僚と欲の皮のつっぱった業者や経営者、こういうクズとクズが寄り合えばロクなことはない。構造改革、政治改革をやられればこういう汚職の温床が無くなるから多くの官僚は抵抗する。要するにクズが権益を奪われないようにクズを摘発するという、いわばニセモノの浅ましい勧善懲悪ごっこが横行しはじめたのが最近の日本であるという認識を私は持っている。
人間は欲のかたまりであるという事実に目を向けずに構造改革や政治改革を叫び、規制緩和や民営化を断行すれば、人間の欲望は際限なく広がって国家の土台を食い潰す。後に残るのは改革断行を気取った政治家の名誉欲と権力欲ばかりである。
ところでニセモノの横行は政治や経済の世界にとどまらず、科学技術の世界にも広がっているという印象をお持ちの方は多いだろう。論文データの捏造が横行していることは事実であり、学者というものは発表した論文の内容と数でしか評価されないものだから、功を焦った学者がつい勇み足ということもあり得ないことではない。論文を出せなければ然るべき地位(ポスト)にも就けず、研究費も貰えないことになるので、これを単なる学者の功名心や名誉欲とばかり片付けることはできないだろう。
ここで私は論文データ捏造事件として報道されたもののうち、少なくとも2つに関しては釈然としないものを感じている。一つはベル研究所のヘンドリック・シェーン博士による超伝導実験のデータ捏造、もう一つはソウル大学の黄教授によるES(胚性幹)細胞のデータ捏造で、前者はエネルギー問題の解決のため、後者は再生医療応用のため、いずれも特許となれば産業界に莫大な利益をもたらす研究である。
この分野の研究者であれば、自分の出した論文はすぐに注目されて世界中で追試が始まることくらい自覚しているはず、目先の功名心だけでチャチな小細工をしてもたちまちボロが出て、自分自身の科学者生命を縮めることになることを理解していなかったはずはない。
先ほどの日本の政財界のことでも書いたが、ニセモノ=悪、ニセモノの摘発=善、という単純な図式で考えていると、思わぬ間違いを犯すことになりかねない。そもそもこういう勧善懲悪劇自体がニセモノなのだから…。
超伝導やES細胞の研究の特許には全世界の産業界の莫大な富が動くことを考えれば、“事件”の陰に科学者としての功績の評価を越えた巨大な思惑が働いていたとしても不思議ではあるまい。
産業界の莫大な富と言ったが、研究成果が公になれば、新しい分野に莫大な投資が行なわれて利潤を生むということだけではない。従来の分野の需要が無くなって莫大な投資が撤退することでもあるのだ。確たる証拠がないのに憶測だけで物事をこれ以上論じるのは止めておくが、表向き報道された事実を鵜呑みにするだけでなく、その裏側にどういう真実の存在する可能性があるのか、それを1人1人が自分の頭で考える習慣をつけておかないと、いつ自分がニセモノの餌食にされるか判ったものではない。
補遺
論文の捏造に関して、一般の人はやっぱりあれは研究者が悪いんだろうと思ってしまうだろうから、この世界がいかにエゲツナイものであるかを追加しておく。
研究者や研究グループが、未だ誰もやったことのない研究、未だ誰も見つけていない発見を行なう、それを世界の学会のトップレベルのレフェリーが公正に判定して、本当に素晴らしいものであれば専門雑誌に掲載して世界中に紹介する。まあ、そういうフェアなメカニズムが機能しているのがサイエンスの世界だと、普通の人は思っているだろう。
ところが産業界の利益に直結しない、研究者の名誉だけしか関わらないような研究においても、信じられないようなアンフェアが罷り通っているのが“学会”という世界である。
私のある後輩たちが外国の学会誌に研究成果を投稿した。世界でも最初の知見だったという。ところがその雑誌のレフェリーから、これではまだ不足だからコレコレの内容を追加しなさいという指示が返ってきた。そこで指示どおりに修正を行なっていたら、その間にレフェリーの属する外国のグループがまったく同じ内容の論文を投稿して採用されてしまった。要するにレフェリーの職権を濫用されて論文の内容を盗まれてしまったのである。
外国の事例だけだと思ってはいけない。私が所属するような取るに足りない国内の某学会においても、私のグループが珍しい教訓的な症例だと思って学会誌に投稿したら、こんなものは珍しくもないというレフェリーの返事が返ってきたので再投稿を見送っていたところ、何と数ヶ月後、そのレフェリーと思われる人物が属する別のグループからまったく同じ内容の症例が学会誌に掲載されていたことがあった。要するにそのレフェリーは私たちのグループに先を越されそうになったので、言い掛かりをつけて私たちの報告をボツにしておいて、自分たちの症例報告論文を優先したのである。
“学会”とはそういう世界である。まして産業界の特許がかかってくるような研究には、どんなエゲツナイ手段が用いられても私はちっとも不思議だとは思わない。例えば最先端を行く研究グループに手先を弟子入りさせておいて、ワザと捏造データを投稿させるとか…。また例えば日本の衛星打ち上げロケットが立て続けに失敗したことがあったが、私には単純な技術ミスだけとは思えない。あんまりこんな事ばっかり言っていると「ゴルゴ13」の読み過ぎとか言われるので止めておく。
時間旅行
最近(2006年1月31日と2月7日)、日本テレビで「戦国自衛隊」が初めてテレビドラマ化された。自衛隊が戦国時代にタイムスリップして活躍するという物語で、原作は半村良さんのSF小説。「歴史は俺たちに何をさせようとしているのか!」というキャッチフレーズで1979年と2005年に2度にわたって映画化されているが、テレビドラマ化は今回が初めてである。
もっとも過去2回の映画化と、今回のテレビドラマ化は、すべて舞台となる年代が異なっていて、最初の映画化は原作どおり1582年頃、2度目の映画化は題名にも副題が付いているとおり1543年頃、そして今回のテレビドラマ化は1600年の関が原合戦の前後であった。だがこのシリーズのいずれにも共通するのが、近代装備の自衛隊が戦国時代にまぎれ込んで騎馬武者や足軽たちの間で荒唐無稽な大活躍をするという、まさにこれぞSFという醍醐味を味わわせてくれる映像の面白さである。
今回のテレビドラマも、演習中の陸上自衛隊が戦車やヘリコプターもろとも関が原合戦前夜にタイムスリップ、徳川家康や石田三成、小早川秀秋らと虚々実々のドラマを繰り広げながら、クライマックスの関が原へともつれ込んでいく設定であった。近代装備の自衛隊vs騎馬・足軽軍団の映像の面白さはテレビドラマとは思えぬほどの圧巻であったが、ストーリーはと言うと、これではちょっと主人公が可哀そうという内容だったので少し補足させていただくついでに、タイムトラベルやタイムスリップについて真面目に論じてみたいと思う。
ところで日本テレビの「戦国自衛隊」のドラマで誰が可哀そうかというと、渡部篤郎さん扮する島村ニ尉(中尉)。元の時代に戻る可能性が無いならばと、家康を倒して歴史を変え、自分がこの戦国時代に生きた証しを残そうと決意する。そして彼に従う隊員たちと共に関が原合戦に介入するのだが、その戦い方が腑に落ちない。
せっかく戦車やヘリコプターなど近代兵器を擁し、後世の歴史書などから東軍の陣容も正確に把握していながら、合戦が始まると徒らに敵の足軽・雑兵など前衛部隊との交戦に終始して燃料・弾薬を浪費し、弾薬補給に戻ったところを逆に東軍の「くノ一(女忍)」の手に掛かって撃破されてしまう。“未来兵器”を保有する職業軍人が、歴史を覆すという強い意思と野望を持って参戦したのであれば、ヘリコプターで足軽・雑兵などの頭上を飛び越えて、一気に家康の本陣に空襲を決行、さらに戦場への途上にあった秀忠の部隊を戦車で待ち伏せして撃滅し、さっさと家康・秀忠を討ち取ってしまうのが定石ではなかろうか。
そうすれば赤子の手をひねるように日本の歴史は変えられたものを、足軽・雑兵の無益な殺戮に没頭している間に戦機を逸し、結局は徳川方に捕らえられて、石田三成の代わりに処刑されてしまう。こんな間抜けなキャラクターにされた主人公(島村ニ尉)が可哀そうだというのである。
そもそも関が原の戦いというのは、純粋に軍事的観点から見れば、自衛隊が参戦しなくても西軍が圧倒的に有利なはずだったと言われている。太平洋戦争前、ドイツ陸軍の駐在武官が関が原の古戦場を見学し、東西両軍の布陣を見た時、これは当然西軍の勝ちだろうと自信を持って述べたという。それだけ東軍・家康の事前工作が巧妙だったということだが、そういうことまで知ったうえで参戦できる“未来人”の特権を行使させなかったのは、ドラマを気楽に見ている身としては不満が残った。
さてテレビドラマの話はそのくらいにして、ではこの時に自衛隊が家康を殺していたらどうなったのか。空想科学小説(SF)の世界では、これをタイム・パラドックスといって、いろいろな作家がいろいろな解決を試みているが、誰一人として矛盾のない作品を残した人はいないのではなかろうか。(別に解決しなくてはいけない問題ではないが、SFファンにとっては実に心の弾む問題であって、推理小説ファンが犯罪トリックを解き明かすのと同じくらい楽しいのである。)
SFファンでない人のために簡単に説明するとすれば、最も単純なタイム・パラドックスとは例えばこういうことである。
『もしタイムマシン(時間航行機)で過去に行って、まだ子供だった自分自身を殺してしまったらどうなるか?』
これを“殺人”と呼ぶか“自殺”と呼ぶかはともかく、子供だった自分を殺してしまえば成長して大人になることはなく、したがってタイムマシンで過去に行って子供だった自分を殺すことは出来ない。そうすると子供だった自分は大人になって、将来タイムマシンに乗って子供だった自分を殺しに来る。そうすると自分は成長して大人にならず…、と大変ややこしい問題になる、これがタイム・パラドックスの原型である。
タイム・パラドックスを映画化、ドラマ化するのは、おそらく制作者にとって至難のワザだろう。タイムマシンの元祖は、1895年ウェルズ(H・G・Wells)原作の「タイム・マシン(The
Time Machine)」に登場する機械であり、この原作は2回ほど映画化されているが、こちらは未来へ飛んで行くのでパラドックスは起こらなかった。
ただしウェルズの原作が描いた未来は、資本家と労働者が生物学的に二極分化してしまい(ダーウィンの進化論の影響があったに違いない)、資本家の末裔は地上で華奢な肉体を持って文明を享受しているが、一方の労働者の末裔は地下の世界で生産を行なう別種の生物に“進化”している世界なのである。だから現代の“資本家”が制作した「タイム・マシン」の映画には、原作にあった社会風刺はまったく失われており、地下に潜った労働者階級の末裔たちは一方的な怪物、悪役として描かれているに過ぎない。(このことは次項でも述べる)
タイム・パラドックスが問題となるような映画、つまり主人公が過去に遡る話の映画で最も知られているのは、「Back
to the Future」のシリーズだろう。過去に戻って両親を結婚させなければ現在の自分が存在し得なくなるというパラドックスに挑んだ第一作に始まり、未来のプロ・スポーツの勝敗記録がすべて載っているデータブック(悪用すれば億万長者になれる)の争奪戦など、過去と未来を行き来する息詰まるようなストーリーの展開は文句なく面白い。
この種のストーリー展開は、小説ならばハインライン(R・A・Heinlein)の「夏への扉(The
Door into Summer)」が名作で、ちょっとした推理小説のような読後感があり、興味のある人にはお勧めである。
こういう個人的なタイム・パラドックスなら映画化やドラマ化も何とかなるだろうが、誰もが知っているような歴史的大事件を覆すようなパラドックスが絡んでくるとなると、映画やドラマに限らず、小説で文章にするのも困難ではなかろうか。まともな大作にするのは不可能とも思える。
歴史的大事件が絡むタイム・パラドックスの映画で「ファイナル・カウントダウン(The
Final Countdown)」というのがあった。アメリカ海軍の原子力空母ニミッツが1941年12月7日にタイム・スリップする。つまり真珠湾攻撃の前日に遡ってしまう。
タイムマシンで時間旅行しようという意思のもとに過去や未来へ行くことをタイム・トラベルというのに対して、そういう意思もなく突然落とし穴に落ちたように過去や未来へ行ってしまうことを、SFファンはタイム・スリップと呼んでいる。太平洋戦争前夜に来てしまった原子力空母も、戦国時代に来てしまった自衛隊も、タイム・スリップというわけだ。
空母の上では歴史を変えても良いのかという議論(まさにタイム・パラドックスの議論)が繰り返されるが、最後にはやはり「我々は二度も負けるわけにはいかない」という強硬論に決し、原子力空母の甲板を蹴って最新鋭のジェット戦闘機やジェット攻撃機が日本海軍の南雲機動部隊を攻撃するために発進していく。ところが、さあ、歴史が変わったらどうなるのか、というSFファンの期待も空しく、映画では元の時代へ帰れそうだということになって、攻撃隊は直ちに呼び戻される。歴史は何も変わらなかった!零戦とジェット戦闘機の小競り合いくらいはあったが、原子力空母が太平洋戦争に歴史的に介入することはなかったという結論で、タイム・スリップものとしては駄作に近い。
そこへいくと、一流SF作家の半村良さんの戦国自衛隊の原作は大したものである。歴史の流れに狂いが生じて織田信長が生まれないことになってしまった、このままでは甲斐の武田の世になる、このミスを修正するために“歴史”は20世紀の自衛隊の一部隊を戦国時代に送り込み、武田騎馬隊を撃滅させた、これで戦国時代から江戸時代、明治時代を経て昭和への流れは回復したということになっている。ただし映画化した時には、このSF的解釈がずいぶん薄まってしまっていたのは仕方ないことか。
今回の関が原の戦国自衛隊もタイム・スリップものとしてはちょっと物足りない。もっともこのシリーズは戦国騎馬武者が戦車やヘリコプターと共に進軍する光景が絵になるのだから、それだけで良いとも言えるが、やはりSFファンとしてはドラマの中できちんと家康を討ち取って欲しかった。そうしたら後の日本の歴史はどうなったか。
豊臣の大坂幕府が出来ただろう。
しかし200年以上も続いたかどうか。
鎖国をせずに西欧との交易開始は早まったかも知れない。
キリシタンへの警戒は豊臣にも強かっただろう。
日本人に関西の実利的考え方がもっと身についたかも…。
等、等、考えていくと、やはり歴史的事件が絡むタイム・パラドックスは一本の映画やドラマで描ききれる単純な題材ではなさそうだ。
家康を殺した自衛隊員が現代に帰って来たら、日本の首都は大阪になっていて、街角では阪神ジャイアンツvs読売タイガースのフットボールの試合中継に人々が熱狂していた…
ウェルズのタイム・マシン
タイム・マシンのアイディアが初めて物語になったのは、イギリスのウェルズ(H.G.Wells、1866-1946)の処女作「The
Time Machine」であることはすでに書いた。ウェルズはタイム・マシンの他にも宇宙戦争とか生体改造だとか、空想科学小説の多くのアイディアを開発し、SF小説の創始者とも言われている。我々の学生時代は、大体どこの大学や高校にも、女子校でない限り、SF研究会というサークルがあったものだ。概して男子の方がSFのような夢物語に夢中になる傾向がある。(つまらない余談だが、ある大学のSF研究会の学生がサークル勧誘で、新入女子大生に「SF研究会に入りませんか」と声を掛けたら、「そんな趣味はありません」といきなり平手打ちを食らったという“実話”がある。何を勘違いされたんだか…)
さてウェルズ原作のタイムマシンは1960年頃と2002年の2回、映画化されていることもすでに書いたが、もう少し詳しく述べておこう。
映画の基本的な筋立ては2回とも共通していて、80万年後の未来へ行った主人公の科学者が美女を守り、襲いかかってくる恐ろしい化け物と戦うという、いかにもアメリカ人が好みそうなヒーロー・アクションものに仕立て上がっていた。だから映画「タイム・マシン」を観た多くの人が、ウェルズの原作もそうなのだろうと誤解しているといけないので、本当にウェルズが書きたかったことをかいつまんでお話ししておく。
80万年後の世界で主人公が見たものは、エロイ(eloi)とモオロック(morlock)という2種類の種族に分化した人類の姿だった。映画に出てきた美女がエロイ、その美女を襲う化け物がモオロックだ。
エロイというのはかつての富める資産階級の末裔で、長年にわたり労働者階級を搾取することによって、地上の世界に君臨しているが、体力を使うこともせず、あらゆる厄介事が取り除かれた楽園に暮らしてきたため、肉体は華奢で脆弱になり、知能も退化している。
一方、何万世代にもわたって資産階級のための生産に奉仕してきた労働者階級は、機械などを取り扱っている関係でエロイよりは多少知能が保たれているが、地下空間の工場施設に適応してきたため、眼の構造などが変化して明るい場所では活動できない生物に変貌してしまっている。
人類が元々の社会的階層に基づいてエロイとモオロックの2つの種族へ分化する、その発想にはダーウィンの進化論の他に、マルクスの「資本論」の影響も明らかに混じっているようだ。
2つの種族へと分化した人類だが、ある時期に訪れた食糧危機の際に、モオロック族は地上のエロイ族を食用にすることを思いつく。多少は機械操作に慣れたモオロック族にとって、地上でのうのうと遊び呆けて知能の退化したエロイ族を捕らえて食うことなど簡単だった。アメリカ人向けの娯楽映画の主人公がやってきたのは、まさにこういう未来世界だった。
所詮は人間の文明の将来などは悲観的であるというウェルズの風刺は、アメリカでの2度にわたる映画化の過程でいずれも無視された。カッコイイ男が未来世界の美女を守ってヒーローになる単純な冒険譚の原作者と言われては、さぞやウェルズも迷惑なことであろう。
人類の未来は悲観的である。いわゆる文明の成果など、いくら蓄積したところで、時がくれば一挙に崩壊して、却って我々の悩みの種となりかねない。
こういう主張は21世紀初頭の現在でこそ、誰もが薄々感じており、誰かがこういう事を言ってもそれほど違和感を覚えないが、ウェルズは1895年にそう書いたのである。当時のイギリスは、世界最初の産業革命に引き続いて、アジアやアフリカに広大な植民地を持ち、機械文明の最先端を独走している優等生国家だった。その国で文明の終末論をブチ上げたわけである。
やはりアメリカの哲学は21世紀になっても、文明を洞察するというような分野において、まだ19世紀のイギリスの哲学に追いついていないような気がする。日本もアメリカ文化一辺倒の道を歩んでいては、物理的な“国力”がない分、ウェルズの描いたエロイ族のような脆弱な国に堕してしまうのではなかろうか。
我が国でも、明治時代にイギリスに留学した夏目漱石がウェルズの影響も受けていたかも知れないが、文明の限界、国家の限界などについて、ごく自然に洞察を加えている。名作「三四郎」の中の、熊本から上京する三四郎が汽車の中で初めて廣田先生に出会った場面に、次のような会話がある。
(三四郎は)「しかしこれからは日本もだんだん発展するでしょう」と弁護した。すると、かの男はすましたもので、「亡びるね」と言った。―熊本でこんなことを口に出せば、すぐ殴られる。悪くすると国賊取扱にされる。三四郎は頭の中の何処の隅にもこういう思想を入れる余裕はないような空気の裡で成長した。(中略)すると男が、こう言った。
「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より…」でちょっと切ったが、三四郎の顔を見ると耳を傾けている。
「日本より頭の中の方が広いでしょう」と言った。「囚われちゃ駄目だ。いくら日本の為を思ったって贔屓の引き倒しになるばかりだ。」
私は夏目漱石の「三四郎」のこの部分を読むと、明治日本の知的勃興を感じる。それは明らかにヨーロッパからもたらされた考え方だ。国のため、国民のため、発展のためと、軍事あるいは経済一本に逼塞して突進した昭和日本には、この知的態度はほとんど見られなかった。
ウェルズはSFの他にも未来戦ものの小説も書いている。「陸の甲鉄艦(The Land
Iron-clads)」というのを読んだことがあるが、機関推進と特殊な車輪で陸上の複雑な地形を安定して走行することの出来る兵器のことである。サイズは軍艦並みということであったが、第一次世界大戦を待たずに戦車の出現を予言したと言ってよい。
ウェルズはこのような戦闘機械の出現で、戦闘のやり方や、兵士に求められる素質が従来と著しく異なってくるはずだと書いているが、御存知のように第二次世界大戦までの昭和日本では、機械化部隊に対して古来の大和魂のみで戦ったのである。ウェルズの作品に見られるような文明批判、文明風刺の精神を失って硬直化した国家の悲劇であった。
もしもタイム・マシンができたら
タイム・トラベルだとか、タイム・スリップとか言ったって、どうせSF小説の中の話だろう、真剣に考えたって何の意味も無い、時間の無駄だ、という人は別に考えなくたってよろしい。しかし「三四郎」に登場する廣田先生のように、頭の中を広げておきたいと思うならば、たまにはこういう荒唐無稽な事を思案するのも良い訓練になる。
それに時間を航行して別の時代へ行ったり来たり、というのも、まったくのデタラメと限ったわけではなかろう。時間というものは、
行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず
という方丈記の冒頭の文章のイメージのように、一貫して過去から未来へ流れる定常流のように、日常生活の中で認識されはするが、実はそれは間違っているのかも知れない。
「浦島太郎」の昔話の内容は子供心にも不思議ではなかったか。助けた亀に連れられてやって来た龍宮城で、乙姫様に歓迎されて、楽しく遊び暮らした数ヶ月。里心がついて元の世界に帰して貰ってみれば、元の世界では何十年もの歳月が過ぎ去っていた。龍宮城には元の世界とは別の時間が流れていたのだ。
アインシュタインは相対性理論を発表して、時間の流れは絶対のものではないと喝破したが(光速近くで飛来する宇宙線の粒子では時間の遅れが実際に計測されているらしい)、相対性理論を知らなかった大昔の人が「浦島太郎」の物語を考えたというのは面白い。実は時間を越えた旅人を本当に見聞きしたのではないか?(ちなみにアインシュタインの相対性理論が発表された当時、無知な日本人の中には“相対セックス理論”と勘違いして赤面する人がいたというのは実話のようだ。)
まあ、考えてみれば「かぐや姫」も月世界の住人ということだから、昔の人は月が別の天体であることを感じていたのだろう。日本人は意外にSF的発想に長けた民族かも知れない。
私が子供の頃(1960年代)、少年雑誌等に何回か掲載された不思議な話があった。たぶん覚えている人もいるだろう。「30年前の空を飛んだセスナ機」という話である。アメリカのあるパイロットがセスナ機を操縦していると、突然嵐に遭って方向が判らなくなる、すると雲間から旧式な複葉機(二枚羽根の飛行機)が現れてセスナ機と接触した、幸いどちらも飛行に支障はなく、パイロットは無事に地上に戻ることが出来た。その後、そのパイロットは偶然ある格納庫の隅で見覚えのある旧式複葉機を発見、調べてみると30年も前にすでに飛ばなくなって、今は記念品として保存されているだけの機体だったが、その翼の先端が壊れていて彼のセスナ機の塗料がこびり付いていた。その複葉機の航空日誌を取り寄せて読んでみると、1930年代の某月某日、突然雲間より現れた不思議な金属製の単葉機(一枚羽根の飛行機)と空中接触した、との記載があったという。
つまりセスナ機と旧式の複葉機は時間を越えて接触した、どちらかの機体が時間を越えたのだという説明だったが、今これを考えてみると、ネス湖のネッシー同様、どうも胡散臭い話だ。ネス湖の恐竜生存説は冗談好きの人間の手の込んだ悪戯だった。この時間を越えたセスナ機の話もホラの一種だったのだろう。なぜなら、その後この話はどこにも掲載されることはなかったし、それに第一、重要な証拠である複葉機の航空日誌のコピーが公開されたわけでもなく、また複葉機の翼に付いていたセスナ機の塗料について科学的に検証されたという話も聞かないからだ。
だからと言ってタイム・トラベルがまったくの絵空事かというと、そうでもないらしい。ポール・デイヴィス(Paul
Davies)という理論物理学者が、タイム・マシンは理論的に可能であるという本を、一般向けに書いている。日本でも林一氏の訳で草思社から出版されているので(「タイムマシンをつくろう!」How to build a time machine)、お読みになった方もいらっしゃるだろう。
私は理論物理など理解できる能力が欠如しているので、デイヴィス氏は以下のように考えているとだけ書いておく。10兆℃の高温を発生させ、圧縮機で圧縮してワームホールという時空の特異点を作り出し、負のエネルギーを注入して(カシミール効果とか言うらしい)ホールを拡張させ、ホールの両端に恒久的な時間差を作れば、過去へ遡れるということらしい。SFファンから見れば、タイム・マシンというよりは、タイム・トンネルのアイディアである。
つまり膨大なエネルギーを制御できるようになれば、時間を遡ることも可能なわけだが、まあ、我々が生きている間に“未来や過去の見学ツァー”などは実現しないから、せいぜいSF的発想で現世を楽しむのが良かろう。ただし人知を超えた大宇宙の事象の中では何が起こるか判らないから、たまたま膨大なエネルギーが集積した時空の特異点に居合わせたりすると、複葉機と接触したセスナ機だとか、戦国時代へ行った自衛隊だとか、真珠湾攻撃前夜に行った原子力空母のような、摩訶不思議な体験をしないとも限らないが…。
もしも人類がタイム・マシンを開発したら何に利用するのが最善だろうか。“古代歴史ツァー”とか“恐竜ツァー”とか“三国志ツァー”だとかの企画を組んで観光客を募集すれば、タイム・マシン開発費の元も取ったうえで大儲けできるが、不注意・不心得な一般観光客がとんでもない事をしでかす恐れがある。
2006年春に公開された映画「サウンド・オブ・サンダー(A Sound of Thunder)」は、過去へ行った観光客が現代に持ち込んだ少量の物質の為に、本来ならば進化しなかった種が進化を遂げて生態系まで破壊されてしまうという大掛かりな物語らしいが、確か原作では古生代に行った観光客が誤って小さな蝶々を踏み潰してしまい、現代へ帰って来ると政権が変わっていたという程度の内容だったと思う。
いずれにせよ、時間を遡った人間がたとえわずかでも過去を変えると現在に至るまでの歴史も変わってしまうという設定である。
そんなわけで、もしもタイム・マシンが完成しても、一般人の時間渡航は厳しく制限されるべきだと考える人が多い。(別にそんなに真剣に論じなくたって良いんだけれど…)
タイム・マシンの実用的な価値として犯罪捜査が挙げられる。つまりどんな巧妙な犯罪でも過去に戻って現場検証すれば迷宮入りすることはなくなり、治安は完全に保たれるはずだ。
とこう書かれて、ちょっと待って、それはおかしいんじゃない?と思った人はSFのセンスがある。
例えばAさんが朝食後、出勤のため家を出たまま行方不明となり、夕方に自宅から離れた山林で射殺されていたとする。刑事がこの事件の捜査のためにタイム・マシンに乗って、Aさんが朝食を済ませた過去にまで遡り、Aさんが犯罪に巻き込まれる瞬間まで尾行する。すると出勤途上で待ち伏せしていたBとCがAさんを車で拉致して山林に運び、拳銃で射殺した。
一部始終を目撃した刑事はどうするか?現在へ戻ってBとCを殺人罪で逮捕すればそれで良いのか?
1985年6月、純金セールス詐欺事件の責任者である豊田商事の永野会長宅に男が乱入して会長を殺害するという事件が起きた。ところが会長宅周辺に張り込んでいた報道関係者たちが、犯人を取り押さえることもせずにカメラを回していたというので、世論の批判を浴びたことがあった。ご記憶の方も多いだろう。
報道関係者でさえ、事件現場に居合わせながら事件を阻止しなかったという理由で、世の人々の謗りを受けたのである。ましてタイム・マシンで事件現場に遡った刑事が、被害者が殺されるのを指をくわえて傍観していることが許されるだろうか。あるいは過去の現場での犯罪捜査については絶対に過去を変えてはいけないという警察の内規が作られているかも知れないが、刑事を志す人の中には正義感を抑制できぬ人の方が多いだろう。
仮に被害者のAさんがBとCに拉致されそうになった時に、刑事が現場に割って入ったらどうなるか。そこまでしなくとも、今日は危ないから自宅に居なさいとAさんに事前に警告したらどうなるか。まさにタイム・パラドックスが起こるのである。つまり刑事の助言や助力でAさんは被害に遭わずに済む、すなわち殺人事件は起こらなかった、すると刑事が過去に戻って捜査することにはならず、Aさんは誰からも助言や助力を貰えないのでBとCに殺されてしまう、それで刑事が過去へ事件捜査にやってくる…と、まるで絵に描いたようなパラドックスである。
実は先にタイム・マシンの作り方を書いたポール・デイヴィス氏は、この種のタイム・パラドックスについても触れている。それによれば多くの物理学者は次のように考えているらしい。素粒子の世界では量子の不確定性の原理が支配しており、ある粒子が次の瞬間にどういう状態にあるかを予測できない。すなわち今の瞬間にこういう状態だから、次の瞬間にはこういう状態だ、という原因と結果が確定しないのである。こうした因果律の不確定性は、そのまま我々が認識できる世界にも適用されると考えている物理学者が多いという。
どういうことかと言うと、先ほどのAさんが殺された世界と、Aさんが殺害を免れた世界とが同時に存在するのである。これを多元宇宙論といって、物理学者だけでなくSFマニアにもお馴染みの考え方であるが、あまり考えすぎると普通の人には頭痛のタネになるだけだから、クドクド書かない。
ただ宇宙を構成するすべての素粒子だけでなく、すべての物体や事象について、あらゆる瞬間にあらゆる可能性があるわけだから、同時に存在しうる宇宙の数は無限大の無限大乗とでも言うべきだろうか。
こうしてタイム・マシンによる犯罪捜査もややこしい問題が付随するとなれば、最後に挙げられる使い道は学術調査ということになる。もし本当にタイム・マシンが完成したとすれば、歴史学や考古学、古生物学などの研究にとっては革命的だ。
先日、冥王星探査機が打ち上げられたが、あの探査機が目的地点に到達するのは何年も先のことである。しかし過去を探査する場合、有人でも無人でもよいが、タイム・マシンを目的の時代に向けて発射した後、帰還する時期を1秒後に設定しておけば、“現在”で待っている人間にとっては即座に成果を見ることが出来るわけだ。
しかし“今日”探査機を送り出しておいて、“昨日”回収するということになると、また例のパラドックスが起こる可能性がある。どんなパラドックスかというと、これはちょっとマニアックである。例えば西暦20xx年2月26日に“15世紀探査機”を発射して、2月25日(前日)に回収ということになったとする。ということは、探査機を発射する時には、すでに探査機の成果がもたらされているのである。もう15世紀の探査結果が入手された段階で、改めて“15世紀探査機”を発射する必要がどこにあるだろうか。そこで急遽、この探査機の目標を16世紀に変更して発射したらどうなるか?SFファンはこんな事ばかり考えているのである。
さて、もし“過去”の探査が可能になったとしたら、私としては個人的にこんな時代を真っ先に学術調査して貰いたいと思う。
①最初の人類が出現した時代
②邪馬台国はどこか
③神風特攻隊成立の経緯
意外に平凡か(苦笑)。少しツウなところで5世紀の日本も良いかも。本当は日本の歴史を全部ダイジェストで見たいものですが…。
常在戦場は昔のこと?
最近、自衛隊や警察などからとんでもない極秘情報がインターネット上に漏洩するという、不祥事とも過失とも言いようのない事態が発生している。自衛隊からは国防上の機密、警察からは捜査情報など、それぞれ信じられないような情報がネットに流れたらしい。
Winny(ウィニー)というファイル交換ソフトをインストールしてある個人用パソコンに、職場(自衛隊や警察)のデータやファイルを保存していたところ、コンピューター・ウイルスの感染を受けて、極秘扱いのファイルまでがインターネット上に流出したのである。
ウィニーというのは、あるファイルを自分のパソコン上で“公開”の扱いにしておけば、ウィニー使用者同士が皆そのファイルを共有できるようにしたソフトで、著作権侵害問題まで起こしているソフトである。そしてその“公開”されていたファイルから感染したウイルスの攻撃を受けたために、本来自分のパソコン上で“公開”していなかったファイルまでが“公開”の扱いにされて、ネット上に流出したのだそうだ。
つまりウィニー使用者同士、お互いの家の応接間を訪問して見聞を広め合いましょうという親睦だけのつもりだったのが、いつの間にか風呂場もトイレも丸見えにされてしまったようなものだ。
驚いたことに、職場のマル秘情報を保存した自宅の私用パソコンには、ウイルス感染対策は何も施されていなかったという。
こういうインターネットの初心者に近い未熟者が、国家機密まで含む職場のデータを自宅のパソコンに保存していた迂闊さや業務体制の杜撰さについては、さまざまなメディアで指摘されているので、今さら私が書くほどのことでもなかろう。
重要情報が漏洩していたために大事に至ってしまった太平洋戦争中のミッドウェイ海戦や山本五十六連合艦隊司令長官の前線視察などの事例も頭に浮かぶが、今回の自衛隊や警察のようなことが諸外国でも起きているのかどうか知らないので、一概に日本人の情報管理の甘さと言いきる自信はない。
しかし今回発覚した事例で特に注目されているのが自衛隊とか警察とか、いわゆる昔の武士階級の不覚であることが気になる。主君が大切にしていたお家の目録を自宅に持ち帰って保管していたら泥棒に盗まれてしまった、では腹を切ってお詫びしても済まされることではなかったであろう。
そもそもインターネットとかウィニーとか関係なかったとしても、職場の大切な情報を持ち帰って身辺に保管するという行為自体、いかに危険であるか、私も含めてほとんどの日本人があまりにも無頓着であることを深く自戒する次第である。ウィニーを通じてネット上に流出したデータは自衛隊や警察関係にとどまらず、民間企業や医療・金融・保険関係などの情報も含まれる。これではいくら「個人情報保護法」などと言って大騒ぎしても、ザルに水を入れておくようなもので、プライバシーなど世間に筒抜けである。
まず職場の情報を自分の身辺に置いておく場合、もし自分が明日突然死んだらこの情報はどうなってしまうのか、考えなければいけない。私たち医師の例でお話しすれば、医学部や大病院の医師が研究用のデータとしてカルテや検査報告書などをコピーして手元にファイルしている場合がほとんどである。必ずしもパソコンに保管しているだけではなく、コピーした紙をファイルに綴じておく行為も含まれる。
明日と言わず、今日の帰り道にでも、もし自分が不慮の事故で死んだら、これらのデータはどうなるのか、恥ずかしいことであるが、私も今までそこまでは深刻に考えたことはなかった。患者さんのデータをパソコンには保管していないが、職場の書庫には検査報告書のコピーの束はある。さすがに自宅にはいっさい持ち帰っていないので、私が個人的に保管している患者さんの情報は、心ある同僚が私の死後に適切に処分してくれるとは思うが…。
他人のプライバシーに関する情報を取り扱う人は皆、もし自分が突然明日死んだらこの情報はどうなるか、よく考えて頂きたい。死んだ後のことなどどうでもいいや、と思うような人には大事な情報を取り扱う資格はない。
思えば自分が死ぬことを考えなくてもよい時代であることが、こういう情報漏洩事件にも関係しているような気がする。昔の武士は「常在戦場」と言って、常に生命のやりとりをする戦場にある時の緊張感を保ち続けたが、そういう武士に相当する自衛官や警察官にさえ、明日は戦場の露と消えるかも知れないという覚悟がなくなったのは良い事なのか、それとも悪い事なのか…。
昔、合戦に赴く武士に妻が朝食の握り飯を差し出した。ところが武士がそれを謝絶して言うことには、「もし合戦で万一敵に首を討たれた時に腹の中から飯粒が出て来ては物笑いのタネになる」。そして軽く粥のみをすすって出陣したという。
昔の武士は名を惜しんだが、現在それなりの機密や個人情報を扱う職種の人間が惜しまねばならないのは、情報に対する責任観念である。
良き同盟国日本?
明治維新以来、日本の進路に重要な影響を及ぼした国際的な同盟を3つ挙げるとすれば、①日英同盟、②日独伊三国同盟、③日米安全保障条約、ということになろうか。③の日米安全保障条約は名称の上では“同盟”という語句が入っていないが、最近、特に政権与党のタカ派寄りの立場の人たちからは、いわゆる“軍事同盟”に近いニュアンスで語られることも多くなっており、戦後日本にとって前2者と同等以上の意味を持つ国際関係ということで、一応ここに挙げてみた。
現代世界ではアメリカ、ロシア、中国を指して三大国という呼び方をするが、この3国すべてと戦争の手合わせをした国は世界広しといえども日本だけである。そしてそれらの戦争に際して重要な意味を持っていたのが、日英同盟と日独伊三国同盟であり、もし今後戦争が起こるとすればその時に意味を持ってくるのが日米安全保障条約であることに異論はあるまい。
さて、私はここで上の3つの国際同盟それぞれについて、歴史上の善悪や国際関係論上の妥当性について話題にしたいのではない。それぞれの同盟や条約の中で、日本は良き同盟国であったか、あるいは良き同盟国であるか、について検討してみたい。
良き同盟国か否かは、我が日本が国際舞台でとった行動が相手国にとって利益になったかどうかで判断される。地球上に数ある諸国の中で2つ以上の国家が集まって同盟を結ぶということは、互いに一致している何らかの利害に対して協調して行動を起こすことを約束し、それが互いの恩恵になるということである。
日露戦争における日英同盟は一番話が判りやすい。日英同盟はロシアの南下政策に対抗してアジア大陸における両国の利権を擁護するために1902年に締結され(日暮れに結ぶ日と英)、その2年後の1904年に日露は戦闘状態に入る(一つくれようロシアに拳骨)。
日英同盟では、締結国の一方が交戦状態に入った場合、他の一方は中立を守る、という内容だったが、戦争中日本はイギリスから中立保持以上の恩恵を受けることが出来た。例えばバルチック艦隊の極東回航にしても、艦隊の行く先々でイギリスの妨害工作が行なわれたのである。
しかしこの事をもって、さすがイギリスは紳士の国であるなどと思ってはいけない。イギリスは日英同盟によって、ヨーロッパにおけるロシアの勢力を極東へ分散できれば御の字と考えていただけであって、その意味で日本はイギリスのためにもよく戦ったと言える。つまり良き同盟国であった。
確かに日英同盟は日本にもイギリスにも相互に恩恵をもたらし、国際同盟のお手本のような成功例であったが、イギリスが庶民レベルで考える“紳士”であったと考える必要はない。彼らは極東の黄色人種の新興国が、まさか大国ロシアに勝利するとは本気で考えていたわけではあるまい。黄色いネズミが東の方で暴れてくれれば、ロシアの脅威も半減する、というのが彼らの本音である。その証拠に、同盟国の一方が交戦状態に入った場合、片方は中立を守るとしか明記していないのである。ロシアの南下は困るが、だからと言って直接ロシアと戦争する意思は毛頭なかったというイギリスの本音がミエミエではないか。
案に相違して日本がロシアに勝ってしまったために、その後の大英帝国の極東政策に重大な齟齬が生じて、第二次世界大戦へとつながっていくわけだが、それは別の話。とにかく同盟とはそんなものである。
20世紀初頭の対露政策においては、日本はイギリスの良き同盟国であったが、では20世紀中期のヒトラー率いるナチスドイツにとって、日本は良き同盟国であったか否か。
日独伊三国同盟は、枢軸国による世界秩序建設のためにこの3ヶ国が政治・経済・軍事の各方面で協力する目的で、防共協定を基盤にして1940年に締結された。すでにヨーロッパでは第二次世界大戦の幕が切って落とされており、ナチスドイツの快進撃が全世界の耳目を集めていた時である。日本史の観点からは、日本国内の強硬派が「バスに乗り遅れるな」とばかり、ナチスドイツの尻馬に乗ってしまった側面ばかりが強調されているが、実はドイツの方も同盟締結を望んでおり、日本海軍などの穏健派・三国同盟反対派を中心に進められている国際協調路線に対して、ベルリンが露骨な不快感と苛立ちを表明していた事実もある。ナチスドイツは大日本帝国に何を期待していて、日本は果たしてその期待に応えることができたのかどうか。
ドイツが三国同盟で日本に期待していたものは何か。またヒトラーは日本の真珠湾攻撃をどう捉えたのか。
1941年12月8日(日本時間)、日本海軍の真珠湾奇襲攻撃は全世界に衝撃を与えた。ヨーロッパで始まっていた戦争がついに太平洋にまで飛び火した。文字どおり、第二次世界大戦の始まりである。おそらく平和を願っていた人々にとってはショックだったろうが、少なくとも敵方のイギリスのチャーチルと中国の蒋介石にとっては朗報だったはずだ。これでついにアメリカが連合国側に参戦して、ヨーロッパにもアジアにも援軍を送ってくれることが確実になったからだ。
では同盟者ヒトラーが真珠湾攻撃をどう捉えたか、諸説あるが、まさか日本が対米開戦するとは期待していなかったはずだ。第一次世界大戦では、ドイツが無制限潜水艦戦の開始に伴って、英国客船ルシタニア号を撃沈し、多数のアメリカ人船客の生命を奪ったことからアメリカの参戦を招いて、一挙に戦況が不利に傾いた歴史的教訓を、ヒトラーが忘れていたはずがない。
ヒトラーもソ連に対して防共政策をとるかと思えば協同してポーランドを分割し、そうかと思えば一転して独ソ戦を開始する。日本にとっても到底信頼するに足る定見を持った同盟者とは言えないが、ヒトラーもアメリカだけは局外中立に置いておきたかったのではなかろうか。少なくともチャーチルと蒋介石が真珠湾攻撃の報に喜んだことだけは間違いなく、敵を喜ばすようなことをしでかす国が良き同盟者であったとは到底言えまい。
ヒトラーが日本に望んでいたのは、極東におけるイギリス植民地の奪取、および対ソ戦における東西からの挟み撃ちの2点であって、それは当時の世界地図をゲーム盤に見立ててゲームをすれば、どんな軍事的素人でも思いつく明快な戦略である。真珠湾攻撃はヒトラーから見れば軽挙盲動であったというのが私の見解。軽率な同盟者が相手方の大番長の向こう脛を蹴っ飛ばして喧嘩を売ってしまったので、自分もまた望まぬ余計な敵を作ってしまったと、臍を噛む思いだったに違いないが、あの独裁者も気分次第でいろんな事を言ったのであろう、諸説残っていてどれが本当かは今となっては明らかでない。
日本の政治的、軍事的指導者には、ドイツが日本に何を期待しているかを慎重に検討する思慮もなかったのか。しかも第二次世界大戦参戦後も、アフリカ東岸の連合軍の物資輸送路を攻略して独伊のアフリカ戦線を援護するような作戦を展開するどころか、南方で対米戦闘の泥沼に自らのめり込んでいく愚を犯したと、佐藤晃氏は「太平洋に消えた勝機」(光文社)の中で嘆いている。ドイツの同盟国として当然の軍事的義務を果たしていなかったと…。
まあ、過去のことはおいておくとしても、現在の“日米同盟”(日米安全保障条約)では果たして日本はアメリカの良き同盟者だろうか。
日米安保条約に軍事的側面がある以上、将来的な軍事的衝突を想定していることは間違いない。どの国とどの国の衝突が最も深刻かつ現実的か、誤解を恐れずに言えばアメリカと中国である。アメリカにとって中国とは自由と民主主義に反するライバル、枢軸国、共産圏に次いで打倒すべき仮想敵国であり、中国の人権問題にも深く介入する姿勢を見せている。一方の中国にもそのようなアメリカの大国主義に反発して反米主義も台頭してきているが、何より不幸なことに、アメリカと中国の間には台湾問題が存在しているのである。しかも非常に危険なのは、ひとたび台湾海峡に不測の事態が発生すれば、両国とも互いに台湾に武力を発動して自動的に交戦状態に至る法律的プロセスを持っていることである。
万一、アメリカと中国が交戦状態に入ってしまえば、日本としてはもう手の施しようがない。作戦上の要求から日本国内の基地設備は在日米軍に半強制的に徴用される結果となるが、そうなってしまえば日本もそれを“同盟国”としての当然の義務として受け入れざるを得まい。
問題は交戦状態に至らない前の“同盟国”たる義務を果たしているかどうかである。中国は何千年にも及ぶ戦乱の歴史を持っているので、まさかアメリカの強大な軍事力とまともに衝突するような愚かな挙動に出ることはないであろうし(かつての日本の真珠湾攻撃は本当に愚かである)、アメリカもまたイラク、中東、北朝鮮などに問題を抱えている以上、敢えて中国と軍事的に事を構えることはしたくないと見るのが順当である。
国家間の正面戦争がやりにくくなった現代世界において、同盟の意義は昔とはずいぶん変わってきているが、相手国が同盟を通じて自国に何を期待しているかを把握することが、良き同盟者の条件であろう。日本はアメリカの良き同盟者なのか。
日本の最近の指導者は、現代世界における対中国戦略の要点をアメリカと共有していないのではないかというのが私の危惧である。そのことを最も端的に表わしているのが、日本政府首脳による靖国参拝である。日米陣営の対中戦略の要点は、できるだけ軍事力を行使せずに中国を封じ込めることに尽きる。(私はここでは親米、親中いずれの立場で論じているのでもない。日米安保条約すなわち日米同盟の目的論を一般的に考察しているだけである)
中国を政治的、経済的手段だけで押さえ込んで国際的発言力を弱めることができれば、日米のアジアにおける権益は相対的に増加する。しかし中国の発言力が一方的に増加すれば日米の権益は脅かされて、将来的に軍事力に訴えなければならぬ事態に発展する危険性は増す。
日本の首相が靖国参拝することは、中国にとって日本の国際的発言力を弱める口実に使える材料をわざわざ増やしてやるようなものだが、そればかりでなく、本来日米陣営側につくべき韓国をも離反させてしまう結果になる。こういう“利敵行為”を平然となす愚かな人間を首相に選出して諌められないような国が、アメリカにとって良き同盟者であるはずはない。最近ではワシントンの高官も小泉首相の靖国参拝に不快感を表明しているではないか。
日本人というのは本当に国際同盟の意義を知っているのだろうかと疑問を感じてしまう。「俺の背後にはアメリカがいるんだぞ」とばかりに日米同盟の威力をかさに着て、さんざん中国に日本攻撃の口実を与えて国際的発言力を高めてやる。ナチスドイツの快進撃に目が眩んでアメリカにちょっかいを出した馬鹿さ加減と妙にダブって見える。
私の母子手帳の頃
私は今さら年齢を詐称するまでもなく、昭和26年8月生まれである。戦争が終わってちょうど6年目の夏、私はこの世に生まれた。
平成の現在から考えると、特に戦後しか知らない世代にとっては、昭和20年8月15日以降の日々はすべて「戦後」として一括してしまう傾向があり、自由と民主主義の世の中に変わろうとしていたのと同時に、物資も豊かで生活も安定した時代もまた到来していたかのような錯覚にとらわれやすい。今回、私が生まれた頃の「戦後日本」の物資事情を表わしている資料を見つけたのでご紹介したい。
私の両親も老境に至り、これまで育児の思い出に大切に保管していた母子手帳を私に譲ってくれた。私もかつて小児科医、産科医としてそれこそ延べ何万人もの新生児・乳児や妊産婦さんの「母子健康手帳」に必要事項を記入してきたが、自分の「母子手帳」を実際に見たのは今回が初めてだった。(私の母子手帳)
母子手帳の歴史は、まず昭和17年に「妊産婦手帳」として発足、昭和22年の児童福祉法制定に伴ってこれに児の記録も書き込む「母子手帳」となり、1950年、1953年と改訂を経て、1965年の母子保険法の制定で「母子健康手帳」となった。国家の最初の動機としては健康な兵隊を生むために妊産婦の教育をするというものだったであろうが、やがて時を経て、それは母子の健康な生活を援助する本来の目的に使われるようになり、お蔭で我が国の妊産婦死亡率、周産期死亡率、乳児死亡率を戦後半世紀で激減させることに成功したのである。
昔、周産期医療に携わった私としては、当然自分の“被”妊娠中の記録や新生児・乳児期の体重の推移などを見たいと思うのが当然の好奇心というものであろう。ところが…、
けしからんことに、分娩前後の短期間を除いて医学的記録は皆無!
妊婦検診の記入欄はもともとない。昔はわざわざ医療機関へ行って検診する妊婦さんはいなかったのだろう。親族内に経験豊かな女性たちが何人かいたし、近所には産婆さん(後の助産婦、今は助産師)がいたので、そういう人たちが地域ぐるみで相談に乗っていたと思われる。
「産後の母の健康状態」空白。
「こどもの記事」 空白。
「お誕生までの乳兒の健康状態」 空白。
「学校へ行くまでの幼兒の健康状態」 3歳と4歳時の体重、身長の記載があるのみ。
あとは予防接種法による百日咳予防接種、種痘、ヂフテリア予防接種の記載があるのみ。
何のための母子手帳かと思われるだろうが、当時の「母子手帳」の最も重要な目的は、妊産婦や乳幼児に栄養物資の配給を保証することだったのである。私が生まれる約2ヶ月前に「妊婦砂糖購入券交付済」、また生まれた1ヶ月後に「混合砂糖購入通帳交付済」の検印が押されており、また別のページには必要物資の加配を受けるために出張所長の検印を押す欄があって、ここには几帳面に判子が並んでいる。
要するにどういう時代だったかと言うと、戦後数年たって食糧事情はかなり改善されてきてはいたが、それでもまだ1人の人間は1人分しか食ってはならない状況だったのである。1人の人間が必要以上のカロリーを摂取しようとすれば非難される、そういう社会的状況があった。だから当時の妊婦さんは、「私は1人ではありません、お腹にもう1人いるんです」ということを主張して、食べ物を少し余分に分配して貰うために母子手帳が必要だったのであろう。
ちなみに私が産科医をしていた時は、妊娠中毒症の予防のためにカロリーの摂りすぎには注意しましょうと、妊婦教室で話したものだ。
慢性的に食糧が不足していた時代を、私たちは想像できなくなっている。お腹にいるのが子供だろうが皮下脂肪だろうが、金さえ払えばいくらでも好きな物をたらふく食べられる時代、平成の日本人はそれが永続するものだと考えがちだが、私の世代の人間が一生を送っている短い間にもたらされた束の間の「飽食」なのだ。もっと短い期間で元に戻ってしまわないという保証はない。
母子手帳に見た時代の推移に愕然とする思いだった。
シンドラーズ・リフト
もう10数年前のことだったろうか、「シンドラーズ・リスト(Schindler's list)」というノンフィクション・ノベルが話題になり、1993年にはスピルバーグ監督によって映画化されたこともあった。オスカー・シンドラーというドイツ人実業家が、ナチス・ドイツの要人にコネをつけて強制収容所のユダヤ人を自分の工場へ引き取り、彼らの生命を救ったという物語である。
映画のDVDも出ているらしいし、新潮文庫から出版もされているので、興味のある方はそちらを参照していただくとして、今回の話はそれとはまったく別の話である。
10年以上も前に読んだノンフィクション・ノベルや、同じ頃に観た映画の題名をふと思い出したのは、2006年6月、スイスに本社のあるシンドラー社のエレベーター(米:elevator, 英:lift)が事故を起こし、マンションでエレベーターから降りようとした男子高校生が扉に挟まれて亡くなったという痛ましい事故があったからである。その後の報道によると、単なる偶発的な事故ではなく、これまでに何度も問題を起こしていただけでなく、シンドラー社製のエレベーターは世界各地で大小の事故を起こしていたという。
まさに“シンドラーズ・リフト”であるが、かつて収容所の多数のユダヤ人の生命を救ったとされるシンドラー氏の名前も、とんだところでミソをつけられてしまったものである。
さてこういう事故が起きた以上は、製造者責任、管理者責任は厳しく問われるべきであり、安全な製品を提供する債務を怠った製造者や、安全運行を管理する債務を怠った管理者は、きちんと責任を明らかにして、被害者の賠償と共に将来の安全保障に務めるべきだが、一方でマンションの骨抜きだとか、自動車部品の欠陥だとか、世の中がここまで信用できなくなったこの時代、消費者・利用者の側も自衛の心構えを固めるべきだと言いたい。
製造者や管理者の過失をいくら咎めてみても、一旦被害者になってしまってからでは、賠償金などいくら積まれたって間尺に合わないのである。生命まで失ってしまっては元も子もないし、怪我をしただけだって治癒するまでの期間はまったくの無駄である。
今回のエレベーターで亡くなられた少年の事故の経過を知って、私はあまりに惜しいと思う。自分のことのように口惜しい。この少年を不注意だと言うわけではないが、今後同じような目に会う人が1人でも少なくて済むよう、批判は覚悟で敢えて言わせて頂きたい。
この少年は自転車に乗ったままエレベーターに乗り込み、後ろ向きで降りようとして事故に遭ったらしい。その態勢では何か起こった時、咄嗟の防御行動が取れなくなる。そして不幸にも“何か”は最悪の形で起こってしまった。きちんと前向きに自転車を押していれば、野球部に所属していたような運動神経の良い少年であるから難は避けられただろう。
こう言うと、被害者の少年を責めるとは怪しからん、悪いのはシンドラー社と管理会社ではないか、と憤激する人が多いのが日本人である。確かに誰が何と言ったって製造者と管理者が悪いに決まっているが、相手の過失をいくら責めたところで被害者になってしまってからでは遅い。誰が悪いかという問題は別にして、こういう信頼感のない世の中である以上、遭わなくても済む事故には遭わないように、お互いに気持ちを引き締めましょうと言っているだけだ。
それに自転車で後ろ向きに降りようとすれば、エレベーターに乗ろうとしていた老人や子供と衝突して、少年自身が加害者になる可能性もあった。
エレベーターが日常生活に浸透してきたのは私の幼年~少年時代の頃で、東京都内の百貨店などにボチボチ設置され始めていた。最初は必ずエレベーター・ガールと呼ばれる女性が乗っていて、扉の開閉から行き先階の指定まで、すべてその女性が操作していたものだ。初めて自分の手でボタンを押してエレベーターを動かしたのは10歳の時で、あの感動は今でも忘れられない。
そんな頃、私の両親がエレベーターの前で言ったのは、扉が開いても絶対にすぐに乗り込んではいけない、きちんとエレベーターの箱が来たことを確認しなさいということだった。用心に用心を重ねるに越したことはないのである。当時は停電はあるわ、自動車はエンストするわ、電化製品のハンダ付けはよく剥がれるわ、真空管は壊れるわという時代で、技術というものに対する信頼感は現在のように磐石ではなかった。
最近では技術の信頼性は当時とは比べ物にならないほど高まったけれど、その運用面にはまだ時々ポカミスの穴が見られる。製造者や管理者の責任ばかりを厳しくしておけば、果たして大船に乗ったように安心していられるのだろうか。
その典型的な例は交通事故である。例えば自動車が歩行者を轢く。悪いのは自動車の運転者である。今さら言うまでもない。しかし運転者=自動車の運行管理者の責任が厳しく問われる制度だからといって、歩行者は安穏と歩いているつもりなのか。
自家用車を運転していても、タクシーなどに乗っていても、自分の身の安全に無頓着としか思えない歩行者や自転車があまりにも多い。車道にはみ出して何人も並んで歩く者、携帯メールを打ちながら歩く者、ヘッドフォンで自分の世界に没頭しきったまま道路を横断する者。仮にこういう不注意な者たちを轢き倒しても運転者の注意義務違反は免れない。日本国内では悪いのはあくまで自動車の運転者である。だが轢かれて骨折でもした場合、いくら治療費や見舞金や賠償金を積んで貰っても、骨はすぐにはくっつかない。死んでしまえば何をか言わんや。
交通事故に関して、以前こんな投書を目にしたことがある。
『とびだすな くるまは急にとまれない』
という有名な交通標語があったが、投書者はこの作者に噛みついていた。何で『こどもは急にとまれない』と書かなかったのかというわけだ。
確かにそうだ。交通事故の防止のためには運転者の教育が最重要課題だし、安全運転義務を怠った運転者は厳しく責任を追及されるべきだ。しかしそういう不注意な運転者の犠牲にならないように、子供に対する呼びかけの標語を作って何が悪いのか?
欧米では子供に対する交通安全教育はさらに徹底しているという。自動車とすれ違う時、自動車の前を横断する時、運転者の目を見なさいと教えているらしい。運転者がきちんと自分のことを確認してくれているかどうか、それを歩行者の方も再確認しなさいということだ。青信号で横断歩道を手を上げて渡っていれば、あとの安全は運転者任せというのでは、最近の世の中、自分の身を守るのにあまりに心もとないのではないか。
青信号で道路を横断していた学童や生徒の列に酒気帯び運転の自動車が突っ込んで死傷者が出たなどという記事に接するたびに、私はやはり自分のことのように口惜しい気持ちがしていた。接近する自動車のエンジン音を聞き分け、運転者の表情を確認する訓練を施してさえいれば失われなかった生命、失われなかった時間なのだ。子供がそんなことまで自己防衛しなければならない世の中が悲しいと正論を吐いたって、失われた生命は帰って来ない。
ああ大増税
2006年夏、日本中のあちこちから悲鳴が聞こえてくる。諸々の税制上の控除が廃止されたために住民税の通知が昨年の3倍から10倍になったとか、医療制度改革で医療費負担が増加したとか、特に高齢者・年金世帯を直撃する大増税によるものである。さらに今後は消費税率引き上げだとか、サラリーマンをターゲットにした増税案だとか、とにかく現在の日本の財政危機を乗り切るために庶民に負担を求める案件が目白押しだという。
具体的な政策自体に関してくわしく語るつもりはないが、テレビ番組や週刊誌の記事を見ていると、「弱者いじめ」だとか「庶民へのしわ寄せ」だとか、恨み節は尽きないようだ。しかし私に言わせれば、今さら何を言ってるのという感じである。2005年9月11日の総選挙で自民党を圧倒的に勝たせたのはあなた方でしょうが…。だから言わんことじゃない。
白髪を振り乱し、声を嗄らして「郵政民営化~!」と連呼するだけの小泉首相がカッコ良い、頼もしい、それだけの理由で自民党に投票したあなた方有権者の責任でしょう、と言いたいところだ。あの時に小泉自民党を支持した日本国民は、今回の大増税も医療費負担増も甘んじて受けて、国家政策に協力する義務がある。そもそも日本国民はかつて消費税を導入した竹下首相、消費税率を上げた橋本首相に参院選大敗という苦汁を飲ませたが、結局は恨み節もその時1回こっきり。ちょっと見栄えの良い首相が登場すればコロッと参ってしまって票をプレゼントするという、お人好しというか馬鹿というか…。
とにかく今回の大増税や医療費負担増に関して言えば、日本国民は何一つ文句は言えないはずである。今さら「庶民いじめ」などと愚痴を言うのは、日本人の政治音痴を世界中に触れ回るようなものだ。今は自分たちの選んだ政府が決定した財政政策に協力する決意を新たにして、国に殉じる覚悟を決めるしかない。
今こそ日本人の大好きな特攻隊精神を発揮すべき時である。知覧の特攻隊を美化した「ホタル帰る」などという物語に感動し、日本の未来を守るために死の出撃をしたなどと戦艦大和を美化した映画に酔いしれ、さらに性懲りもなく来年(2007年)には「俺は、君のためにこそ死ににいく」などというやはり知覧特攻隊の映画に期待している日本国民にとって、今後数年間は一億総特攻の時期なのではないか。
「俺は、君のためにこそ税金を払う」と表明し、日本の未来を守るためになけなしの財産を投げ出し、生活が立ち行かなくなればホタルになって愛する人のもとに帰っていけばよい。
特攻作戦などという、およそ人の道を外れた作戦を考案して実行に移した責任者たちを指弾することなく、特攻で死んだ若者たちを賛美して悲劇に酔っていた平成の日本国民に、その大いなるツケが回ってきたのである。国家や組織の指導者の責任を追及することなく、自己犠牲の精神のみを賛美するというのは、まさにこういうことだったのである。
これで少しは日本人も賢くなって政治音痴が治ればよいが、おそらく上層部の過失に甘い国民性はそう簡単に改善されることはなかろう。税金だけではない、生命までも召し上げられた特攻隊の若者たちを単なる悲劇のヒーローにしてしまった日本人である。敢えて言う。私は特攻隊員たちは“日本”によって2度殺されたと思っている。1度目は無能で無責任な作戦指導部の命令で敵艦隊に突入させられた時、2度目はその無能で無責任な作戦指導部を戦後の国民があっさり免罪してしまった時。彼らは日本の上層部の不条理に対する教訓として、日本の歴史に末永く刻みつけられて“生きる”ことができたはずなのに、戦後の日本国民は悲劇のヒーローに憧憬するあまり再び彼らを殺してしまった。そのツケが巡り巡ってきたと言わざるを得ない。
「三丁目の夕日」の時代
2005年、「ALWAYS三丁目の夕日」という映画が封切られて大ヒットしたことは記憶に新しい。聞くところによると、日本アカデミー賞の最優秀賞はじめ、12部門で受賞したらしい。私も観たが、個人的感想を言えば近年まれに見る傑作だと思う。昭和33年の東京が舞台であるが、あの頃を知る人たちならば、観れば何か懐かしい気がするはずだ。この年は私が小学校に入学した年に当たるが、あの画面の中の情景には少しも違和感がなかった。昭和33年の東京は、家並みも、路地裏も大通りも、自動車の数も人々の服装も、私の記憶に残っているものと寸分違わぬと言ってよい。よくあそこまで当時の情景を再現したものだと感心する。
制作者たちは、映画の題材が地味なのでこんなにヒットするとは思ってもいなかったらしいが、やはりこういう舞台設定自体が新鮮であるし、何より現在最も消費力のある世代がターゲットであるから興行的にはまず成功するに決まっているとは思っていた。
この映画の原作はビッグコミックオリジナル誌(小学館)に長年にわたって連載されている西岸良平さんの漫画「三丁目の夕日」で、私も欠かさず愛読している。読みながら、ウンウン、あの頃はそうだったよなぁ、と頷いてしまうことの多い漫画である。その名作が実写になって映画化されたのだから、これはもう絶対に観ようと決めていた。

これは数年前のゴールデンウィーク前後に発売のビッグコミックオリジナル誌の付録、鈴木オートのオート三輪車と東京都電の“紙模型”。昭和33年頃はこんなオート三輪車が大通りでも路地裏でもパタパタとエンジン音を立てて走り回っていたし、現在のように地下鉄ネットワークが完成していなかった頃の都民の足はもっぱらバスと路面電車だった。
ちなみにこの“紙模型”の都電、黄色の車体に小豆色の帯という派手な塗装になっているが、この塗装は昭和30年代後半くらいからのもので、昭和33年頃は映画に登場するようなグリーン系の地味な色をしていた。
また昭和30年代の子供向け雑誌(ほとんどが月刊誌)には、この写真のような“紙模型”が付録として付いてきたものだった。私が作った一番大きな“紙模型”は全長1メートルくらいある大きな戦艦大和だったが、その主砲はマッチ棒だった。
原作漫画と実写の違いで一番目につくのは配役である。駄菓子屋の店主の茶川竜之介はあんなに若くてハンサムではなく(吉岡秀隆さん)、原作では初老のおじさん。そこに転がり込んでくるヒロミもあんな目の覚めるような美女ではなく(小雪さん)、もっとどこにでもいるような姉ちゃん。集団就職で鈴木オートに就職する六子(堀北真希さん)は、原作では腕利きだが内気な男性青年である。いずれも映画に登場させるためには、この方が絵になるのだから仕方ないが、絶対にあの頃ではあり得ないよ、というのが鈴木オートの六子である。映画のストーリーでは、鈴木オートの店主(堤真一さん)が六子の履歴書の特技欄に『自転車修理』と書いてあったのを、『自動車修理』と勘違いして採用してしまったことになっているが、昭和33年には自動車修理はおろか、自転車修理を特技とする女の子がいたらかなり物珍しかったはずで、女の子の履歴書にそんなことが書いてあったら、どんなウッカリ親父でも書類に穴のあくほど確認したに違いない。
昭和30年代は、男女の役割分担は現在とは比べ物にならないくらい厳密に決まっていて、男の子と女の子も将来の役割分担に備えて学校の教科にも多少の差があった。中学や高等学校になると、男女共学校で男子が「技術科」の実習を受ける間、女子は「家庭科」の実習というのが普通だったのではないか。私は男子校だったから正確な事情を知らないが、中学以降「家庭科」の授業や実習は無かった。
また服装の色も男と女で暗黙のうちに違っていて、男の子は青系統の服を着るのが当たり前、赤や黄色の服を着ると「ヤーイ、女、女」と馬鹿にされたものである。(この話は西岸氏の原作にもあった。)大人も男性の着るシャツは白と相場が決まっていて、このホワイトシャツが日本風に訛ってワイシャツとなったのだが、そのうち青いホワイトシャツとかピンクのホワイトシャツとか、色柄物のシャツが売られるようになり、初めて着た時には何だか照れくさかった。
さらに言葉使いに至ってはもっと厳しく、男の子が女言葉を喋ったり、女の子が男言葉を喋ったりすると異様な目で見られた。そういう時代に育ったから、最近のように小中学校の女の子が、俺とかお前とか言いながら大声で話しているのを聞くと、私などはびっくりしてしまう。
それはともかく昭和33年とはどんな時代だったのか。
太平洋戦争が終わって13年、人々の生活はそれなりに落ち着いてはいたが、まだまだ日本人だけが世界の片隅でひっそり暮らしているような感じだった。この文章を書きながらふと思いついたのだが、昭和33年頃と現在の一番根本的な違いは、あの頃の多くの日本の庶民は“世界”というものを意識していなかったことではなかろうか。もちろん丸い地球の上にはアメリカとかソ連とかイギリスとかフランスといった多くの国があることは常識だったが、それらと日本との関係などは意識しなかった、あるいは意識する必要もなかった、または意識せずに済んだ。
必ずしも敗戦国民という卑屈さが原因ではない。当時の大人たちはどうだったか知らないが、小学校の社会科で世界地理などを習っても、それはどこか別世界のことにしか聞こえなかった。当時は1米ドル=360円の固定相場制。つまり360円出さなければ米ドルに換えて貰えなかった。アイスキャンディー1本10円の時代である。アイスキャンディー36本分。最近の貨幣価値感覚に直せば1米ドルが3600円もしたことになる。そんな時代に誰が庶民感覚で外国のことなど意識できようか。円がドルに対して変動相場制に移行したのは昭和48年のことだった。
日本の庶民が外国を意識できるようになったのは昭和39年の東京オリンピックからである。世界中の国々からお客様をお迎えするというだけでなく、東京オリンピック以後着々と実力をつけていった日本経済と共に、日本の庶民の意識もまた世界へと羽ばたいたのであった。
要するに昭和33年頃は現在に比べれば貧しかったわけだが、その貧しさはまったく意識しなかった。むしろ精神的な余裕があったと言ってもよい。先の軍事的な戦争で受けた痛手も癒えかけて、次の経済的な闘争に打って出るまでの一時の安らぎ、束の間の休息…、それが昭和33年頃の日本だったと思う。
「三丁目の夕日」の頃の学校教育
昭和30年代は、日本にとっての安息の時期だったと書いた。軍事力の時代がもたらした破壊と悲劇からは立ち直っていたが、経済競争の時代が到来するまでにはまだ間があった。日本にとっては本当に戦争も経済競争も何も心配しなくてよい、ある意味で最も幸せな時期だったかも知れない。私の世代はそういう時代に少年時代を送った。
私たちの一世代前の人たちは『神国日本』『忠君愛国』を叩き込まれ、男の子は立派な兵士になることを要求され、女の子は丈夫な男子を育てて靖国の母になることを要求された。そして敗戦。昭和20年の1学期の終業式に黒板に『米英撃滅』と書いていた教師が、2学期になると豹変して『民主主義』と書いた。子供たちの大人への信頼を失わせるそんな教育現場の混乱も収まっていたのが昭和30年代。
これが昭和40年代以降になると、国家レベルでも個人レベルでも経済競争に勝ち抜くことが至上命題となり、そのことは必然的に学校教育へも影響を及ぼすことになる。それが現在までのいわゆる格差社会にもつながっているのだろうが、将来ひとつでも上のランクの階層に食い込むために、子供たちは勉強・勉強と追い立てられるようになった。良い成績を取って良い上級学校へ進学し、安定した高収入の職業に就くために…。
私たちの頃も塾はあったが、平日の放課後からそんな所に通っている子供はほとんどいなかった。長期間病欠した子供が補習のために通うくらいのものだったのではないか。ところが最近では、ほとんどすべての子供たちは小学校低学年のうちから学校から帰ると学習塾に通うらしい。すべては良い点数を取るために…。聞くところによると、幼稚園児のための学習塾まであるそうだ。良い小学校に上がるために…。そんな競争=狂騒も始まっていなかったのが昭和30年代。当時は教育にも精神的なゆとりがあった。
ここ何年間も“ゆとり教育”が叫ばれて久しいが、過当な成績競争への反省とか言いながら我が国が行なってきた施策は、学校も土曜日を休みにして授業時間を減らし、ついでに教科内容も大幅に減量して簡略化することでしかなかった。
最も愚かな例が円周率πの数値に代表されている。何も円周率を小数点以下何十桁も暗誦する必要はないが、私たちの小学校の頃はπ=3.14として計算させられたものだ。ところが最近ではπ=3で計算するそうだ。π=3.14を使うことで私たちは小数の掛け算・割り算に習熟したのである。π=3で習った子供たちは明らかに計算能力が上達しないだろう。いくら電卓やパソコンに計算させる時代であっても、生身の頭脳で計算できなくてもよいはずはない。それに計算させずに負担を減らした頭脳に代わりに何をさせようというのか。
最近の大学生の学力低下は目を覆うものがある。多くの人が言っているし、私自身も多くの大学生、あるいは数年前まで大学生だった若手たちを見て感じていることだから、たぶん全国的にそうなのだろう。しかも世間では偏差値が高いとされている大学の学生や卒業生にして然りである。計算が速くない、確実でない。文章を書けない。基本的な漢字を知らない。教養としての知識が浅い。本を読んでいない。等、等…。
読み書き計算などの能力は私の年齢になれば生理的にかなり劣化してくるものであるが、まだまだ20歳代、30歳代という大学生、大学卒業生の能力が私と同程度以下というのはどういうことか。それに読書量の不足による基本的教養の欠如は、もはや大人になってからでは補うことが不可能で、そのために十分な判断力、分析力を発揮することが出来ないとなれば、これはもう致命的だ。これが“ゆとり教育”によって育ってきた人材である。
それでも“ゆとり教育”によって詰め込み教育を減らしたお蔭で、感受性が豊かで情緒の深い人材が数多く育ってきたというならまだ救いもある。しかし大学生だけを見ても、最近の若者たちの殺人事件、暴力事件、性犯罪、金融犯罪などの件数は圧倒的に増加しているではないか。これでもまだ“ゆとり教育”の成果を強調するつもりなのか。
少年時代に軍国の担い手になることも期待されず、経済競争の戦士になることも期待されなかった私たちの世代が受けた初等教育こそ、本当の意味でのゆとり教育ではなかったか。国家の目標が、あるいは時代の趨勢が、ある一方向に向かって流れ始めた時、子供たちの教育も影響を受けるのは当然である。“ゆとり教育”などと言って読み書き計算などの負担を減らしてやったところで、世の中全体がやはり読み書き計算などの基礎学力の優れた人間の方に高い評価を与え続けていれば、結局のところ、負担を減らしてやったことが却って仇になって子供たちを追い詰めてしまうのではないか。
そもそも現在の学校教育がどのようにして確立されてきたか、私がしばしば引用するA.トフラーの『第三の波』の示唆は深い。人類が農業革命を起こして巨大共同体集落を形成して以来、近世が終わるまでの“農耕社会”(第一の波)においては、現在のような学校はなかった。子供たちは地域社会の中で親や近隣の大人たちによって生活に必要な知識を教え込まれ、それらの大人たちと同じような人生を送っていたものだ。そういう社会では立身出世を目指す必要もなく、地域社会で分相応の役割分担をしていればよかった。“学問”や“芸術”を学ぶために学校や特別な集団に入るのは、原則として貴族や上流階層のごくわずかな子弟たちだけだった。
そういう農耕社会においては、現代のような“落ちこぼれ”はない。勉強ができないからと言って差別される必然性もない。それは江戸前落語に出てくる長屋の住人たちを見れば判る。長屋には大家がいて、これは博識で頼りになる大家もいれば、見栄っ張りで知ったかぶりをする困った大家もいる。他に八つぁんや熊さんがいて、これは乱暴者だったりオッチョコチョイの慌て者だったり、酒癖の悪い飲兵衛だったりする。さらに与太郎というのがいて、これはちょっと頭の回転は鈍いが何の悪気もない愛すべきキャラクターである。
この与太郎は、現代で言えば学校の成績も悪い“落ちこぼれ”に相当するのだが、江戸時代においては誰も与太郎を邪魔者扱いしていない。また差別するとかしないとかいう発想すらもない。「勉強ができない」という人間の特性は、「暴れ者」だとか「慌て者」とかいう特性とまったく同じ次元でしか意識されていない。こういう社会では与太郎のような者も、他の八つぁんや熊さんと同じように、自分の分相応の役割を持って地域の共同体社会に貢献していたのであろう。
では「勉強ができない」という特性が格別に問題視される社会とはどのようなものか。人類が産業革命を起こして“産業社会”(第二の波)に突入したとき、社会が個々の人間に要求した能力を考えば判る。それが読み書き計算である。産業社会の特質は、工場で製品を大量生産して大量消費することである。すなわち画一化された製品を量産するために最低限の“学力”を有する労働者が必要とされ、製品の広告を見て購買して貰うために最低限の“学力”を有する消費者が必要とされ、さらに余った製品を売りさばくための海外植民地を防衛するために最低限の“学力”を有する兵隊が必要とされる。そしてこれらの“学力”が高い人間ほど他の人間よりも評価され、必要とされるのである。
こういう産業社会の要請に応えて現在の学校制度はできた。万人に教育を、というと聞こえは良いが、結局は産業社会が欲する人材を大量に確保するための手段に過ぎない。最近の教育論議にはこの視点が欠けている。
私自身は、もう日本は世界に先がけて産業社会を脱し、“情報化社会”(第三の波)への移行を見据えるべきだと考えているが、それにしても明日からすぐに情報化社会ですというわけには行かない以上、子供たちには産業社会に生きていく能力を身につけさせるべきだと思っている。最近の個性尊重だとか一芸に秀でるとかいう、いわゆる“ゆとり教育”の理念は、情報化社会にこそ活きてくるものだが、まだ産業社会の価値観から脱する気配すらも見えない現在、子供たちの学力を低下させるような施策はいたずらに子供たちを追い詰める結果にしかならないと思う。
産業社会における最も理想的なゆとり教育、すなわち私たちが昭和30年代に受けた教育そのものだったのではないか。私たちは立派な軍人になって御国に御奉公しなさいとは言われなかった。高学歴を獲得して高収入を保証されることが人生の幸福だとも言われなかったし、そんな期待もされなかった。しかし読み書き計算はしっかり叩き込まれた。本も読まされた。作文も書かされた。課外活動も奨励された。いろんな話も聞かされた。
「○○のために」ではない。ただ教えられた。子供たちに教育という“財産”を分与しておこうという意図しかなかったように思う。そういう初等教育は昭和30年代という特殊な時代、軍事戦争と経済競争の端境期だからこそ可能な蜃気楼だったのか。この事情を考えていくことが、現代における真の意味でのゆとり教育につながるような気がする。
補遺(1):
このように書くと、お前は偏差値の高いコースを歩んできたから、そんな気楽な評論家みたいなことを書けるんだろうとお叱りを受けるかも知れないので、補足しておきたい。
まずそういうお叱り自体、産業社会の価値観から抜け出ていない。お前は勉強ができた→良い学校へ行けた→だから今は良い身分だろ、というのは、まさに学校教育を産業社会における損得でしか計っていない考え方であって、子供たち自身はお互いにそんなことは何の関係もないのである。私は確かにテストの成績は良かった、しかし運動会の徒競走になると気が重かったし、体育の授業でマット運動や跳び箱を楽々とこなす級友が羨ましかった。
だけど学校の休み時間や放課後には皆で一緒になって「水雷艦長」だとか「士農工商」だとかいう遊びをやった。勉強や運動神経の良し悪しは何の関係もなかった。テストの点数が良くない子でも他の時は威張っていた。「あの子は将来大学へ行く子」とか「あの子は家業を継ぐ子」などという大人の世界の色分けは、子供たち同士の世界には入ってこなかったし、また大人たちも持ち込もうとはしなかった。ここのところが、たぶん昭和30年代と現在との学校教育における一番大きな違いなんだろうと思う。
だから私たちの世代は、小学校を出て何十年も経ってから久し振りにひょっこり出会った友達同士でも、現在の職業や地位など何の関係もなく話が弾む。“勝ち組”も“負け組”もない。子供たちにとっては「現在の子供時代」が大切なのである。大人の世界の価値判断はいらない。そうすればさまざまな能力や才能を持った子供たちが互いに影響しあって自ら伸びて行くのではないか。
補遺(2):
私の言っていることが矛盾しているのは承知している。大人の世界の価値基準を子供の世界に持ち込むなと言っておきながら、大人の世界の産業社会で生きていくための“学力”=読み書き計算の能力もしっかり教えておけと言っているのだから…。
しかし今にして思えば、昭和30年代はそれが両立したのである。なぜなら当時は日本という国家が産業社会としての価値判断を停止していたからである。戦争は放棄したし、経済競争はまだ機が熟していなかった、つまり当時の日本は産業社会としてはきわめて特殊な状況にあったのである。兵隊も要らなきゃ、労働者もそんなに要らない。人々が日々暮らしていけるだけの物資が生産できればそれでいい。日本は一時的に“農耕社会”的な段階に逆戻りしていたのだ。
それでも“産業社会”的な学校だけはあった。だから私たちが昭和30年代に受けた初等教育は歴史的に見てかなり変則的なものだった可能性がある。産業社会で必要とされる読み書き計算の能力を教え込まれながら、それが決して将来の産業社会の構成員を養成するという目的でなされたわけではないからである。学力を重視しつつも、学力の成績が必ずしも児童の選別に直接つながらない教育が存在しえたというのは、現在から見れば奇跡的なことだった。
私の心の中では、小学校の教育は現在に至るまでの人生の単なる通過点ではない。中学校へ上がるための階段ではなかった。小学校の先生方の言葉が今でも心によみがえって現在の生活を律することがあるからだ。
「物を盗む人も悪いが、無用心で警戒しない人はもっと悪い。弱い心のある人を泥棒にしてしまったからだ。」
「雨戸を開け閉めする音で人の心が判る。怒りや苛立ちの気持ちをそんな音に表わしてしまう人の周りには誰も寄って来なくなる。」
クラスで何かトラブルがあると、昔の先生は教科の時間を割いて20分でも30分でもそんな話をしてくれたもので、それが今になってみると身に沁みることが多い。また音楽で『スキー』の歌の時にはご自身のスキーの体験を、『我は海の子』では水泳の体験を、ずいぶん長々と話して下さった。6歳から12歳までの小学生の頃に、その子供心に長く残るような話であった。昔は学力も重視されたが、それ以外にもこういうところで先生と生徒が直に向き合う機会も多かったと思う。
個人的な話で申し訳ないが、こういうところに教育改革のヒントがあるかも知れないと思って書かせて貰った。今さら昭和30年代の日本に戻れるわけはないし、また必ずしも昭和30年代の学校教育が理想だったとは思っていない。小学生に対して過剰な体罰を行なう教師などもその頃からいたが、昔はそれを表沙汰にすることも憚られるような時代だった。悪いところは悪いところとして認識し、現在の教育にも取り入れられるものは何かを検証していく必要があるのではなかろうか。
補遺(3):
最近の学校では円周率π=3.14ではなく、π=3を使うと書いたが、これには多少の誤解があるらしいことが判った。ある教育関連サイトを見ると、 2002年度からの学習指導要領には次のように書かれているとのこと。小数の掛け算・割り算について小学校5年生で1/10の位までの小数の計算(小数点以下1桁)ができればよい,また円周率としては3.14を用いるが,目的に応じては3を用いてもよいということらしい。またこれは1989年の学習指導要領から変わっていないとのことで、π=3がかなり物議を醸したことへの弁解とも反論とも受け取れる。
確かに私もここまで詳しく調べてから物を書いたわけではないので、ちょっと軽率だったことは反省しなければならないが、やはり私の主張自体までを訂正する気にはならない。むしろπ=3の手抜き教育が1989年から行なわれていたことに唖然とする思いである。
『円形の池の周りを歩測したら30メートルありました。池の直径は何メートルでしょうか。』
昭和30年代にはπ=3でも良いなどという結構なお達しはなかったから、当時の小学生は誰でも30m÷3.14≒9.6mを計算したのである。ところが今では、どうせ池の周りの距離など厳密に測れるわけないからπ=3で割って直径10mでも正解ということだ。しかも小数点以下2桁の3.14という数字の割り算はできなくてよいから、必要に応じて電卓を使っても良いらしい。つまり今の小学生たちは、普通は円周率としては3.14を使うという知識だけは詰め込まれているが、実際にその数値を使った生身での計算はやっていない。
要するに学習指導要領の文面の解釈がどうなっているか知らないが、1989年以降の小学生は生身の頭脳で小数点以下2桁の計算を行なう訓練をして貰っていないのだ。まったく気の毒なことである。計算のトレーニングなどは若いうち、幼いうちにやっておけば、一生を通じての(まあ少なくとも中年くらいまでの)財産になるのに、それをやって貰っていない。子供たちが本来獲得できたはずの計算能力の半分も獲得できなかったとすれば、それは誰の責任なのか?
首都圏大停電と危機管理
2006年8月14日の朝、東京・神奈川・千葉の首都圏を大停電が直撃した。旧江戸川を航行するクレーン船が川を跨ぐ高圧送電線を損傷したためだそうだ。今回ニュース解説などを聞いていて初めて知ったが、送電線の鉄塔は両側に腕が伸びていて、それぞれに高圧送電線が張られているが、あの1対の電線は一方がもう一方のバックアップになっているらしい。つまりどちらか一本が損傷しても、もう1本が残っていれば送電には支障が出ないらしい。
ところが今回はクレーン船がその2本とも引きちぎってしまったために、首都圏の広範な地域で長時間にわたる停電が発生したようだ。今や日常生活から国家活動にいたるまで一時たりとも欠かすことの出来ない電気が、ずいぶん脆弱なルートを通って配給されていることが改めて思い知らされたわけである。
私たちの世代が子供だった昭和30年代には停電はしょっちゅうあった。特に台風が来ればどこかで電線が切れて停電する可能性が高いことは常識だったので、天気予報で台風が来るとなると、必ず蝋燭とマッチを準備して待機したものであった。その天気予報だって現在のように気象レーダーで探知したものではなく、各地の測候所の気圧変化だとか、戦時中のB29爆撃機を改造した気象観測機が暴風の中に突っ込んで行って測定したデータをもとに進路を割り出したものだったから、空振りもずいぶんあったが、子供心には蝋燭とマッチを手元に置いて台風を待ち構える時の心境は、結構ワクワクするものだった。まあ、戦争ごっこみたいなものだ。
現在では台風が来るたびに停電されていては日常生活そのものが成り立つまい。電力の必要性が昭和30年代当時とは比べ物にならないほど高くなったのに対応して、電力供給システムが堅固になったことは実に賞賛に値する。戦前はあのアメリカ合衆国でさえ、サンフランシスコの大停電に際して航空母艦サラトガ1隻の発電機で電力を賄えたというから、昔はずいぶん牧歌的だった。現代のようなハイテク時代に電力を休まず供給する電力会社の重要性が認識される。
今回のクレーン船の事故で判ったことだが、電力会社の送電システムのバックアップ体制は現在のものが限度だろう。飛行機の墜落やテロリストによる爆破で送電用の鉄塔が1本倒されれば都市機能が長時間にわたって麻痺する事態になることが一般市民の目にも明らかになったわけだが、ではそういう非常事態にも備えるとなると、各送電ルートにもう1組ずつ予備の鉄塔を建てるか、あるいはすべての送電ルートを地下に埋設することになり、その莫大な工事費を電気料金に上乗せされたら、おそらく日本経済は負担に耐えきれまい。
問題は電力を供給さえる側のバックアップ体制の充実だが、例えば大きな医療機関などは自家発電によるバックアップ電源を持っていて、広域で停電したからと言って直ちに人工呼吸器が停止したり、手術室のライトが消えたりすることはなく、業務に支障が出ないようになっている。おそらくほとんどの国家機関も同様だろう。ところが今回の停電に際して、東京証券取引所の日経平均株価の算出が一時的に停止したと報じられており、思わずエッと驚いた。一旦は自家発電に切り替えたが、停電の復旧時に電源の切り換えがうまく行かなかったらしい。
経済大国日本にとって株式取引はかつての連合艦隊にも相当するものだろう。その現場で今回のような危機に十分対応できなかったということは重大だ。日本は地震や台風などの自然災害が多い国だから、日本人は災害への対処が上手な国民である、と昔からよく言われてきたが、はたして本当だろうか?とても危機管理の上手な国民には見えない。むしろ何か災害が襲ってきたら、呆然と立ちつくすだけの国民ではなかろうか。頭を抱えて立ちすくんでいるうちに、災害が(天災であろうと人災であろうと)頭の上を素通りして行く。その諦めの良い国民ではなかろうか。
「今日も昨日と同じように無事に済んだ、明日も今日と同じように無事に済むよ。」そういう物の見方に少しも疑いを抱かず、何か事が起こるまでは能天気に毎日を送る楽天的な国民。そして何か起これば頭を抱えてやり過ごせばよい、もしも自分に責任があれば形式的に頭を下げればよい、それが地震や台風を“やり過ごして”きた祖先たちから我々が受け継いだ気質なのかも知れない。代々災害に“立ち向かって”きた国民であれば、我が国の生命線である株価算出の現場には、万々一停電した場合に備えて通常電源と非常電源の切り換え手順に関するマニュアルが常備されていたはずである。
株式の現場だけに限らない。各自ご自分の家庭や職場で、明日と言わず今日にでも地震が起きた場合、火災が発生した場合、長時間停電した場合、不審者が侵入してきた場合、その他およそ考えうるあらゆる非常事態を想定した対処ができているかどうか、改めて確認してみたらいかがですか。
新たな戦前…
2006年8月15日の終戦記念日に小泉純一郎首相が靖国神社を参拝したことについて、私がこのサイトに何か書くだろうと期待している人たちに応えて手短に書く。本当はもう何も書く必要はないくらい私もこのサイトで書き尽くしているのだが、敢えて追加するとすれば、もうこの国にはブレーキは掛からないだろうということだ。心ある人は私のメッセージを後世に伝えて頂きたい。
小泉氏は参拝後、参拝に批判的な人たちを「中国の言うことを聞けばよいのか」と逆に批判して自己を正当化しようとした。私自身、日本は中国の言いなりになるべきではないという見解を持っているし、中国政府の歴史認識の誤りも指摘している。その上で私は日本の首相の靖国参拝に反対であるという論拠を、このサイト上で少なくとも3つ以上示している。私に限らず、首相の靖国参拝反対論者は必ずしも中国の顔色を窺う人間ばかりではないということだ。さまざまな反対の根拠がある。
それなのに小泉氏は、「自分の参拝に反対する人間」=「中国の顔色を窺う人間」と決めつけた単純なステレオタイプの反論しかやらなかった。こういう単細胞なレッテル貼りを、いやしくも民主主義国家と称する一国の宰相が行なったのである。おそらくこの国は当分の間、二度と再び民主主義国家として立っていくことは出来ないだろう。国策に反対する者、批判的な者に「非国民」というレッテルを貼って封じ込めていった戦前と同じことが繰り返されるだろう。
小泉氏の靖国参拝のあった8月15日、かつての盟友・現在の政敵である加藤紘一議員の実家が右翼メンバーによって放火され全焼した。もちろん靖国参拝との関連は不明だし、おそらく明らかになることはないかも知れないが、加藤氏のこれまでの言動と犯人の思想的背景を考慮すれば、世間的には背後関係はかなり疑わしい。もし小泉首相あるいは安倍幹事長の実家が同じタイミングで焼き払われたとすれば、事実関係が明るみに出る前から小泉氏は目を吊り上げ、肩を怒らせて記者団に次のように条件付きで語ったであろう。
「もし私の参拝に関係があるとしても、暴力に訴えるとは許せないことだ」
しかし加藤氏の受難に関しては、小泉氏は疑わしき背後関係に釘を刺すような非難のメッセージは発しなかった。あるいは何か言ったのかも知れないがマスコミはほとんど報じなかった。
加藤氏が意見の違う政敵であっても、いや政敵であればこそなおさら、相手の言論への暴力的威嚇を非難するのが民主主義というものだ。小泉氏は民主主義を国是とする一国の宰相でありながら、民主主義の理念を理解しておらず、民主主義とは自分を讃える支持者たちのためにのみあるという態度を示した。中国共産党の指導者たちと同じである。こういう者を宰相に選出して、今なお国民が高い支持を続けている国においては、民主主義は死んだと言わざるを得ない。
そもそも中国や韓国に対しては、戦後の日本は戦前・戦中とは違うんだというのが、彼らに対する反論の要点ではなかったか。いったいどこが違うんだい?反対派にはレッテルを貼って排除する、言論を封じる暴力が行なわれても政府首脳がそれを黙殺する。これは新たな“戦前”の始まりではないのか。重税と高額な医療費ばかりでなく、息子や娘や孫たちの生命をも国家に差し出すような時代が来ても、それは現政権を支持した西暦2005年当時の有権者全体の責任だぞ。
後日談:
結局、小泉首相は加藤紘一議員の実家放火事件に関して、2週間近くも経ってやっとコメントを発表したようだ。「言論を暴力で封じる行為は許せない」という、事件当日の夕方に発表すべきだったコメントを、2週間も経ってからようやく発表した挙げ句、「靖国参拝について他国(たぶん中国)を刺激するような報道をしたマスコミも反省しろ」という捨てゼリフを吐いたという。
これではまったく何も判っていない器量の小さな宰相だったことを自ら暴露したようなものだ。言論を暴力で封じる行為は許せないと言っておきながら、自分の行動を批判する記事を報道するマスコミは叱りおくぞ、と凄みをきかせようという魂胆がありありである。言論の自由が大事だということは、首相たる自分に批判的な言論も大事だということである。それが判っていない。しかも小泉首相がそんな民主主義の原則さえ理解していないということを、多くの国民がもっと理解していない。いったいこの国はどういう国なのか。
思うに小泉首相は本気で言論の自由を擁護するコメントをしたわけではなかったのであろう。不機嫌丸出しの表情と声色だった。おそらく加藤議員宅放火事件が迷宮入りしてしまえば、そのままダンマリを決め込むつもりだったのではないか。加藤議員宅に放火して割腹を図った男が入院先の病院で容態が回復して、警察の事情聴取が始まることが報道されたのは、例の小泉首相のコメントの直後であった。男が回復したという情報が官邸に入り、首相の靖国参拝に反対する加藤氏を標的にしたなどと供述されれば小泉氏の立場が微妙になる、そして当然小泉後継者の安倍氏の立場も微妙になるという情勢判断がなされた。それで側近に言われてイヤイヤながらコメントしたから、あんな不機嫌丸出しだった、そんな舞台裏が丸見えである。そもそも機嫌の良し悪しを露骨にあらわにするような人間は人の上に立つ資格はない。
高校野球と特攻隊
2006年甲子園の夏の高校野球は、早稲田実業と駒大苫小牧の決勝戦が延長15回引き分け再試合となり、2試合にわたって球史に残る見ごたえのある投手戦を繰り広げ、多くの高校野球ファンの心に鮮烈な印象を残した。
私事になるが、私の高校の野球部は私の在学中は意外に強く、もちろん甲子園に行けるほどではなかったが、東京都大会では第七シードくらいのレベルであった。ところが私の高校には応援部が無かったので、ある年に音楽部のブラスバンド班が野球部から頼まれて神宮球場に応援に行った。私はドラム担当だったし、また校内の体育祭で応援団の経験もあったので、応援団長を買って出て、真夏の炎天下で黒い詰襟の学生服を着て、声を枯らして応援したことを懐かしく思い出す。
よく熱中症にならなかったものだが、あの年齢の頃はおそらく誰でも、そういうあまり意味のないことに無理を承知で没頭する自分に、何となく陶酔の気持ちを抱くものではなかろうか。だから毎年毎年、日本人は飽きもせずに夏や春になると甲子園の高校球児たちの姿にかつての自分自身を重ね合わせて、つい応援したくなってしまうのかも知れない。高校野球はつまらないという人もたまにはいるが、ご自分は高校時代に何かに憑かれたように熱中したことがないのではないかと思われるから、あまり口に出さない方がよい。
ところで私がこのサイトに「高校野球と特攻隊」などと書くと、ああ、きっと戦前・戦中の高校球児たちが特攻に行った悲劇などを書くのだなと期待された人も多いだろうが、まったく違う。私も長年にわたって高校野球を見てきたが、その高校野球を見る心が、実はかつて多くの日本人が特攻隊員を見殺しにした心と一脈通じるものがあるのではないかと思ったのである。
高校野球甲子園大会のトーナメントが進んで強豪校が勝ち残ってくる頃になると、ここ20年ばかり何となく違和感を覚えることが多くなっていたのだが、今年(2006年)の夏の決勝戦再試合を見て、その違和感の正体が見えたような気がした。
高校野球はどのチームも1年生から3年生までの3学年しか出場できない。(春の選抜大会は2学年だけである。)当然、信頼できる投手がプロ野球のように3人も4人もいてローテーションを組んで登板することなどあり得ない。どのチームも控えの投手が1人か2人はいるだろうが、いよいよ強豪校が出揃ってくる準々決勝、準決勝、さらに決勝となると、エース級投手が連投に次ぐ連投となる。日程や天候の関係で中1日の休養となることもあるが、それでもこれは最近のスポーツ医学の常識から言ってきわめて憂慮すべき危険な事態である。今年は特に決勝戦が2試合にわたり、早稲田実業も駒大苫小牧もエースは常人の想像を超える球数を投げ込んできた。まだ10歳代の若者の腕にこんな負担をかけて良いのか。
投手自身はそういう無理を承知でチームのために登板することに陶酔を感じる年齢であるが、高校野球を見る側も指導する側もそれを「気力」だ「根性」だと言って褒め称えこそすれ、問題があるのではないかと然るべき立場の人たちが声を上げたことはなかった。これって何かの心象風景に似ているなあ、というのがここ20年来の私の違和感だったのである。
高校球児たち、特に投手は卒業後にプロ野球や社会人野球の道に進む人が多い。つまり彼らの腕は今後の彼らの将来の人生を支えていく大事な商売道具なのである。その腕に故障を抱えてしまったら、彼らの野球生命は断たれるかも知れない。それを承知で真夏の炎天下、3試合も4試合も連投せざるを得ない強行日程を組むのはなぜなのか。敢えて現代のスポーツ医学に反するような無理な運動をさせて、それを「気力」だ「根性」だと賞賛する日本人とは一体いかなる民族なのか。
各学校の夏休みや春休みなど教育日程の関係もあるだろう。阪神タイガースが甲子園で試合ができないというプロ野球の日程もあるだろう。しかしそれはどれも大人の都合ではないか。大人の都合で球児たちの肉体に過酷な負荷を強いておいて、周囲で皆で「万歳」「万歳」をしている。これって昔、特攻隊を見送った大人たちの心象風景に似てはいないか。あんな若い子たちを出撃させて可哀そうにと心の中では誰もが思いながら、それでも何とか“無事に”敵艦に当たってくれよと願っていた当時の大人たちの心に…。
自民党安倍新総裁誕生
2006年9月20日、小泉純一郎氏の任期満了に伴って、自民党新総裁に安倍晋三氏が選出され、26日の臨時国会で首相に指名される見通しとなった。安倍政権の政策については先ずはお手並み拝見というところだが、昨年の9・11総選挙で圧勝した小泉自民党(+公明党)の与党政権に対して国民が不信任を突きつけたわけでもないのに、自民党という“単なる一政党”の総裁任期切れという都合だけで“一国”の首相が交代するというのは大変おかしな現象と言える。
自民党は憲政上、単なる一政党と見なされる集団だが、その内部の都合だけで国政が変わるというのでは、日本はかつての平家や藤原氏の時代から大して変わっていないのだなという感慨を持った。こういう体質だから、小泉首相は郵政改革やイラク派兵で反対派・批判派に対してぶっきら棒で言葉足らずの説明しかしないまま、おのれの信念のみで国政を動かし、靖国参拝に関しては党内の論議すら一致させる努力も傲然と怠ったのではないか。
また上が上なら下も下、郵政改革で小泉自民党から掌を返されたような仕打ちを受けながらも、「私は自民党が好きなんです」と涙ながらに訴えた女性元郵政大臣がいた。自身の国政の信念よりもそんなに“自民党”が大事なのか?こういう輩は来年の参院選でピンチに立つであろう自民党からお声が掛かれば、嬉し涙にかきくれていそいそと復党するのであろうなあ。まさに忠誠(中世)美談である。
さらに巷ではここ何年間か、“純ちゃん饅頭”なる馬鹿げた菓子も売れたようである。ニコニコしながらTV取材の前で箱詰めの饅頭を買っていく善男善女たちが、同じように喜んで税金や医療費を納めるとはとても思えないが…。
こういう中世日本で船出した安倍新政権の前途は多難であろうと同情する。大差をつけての新総裁就任とはいえ、当初は80%得票できるのではないかと思われるほどの勢いがあり、事前には70%の得票で“圧勝”したいと目論んでいた安倍陣営が、結局66%しか得票できなかったのは頭が痛いことであろう。結局、自民党内の高い安倍氏支持は、安倍氏の背後に小泉の生霊を見ているだけなのではないか。小泉人気の余韻があるうちはその“おこぼれ”を頂戴して、できれば次の国政選挙に便乗したいという魂胆が見え見えである。また生霊の祟りに触れて、1年前の郵政選挙の時のように党を追い出されてはたまらんという恐怖もあるのだろう。
おのれの政治信念は二の次で、こういう情勢判断(洞ヶ峠)だけで去就を決める自民党の木っ端議員がいることは問題だ。次回の選挙ポスター用に安倍氏と並んだ写真撮影を希望する議員も多かったという。しかし小泉の生霊の威力が失せてきた時に、年若い安倍氏は与党政権を束ねていけるだけの器量があるのだろうか。今回の得票の比較的多くの部分は洞ヶ峠の木っ端議員どもだと思われるから、確実な支持基盤はもっと頼りないはずである。すでにあるTV局のバラエティトーク番組に出演した某自民党参院議員がカメラの前で堂々と「血も涙もない小泉」と呼び捨てにしていた。全盛期の小泉氏には逆らえなかったくせに、首相任期が終わる間際になってやっとこういうことを言える議員の心情も情けないが、いずれ生霊の威力が減衰すれば安倍氏の真の実力が問われることになろう。
最も深刻なのは、安倍氏がこういう党内情勢に対抗するために、ナショナリズムを煽って国民の支持率を上げようと画策することである。これまでの安倍氏の言動にはその兆候が見られる。今回洞ヶ峠に集合した木っ端議員どもの中には、そうなりそうな事態になってから反対すれば間に合うだろうと思っている者も多かろうが、例えば今月来月あたりにも某国よりミサイルが発射されたり、別の某国内でこれまで例を見ない大規模な反日運動が起きたりして、国民のナショナリズムが暴発しやすくなる状況だって起こり得る。それを機に安倍氏が強権を発動すれば、これら木っ端議員連もまた大政翼賛政治の片棒を担ぐ破目になるのである。考えてみれば信念を曲げて安倍氏に一票を投じた段階で、こういう木っ端連中にはすでに大政翼賛の根性が染み付いていると言うべきかも知れない。
日の丸・君が代問題
2006年9月21日、東京都教育委員会が学校行事に際して国旗掲揚と国歌斉唱を義務付けた委員会通達は思想の自由を侵害しており、憲法違反であるとの判決が東京地方裁判所より出された。相変わらずの不毛な国旗・国歌論争である。
反対派は日の丸・君が代はかつての軍国主義の精神的支柱であったから反対ということだろうが、それではオリンピックやワールドカップの各種競技選手団は軍国主義を背負って競技しているというのか?大相撲の千秋楽では軍国主義を讃えて君が代を歌うのか?外国の大きなホテルに日本人が宿泊すると他国宿泊者の旗と共に日の丸も玄関に掲げられるが、それは日本の軍国主義者が来たぞという合図なのか?
そもそも国旗や国歌はいかなる国においても国民の統合のシンボルであって、本来ニュートラルな意味しか持たない。もちろん他国を侵略する時の旗印にも使われるが、国際的なスポーツ競技や国際会議や国際博覧会の会場にも掲げられるし、国際援助の舞台にも登場する。国旗も国歌もポジティブな国家活動もネガティブな国家活動も象徴しうるものであって、それをどちらに使用するかは国民の自覚次第である。
それをかつて軍国主義の象徴だったから悪いものですというのは、あまりに短絡的、あまりに独善的、あまりに自己欺瞞的な考え方であって、殺人者が血の付いた衣服を脱ぎ捨てれば禊も済んで罪も消滅するというのと同じ類の身勝手な理屈である。こういうことを主張する教職員というのは生徒にどういう教育をしているのだろうか。シャツに付いた血は誰のものか、どうして付いたのか、今後は誰の血にも染まらないようにするにはどうすべきなのか、それを考えていくことが次の世代への責任であり、本来ニュートラルな意味しかない国旗と国歌に対する義務なのではないか。それとも日本人は20世紀前半の歴史ゆえに国旗と国歌という衣服を脱ぎ捨てて未来永劫にわたり素っ裸で世界を渡っていけというのか。
一方、各都道府県の教育委員会が学校行事で国旗掲揚・国歌斉唱を義務付けたのは文部科学省の通達による。国民に“国を愛する心”を植えつけようという政策の一端と思われるが、では国家の側には“国民から愛されるように努力する心”はあるのだろうか。税金は上げ放題、金利は抑え放題、官僚は天下りし放題、国税の無駄もやりたい放題…、こんなことだからいつまでも国民が国を愛する気持ちになれず、日の丸や君が代を厄介扱いする教職員の精神的温床を断ち切れないのだ。変人と言われた強権指向の小泉首相でさえ、財政改革と言いつつ実質的にはほとんど財政の無駄を省くことはできなかったと国民は感じている。取り上げるものは何でもかんでも取り上げた挙げ句、国を愛せよとはあまりに勝手な言い分、江戸時代の悪代官と大して変わらぬ仕打ちである。次には子息の生命を頂きますとくるだろうな。悲しいことに市民革命を経験していない日本国民は、こういう国家の非道を見抜くことが出来ずに、またしても日の丸を血に染めてしまうことになるのか。
権力をもって国旗と国歌を強制しようとする国家と、シンボルとしての国旗と国歌を象徴的に捨てることで事済めりとする一部の教職員とが、いずれ競合して国を滅ぼすことになりかねない。
補遺:
日の丸・君が代とは直接関係ないが、最近の教育責任者って何を考えてるのと思わせる映像をTVで目にした。各県の教育委員会が上からの通達に基づいて各学校に国旗掲揚と国歌斉唱を義務付けるのは、生徒たちに日本国民たる心の形を外に表わすように指導せよということであろう。心を外に表わすということは大事なことである。
ところが千葉県の教育委員会管内で今年になって2件ほど不祥事が発覚し、しかも1件は委員会の対応にも不備があったため、監督責任者がTVで記者会見して陳謝の意を表わした。ところがカメラの前に居並ぶ数人の責任者たちはいずれもネクタイをしておらず、開襟シャツの第一ボタンは外したままで、いかにもだらしない印象だった。他の業界が陳謝の会見をする時は、男性は背広にネクタイは常識、現場の医師・看護師や自衛官なら白衣や軍服などの制服を着用する場合もある。
別に背広にネクタイをしたからといって陳謝の心が深まるわけではないが、やはり全国に放映される画面である以上、自分の業界の不祥事に遺憾の意を表わすために正装するのは当然の礼儀ではないのか。それが心を表に表わすということ、自国の国旗に敬意を表するのと同じことである。TV画面に出るたびにノーネクタイのだらしない姿を晒す千葉県教育委員会の馬鹿どもを見て唖然としてしまった。こんな奴輩が国旗や国歌の文科省通達を中継しているのかと思うと国民として情けない。
核実験-北朝鮮以外なら良いのか
2006年10月9日、北朝鮮が地下核実験を強行、たちまち国際的な非難が巻き起こった。これまで北朝鮮を擁護してきた中国、ロシアまでが強い調子の非難を行ない、国連の制裁決議案を容認する構えだという(11日報道)。アメリカは言うに及ばず。
これは北朝鮮にとっては、かつての日本の国際連盟脱退(1933年)や真珠湾攻撃(1941年)にも匹敵する暴挙であり、あまりに無謀で傲慢な指導者に率いられた北朝鮮国民の5年後の運命を思うと暗澹たる気持ちである。
しかし今さら北朝鮮を非難する国際社会もいい気なものである。アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国は恒常的に核戦争の実戦配備体制を敷いており、自分の核兵器は正義だと主張し、これら核保有クラブ同士は互いに相手を非難することもない。インド、パキスタンが核実験をした時には、確かに一時的に非難はしたけれども、結局はこの2ヶ国も暗黙のうちに核保有クラブの会員と見なされて、相応の国際的待遇を受けるに至った。
北朝鮮はインド、パキスタンの核クラブ入りを許した国際社会の盲点を突いて今回の実験に及んだとの論調がある。つまり核兵器は持ってしまった者のゴネ得になるというわけだ。まさにその通りで、インドやパキスタンは許して北朝鮮は許さないというわけにはいかなくなる。さらにこの風潮が定着すれば、いずれイランやイラクも核実験をするだろうし、日本やドイツだって核兵器保有へと動く可能性がある。少なくとも数年以内のイランの核実験は確実だろう。
その時、世界の保安官を自認するアメリカはどうするのだろうか。すでにアメリカは二重の意味でジレンマに陥った。インドやパキスタンを見逃しても北朝鮮を見逃すわけには行かないというジレンマ、また大量破壊兵器があるという憶測だけでイラクに侵攻した以上、実際に大量破壊兵器を爆発させた北朝鮮にも軍事行動を取らなければ中東での戦闘行為の正当性が崩れるというジレンマ…。
着々と最終戦争への道を転がり出した人類。これを救うのは、事あるごとに“唯一の被爆国”を謳い文句にしている我が日本であるはずなのだが、この国の何と頼りないことか。言うことは核保有クラブの面々と同じ、クラブ国には一切非難せず、インドやパキスタンの時も一時は皆と一緒に非難してみたものの、やはり最後は腰砕け。今回は真っ先かけて北朝鮮を非難したがどうなることやら…。必ず皆も非難するに決まっているからお先棒を担いだだけか。
唯一の被爆国であるなら、すべての核保有国を非難するところから始めなければならない。核クラブとそれに牛耳られているすべての国際社会を向こうに回しても、すべての国の核兵器を否定する発言をするべきである。どうせ核戦争の道連れで滅亡させられるのなら、鎖国も覚悟の上で日本一国くらい全面核否定を主張したらいい。それこそ“美しい国”ではないのか。
日本が核保有クラブの面々に対しては腰砕けで、「私は核クラブの準メンバーです」と言わんばかりの卑屈な低姿勢を貫いていることを象徴的に表わしている報道があった。1995年9月6日のNHKニュースである。この日、フランスは太平洋のムルロア環礁で一連の地下核実験の第一回目を行なった(フランス本国時間では9月5日)。南太平洋周辺の諸国民から反対の声が上がっていたにもかかわらずフランスは実験を強行したのであるが、NHKニュースはこれら弱小国の声を無視してフランスに媚びた。
この日はNHKや背後の日本政府関係者にとって都合の良いことに、オウム真理教に殺害された坂本弁護士一家の遺体が相次いで発見されたという大ニュースも飛び込んでいた。確かに日本全国を震撼させた大事件の鍵でもあった坂本弁護士一家殺害事件の下手人が確定したことでもあり、トップニュースで報じるのは当然である。しかしこの日のNHKは遺体が出てきた山林の映像を繰り返し繰り返し流し、同じニュース原稿を何度も何度もアナウンサーが棒読みするばかり、一向にフランスの核実験関連のニュースを報じることはなかった。
私はただちにNHKに電話して抗議したが、これはNHKに報道させている背後の政府関係者の意向が反映されていたと見てよいだろう。坂本弁護士一家の事件は痛ましいことであったが、一度聞けば判るニュース原稿を何度も読んで貰う必要はない。NHKはムルロア環礁周辺の諸国民の声を日本国民に伝える使命を放棄し、国際的にも日本が核クラブに媚びる国であることを実証し、もって来るべき核戦争への過程をわずかながらでも後押ししたのである。これが本当に“美しい国”のありようか?
核軍縮外交も下手、日本…
日本は核保有クラブに媚びることなく、すべての国の核兵器を否定するべきだと前項に書いた。そのための外交戦略はもっとしたたかでよい。現在の日本のやり方はあまりにもナイーブ過ぎるのではないか。
例えば今回の北朝鮮の核実験に際して、自民党の中川昭一政調会長が民放の討論番組(テレビ朝日)に出演して、日本も対抗策として核兵器保有の選択肢もあると述べたことが、全世界に波紋を広げた。国内でもマスコミから野党から、さらには政権与党内からさえも中川会長の発言は不適切だとの批判が上がっている。まったくナイーブである。純情で汚れを知らない少年のようだ。
この発言に対して中国はもちろん、アメリカの要人までが敏感に反応した。中国共産党幹部は安倍首相を表敬訪問した際、日本に非核三原則の遵守を求めたというし、アメリカのブッシュ大統領も中国を口実にして遠まわしに日本の核武装を懸念した。両国とも、世界を何度も破滅させることのできるほど大量の核兵器を実戦配備しておきながらいい気なものである。
だがこれで世界が本当は何を恐れているのかが判ったわけである。世界は日本の核武装を恐れているのだ。すでに日本が核兵器保有の潜在的能力を有していることは周知の事実であり、日本が核兵器を持てば世界の軍事情勢は一挙に混沌としてしまう。核大国の世界支配体制が根本から引っくり返るのだ。その影響は北朝鮮など問題にならない。何しろ日本は宇宙の彼方の小惑星に探査機を着陸させるほどの精密運搬技術も保有しているのだから。
米中の核大国に本音を言わせたという点で、今回の中川発言は外交戦略上評価すべきものであったのに、日本国内のあまりに潔癖な反応はどうしたことか。世界の核保有国にハッタリをかませて徹底的な核廃絶を迫る千載一遇のチャンスなのだが、世論もマスコミも野党も与党も奇麗事ばかり口にして好機を逸してしまうのではないか。
すなわち、我が国はせっかくこれまで非核でやってきたのに、ついに北朝鮮に核を保有されてしまったではありませんか、世界が北朝鮮の核兵器を廃棄してくれないならば日本も次の世代には核を持ちますよ、というブラフを噛ませる。それこそ外交の駆け引きというものである。ついでに皆さん核保有クラブの国々もすべての核兵器の廃棄に向かってもっと努力しなさい、さもないと…、と脅しをかければ満点である。全世界の核廃絶という目的のためなら交渉の手段を選ぶ必要がどこにあるか!
日本が核兵器開発という切り札を留保する、そのくらいの芸当はどこの国の外交担当者もやっていることだ。それを世論もマスコミも与党も野党も奇麗事を並べ立てて、せっかくの切り札を放棄させてしまうのか。アメリカも中国もロシアも手を叩いて喜んでいるだろう。日本は何とお人好しの国家だろうと…。正々堂々の奇麗事しか能が無い国民にも困ったものである。
昔、手塚治虫さんの連載漫画(少年サンデー)で『W3(ワンダースリー)』というのがあった。銀河の果ての宇宙人たちが地球の平和を監視するというSFものだったが、最終回のシーン、地球の中心に究極の核兵器である反陽子爆弾が埋まったままになってしまったと世界中が誤解してしまう。これが爆発したら人類に勝者も敗者もない、恐怖が世界を走る、各国の指導者たちは慌てて核兵器の廃絶を協議しはじめるというエンディングだったと思う。とにかく主人公たちは地球の中心に埋まった反陽子爆弾を切り札にして、世界中の首脳に核兵器廃棄を迫ったのである。
現実の世界はもちろんこんなにナイーブには動かないにしても、日本核武装の可能性という切り札を日本人自身が寄ってたかってオシャカにしようと躍起になる様子は異様かつ滑稽である。日本は外交下手な国民と言われても仕方あるまい。
ただ中川会長がどういう意図で言ったかは知らない。単に北朝鮮に挑発のお返しをしただけかも知れないが、世界を相手に核廃絶の大博打を打てるような政治家はいないのだろうか。
伝家の宝刀『非核の恫喝』
ちょっと前項に追加しておく。自らが非核であることをもって、国際社会の中の核保有国を恫喝することが出来るのは日本しかない。それは“唯一の核被爆国”であるという歴史的事実が基本にあることは確かだが、それだけでは成立し得ないものだ。唯一の被爆国であると同時に、その気になれば核兵器を開発して、地球上のいかなる場所に対しても正確に射ち込むことが可能な潜在的能力を誇示することによって、初めて“非核の恫喝”が成立する。
国際社会がいつまでも全面核軍縮に誠意を示さないならば俺も核クラブに参入するぞ、という脅しを使えるのは日本だけだ。まさに伝家の宝刀と言ってよい。もちろん使い方を誤れば日本自体が亡国となるし、また使うチャンスは1回きりだ。伝家の宝刀の所以である。この恫喝力を正しく使って世界を核戦争の危機から救うのが日本の使命だと思う。
アメリカと中国は確実にこの日本の潜在能力に恐れを抱いていることが、中川政調会長の発言後の一連の動きによって明らかになった。おそらくロシアも同じだろう。国民も政党もマスコミも奇麗事ばかり並べてこの恫喝力を失効させないことだ。
これら核大国に恐れられる存在であることが、一方で我が国の安全保障にも役立つのである。今回の北朝鮮の核実験の後、中国が朝鮮戦争以来の同盟の誼を破って北朝鮮に強い圧力を加えるに至った大きな理由の一つは、日本をこれ以上刺激して核武装されたら大変だという思惑があるからである。
また将来、万一アメリカが北朝鮮への武力発動を決意した場合、どんなシナリオが考えられるだろうか。大体これまでの歴史を見てもアメリカは自分から先に手を出すことはない。自国か同盟国に対する相手の攻撃を誘発しておいて、おもむろに戦争を始める口実にするというのが常套手段である。本当ならば在日あるいは在韓米軍基地あたりに小規模な核攻撃を誘発したいところであろうが、日本の国土への核攻撃があれば日本の世論は一気に核武装へと傾く可能性が高い。それはアメリカにとって非常に大きなリスクである。だから日本国内のどこかが北朝鮮の攻撃を誘発するための「真珠湾」にされる危険は少ない。
このように日本が最先端の軍事技術とともに核兵器開発能力を秘めているという事実が、今後は我が国と東アジアの安全を保障する要となるのである。“核兵器を保持すること”を議論することに抵抗があると言うのなら、“核兵器開発能力を外交交渉カードにすること”を議論するべきである。バラの花が自ら棘を落とすようなことをしてはならない。
ここは歴史独り旅の第4巻です。 第3巻に戻る 第5巻に進む
 トップページへ戻る 歴史独り旅の目次へ
トップページへ戻る 歴史独り旅の目次へ