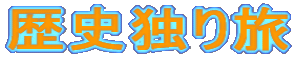
情報化社会の落とし穴
情報化社会というと、何となく高度な技術に支えられたバラ色の未来を連想させる言葉であるが、考えてみれば捉えどころのない言葉ではある。大体、縄文時代の人間たちだって、あっちの山には猪がいるぞ、とか、こっちの林には松茸が生えているぞ、といった「情報」に基づいて毎日の糧を探し求めていたはずであるし、60年前の太平洋戦争では、日本は情報を軽視して負けた、などと言われているのであるから、今さら改めて「情報化」などといって、何か特別な時代であるかのように考える必要もなさそうである。
情報化社会という時、1980年にAlvin Toffler (アルビン・トフラー)という人が書いた書物「第3の波」を参考にすると定義しやすい。A.トフラーは人類の歴史を大きく3つに分けて、我々の文明は、第1の波=農業革命、第2の波=産業革命(工業革命)、第3の波=情報革命、という3つの波を経験してきたと述べている。
先ず我々の祖先は、農業革命で農作物の栽培と保存技術を獲得したおかげで、食糧の備蓄が可能になり、人間は慢性的な飢えから救われたばかりでなく、国家と呼ぶにふさわしい大集落を形成するに到る。
続いて18〜19世紀の産業革命は、蒸気機関に代表される工業技術の発展により、人類に大量生産・大量消費の時代をもたらした。工業技術の進歩は農業の飛躍的発展(農耕機械や化学肥料)をも促したために食糧増産が一気に進み、大規模な人口を擁する近代国家群が成立する。しかも第2の波の影響は単に技術革新にとどまらず、マス・コミュニケーション、マス・プロダクションという言葉によく示されているように、画一化された情報や文化の伝達、画一化された商品の大量流通という現象を生み出し、それ以前の農業社会とは似ても似つかぬ中央集権的な社会が完成したのである。
そしてA.トフラーによれば、現在は第2の波の時代から第3の波に移行する、人類の歴史の中で3番目の大きな変革点にさしかかっているのである。第3の波は情報革命ともいわれ、電子技術の発達によって情報ネットワークが緊密に整備され、生産と消費も、文化や芸能も、その他の社会のあらゆるものが個人や小グループごとに細分化していくのである。
第3の波の特徴を第2の波と比較すれば、中央集権から地方分権へ、大量生産から個別注文生産へ、画一化された情報の一方的伝達から個別に選択された双方向の情報伝達へ、ということになるが、これらは1980年代にA.トフラーの「第3の波」を読んだ頃は、ちょっとピンと来ない部分も正直あったけれど、21世紀を迎えた現在、あの本の内容を思い出してみると、なかなか優れた文明の分析だったと感嘆せざるを得ない。こういうことを可能にさせたものは、言うまでもなくパソコンだとか携帯電話だとか双方向テレビだとかいう高度に発達した情報機器である。もしかしたらA.トフラーの言う第3の波はすでに成就したと考えてもよいかも知れない。
ここで情報化社会というものがある程度定義できたと思うので、この新たな社会における落とし穴について考えてみる。
第3の波の情報革命を支える電子技術が生み出した数々の情報機器は、もともとは政治や産業や文化などの「情報化」を目的に開発されたものである。ところがこういう文明の利器は、その性能が高ければ高いほど、開発者たちが当初に予期した以上の広がりを見せて利用されるようになるものである。例えば携帯電話などという機械は、もともとはビジネスマンや現場の技術者たちが、わざわざ電話口まで行かなくてもリアルタイムで情報の授受が出来るようにと開発されたものであろうが(昔はトランシーバーという大仰な機械があったものだ)、最近の一般大衆が公共の場で長々と喋りまくっている愚にもつかない内容を聞いていると(別に聞きたくて聞いているわけではない)、その精巧な機械はそんな馬鹿話をするために作られたわけじゃないぞ、と言いたくなることも多い。
つまり第3の波をもたらした高度な電子機器は、今や単なる情報伝達機器の域を越えて、人々の日常的なコミュニケーション手段となったのである。携帯電話、携帯メール、パソコンの電子メール、ホームページの掲示板…、私くらいの年配者でも利用しているこれらの電子機器のうち、第2の波の時代からも漠然と「未来の道具」として想像できたものは携帯電話くらい、これは従来の電話機と使用法がほとんど同じだからであるが、その他のものはまったくと言っていいほどコミュニケーションの概念を根底から覆してしまった。その証拠に、私よりさらに年配の世代の方々でも携帯電話は楽々と使いこなせるが、電子メールとかホームページになると、私と同世代の人たち(つまり21世紀初頭の中年世代)の中にも使えない、あるいは使いたがらない方々が多いのである。
これは何故かというと、直接の音声によらない、テキストファイルに変換された内容を、通信回線を介して発信する、という動作に心理的な抵抗があるのではなかろうか。
先ず、自分が相手に伝えたい内容をテキストファイルに変換するという動作。これはワープロを使うようになった人なら何とかこなせる。あくまで手書きにこだわる人々はこの段階で脱落するが、まあ、私の世代以下の人たちなら、職業上の必要からかなりの人が否応なく順応させられていると思う。
だが次に主としてテキストファイルの形で作り上げたものを回線に向かって発信する。これはなかなか心理的な抵抗が大きい。それは必ずしもパソコンや携帯メールという機械に対する無知から来ているのではない。そんなことを言い出せば、例えば従来の電話機がどうやって人の音声を電気信号に変えているのか、その原理や仕組みまで理解している人は果たしてどれくらいいるだろうか?
「古き良き第2の波の時代」の人々が電子メールに馴染めない理由。そこには情報化社会の個人間コミュニケーションの落とし穴に関するヒントが隠されている。第2の波の時代までの人間は、必ず目の前にいる相手に向かって直接に話をしたのである。電話機だって相手の姿は見えないが、相手の声はリアルタイムで自分の耳に届く。だからテキストファイルでやりとり出来るような内容のコミュニケーションについては、直接に話をしているのと同じだ。
人類は言語を獲得して以来、コミュニケーションは目の前にいる相手に直接内容を伝えるのを原則としていた。いや、それしか出来なかった。人類は複雑な内容を議論する時も、喜びや悲しみや怒りなどの感情を伝える時も、自分の要求を表わす時も、常に相手を目の前に置いて言語を駆使してきた。
相手を目の前に置いて話すということは、自分の喋りたい内容を一方的に相手に送り付けることではない。自分の発声・発語に対する相手の反応を注意深く受け止めることも同時に行なっているのだ。つまり相手の返事だけでなく、相手の表情・動作・顔色といったさまざまな要素を観察し、分析し、それに応じて自分の次の発声・発語内容、さらに自分の表情や動作までも調節して、相手が自分とのコミュニケーションを出来るだけ受け入れやすくなるよう工夫しているのである。
こういうことは直接のコミュニケーションの場では誰でも無意識のうちにやっていることであるが、私の小児科医時代の恩師、小林登先生の研究によれば、人間の赤ん坊は生まれて間もなくから、周囲の大人たち(特に母親)との間で将来のコミュニケーションの初歩訓練を始めているのだそうだ。母親と赤ん坊の相互の発声・発語や体の動きの間には明確な相関が観察されるという。自分が喜べば相手も喜ぶ、相手が喜べば自分はもっと嬉しくなる、といった人間同士の相互の関係が、最初は「バブバブ」という原始的な発語や体の動きでしかないが、成長につれてどんどん複雑な言語や感情に裏打ちされた堅固なものになってくるのである。
こうして人類が永年かけて完成させてきた高度な言語を介するコミュニケーションの基盤を、電子技術は根底からブチ壊してしまった。電子メールなどは時刻や場所の指定などのような単純な連絡事項の伝達程度のことであれば、従来の郵便や電話機などよりもはるかに便利である。こちらから伝達事項を相手のアドレスに送信しておけば、相手は自分が便利な時刻にそれを閲覧することが可能で、電話機のように忙しい相手をわざわざ電話口に呼び出さなくても済むからだ。
しかし複雑な意見や感情を相手と交し合う時は、この利便性が却って仇になる可能性が大きい。人間は複雑な内容の会話をする時、無意識のうちに相手の表情や声色を観察しながら、議論が円滑に進むように自分の方もさまざまな表情や声色で言語に色付けをしている。これは幼少時の母親との初めてのコミュニケーション以来、営々と培ってきた技術を駆使しているのだ。
だが議論の内容を無味乾燥なテキストファイルに変換して、相手のアドレスに送り込むだけの電子メールを介したコミュニケーションでは、この表情や声色を駆使した技術はまったく活かされてこない。それでパソコンや携帯でのメールは、時として深刻な(しかし避けられ得る)感情的対立を引き起こすことになる。
例えばある人が、今日は何事も万事うまく行ったと有頂天になってテンションも高くなった時に友人にメールを出したとする、ところが相手の友人はたまたま悪い事が重なって気分も落ち込んでいた。気分高揚した友人から受け取ったテキストファイルの文字は、非常に微妙な作用をもたらすことになるだろう。相手が目の前にいれば、あるいは電話口で直接相手の声を聞けば、普段親しい友人同士なら、ああ今日はあいつちょっと落ち込んでいるな、とすぐに察して、自分の高揚した気分を抑えようとするだろう。しかし電子メールでの会話ではそういう調節はまったく不可能であり、些細な言葉のニュアンスの受け取り方がもとで、深刻な感情的対立に到りかねない。
長崎県で小学生がホームページでの書き込みを巡って感情的に対立し、友人を殺してしまったという悲惨でやり切れない事件が起こった。識者がいろいろコメントしているが、元々は第3の波がもたらした電子機器が人間本来のコミュニケーションの形態を破壊してしまったことが原因である。大人でさえネット上でのテキストファイルの交換で気まずい思いをすることが多いのだから、多感な女の子たちがあのような事件の当事者になってしまったことも、まんざら予想も出来ないことではなかった。
ネット上で会話をする時は、(笑)とか(^-^)とか付け加えれば良いと言う人もいるが、所詮はこれらとてテキストファイルである。(笑)だって微笑から大笑、苦笑、冷笑、嘲笑までいろいろある。
第3の波=情報革命を支えるために開発された電子機器が、当初の予想を越えて個人間の不可欠なコミュニケーション手段になってしまった現在、複雑な内容の会話をネット上で交わすのは止めましょう、と警告するのもナンセンスだ。人類がテキストファイルで円滑に会話を出来るようになるまでに、これから数十年〜数百年の訓練期間が必要なのだろうか?
続・情報化社会の落とし穴
人類が言語を獲得して以来、営々と訓練してきた直接対話によるコミュニケーション法が破綻の危機を迎えたことは、情報化社会の大きな落とし穴の一つである。電子メールは、従来の言語コミュニケーションの良さ(利便性、即時性)と、手紙などの文字コミュニケーションの良さ(永続性)を併せて持った新しい伝達手段だと言われたこともあったが、それは同時に両者の悪さを併せ持ったとも言えるのである。表情や声調を伴わなければ単なる悪意にしか読めない文章が、相手の電子媒体の中に半永久的に残ってしまう可能性があるのだから…。
ところで光瀬龍というSF作家がいた。1960年代に次々と発表された「宇宙年代記シリーズ」を、当時中学生だった私は貪るように読んだもので、あまりに果てしない、あまりに虚無的な内容に、高校生になる頃には次第に敬遠するようになってしまったが、間違いなく私の中学時代の最大の愛読書だった。このシリーズは、未来の宇宙に生きた人々の物語を、年代記の形をとって叙事詩的に書き連ねた一連のSF短編小説で、その内容の幾つかは40年を経た現在でも鮮明に覚えている。そしてそれらの中に、情報化社会の終末とでもいうべき恐るべき未来像を予言しているように思える作品があったので紹介しておきたい。
(1)ソロモン1942年 (1963年10月発表)
題名からいうと未来の宇宙年代記になっていないが、これは実は太平洋戦争の史実とはあまり関係がない。ソロモン海域で日米の航空隊の決戦があるのだが、この戦いで発散される憎悪のエネルギーが、我々の世界と次元を超えて重なり合っている別の世界に影響を及ぼすという物語である。次元を超えて重なり合う世界というのは、SF小説の重要なモチーフの一つであるが、SFに興味の無い人にはクドクド説明するのも大変なので割愛させて頂く。また別に知らなくても今回の話には関係ない。
我々の世界と重なり合う別の世界では、「神の塔」と呼ばれるプロバイダーのような機械が、人々の脳内の思念を増幅して、それを目指す相手の脳に送り込んでくれるおかげで、人々は言語によるコミュニケーションをしなくても済むようになり、テレパシーのような意思伝達が可能になっていた。ところが我々の世界で起こった空中戦で放散される憎悪のエネルギーがこの世界の「神の塔」の機能を麻痺させてしまい、互いのコミュニケーションが出来なくなった人々がパニックに陥って、暴行、放火、略奪などの暴動を起こすという筋書きだった。
テキストファイルではなく、テレパシーのような進歩した伝達手段ということであるが、集中的に管理された便利な個人間コミュニケーション法に依存して、人間が本来持っていた言語を使用しなくなった社会、という視点で考えてみると、この作品は将来の情報化社会が抱える重大な弱点を暗示しているように思える。
第2の波の時代では、大量生産、大量消費のラインが一括管理されていて、情報も新聞やラジオ・テレビなどで一方的に大量伝達されたものだったが、個人間の情報交換(お喋り)の方法は各個人の耳と口と表情等に完璧に依存していた。手紙は郵便屋さんに配達して貰わなければならないし、電話をかけるには電話局が必要だったが、個人間の情報交換が手紙や電話に依存する程度は多寡が知れていた。
ところが第3の波によって情報化社会になると、個人間のお喋りもまた電子機器に依存する比率が増えてきている。雑踏を歩きながら携帯電話で話している若者の会話を耳にしたり、電車の中で携帯メールを打ちながらニヤニヤしているお嬢さんの姿を目にしたりすれば、敢えて証明する必要も無いと思われる。そしてこのような個人間のお喋りは、もはや携帯電話会社やインターネット会社のプロバイダーの機能を借りずに行なうことは不可能で、この意味で人々のコミュニケーション手段が中央が一括管理される体制に近づいたのである。
この体制が究極の形になったのが、光瀬龍の「ソロモン1942年」である。もし人々のコミュニケーションをサポートしている機械が故障したら、大衆はおそらくパニックになるであろう。もし現在でも、日本国内のすべての機種の携帯電話が1週間まったく通じなくなったら、特に若者たちのパニックは大きいに違いない。
さらに光瀬龍はこの作品に恐ろしい予言を含ませている。舞台となった異郷世界における「神の塔」は、人々のさまざまな思念を読み取って相手に伝えるだけでなく、人々の思念の中に潜む邪悪な観念を自動的に除去しているのだという。だが例えば人を殺したい、とか、あいつの物を盗みたい、といった観念を除去してくれるだけなら結構だが、時の権力者がこの機能を悪用したらどうなるか。光瀬龍はこの点には何も触れていないが、この問題はさらに情報化が進んだ我々の世界にとっては、きわめて危険な脅威となるであろう。
(2)辺境5320年 (1963年9月発表)
これが本来の典型的な「宇宙年代記」のタイトルである。他にも「宇宙救助隊2180年」とか「墓碑銘2007年」とか「落陽2217年」などがあり、こういうタイトルのつけ方にも中学生の私は夢中になっていた。
さて「辺境5320年」では、宇宙の辺境にある植民惑星都市に異変があって調査に向かうと、その都市の全住民はそれぞれ自分自身の肉体的・心理的特性を1枚ずつのカードにインプットして、永劫の時間の流れに抗するかのように永遠の存在と化していたのだ。
これがどういうことかお判りだろうか。調査員が宇宙の辺境で目にしたものは、1枚のカードと化した住民の姿なのである。初めて読んだ当初はあまりの異様な結末にショックを覚えたものだったが、21世紀初頭になった現在、光瀬龍は科学の面だけでも2つの重大な予言をしていたことになるのだ。
一つは個々の人間の肉体的特性(=遺伝情報)がデジタル情報として記録できるということ。言うまでもなくヒトゲノム解読計画が完遂されれることを予言している。さらに心理的特性の記録についても、将来大脳を中心とした中枢神経系のニューロンの連結様式が解読されて個々の人間の性格や記憶や思い出などもすべてデジタル情報化されれば可能である。(少なくとも54世紀までには…!)
もう一つの予言は、ヒトの遺伝情報のような莫大な情報を収納できる小型で軽量の電子記憶媒体が開発されるということ。作品では1枚の磁気カードとなっているが、現在のDVDなどを考えれば光瀬龍の予言はすでに20世紀中に成就したと言っても良いであろう。
さて一人一人の人間が自らを電子媒体の中に「情報化」してしまう。これは情報化社会の究極の選択ではなかろうか。
もう一度、A.トフラーの文明論に戻ってみよう。先ず第1の波で農業革命の結果、人類は食物の増産と保存に成功した。これで人類は農作物の蓄積した地域に、それなりの人口を抱えた国家を構えることが可能になった。この農業社会にはもちろん軽工業や商業もあったが、それは農業によって蓄積した富に見合うだけのものでしかなかったし、人口も漸増したものの爆発的増加ではなかった。
次に第2の波で産業革命が起こって工業社会になると、大量生産・大量消費が国家経済の原則となる。工業化した農業によって食糧も飛躍的に増産され、膨大な人口を支えられるようになった。こうなると大勢の労働者が工場に働きに出て大量の工業製品を生産し、大量の商品を大勢の消費者に売りつけることが至上命題となる。場合によっては戦争で植民地を獲得して、国家の経済基盤を拡大させる必要も出てくる。この時代の国家の標語は「富国強兵」である。大量の労働者と大量の兵隊が必要だ。そしてその母体となる大量の人口を養うことは工業化した農業による食糧増産によって可能だった。当然、「生めよ殖やせよ」となる。
第1の波、第2の波の共通点は何か。それは技術革新によって食糧が飛躍的に増産され、それぞれ農業社会、工業社会の基盤を支えるだけの人口を養えるようになったことである。ところが第3の波には食糧の増産は伴わない。たとえ世界中の人々が高度な電子機器を操作して、互いに情報を交換し合ったところで、人類の生物学的生存を支える食糧の生産が増えることはないのだ。
しかも第3の波では、画一化された大量生産から、個別のニーズに応じた注文生産の時代に移行するということである。そうすると例えば10トンの小麦からパンを作ることを考えると、すべての小麦を画一化された規格品のコッペパンにしてしまうのが、最も無駄のない材料の使い方である。個別のニーズを睨んで、一部は食パン、一部はフランスパン、一部は菓子パンなどと分けていくと、材料にも無駄が出るし、パン職人の労働量にも無駄が出て、同じ10トンの小麦で養える人口は、第2の波の時代よりも少なくなるのは確実だ。
つまり原始社会よりは農業社会、農業社会よりは工業社会の方が、多数の人口を養うことが出来たし、また労働力や兵隊を確保するために人口を殖やさなければならなかった。しかし情報化社会では大量の人口を養うことは不可能に近いし、個別のニーズにより密着してキメの細かいサービスを提供していくことになると、大量生産工場の労働者も要らないし、植民地獲得のための兵隊も要らない。基本的に第3の波を経た後の情報化社会では、少子化による人口減少が基本のはずである。現在の日本が少子化、少子化と大騒ぎしているのは、労働者や兵隊を殖やして富国強兵を目的とするものではなく、ただ次世代の者たちに年金の財源を担わせたいと考えているだけである。
しかし考えてみるがいい。特に都市部に住む人々にとっては顕著なことだが、地方に住む人々だって、自分のまわりにいる知人が何の職業に就いているかを考えてみれば、実際に物を作っている人々、特に食糧を生産している人々の比率は驚くほど少ないに違いない。そして大部分の人たちは製品を流通させたり、資金を流動させたり、サービスや娯楽を提供したりするような職業に就いているのだ。医師や教師もすべてこの範疇に入る。
人類の生物学的生存を直接支える職業(つまり食い物を作る仕事)にタッチしていない人々の頭数がいくら増えたって、年金の財源問題は決して解決しないどころか、人類の生存そのものも危うくなる。情報化社会における大命題は、いかにして人間の口を増やさないようにしながら情報サービスを充実させていくかということになるから、その究極の解決法はもうお判りだろう。光瀬龍が「辺境5320年」で予言したように、人間自体が生物学的存在であることを放棄して、自らが情報化されることである。
高校時代以降、私は光瀬龍のSF小説の虚無的な内容や文体の暗さに辟易して敬遠するようになってしまったが、やはり作品の中に潜んでいた予言めいたものにはずっと心を惹かれていたようだ。その光瀬龍も1999年7月7日、七夕の日に逝去されたという。(合掌)
映画の海戦シーンについて
スペクタクル映画としては「スターウォーズ」とか「ハリー・ポッター」などのSFやファンタジーも楽しいが、過去の世界を舞台にした歴史物もなかなか興味深い。西部劇や時代劇なども広い意味で歴史スペクタクルと呼んで差し支えないと思われるが、いずれもSFやファンタジーのような架空の状況と違って、舞台となる各時代の背景をかなり正確に考証しなければ興醒めとなってしまう。
例えば戦国の合戦シーンに送電線の鉄塔などが写っていては台無しだし、西部劇に高速道路などもっての他であろう。ベテランの製作者たちは、おそらく空撮シーンでもヘリコプターの影が入らないように苦心しているに違いない。
とにかく映画の舞台となっている時代にあってはならぬ物体が画面に入ってしまっては、観客はシラけてしまう。1984年に日本で作られたある戦争映画では、太平洋戦争中の南方の飛行場に、曲面のフロントガラスを備えた、どう見ても1970年代製のトラックが走っていたり、空襲警報下の日本の都市に横断歩道があったりして、まったくシラけてしまった。しかも功績抜群の兵士や部隊の名前を全軍に布告するために司令部から授与される「感状」を、「感謝状」と勘違いしているとしか思えない滑稽な場面もあったが、こういうのは論外である。
こういうお粗末な映画は別として、陸上のスペクタクルシーンは、ある程度お金をかければかなり見応えのある場面を作れそうだとは思っているが、これに対して、特に近代以降の時代に設定された洋上シーンで迫力を出すのは難しく、映画製作者泣かせではなかろうか。
映画の海戦シーンと言えば真っ先に思い出すのが「ベン・ハー(Ben-Hur)」(1959年)のローマ艦隊と海賊船団の戦いである。実物大のガレー船のセットで、鎖に繋がれた奴隷たちがローマ兵の打ち鳴らす太鼓に合わせてオールを漕ぐシーンは圧巻だったが、敵味方の軍船が入り乱れて突撃し、次々に炎上するシーンはいかにもミニチュアの船で撮影したというのが判ってしまう。
陸上のシーンで深紅のマントや銀色の甲冑を身につけたローマ兵の大行進がフル・スクリーンの実写で迫ってきた後だけに、この海戦シーンの製作担当者には気の毒であった。軍船のミニチュアもオールが自動的に動いたり、矢が飛び出したりして、なかなかよく出来ているのだが、やはり本物の迫力にはかなわない。船の撮影角度を変えたり、船が写るシーンを必要最小限の時間に切り詰めたりして、観客にミニチュアであることを悟らせないための工夫は並大抵ではなかっただろう。
こうなるとやはり「本物」の艦船を使用しなければならなくなる。実物とミニチュアを巧みに組み合わせて、観客にある種の錯覚を起こさせ、どのシーンがミニチュアであるかを悟らせないようにするのである。上記の「ベン・ハー」の海戦シーンも当然ミニチュアと実物大セットとの組み合わせなのだが、オールで動くガレー船のミニチュアは、やはり当時としては技術的にアラが出てしまうのも当然だった。
2004年に公開された「マスター・アンド・コマンダー(Master and Commander)」は19世紀初頭のナポレオン戦争時代の帆船同士の海戦を描いた映画で、英国軍艦サプライズ号の全長7.6メートルのミニチュアが使われたというが、帆に風を孕む帆船のミニチュア化の技術は相当に難しいと思われるにもかかわらず、私はどのシーンがミニチュアだったのか悟らないまま終わってしまった。この半世紀間のミニチュア技術の進歩に驚かされる。
ミニチュアと実物の組み合わせは、もちろん近代以降の甲鉄艦の時代の海戦映画にも用いられている。「ビスマルク号を撃沈せよ!(Sink
the Bismarck)」(1960年)ではドイツ戦艦ビスマルクはもちろんミニチュア、返り討ちに会うイギリス戦艦フッドもミニチュアだが、撮影時にはまだ健在だったイギリス海軍の巡洋艦や駆逐艦が随所に実写で登場してきて、チャチなミニチュアシーンをよく補っていた。
また「戦艦シュペー号の最後(The Battle of the River Plate)」(1956年)では、ドイツ戦艦シュペー号を追跡するイギリス艦隊は大部分が実戦当時と同クラスの巡洋艦・駆逐艦、さらにシュペー号の方もアメリカ軍艦を替え玉にした実艦が使用されていて、艦船マニアが見れば艦型が違うのは一目瞭然だったのだが、映画の迫力という点からは満点の出来だった。もちろん炎に包まれて沈没していくシーンのシュペー号はミニチュアだったが……。
海国日本の海戦映画では、やはり吉田満氏の原作を映画化した新東宝の「戦艦大和」(1953年)を先ず挙げなければならないだろう。原作者の吉田氏がある日系人から、この映画の戦艦大和のミニチュアがチャチだと言われたことを書いた文章があり、その話に関連して興味深い逸話を紹介しておられる。実はこの映画も臨場感を出すために、ミニチュアと実物を組み合わせて製作する予定になっていたのだそうだ。もちろん実物の戦艦大和は戦争中に沈んでしまっているから、代艦として白羽の矢が立ったのがアメリカ海軍の戦艦ミズーリ号。日本の降伏調印式が行なわれた軍艦である。ミズーリ号は2本煙突で大和より1本多いが、艦首方向から撮影すれば、ほとんどそっくりだったという。
アメリカは気前が良い国で、上記の「戦艦シュペー号の最後」でも、旧敵国ドイツ戦艦の替え玉に自国の軍艦をポイと貸してくれたように、ミズーリ号が大和に扮する話にも最初は大いに乗り気だったそうだ。ところが新東宝の映画製作者が、艦首に菊の御紋章を付けさせてくれと頼んだ途端、激怒したアメリカ海軍関係者は態度を硬化させ、話は一転してボツになってしまったらしい。こうして「戦艦大和」はミニチュアだけで撮影しなければならない羽目になったのである。
ついでにこの映画の原作となった吉田満氏の「戦艦大和の最期」であるが、この中に米軍機の攻撃で左舷に傾いた大和が傾斜復旧のため、右舷機械室と罐室に注水する場面が描かれている。機関科の兵員がまだ作業に没頭しているこれらの区画に海水を注入して、反対舷への傾斜を元に戻すためである。
機関科員数百名、海水奔入の瞬時、飛沫の一滴となってくだけ散る
と悲痛な文章が綴られているが、実はこれが史実かどうか疑わしいという論議がある。そのような場合の艦内注排水などを命令する防御指揮官たる副長が否定しているのだ。もちろん副長の記憶違いということもあろうし、非情な注水命令を下した良心の呵責から戦後は一切その件に触れなかった可能性もある。大和副長だった能村次郎氏は映画「戦艦大和」のスタッフに加わっており、原作者の吉田氏との間にどのようなやりとりがあったか、今となっては知り得ないことだが興味のあるところである。映画の真実とは、映像の迫真だけではないという一例か。映画「戦艦大和」には機械室注水のシーンは採用されていない。
新東宝の「戦艦大和」ではおそらく全長せいぜい2〜3メートルのミニチュアで撮影を進めたと思われるが、東宝の「連合艦隊司令長官山本五十六」(1968年)では全長7メートルの戦艦大和、13メートルの米空母ヨークタウン、11メートルの空母赤城が登場、さらに「連合艦隊」(1981年)では全長13.15メートルという実物の1/20の戦艦大和が使用された。この1/20の戦艦大和は撮影終了後、しばらく東武動物公園の池でショーに使われていたが、その後はお台場の船の科学館に展示されている(写真↓)。一応ミニチュアとは言っても、3人乗りで6ノットで航走し、当時の運輸省かどこかに「船舶」として登録されたはずだ。
 しかし使用するミニチュアが大きくなれば、それだけ真に迫るかというと、なかなかそうは行かないところが洋上シーンの難しさである。戦艦大和を1/20で作ってみても、水と火は1/20にならないから、艦首が切り裂く波や、大砲発射の時の爆煙や、艦上に炸裂する炎などと比べると、絶対に本物のようには見えないのだ。特撮技術者たちの話によると、火と水だけはどうしても誤魔化せないというのが彼らの泣き所だそうである。だからこの1/20の大和も、白昼堂々と大海原を行くシーンは無かった。
しかし使用するミニチュアが大きくなれば、それだけ真に迫るかというと、なかなかそうは行かないところが洋上シーンの難しさである。戦艦大和を1/20で作ってみても、水と火は1/20にならないから、艦首が切り裂く波や、大砲発射の時の爆煙や、艦上に炸裂する炎などと比べると、絶対に本物のようには見えないのだ。特撮技術者たちの話によると、火と水だけはどうしても誤魔化せないというのが彼らの泣き所だそうである。だからこの1/20の大和も、白昼堂々と大海原を行くシーンは無かった。
東宝の特撮映画と言えば、特撮の神様と呼ばれた故円谷英二さんを忘れるわけにはいかない。我々の世代が少年だった頃、黒澤明監督は知らなくても、円谷英二特技監督を知らない男の子はいなかったのではないか。
円谷英二さんは「ゴジラ」や「モスラ」などの怪獣映画、「妖星ゴラス」や「海底軍艦」などのSF映画の特撮シーンを多数作り上げて、「世界のツブラヤ」としてその名を轟かせ、当時の多くの少年たちの憧れの的であったが、やはり円谷さん本領発揮は戦争映画の特撮シーンであっただろう。
1960年に公開された総天然色の東宝映画「太平洋の嵐」の洋上シーンは、まさにこれぞ特撮というべき秀逸なもので、同じ年にモノクロで公開された前記の「ビスマルク号を撃沈せよ!」のミニチュアシーンをはるかに凌駕している。CG(コンピュータ・グラフィクス)の技術もない時代に、どうしてこれだけの映像を作ることが出来たのか、未だに不思議でならないほどの出来栄えで、いかに円谷監督のチームが優れていたかを示す映画ではあるが、著作権の関係上、ここにお見せできないのが残念である。ちなみに1976年、ハリウッドの戦争映画「ミッドウェイ(Midway)」を見に行った時、戦闘場面で十数年も前の「太平洋の嵐」の特撮シーンがふんだんに使われていたのに驚き、改めて円谷監督の偉大さに感服したものである。
さて映画界に革命をもたらしたと言われるCG(コンピュータ・グラフィクス)技術がふんだんに使用されるようになってから、従来の特撮技術はすっかり過去のものになったような観がある。「ジュラシック・パーク」でまるで本当に生きているように見える恐竜に驚かされたのが1993年、その後もCG技術に不可能な映像はないことが次々と証明され、洋上シーンでも1997年の「タイタニック(Titanic)」の海難シーンは完璧なものであった。
しかしこうなると不思議なもので、CG技術による完璧なスペクタクル・シーンをいくら見せられても何だか物足りないと思うようになった。従来の特撮映画というものは、ウソだと判っているシーンをどれほど本物らしく見せてくれるかという期待があったのだが、最初から本物らしく見えることが判っているCGのシーンをいくら見せられても、却って当たり前としか思えないのである。つまり従来の特撮映画は、推理小説の作者と読者の知恵比べのような緊張感が、特撮スタッフと観客の間にあったような気がする。円谷監督の特撮映画が今、無性に懐かしい。
こういう特撮の戦争映画に代わって、ここ十年ほどの間に、アメリカ国防省や防衛庁戦史室などに保管されていた記録フィルムを編集して、「真実の映像」で戦史を振り返ろうという企画が出回るようになった。私もその幾つかを見る機会に恵まれたが、こういういわゆる「真実の映像」が必ずしも真実でないことを知ってしまった。
例えば、昭和19年のマリアナ沖海戦に出撃した日本の機動部隊と称する「真実の映像」に、昭和17年のミッドウェイ海戦で沈没した空母赤城と飛龍が写っていたりする。この2隻の空母だけは艦橋が左舷側にある特異な形態をしており、どんなに不明瞭な映像であっても艦船マニアを欺くことは出来ないのだ。こういう偽物が「真実の映像」として、何も知らない視聴者に届けられている。
アメリカ国防省から出された映像の中にも、ミッドウェイ海戦で撃破された空母ヨークタウンの映像と称して、沖縄戦で特攻機に突入されたエセックス級空母の映像が堂々と販売ルートに乗っているものもある。
歴史の真実とは何か。ネームヴァリューのある機関や執筆者や製作者が出してきたものなら、何の疑いもなく真実として受け入れてしまう風潮を改める必要を改めて痛感させられる。
映画の空中戦シーンについて
前項で映画の海戦シーンを書いたついでに、空中戦シーンはどうかとメールを下さった方がいる。そこで私が見た空中戦映画で記憶にある限りのことを書いてみようと思うが、これで最後である。陸戦シーンについて問われても、これは古代の三国志やトロイ戦争から、近世以降のヨーロッパ・ロシア・太平洋における第二次世界大戦や、朝鮮戦争・ベトナム戦争・湾岸戦争の陸戦まで、膨大な数の戦争映画が作られているので、これはいちいち書き出したら収拾がつかない羽目になってしまうことは目に見えている。源平合戦や戦国合戦なども陸戦なのだ。
さて私が空中戦の映画について、最初はそれほど書く気に気にならなかったのには理由がある。特に外国の空中戦映画は、本物の飛行機を飛ばして撮影するものが多く、本物さえ使用すれば迫力のあるリアルな映画が出来て当たり前だから、書いても面白くないのだ。
特に戦後四半世紀を過ぎた1970年頃、アメリカ、イギリス、旧ソ連の戦勝国において、第二次世界大戦を実物レベルで映画に残そうという動きが期せずして同時に起こり、それまでの戦争映画の常識を覆すようなスケールの大きな作品が相次いで完成した。
その先陣が1969年の「空軍大戦略(Battle of Britain)」で、これはナチスドイツの英本土空襲に立ち向かったイギリス空軍の物語で、イギリスの名機と言われたスピットファイア戦闘機は本物、ロンドンに襲いかかるドイツ空軍機も、スペイン空軍が当時もまだ現役で保有していた実物をゴッソリ買い込んで撮影に使用したというから話は大きい。何でもスペイン空軍は映画会社に旧ドイツ空軍機を売却した金で、新鋭のジェット戦闘機を新調したらしい。こういう時代物の貴重な旧軍用機の実物が映画撮影のために惜し気もなく空中で破壊され、あるいは大地に激突し、あるいは海面に叩きつけられていくのである。こんな金のかかったシーンに、ミニチュアの特撮映画がかなうわけがない。
1970年の旧ソ連の「ヨーロッパの解放」も凄かった。この時は全5部作のうち第1部「クルスク大戦車戦」と第2部「ドニエプル渡河大作戦」の2部が公開されたが、いずれも実戦さながらの実物の戦車と戦闘機が画面を埋めつくし、まさに圧倒される思いであった。
このように飛行機と戦車は実物が残っていればそれを使用できるし、実物が無くても実物大のイミテーションを作るのにそれほど予算の制約もかからないであろう。第一次世界大戦の空中戦を描いた名画「ブルー・マックス(the
Blue Max)」(1966年)では英独の複葉戦闘機を完全復元して、1910年代の空中戦を見事に再現している。このフィルムの一部は1971年の「レッド・バロン(Von
Richthofen and Brown)」にも使用されていた。
このように飛行機と戦車は、大きな映画会社なら比較的簡単に実物や完全復元品を手に利用することができることが、海戦に比べて迫力のある陸戦シーンや空中戦シーンが多い理由であろう。何しろ実物大の軍艦の復元品はおいそれと簡単には出来そうもない。
ところが実際にこれをやったのが真珠湾攻撃を描いたアメリカ映画「トラトラトラ!(ToraToraTora!」だったのである。真珠湾のアメリカ戦艦や航空基地をはじめ、日本の戦艦長門や空母赤城の実物大セットまで作って、あくまでもリアリズムにこだわった作品であった。戦後四半世紀を経て戦勝三大国が製作した戦争映画のうち、この「トラトラトラ!」が、「空軍大戦略」や「ヨーロッパの解放」に比べて最も手間がかかったのではなかろうか。
当初、この映画の日本側監督はあの黒澤明氏であったが、こちらもあまりにリアリズムにこだわるあまり、1000人以上のエキストラに海軍将兵気質を叩き込む目的で、朝から晩までラッパで動く規律正しい生活を何週間にもわたって続けさせ、いつまで経っても撮影に入らず予算ばかり食っていたのが、黒澤監督解任の原因であったと、後になって聞いたことがある。
ところでこの「トラトラトラ!」、日米の戦艦や空母のセットまで作ったからには、飛行機も本物を使いたい。ということで、アメリカのP40戦闘機やB17爆撃機はすぐに見つかったが、問題は日本の零戦、99式艦上爆撃機、97式艦上攻撃機である。敗戦で完膚なきまでに壊滅した日本海軍の軍用機がそんなに残っているはずはない。戦後アメリカで復元されて飛行可能な零戦も何機かはあるらしいのだが、真珠湾を攻撃した日本機の大編隊の再現など不可能であった。
初めスタッフは、南方の密林に眠る日本軍機の残骸を収拾して実物を復元することも考えたらしいが、あの高温多湿の古戦場に20年以上も放置された飛行機を何十機も元通りに復元するなど、素人が考えても莫大な費用と手間がかかる無理な話である。もしこの計画が実現していたら、これは現在も貴重な資料となっていたことだろうが、さすがのアメリカ映画界も諦めざるを得なかった。
そこで白羽の矢が立ったのが、ノースアメリカンT6SNJテキサンとバルティーBT13という練習機で、これらを改造して零戦、99式艦爆、97式艦攻の3機種を作り上げたのは、戦争映画ファンや航空マニアの間では有名な話。いずれもちょっと寸詰まりな印象は拭えなかったが、それでもミニチュアではとても考えられないような迫力のある空襲シーンを見せてくれていた。
真珠湾攻撃の映画というと、最近では日本で悪名高かった「パール・ハーバー(Pearl
Harbor)」(2001年)がある。日本機が病院や市街地を爆撃したり、溺者を執拗に銃撃したり、と史実を曲げて徹底的に日本軍を悪玉に仕立てているが、これはナチスドイツ軍や旧共産圏を敵役にした娯楽映画でも常に用いられる手法であるから、それほど目くじらを立てるほどのことではなかろう。
それよりもこの映画の空中戦シーンでは最新のCG(コンピュータ・グラフィクス)が使われているのだが、その出来栄えが意外に期待外れなのである。CGで作られた零戦が、大戦末期に量産された52型の機体であることも多くのマニアが指摘していることなので、ここでは触れないことにしよう。
先ず、あの映画の空中戦シーンが真に迫ってこないのは、CGであるが故の“悪乗り”が原因である。プロペラで飛ぶ零戦とアメリカのP40戦闘機が、まるで「スターウォーズ」の宇宙船同士の戦いのようにめまぐるしく湾内や市街地を飛び回るのは、どう見ても現実感が無い。
またCGで画面にはめ込んだ日米の戦闘機やアメリカ戦艦の影が濃すぎるのも気になった。「スターウォーズ」のデス・スターのように真空の宇宙に浮かぶ物体ならともかく、地上の物体では大気を通したわずかなボケがあるのが自然なのに、「パール・ハーバー」では飛行機も軍艦もあまりに輪郭がクッキリしすぎていた。
さて潤沢な予算に物を言わせて、本物の軍用機を買い揃え、あるいは本物の飛行機を改造したり復元したりして迫力のある空中戦シーンを撮影した外国の戦争映画の話はこのくらいにして、やはり金はかけずに、知恵と器用さで勝負する我が日本の空中戦映画について振り返ってみたい。
ちょっと変わったところでは、1962年に日活が「零戦黒雲一家」というのを作っていたが、これに登場する零戦は、「トラトラトラ!」で零戦に化けたノースアメリカンT6SNJテキサンが、元のままの姿で登場していたと記憶する。だから本来3翅ある零戦のプロペラが2翅しかなかったり、尾輪が引き込まなかったりして、子供心にはあまり面白くなかったが、この映画は結局は石原裕次郎が主演しているので、ファンにとっては飛行機などどうでもよかったのである。後年、リバイバルで放映しているのを見た時は結構それなりに面白かった。
同じ時期、特撮のメッカ東宝でも、もちろん空中戦映画がかなり作られていた。旧日本軍の戦闘機や爆撃機などはほとんど現存していないから、これはもう円谷英二監督を擁する東宝の独擅場だったと言ってもよい。例えば空中で被弾した飛行機が燃え上がるシーンなど、他社の映画では炎がボワッと上方に燃え上がるのだが、これは高速で飛行する機体が炎上する場面としては不自然である。これが円谷監督の手にかかると炎と黒煙がサッと後方になびくのである。
円谷監督は空中戦シーンにもかなりのアイディアを駆使しておられ、例えば飛行機のミニチュアの内部に黒インクを仕込んで、それを水槽内で動かすと、まるで黒煙を引いて飛ぶように見えたりする。
また手品のタネのような仕掛けもあって、観客は飛行機のミニチュアは“上から”ピアノ線で吊ってあるだろうと思って見てしまうのだが、その心理を逆手に取り、ミニチュアの“前方から”吊ってカメラの方を横向きに倒して撮影するなど、さまざまな工夫を凝らされていたという。まさに黒澤明監督に匹敵する日本映画界の至宝であった。
東宝の空中戦映画を4本上げる。まず1963年の「太平洋の翼」は、ストーリーとしては最高の名作だった。敗色濃厚の太平洋各地に生き残ったエース級の海軍搭乗員が内地に帰って来て、新鋭機紫電改を駆って米軍に一矢報いるという話で、判る人には判ると思うが、343航空隊の実話を元にしたものである。三船敏郎が演じた千田司令は、もちろん源田実をもじった名前だ。
この映画の冒頭、紫電改の大編隊の飛行シーンがあるのだが、そのミニチュアの中の遠景に当たる部分には零戦が何機か混じっていた。こんなことを目敏く見つけるのも特撮映画を見る楽しみのひとつであった。
この映画を父や弟と見たのはもう40年以上も前になるが、最初の方に日本の飛行機が撃墜されて海面に激突する特撮シーンがあり、その時、観客席の中から「可哀そう!」という女性の悲鳴が聞こえたのを今でもよく覚えている。身内や恋人を航空兵として亡くされた方々がまだ大勢残っておられた時代でもあった。
1966年には「ゼロファイター大空戦」があり、これは確かモノクロで、日活の「零戦黒雲一家」の東宝版といったところ。主演は裕次郎の代わりに東宝の若大将として当時トップスターの加山雄三だった。燃料が無ければ大和魂で飛べ、とムチャクチャを言う上層部に反抗する隊長の役で、合理的に戦わねば勝てぬ、と主張して3号爆弾という新兵器を使って敵機を撃退するシーンも確かこの映画だったと思う。3号爆弾とは、敵編隊の頭上で炸裂させると多数の小型弾頭が飛び散って、一挙に何機もの敵機を葬ってしまうという、実際に日本海軍が使用した兵器であるが、この爆弾が空中で炸裂する特撮シーンは圧巻だったと記憶している。
1970年代に入ると、海外では先に書いた「空軍大戦略」とか「トラトラトラ!」とかが製作されて、空中戦映画は実機を使って撮影するものと相場が決まってしまった感があり、また東宝の特撮陣を支えてきた円谷英二監督も1970年の1月に亡くなってしまい、もう東宝の特撮空中戦映画の時代も終わってしまったかと思っていたら、1976年に作られた「大空のサムライ」は素晴らしかった。これはもちろんかつて零戦パイロットとして日本海軍のエースだった坂井三郎さんの原作を映画化したもので、坂井さんの本に書かれているエピソードの幾つかを改編・脚色したストーリーになっている。ちなみに円谷さんの跡を次いでいたのは川北紘一さんという方だった。
この映画はどこか海外の映画祭で特別上映されて、各国の関係者たちを、本当にミニチュアで撮影したのかと驚愕させ、中には実機を使ったに違いないと、なかなか特撮であることを信じようとしない者もあったという記事もあった。
特に海外の関係者を唸らせたシーンとして記事には3つの場面が挙げられていたが、その3番目はガダルカナル島上空で負傷した坂井さんが奇跡的にラバウルへ帰還する際、愛機の操縦も思うに任せず、いつの間にか背面飛行になっているシーン。2番目は体調不良の搭乗員が離陸に失敗して何か障害物に激突して炎上するシーン。
しかし中でも一番驚いたのは、1番目の爆撃機が宙返りをしながら自爆するシーンで、坂井さんの本にあるエピソードを2つ組み合わせた話であるが、これはどう見ても本物にしか見えなかった。画面の左手から日本の双発爆撃機が黒煙を吐きながら画面右上の方へ上昇していく。そして画面上縁に一旦消えた後、宙返りして降下態勢に入ってきた爆撃機はそのまま空中爆発して四散してしまう壮絶な場面である。
まあ、この宙返り後の自爆シーンも、宙返りの頂点を見せていないから、画面を上端に外れたあたりに何か吊りの仕掛けがあったに違いないと誰でも考えるが、1984年に製作された「零戦燃ゆ」ではそんな推測の入る余地も無いほど完璧な零戦の飛行シーンが再現されていた。この映画に出てきた零戦のミニチュアは、画面の中で宙返りから反転ロール、さらには錐揉み状態での急降下から機首を起こす動作まで、実機が行なったに違いない曲技飛行を自由自在にこなしていたのであった。円谷監督亡き後も特撮技術は年々進歩し続け、空中戦に関してはこの映画でコンピュータ・グラフィクスを使用しない撮影技術の頂点を極めたと言って良いのではなかろうか。
ただ東宝は、これだけ優れた特撮技術スタッフを擁しながら、おそらく会社の上層部の姿勢に問題があったのだろう、所詮特撮は子供騙しという偏見からついに抜け切れなかったように思われる。
「零戦燃ゆ」は封切りに先立って、新宿西口の住友ビル広場に、撮影で使用した実物大の零戦のセットを展示したりして宣伝を盛り上げており、私もそのセットは見に行って映画の出来映えの方も大変期待していたのであるが、映画の中に何とも後味の悪い部分がわずかに見られたのが残念であった。
ひとつは空襲警報の鳴っている日本の都市だったと思われるが、道路に横断歩道が描いてあるのである。(あるいは歩道橋だったかも知れない。)映画の初めの方で、零戦の機体は工場から飛行場まで自動車輸送が出来ず、牛車でゆっくり運んだというエピソードが紹介されていたはずであるのに、何故そんな国に横断歩道が必要なのか。
また南方のラバウル基地に明らかに1970年代製の小型トラックがチョコマカと走り回っていたのも目障りだった。これも映画の冒頭で米軍上層部のセリフとして紹介されていたが、自動車も満足に作れない国が何で零戦のような優秀な戦闘機を作れるのかと、世界を驚倒させたわけであるから、別に飛行場に自動車を登場させる必要もないわけだ。
私はあれだけ見事な零戦の飛行シーンを再現できる特撮スタッフが、わざわざ出さずもがなの戦後の自動車を出して、せっかくの画面の雰囲気をブチ壊すはずはないと考える。特撮スタッフはあくまでリアリティーにこだわる人たちばかりだろうと思うからだ。
たぶん撮影現場を見に来た会社の上層部が、航空自衛隊の基地か何かのイメージしかないままに、どうせならもっと派手で賑やかな画面を作れと、何も知らないくせにスタッフに厳命したのではないか。円谷監督亡き後のことだから、スタッフも上層部には逆らえまい。
しかし「零戦燃ゆ」の最も大きな問題点は、主人公の葬儀の場面の脚本である。開戦から零戦を駆って奮戦した主人公も、本土防空戦でついに戦死するのだが、母親を基地に呼んで葬儀に列席させたうえ、司令官から「感謝状」のようなものを授与し(「感状」と間違っているのではないか)、おまけに母親に「あの子は小さい時から勉強家で優しくて…」などと涙ながらに語らせているのである。
日本がパイロットの人命を消耗品扱いしていたことなども映画の中で紹介しておきながら、何でそんな日本軍が遺族の感情を最大限に斟酌したうえ、他の隊員たちの前で母親の涙を見せるような葬儀を執り行なうのか?当時は息子や夫や父親が戦死しても、遺族は御国の為ですと気丈に喜んでみせなければならなかった時代だったはずである。もっと力のある脚本家だったら、息子の戦死を公報で知らされた母親が、近隣の親しい人たちの前だけで密かに涙を流す場面を設定したであろう。
せっかく円谷監督の伝統を受け継いだ優秀な特撮陣も、所詮特撮は子供騙しとしか考えていない上層部の下では、その能力を最大限に発揮することが出来なかったのではなかろうか。
前項の「海戦シーン」の項の最初の方でお粗末と書いたのは、実はこの「零戦燃ゆ」である。題名を伏せたのは別に東宝に遠慮したわけではない。多少のお粗末は、あの見事な特撮シーンがすべて帳消しにしてくれるのであるが、この映画は柳田邦男原作として公開されているのだ。作品の題名を出せば柳田さんの原作と混同される恐れがあったので、前項では敢えて伏せておいた。特に航空関係で名を知られた有数のノンフィクションライター柳田さんの名前を使って映画を宣伝しておきながら、これだけ随所に手抜きをするというのは、原作に対して大変失礼ではなかろうか。
実は柳田邦男さんの渾身の力作「零戦燃ゆ」三部作のうち第一部の飛翔篇は、この映画の封切りと同時期に出版されているのだ。1984年の夏は、零戦を映画で見るか、本で読むか、と新聞などでも盛んにタイアップして宣伝していたものである。柳田さんの「零戦燃ゆ」は飛翔篇、熱闘篇、渾身篇と続々と出版され、零戦の開発段階から終戦までを網羅した読みごたえのある作品だった。
もちろん原作の映画化権など、法的な問題はすべてクリアしていたに違いないが、やはり柳田さんのそれまでの仕事を知っていたなら、映画製作も特撮だけでなく、東宝の全力を注ぎ込んで欲しかった。これからはコンピュータ・グラフィクスの時代になるが、特撮時代に培われた東宝の底力はまだまだ健在のはずである。戦争映画、怪獣映画、SF映画などでも大人が鑑賞できる優れた作品をこれからも目指して頂きたい。
補遺 「零戦燃ゆ」の主人公の名前は浜田正一といったが、山本五十六の最期の飛行の護衛していたこと、ガダルカナル島で全身火傷を負って内地に送還され、本土防空戦で戦死したことなどから、このモデルは杉田庄一氏であることは明らかである。主人公は最期まで零戦に乗っていたが、実際の杉田さんは紫電改で戦死された。しかし、これは作品の題名から考えて、当然の改編であろう。
均質国家日本の危機
最近、ちょっと気になる光景を見たので、簡単に報告しておきます。実はある学会の会議場に出かけたのですが(もちろん本業の勉強もしてきました)、隣りのホールで幾つもの有名一部上場企業が来春の就職希望者のための説明会や面接を行なっておりました。
会場にはおそらく何百人もの就職希望者が列をなして集まっており、また最寄りの駅からはこれまた会場に向かう何百人もの若者たちが三々五々連れ立って歩いていましたが、驚いたことに、これら何百何千という若者たちが、揃いも揃って黒や紺やグレーの背広のスーツ(女子はいわゆるリクルートスーツ)に身を包み、ピカピカに磨き上げた革靴を履き、髪も適当な長さに刈り上げて調髪しているのです。男子は当然地味なネクタイを全員がしています。赤系統のネクタイを締めていた私が気恥ずかしくなるほどでした。
彼らの中には、きっと昨日まではロンゲ(長髪)を茶髪や金髪に染めてイヤリングをしていた男子もいるでしょう。おそらく女子も含む大部分はジーンズにサンダルという気軽な服装で大学の講義に出席していたに違いありません。それが何で就職が絡んでくると、百人が百人とも同じ服装に統一されてしまうのでしょうか。
これら若い男女は、こういう準規格化された黒っぽい地味な服装をすることによって、「私は他人様と違うことはいたしません」という意志表示をしているように見えます。
そしてこれはきっと、中学・高校時代に学生服やセーラー服の着用を強制されて、「他人と違う事をやってはいけません」と叩き込まれた教育の“成果”を表わしているのでしょう。
これが日本の典型的な姿だと思います。中学・高校で画一化された服装や行動を強要されるのは、社会に巣立つ時に良き規格品たるためなのです。そして幸いに大学へ進学できた者たちにとってのみ、大学の4年間だけが自由に振舞える唯一のモラトリアムなのです。
もちろんどこの国にも、軍隊や職業スポーツや職人技の修行の世界など、決して自由でない職域は少なくありません。しかし商社や情報や機械関連など、自由な発想で競争していかなければならない企業に応募しようという若者たちの服装が判で押したように一様なのはあまりに異常です。こんなことで日本の企業は激しい国際競争に勝ち残っていけるのでしょうか?
ああいうリクルートの場にジーンズやサンダルや茶髪で現れる若者はただの“変人”でしかないかも知れないが、実は自分の確固たる意志と独自性を秘めた凄い“変人”である可能性もあります。現在のようにバブルも弾けて企業も新たな生き残りの道を模索している時代には、そういう人材を採用する方が却って有用でしょう。
しかしただの“変人”の中から凄い“変人”を見抜いて採用する企業はどのくらいあるのでしょうか?この人材の選抜には企業にとってかなりのリスクを伴いますが、ほとんどの企業の人事担当者にはこのリスクを負う覚悟は無いに違いありません。何故なら彼ら人事担当者自身、自分が就職した時には無難な服装で、そつなく面接もこなして入社した社員のなれの果てだからです。そういう人たちは、人材選抜における失敗を恐れるあまり、凄い“変人”を見分けるよりは、間違いのないことだけを念頭に置いて、そこそこ無難な人材だけを選んでいると思います。
だから就職希望の若者たちの方も、少しでも人事担当者の心証を悪くしないために、敢えて他人と違う格好をしないのです。
他人と同じ行動しかしない生物の集団がどのように脆いか、医学・生物学の面から一つ例を取ってお話ししておきます。
抗生物質は微生物から作られる抗菌作用を持った医薬品(現在では遺伝子工学で量産されることが多い)ですが、この抗生物質のお蔭でどれくらい多くの人が感染症から救われたか数え切れません。
しかし抗生物質を使い続けるうちに、この強力な抗菌作用にも対抗しうる能力を持った病原菌(薬剤耐性菌という)が出現することは、今や医学の世界の常識です。別に新種の細菌が出現したわけではありません。従来からいた細菌が抗生物質に対抗する能力を新たに獲得したように見えるのです。
ではどうして細菌は抗生物質に対抗する能力を身につけるのでしょうか?それまではある抗生物質を投与されると皆殺しにされていたように見えた細菌どもが、耐性を獲得するのは何故でしょうか?
それは細菌どもの中にも異端児や変人がいるからです。こういう異端児(異端菌?)や変人(変菌?)は、他人(他菌?)とは同じ物を食ったり同じ行動を取らないために、普段は多数派の陰で細々と生きている日陰者です(人間社会と同じ!)。
ところが抗生物質は、多数派細菌の行動パターンの弱点を突いて、細菌を鎮圧する作用を持っているので、抗生物質が投与されると多数派細菌どもは一網打尽に殺されてしまいます。そうするとどういうことが起こるかお判りですね。
それまでは多数派の陰でヒッソリと生きていた変人(変菌?)たちだけが、抗生物質で狙われる弱点を持っていなかったために生き残り、その子孫だけが増えて薬剤耐性菌となるのです。まさに変人(変菌?)たちのお蔭で、その細菌族は抗生物質の攻撃から免れて繁栄を続けることが出来るというわけです。
さて日本はこういう変人を大切にしてきたでしょうか?まさにバブル崩壊、国際テロ激化など、抗生物質の攻撃に勝るとも劣らないほどの状況の悪化の中で日本が生き残るためには、凄い変人を選抜して大切にすることです。ただの変人では駄目です。しかし何がただの変人で、何が凄い変人かも、今後の状況次第ではその価値判断が変わるかも知れません。
企業面接に規格化された服装で現れる志願者は、それなりの従順な労働力にはなり得ましょうが、過分な期待は出来ません。日本の企業や組織は、異端児・変人も取り込んで行動パターンを多様化させ、近い将来訪れる可能性の高い破局から生き残る道を模索しなければなりません。
確かに東京オリンピックの時の日本選手団は開会式の入場行進でも足並みがピッタリ揃って、大変に美しい画一化の模範を見せてくれ、金メダル16個という空前の成績を収めましたが、それから40年、個性派が多く行進の足並みも合わせられないアテネオリンピックの日本選手団もまた金メダル16個を獲得したのです。
スポーツの世界だけでなく、日本全体が個性派を中心に多様化して動くようにならなければ、日本は世界の激動に対する耐性を得られないまま滅んでしまうような気がします。
個性派でも異端児でも変人でもいいけど、やはり人間としての常識とか協調性がねえ、と言う人のために、もう一つ医学・生物学の世界の逸話を紹介しておきます。ただこれから紹介する話があらゆる状況に当てはまるとは申しません。
あくまで逸話として他の人から伝え聞いた話ですので、仮にT博士としておきましょう。最初に断わっておきますが、私ではありません。分子生物学者として免疫機構の重要なキイを遺伝子工学的に解明した世界的に有名な日本人科学者です。(判る人にはすぐ判りますね。)
このT博士はアメリカの研究所ではかなりわがままな変人で、自分の実験に必要となると、他の研究者が使用中の超高速遠心分離機を停めてしまって、代わりに自分の検体を入れてしまうのだそうです。
こういう医学の実験では遠心分離機を何時間も、場合によっては何十時間も継続的に使用することがあって、それを途中で停められてしまえば実験はオシャカになってしまいます。T博士に機械を停められた研究者たちの怒り心頭の顔が目に浮かぶようです。
もちろん機械を停められた研究者たちは研究所のボスに苦情を言いに行きました。するとこのボスは何と言ったと思いますか。日本の職場であれば、ほとんどの上司は、他人との協調性を乱すのは良くないよ、と注意することでしょう。
ところがボスのアメリカ人は、T博士を非難しに来た研究者に向かってこう言ったそうです。お前の研究よりドクターTの研究の方が優れているんだから仕方ないだろ、と。
まず日本では考えられない逸話です。特に相手が中国人や韓国人など他のアジア人スタッフだったりしたら、偏見も加わって中傷に近い言葉まで口にする日本人だっているかも知れません。
T博士のような人材に思う存分自由に振る舞わせるアメリカの社会の方が、厳しい状況の中でも生き残る選択の余地が大きいように思いますが、ただちに日本でも真似をせよと言っているわけではありません。しかし行動の多様性とは、そういう道徳的観念までを乗り越えたものであることも知っておいた方が、今後世界の国々と競争や協調をしていくに当たって有利だと申し上げておきます。
日米の比較をしたついでに、もう一つ話を思い出しました。アメリカの軍人は、訓練中や実戦中でさえもジョークを口にしたり、ガムをクチャクチャ噛んだりしているのが多いようで、昔の大日本帝国陸海軍の上官が見たら目を剥いて怒るところでしょう。
例えばこんな話があります。機動部隊周辺のピケットラインについて敵機の接近を防ぐ駆逐艦には、日本軍の特攻機が殺到して甚大な被害を出していたのですが、その中の1隻の甲板には英語で「空母はあちら→」と書いてあったそうです。特攻機に向かって、俺たちを狙わずにあっちへ行けよというアメリカ人独特のジョークですが、自分たちの生命も危ないという瀬戸際に、こういうジョークをやってのける水兵を許した駆逐艦の上官にも感心します。日本の軍艦だったら、その水兵はビンタの嵐を食らって飯抜きだったかも知れませんね。
敵艦隊を攻撃に行く味方航空隊を見送りながら、日本の戦艦の水兵が、俺たちがやっつける分も残しておけよ、と叫んだところ、副長から、つまらん事を言うな、とこっぴどく怒鳴られた話も残っています。
自分の義務を果たしていれば、ガムを噛みながらジョークを飛ばしてゲラゲラ笑っていても良いと思うのですがね。どうも日本の社会は、構成員全員が足並み揃えて真面目に取り組んでいなければ気に入らない人が多いようです。
明治維新と戦後復興の際には、そういう日本人の生真面目さが良い方向に作用したように思いますが、それらの成果が崩れる時には却って悪い方向に作用する可能性があるかも知れません。
さっきも述べた東京オリンピック(1964年)とアテネオリンピック(2004年)の日本選手団はどちらも同じ数の金メダルを獲得していますが、その気質はまるで違います。戦後復興の頂点を目指していた頃の日本に比べて、すべて落ち目になってきた現在の日本が今後どのように変わって行くべきか、両選手団の比較はきわめて示唆に富んだ内容を含んでいると思われます。
インド洋大津波とタイ国政府について
2004年12月26日、スマトラ沖大地震による大津波によってインド洋沿岸諸国は未曾有の大災害を蒙った。南国の楽園として世界的な観光地でもあったため、日本人や欧米人まで含む十数万人が犠牲となったばかりでなく、インドネシアやスリランカやモルディブなど、それほど裕福とは言えないインド洋沿岸諸国の経済基盤に大打撃を与えた。これらの諸国が被害から完全に回復するまでには、この先何年もかかるに違いない。
信じられないほどの規模の津波の被害が明らかになるにつれ、世界各国から国際的な支援の輪が広がりつつある。医薬品や食糧・飲料水など当面の必需品や、医療チームや救助隊など人的支援などの他に、将来にわたる経済復興支援も重要だ。
日本政府もまたアメリカや中国と競うようにして多額の援助を行なうことを決定したが、このニュースに関連して、実に驚くような感動的な記事が、2005年1月9日の毎日新聞朝刊に報道されていた。小さな紙面での記事だったので見逃した方もいるかも知れないので、改めてその部分だけを引用しておく。
タイ 日本の資金援助を辞退
【バンコク発】町村信孝外相は8日、タイ南部プーケットを視察後、バンコクでスラキアット外相と会談した。スラキアット外相は、日本が緊急支援としてタイに供与を予定していた約20億円の無償資金について「より被害が大きい国に回してほしい」と辞退する考えを表明した。日本政府は、予定額をインドネシア、スリランカ、モルディブなどへの支援に回す方針。
確かにタイは震源地からはスマトラ島の島陰に当たり、また半島の反対側のタイランド湾沿いの主要部は直接の被害を免れたとはいえ、世界的なリゾート地として知られるプーケット島をはじめとする南部は甚大な人的・物的被害を受けているのだ。「経済大国」が無償の資金供与を申し出ているのに、それをより被害の大きい国に回してくれと言って辞退する政府が、この世界に存在するとは想像もしていなかった。
さすがはシャム王国として古くから栄え、近世以降も日本と並んで列強の植民地とならなかったタイである。この自存自立の民族の誇りがある限り、この国はいずれまたアジアに大きな影響を及ぼす強国の一つとなるのではなかろうか。決して小さな被害ではなかったにもかかわらず、東南アジア諸国全体の将来の繁栄を考慮したうえで、自国のみの利益を放棄した決定は実に見事である。このくらいの被害は自分たちで乗り越えてみせるという自信もあるのだろう。
一方で核兵器や人工衛星を開発しながら我が国からODA援助を毟り取る某大国はさておいて、日本人自身の自存自立の誇りはどうなっているだろうか。今回の大災害に際してタイ国政府が示した誇りを鏡として、自らの姿を映してみる良い機会ではないかと思われる。
思えば2004年は多数の台風上陸や新潟県地震など、日本国内でも近年まれに見る災害の当たり年となったが、被災地の方々はおそらく国民から寄せられた一時の救援や援助に甘んじることなく、今後は自力で復興して神戸に続くことだろう。日本民族の底力も決してタイに劣るものではないと思われる。(だからこの2カ国はアジアで欧米の植民地にならずに済んだとも言える。)
しかし最近の日本を見ていると、災害に被災したわけでもないのに他人のフトコロを当てにしている人間が多いのが気になる。万事、金、金の世の中、しかもバブルは弾けて景気は悪い。そんな中で大した自助努力もせずに、他人に寄付金をせびったり、消費者をおだててウマイ汁だけ吸おうとする団体や企業があまりに目につく。大体、役人が天下りしていると思われる団体からも、税制上の特典が受けられるとか何とか書かれた寄付金を募る通知が舞い込んだりして、お前らに寄付するより被災地の人たちが先だろうと、思わずクシャクシャに丸めてゴミ箱に放り込んだりする。
日本人はいつからこんなになってしまったのだろうか。こんなことでは近い将来、経済面でも国際的な影響力の面でも、タイ国に抜かれてしまうかも知れない。私は2005年の年明け早々、学会でタイを訪れることになっているので、小さな新聞記事がすぐに目に付いた。帰国したら改めて彼の国の様子を報告したいと思います。
(ドクターブンブンの旅日記「タイのリゾート海岸」を参照して下さい)
雪かきの話
2004年から2005年にかけての冬は東京でも雪が多かった。もともと東京をはじめとする関東平野の海側では、冬は乾燥して雪も雨も少ないのが普通であり、東京の雪は春先の低気圧が太平洋沿岸を通過する3月頃に最も多いのである。
イルカの「なごり雪」という歌の歌詞を見ればわかる。
「東京で見る雪はこれが最後ね」と
さみしそうに君がつぶやく
なごり雪も降る時を知り
ふざけすぎた季節のあとで
今 春が来て君はきれいになった
去年よりずっときれいになった
つまり東京では、卒業とか転職とか、別れの季節である春先までは雪は降らないのである。たまに降る時を知らない大雪が東京を襲うと、積雪に慣れていない東京人は大混乱することになる。
春先の雪なら雨混じりだし、気温もそれほど低くないので、すぐに解けるが、冬の雪はなかなか解けない。雪の積もった道を歩くことに慣れていない東京人は、滑って転んで大怪我をする率も高い。北海道や東北地方の出身者が見ると、雪の日の東京人の歩き方は滑稽だそうだ。まるで歩き始めた幼児のようだという。
ところで何でこんな東京の雪の話を始めたかというと、雪が降るたびに、小学校の頃の担任だったある先生がして下さった話を思い出すからである。昔は「ゆとり教育」などというバカな言葉もなかったが、あの頃の小中学校の先生方は、授業以外にもいろいろなことを話してくれたものだ。今になってみると、そっちのことしか覚えていないのも情けないことだが、むしろその後の人生に役立っているのは、そういう授業中の脱線の方である。
その先生が言うには、雪が降ったら、次の日の朝は大変である。家の前の道の雪かきをしなければならないからだ。道の雪かきは各々の家の分担責任であり、もしも積もった雪のせいで転んで怪我をした場合は、除雪しておかなかった家が責められることになるとのこと。だから雪が降った日の朝は、どこの家でも総出で家の前の雪かきをするものだという。
間口の広い家はそれだけ分担範囲も広く、同じ広さの敷地でも間口が狭くて奥行きの広い家の方が少ない範囲で済むのだ、などと言って生徒たちの笑いを取っていた情景も思い出される。
自分の家の前を除雪しておくのは、決して他人のためにやるのではない。自分が外出する時には、今度は近隣の人たちが除雪してくれたお蔭で安全に道を歩けるようになる。つまり「お互い様」ということだ。
これは今にして思えばボランティア活動の原点の考え方ではなかろうか。世の中のことは、他人のためにやっているように見えても、結局は巡り巡って自分のためでもあるのだ、ということを教えて下さっていたように思われる。昔の先生は人生経験が豊富だったのだろうか、とにかく大人になってからも「ああ、なるほど」と思い出されるような話をずいぶんして下さった。
ところが10年ほど前、とんでもない記事を読んだ。東京のある小学校で、雪の降った日に、生徒たちに学校周囲の道の雪かきをさせたら、バカなPTAの親どもが教師たちにクレームをつけたそうだ。
生徒に雪かきをさせるとは何事だ、そんなことは学校の職員がやることではないか!
おそらく生徒たちは、クラスメート同士でふざけ合ったりしながら雪かきをして、楽しい思い出も作ったことだろう。そして何より、積雪で歩きにくかった学校周囲の道が、自分たちの力で安全に通れるようになったことに対して、奉仕の喜びも感じたに違いない。活きた教育とはまさにこのことだ。それなのにこれにクレームをつけるPTAとはどういう大人どもなのだろうか。
雪かきをした生徒の一部が、「勉強の授業」をして貰えなかったことを不服として親に告げ口した挙句の騒動だったとしたら、さらに事態は深刻である。この国が近い将来、どういう姿になっていくのかを垣間見せられたような報道で、今でもよく覚えている。
またしても領土問題
2005年3月、再び日韓両国の間で竹島(韓国名 独島)をめぐる領土問題が険悪化する徴候を見せた。もともと竹島が編入された島根県の議会が『竹島の日』を定める条例を可決したことによる。
そもそも地球上の陸地などというものは、道に落ちていた財布のようなもので、「俺が先に見つけたんだ!」、「いや、俺が先に交番に届けたんじゃないか!」と、所有権をめぐって互いに口論するほど見苦しいことはなく、欧米や日本・中国などの帝国主義的領土拡張政策華やかなりし時代には、時には大量の血まで流して獰猛に奪い合ったものである。
帝国主義的覇権主義による領土拡張欲求が過去のものになった現在、やはり領土問題は最新の法学理論に基づいたルールで解決すべきものであり、路上の財布の例で言えば、最初に交番に届けた人間の所有物とすべきである。
この意味で韓国側の主張には2つの大きな無理がある。第一に、竹島(独島)が朝鮮側に帰属する根拠として、韓国側は中世から古代にいたる文献まで持ち出しているらしいが、レーダーも航空機も無く、性能の安定した船舶さえも無く、したがって日本側も朝鮮側も実効的に支配できなかったような時代の文献などにまったく意味はない。日本という“国家”も、韓国・北朝鮮といった“国家”も存在していなかった時代には、おそらく日本列島と朝鮮半島の漁民や船乗りたちは、竹島(独島)上で互いに顔を突き合わして、権力者とは無関係に情報交換や商売をしていた可能性の方が大きいのだ。
韓国側の第二の主張として、日本が近代国際法にのっとって竹島の領有を宣言したのは、朝鮮側が大日本帝国によって主権を奪われていた時代であったと言っているが、これは逆に言えば、韓国が独島領有を宣言した李承晩大統領の時代は、日韓国交も回復しておらず、日本側の主権が制限されていたわけであって、ドサクサにまぎれて領土を略奪したという論法から言えば五十歩百歩なのである。
ある人に物を盗まれたからと言って、その犯人が刑務所で服役中に、その人の留守宅に忍び込んで物を盗ってきたら、近代国家の刑法はこれをどう裁くのか。少なくとも韓国では、窃盗犯の留守宅に侵入して窃盗をはたらくことを正当な報復行為として認めているとしか思えないではないか。
まあ、現在は帝国主義的領土拡張の時代ではないから、この領土問題は日本政府も国民も節度を持って冷静に見守っていればよろしい。竹島(独島)問題で出血を強いられているのは韓国の方なのだから。今から私の見解を説明しておく。
韓国は独島(竹島)に防衛施設を設けているが、これを維持、保守するための施設費、人件費は年々かさんでいるのである。景気の良い時はそのくらいどうでもいいように思えるが、一度経済が傾き始めると、こういう所に注ぎ込まなければならない国家予算はボディブローとなってジワジワと効いてくるはずだ。韓国は近代化を達成して「漢河の奇跡」と呼ばれる復興を遂げたが、ここ数年来の記憶に新しい大橋や百貨店の崩落事故を見れば判るように、日本の戦後復興に比べればまだまだ国としての基礎体力には問題が残っているのである。
もし韓国が現在の日本のバブル危機のような状況に陥った場合、領土問題に国家予算を注ぎ込まねばならないような彼の国の体質は命取りになりかねない。そう言えば、日本が奇跡の戦後復興を遂げることが出来た要因の一つとして、アジアの植民地を放棄させられて、対外的な領土問題に首を突っ込まなくて済むようになったという点も大きいと思われる。まして韓国は近い将来、民族の悲願である南北統一を成し遂げなければならないのであるから、韓国政府は日本と事を構えることを極力避けなければならないはずである。
日本もいたずらに韓国との領土問題を深刻化させるのではなく、無力であることは判っていても国際司法の場に問題を預けて(いつまでも解決法は出ないだろうが)長期的に棚上げしておくのが望ましい。もともと領土問題などというものは、少なくとも大衆レベルでは自国の方が正当だと頭から信じているわけであるから、互いにナショナリズムを煽るのではなく、両国のメンツが潰れないように保つことが大切である。
あの島と周辺海域の資源を巡って日韓が対立して疲弊することを喜ぶ国はどこなのか、日韓両国民とも考えるべきである。北朝鮮、中国、ロシア、アメリカ、EUだって国際社会では単なるお人好しではないのだから……。他のいずれの国にも漁夫の利を占めさせてはならない。
中国政府の歴史認識に異議あり
中国は歴代の王朝・政権が変わっても、近世までは常に日本の師であった。我々日本人は中国大陸から伝来した仏教文化なしには、古来の“八百万の神々”への信仰だけでは、現在のような高度な文化を築くことはおそらく不可能だったろうし、第一、中国から教えて貰った文字なしには、我々は自分の名前すら書けないのである。そういう意味で、近世以前までの中国との関係は、現在のアメリカ合衆国との関連とは比べ物にならないくらい大きかったはずである。
後漢書や魏志倭人伝の時代も中国との交流はあったが、聖徳太子が遣隋使を送った607年以来(この年号は“カモメ群れなす遣隋使”と覚えます)、日本は積極的に中国の文化を学んだ。菅原道真の建言で894年に遣唐使が廃止されたりもしたが(この年号はまさに“白紙に戻せ遣唐使”です)、結局はそれから現代に至る日本の文化は、古代から中世にかけて蓄積された中国文化のバックボーン無しには考えられないのである。
近世以降、日本はその文化の“師”に対して弓を引いた。それは大変遺憾なことである。この“歴史的事実”の認識に関する日本の歴史教科書問題や靖国神社問題をめぐって、最近(2005年)また中国における反日運動の気運が高まっているという。
明治維新でいちはやく近代化に成功した日本が征台の役や日清戦争を皮切りに、第一次世界大戦のドサクサにまぎれて対華21ヶ条要求を突き付けて中国の植民地化に乗り出し、その後は満州事変を経て本格的な日中戦争の泥沼にのめり込んでいく。これでは中国人が日本に対して憤慨するのは無理もないことである。
しかし現在の日米関係を見れば判るように、日本はアメリカがイラクに出兵すると言えば、ハイ、そうですか、とばかりにこれを全面的に支持する。少なくとも他の西欧諸国のように一応自国の立場を表明することすらしない。良く言えば、強国に対しては愚直なまでに従順な同盟国、悪く言えば単なる忠実な番犬、それが日本外交の基本姿勢である。そんな日本をして、師である中国に弓を引かしめたものは何か?このことに対して中国政府は歴史的反省が足りないのではなかろうか。
以下、中国政府が反省すべき二点を挙げる。日本語の読める中国人がこのホームページを読んで下さったなら、忌憚のない反論をぜひ期待している。
先ず第一点、1840年とはいかなる年であったか。中国ならずとも、東アジアの歴史にとってきわめて重大な分岐点になった年である。
東インド会社を通じて東南アジアに拠点を設け、峻烈な植民地政策に乗り出した大英帝国は、ついにその毒牙を東アジアにも向けた。阿片戦争である。イギリスは清国に禁制品の阿片を密輸することによって、清国から大量の銀を持ち出したばかりか、多数の清国民を阿片中毒で苦しめることになった。これを見かねた道光帝の命を受けた林則徐は、阿片貿易で甘い汁を吸う清国高官や商人の妨害を押し切って阿片禁令を強化、ついにイギリスから阿片を没収して焼却するという大勇断に踏み切ったが、これを好機としてイギリスは清国と戦端を開く。武器で勝るイギリス軍は清国軍を圧倒して、ついに屈辱的な和議に応じさせ、南京条約(江寧条約)で領土割譲、賠償金、治外法権などを認めさせたのであった。後年の日本の対華21ヶ条要求と何ら変わるところはない。ところが中国はこのイギリスの歴然たる侵略行為に対しては現在まで何一つ抗議らしい抗議をしていないのだ。しかも南京条約で割譲させられた香港島に関しては、20世紀も終わりに近い1997年までイギリスの統治を許していたというのだから、まったくお話にもならない。
イギリスの一部の歴史書では、イギリスは清国の変則的で不当な貿易を改めさせるため、阿片の焼き捨てを“口実”に清国に宣戦したと書かれているが、清国は阿片以外の商品については外国との貿易を推奨していたのであるから、このイギリスの書物は歴史歪曲も甚だしい。イギリスは清国に阿片を売りつけて銀を獲得したいというのが本音だったのだから……。
イギリスの議会では、この戦争は禁制品の密輸を保護するという不正で不名誉な目的のために行なわれるという理由で反対論が巻き起こり、271票対262票という僅差でかろうじて承認されたに過ぎないという。当時のイギリス議会の良識派ですら反対していた阿片戦争を、中国人は21世紀になった現在でも容認し、不問に付しているのは何故か。
だからと言って別に日本の侵略行為も不問に付せと言うのではない。中国政府は阿片戦争についても公正な歴史的審判を示すべきであると言いたいのだ。西欧列強の歴史的行為に対しては卑屈に対応して、我が国に対してだけ居丈高に臨んでくるような中国政府の態度は明らかにおかしい。
1840年と言えば、日本では幕末、もちろん当時の日本にも阿片戦争の情報はただちに伝えられた。日本人の驚愕は大きかったに違いない。それまで師と仰いでいた中国が、いとも簡単に西欧の武力の前に屈して、屈辱的な講和を結ばせられたというのだから……。
しかし幕末の日本の何人かのリーダーは国際情勢を正確に把握した。そして明治維新を成し遂げて、西欧に範をとった近代国民国家を建設して諸外国からの侵略に対して未然に的確に対処したのであったが、中国ならびに朝鮮は、人民を搾取して自らの安穏を計るだけの旧態依然とした王朝の下で改革を怠り、列強(ここには残念ながら日本も含まれるが)の侵略を許してしまったのである。
自国の過去の指導者たちのこういう怠慢には目を向けようとせず、何でもかんでも隣国日本が悪かったと声高に叫ぶだけで、自らの欠陥を反省しようとしない国は将来どうなって行くのだろうか。日本が自虐的国家なら、中国や韓国は他罰的国家である。
個人でも、都合の悪いことは「社会が悪い、制度が悪い、学校が悪い、病院が悪い」と何でもかんでも他人のせいにする他罰的傾向の強い性格の人がいるが、こういう人が罹りやすい病気の一つに喘息などのアレルギー疾患がある。(念のために言っておくが、喘息などの人が他罰的な性格だというわけではない、逆は必ずしも真ならず!)
おそらく中国や韓国はいずれの将来にか、交渉で解決しうるような些細な外交問題に過剰に反応して(アレルギー反応)、壊滅的な打撃を受ける可能性があるかも知れない。そういう“病気”に罹っていた国の一つが、何を隠そう、戦前の大日本帝国に他ならないのだ。
以上が阿片戦争をめぐって、中国政府の歴史認識に異議あるところの第一点である。第二点はこのコーナーの別項にも書いたが、戦艦定遠・鎮遠の北洋水師(北洋艦隊)配備の問題である。この問題の軍事的意義については別項の方を読んで貰うことにしたいが、簡単に言えば、1885年に清国がドイツから購入した二大戦艦を対日戦専門の北洋水師に配備したということは、阿片戦争で香港を奪われた恨みを、当のイギリスには向けずに、東夷と侮っていた日本に向けたことしか意味しない。
これはつまり清国が、当時の帝国主義的領土分割ルールにのっとって我が国に挑戦状を送り付けたのと同じである。言うことを聞かなければ日本を侵略するぞというあからさまな恫喝だ。もし当時、日本が明治維新に失敗して、佐幕派と尊王派に分裂した状況のままであったらどうなっていただろうか。もちろんイギリス、フランス、アメリカ、ロシアなどに日本の主権は食い物にされていたに違いないが、これら列強が食い散らかした後の日本列島沖に現れた戦艦定遠・鎮遠の巨砲が火を吹き、続いて上陸して来た清国兵によって幕府軍も薩長軍も壊滅、日本領土内に清国の租界も出来ていた可能性が高い。香港をイギリスに奪われて面目失墜した清国官僚や軍人が汚名挽回できるチャンスはこれしか無かったからである。
列強の帝国主義的アジア侵略の手が伸びつつあった当時、清国としても生き残りの為にはやむを得ざる戦略だったであろう。それが帝国主義的領土分割ルールであれば仕方がない。
そういう当時のルールにのっとって日本に恫喝をかけておきながら、歴史を結果論でしか論じないのはきわめて不公正である。プロレスラーが相手に挑戦状を叩きつけておいて、試合でめった打ちにされて惨敗した途端、相手を傷害罪で告訴するようなものである。
日本の歴史教科書は戦艦定遠・鎮遠による清国の帝国主義的恫喝についてあまりにも記載が不備である。お人好しにもほどがあるのではないか。
阿片戦争で屈辱的な敗北を喫したと言っても、清国は当時まだ多くの日本人の心の中では昔からの師であったはずである。共にアジアの近代化を果たしたい、これからもずっと師であって欲しい、そういう願いもあったはずだ。(現在の対米関係をそっくりそのまま当時の対中関係に当てはめてみればよい。)だがその師から受けた恫喝が日本人をひどく失望させたことは想像に難くない。欧米への対処だけでも精一杯なのに、旧来の師であった中国にまで裏切られたショックは、その後も日本人の心に永く影を落としたのではないか。
日清戦争で巨艦定遠・鎮遠を擁する清国海軍を打ち破ったことで、この失望感は中国に対する侮蔑に変わっていったと思われる。中国は敵とするにも友とするにもあまりに偉大な国であるという認識が、21世紀の今日に至ってもまだ失われたままだ。第二次世界大戦だって、日本は中国に負けたのではない、アメリカに負けたのだという自負(負け惜しみ)が多くの日本人には残っており、これが最近の日中関係にも悪影響を及ぼしている。
中国が一方的に日本に歴史的反省を迫り、自らが過去に日本を恫喝した歴史をちっとも反省しようとしない限り、日中関係は今後も常にギクシャクしたままになろう。中国政府が戦艦定遠・鎮遠を北洋水師に配備して日本を恫喝した歴史的事実を正しく認めない限り、日本人の心の中に中国政府へのわだかまりは消えることはないと思われる。
尼崎列車事故に想うこと
兵庫県尼崎でJR西日本の福知山線で、また死者100名以上を出す大惨事が起こってしまった。「また」と書いたのは、私にとっては、かつての国鉄時代に三河島事故や鶴見事故の新聞報道を見て、電車とは恐いものだという強烈な印象を受けた少年期の体験があるからで、同じような想いに駆られた同世代の方々も多いのではないかと思う。
昭和37年5月3日の午後9時半過ぎ、常磐線三河島駅付近で信号誤認でポイントに進入した蒸気機関車が脱線転覆、この機関車に下り電車が衝突して脱線、さらにこの電車に上り電車が衝突して、その車体が線路上を歩いて駅に引き返す乗客の列を薙ぎ倒し、160名の方々が亡くなった。これが三河島事故で、この事故の教訓からATS(自動列車停止装置)の設置が進められることになった。
ところが翌年の昭和38年11月9日のやはり午後9時半過ぎ、今度は東海道線鶴見駅付近で脱線転覆した貨物列車に、上り下りの横須賀線電車が相次いで衝突して161名が亡くなる大惨事が発生した。私はまだ小学生であったが、当時は電車が恐くて、ちょうど現在の飛行機に乗るくらいの覚悟は決めてから乗ったものである。
その後も平成3年の信楽鉄道衝突事故など鉄道事故は跡を絶たなかったが、最近では大惨事と呼ばれる交通機関の大事故の主役は大型ジェット旅客機に取って代わられた感があった。日本における大規模な航空機事故は昭和41年に相次いで3件発生した。2月4日に全日空ボーイング727型機が羽田空港に着陸に失敗して墜落し135名が亡くなって飛行機恐怖症という言葉が出来たと思ったら、翌3月4日にカナダ太平洋航空のDC8型機が羽田空港に着陸失敗して炎上、64名が亡くなり、さらに3月5日には羽田を離陸したBOAC(英国航空の前身)のボーイング707型機が富士山付近で乱気流のため墜落し、124名が亡くなっている。(いずれも羽田に関連した事故だったので、空港が祟られているという怪説まで出る始末だった。)
それ以降、旅客機は離着陸時の事故だけでなく、自衛隊機に衝突されたり、ハイジャックされたりする事件や事故も相次いで、ますます飛行機恐怖症の人が増加してきたのに対して、列車の方は旧国鉄時代から現在のJR時代にかけて、安全の総点検と設備投資が行なわれた結果、死者100名を越すような大惨事は影をひそめ、列車旅行に対する国民の信頼感は磐石のものになったかに見えた。
そこへ持ってきて今回のJR西日本福知山線での脱線事故である。信じられないというのが事故の第一報をニュースで知った時の感想であった。事故原因については専門家による調査が始まっているので、素人判断で軽率なことを書くのは控えたいが、どうやら背景としては、同一区間を走る阪急電鉄との競争のためにかなり過密なダイヤを組んだ上に、運行時刻の遅れを取り戻そうとして運転歴の浅い運転士が現場となった急カーブで速度を出し過ぎたという事実があるのは確実らしい。人命を預かって列車を運行するJR西日本の責任は重大である。
この事故で大切な家族や肉親を亡くされた遺族の方々の憤りは当然であり、そういう方々がJR職員の胸倉をつかんで罵声を浴びせる気持ちはよく分かる。もし自分が同じ立場だったら同じように振る舞うに違いない。
だがそれ以外の、本来もっと冷静に事故の背景を見きわめなければならない報道や世論の在り方に、私はちょっと不思議なものを感じたのでここに書き止めておきたい。
その第一は、JR西日本が利便性を追及して安全を犠牲にした、との論調であるが、これはいかがなものであるか?利便性を追及したのは単にJR西日本だけではなくて、乗客として日々鉄道を利用する我々一般の日本国民の大多数なのではないか?特に都会の住民は、それほど待たずに列車に乗れて、正確な時刻に目的地に着くのが当たり前と思っている。そういう日常の都市生活にあまりにも慣れ切ってしまっているので、列車が数分遅れたために中間駅での乗り継ぎが出来ずに遅刻したりすると鉄道会社に腹を立てる。ダイヤ間隔が長くて列車が混雑すると、もっと増発してサービスを向上させろ、などと不平も言う。
私が初めてオーストラリアに海外旅行した時、この列車は何時に目的地に着くのかと近くの乗客に尋ねたら、そんなこと誰にも分からないよ、と当然のように答えられたのに驚いたものだった。(実際その時の列車は目的地に正午到着予定だったが、何と早朝に着いてしまった!)日本の鉄道はJR(旧国鉄)、私鉄ともよくこれほどまでの濃密なダイヤで列車を正確に動かしているものと感心せざるを得ない。
鉄道のダイヤ改正で列車が増発され(つまり運行間隔が詰まって)、目的地までの所要時間も短縮された場合、我々日本人は誰一人として列車の安全は大丈夫なのか、などと疑問を挟むことはしない。これで毎日5分間余計に朝寝坊が出来る、と喜ぶのが関の山だろう。
10時に待ち合わせの約束があって、9時半発の電車に乗れば9時55分に所定の場所に到着できると思っても、ダイヤが乱れる場合まで見越して20分も30分も前の電車に乗って行く日本人は果たしてどれくらいいるのか?(ちなみに私は通常20分以上の余裕を見ている。)
私は今回の事故に関して、JR西日本だけが利便性追及に走ったと責めるのは酷であると思う。日本人全体が鉄道会社に対して1分1秒の遅れも許さず、乗車待ち時間も少しでも短縮するようにと、苛酷な要求を当然のように突きつけている現実は踏まえなければならない。
第二に、JR西日本は利益を追求して安全を犠牲にした、との論調がある。これは一見正論であり、もし金儲けのために人命を軽視したとしたら、これは商道徳だけでなく、人の道にも反した行為である。
では鉄道会社は赤字を出してでも列車を運行せよというのだろうか?親方日の丸の国鉄時代のように、列車を安全に動かすためにはいくら金がかかっても構わないというだけの度量が現在の日本経済および日本国民にはあるのだろうか?
安全には必ずコスト(費用)がかかる。最大限の利便性を追及するために、どれくらいのコストまでは許容できるか、というのが、そもそもこういう問題における最も重要な論点のはずなのだが、かつてイザヤ・ベンダサン(実は山本七平氏)が見事に喝破したごとく、日本人は水と安全はタダだと思っているから、今回のような事故が起こっても、利便性と安全のバランスといった見解はほとんど出て来ない。新聞の論説者もテレビの報道番組のコメンテーターも、JR西日本の利益優先の体質を強い論調で批判すれば大衆受けするので、ほとんど百人が百人とも同じようなことを述べているに過ぎない。
もちろんJR西日本が安全面を軽視した罪は大きい。それでは本来ならばその安全コスト(新型のATS導入や余裕のある運転士教育体制など)はどこに転嫁すれば良かったのか。偉そうな顔でJR批判のコメントをしている方々は何か答えられるのだろうか?
当然、行きつく先は運賃の値上げであるが、これは監督官庁の認可が無ければ実施できないし、それに頻繁かつ大幅な運賃値上げは利用者の批判を招いて、今回のように他社と競合する路線では利用者離れが起こって一気に経営が悪循環に陥ってしまう。
それで利便性を上げてサービス向上させようとすれば、それに関わる安全コストは、施設整備の先延ばしとか、人員採用の削減といった所に必然的にシワ寄せされてしまうことになる。今回の福知山線のように運転の難しい路線に、まだ経験の浅い(運転歴11ヶ月)運転士を配置せざるを得なかったのも、恐らく中堅クラスの運転士の不足という事情があったものと推察される。この中堅クラスの人員不足は、実は鉄道に限らず、現在の日本のあらゆる重要なシステムを根底から覆しかねない重大な問題であり、今回の脱線事故はもしかしたら日本の近未来を予言したものと言えなくもない。
あらゆる組織の人員構成は、ベテラン・中堅・新人という三段構えでなければその機能は永続しえない。ベテランが退役した後は中堅が取って代わって組織全体を統括する、また新人の補充によって、かつての新人は中堅となり、新たな構成員の実質的教育にあたる。この代送りの構造が構成員の教育を円滑にして、組織の機能を保持する上で大切なのである。
ところがJRにおいては、民営化と共に国鉄時代の余剰人員を整理するために新人採用を切り詰めた時期があり、そのため現在のJR各社では中堅社員が払底している現状だったという。これは日本の他の組織にとっても他人事ではないはずだ。バブル経済の崩壊によってどの組織も(もちろん医療機関も)新人採用が極端に減った時期がある。多くの病院でもしばらく新人採用が減少し、最近になってようやく少しずつ戻ってはきたが、近い将来、ベテランと新人だけの構成となり、さらに次は中堅と新人だけとなり、取り返しのつかない事態になるのではないかと私は密かに危惧している。鉄道や医療だけではなく、国防、航空機、原子力関係など、新人採用を見送った時期のツケが一気に噴き出す可能性が非常に高く、今回のJR脱線事故はその予兆に過ぎないのではないか。
先に述べたように日本人は安全へのコスト(費用)という意識があまりに低すぎる。ほとんど無限の利便性だけを追及しながら、それに対する安全コストの投資はタダで済むと思っている。
安全コストは各組織や機関が利潤を上げて投資するか、税金から支出するしかないわけだが、現在のようにどの組織も個別採算という制約の下でやらなければならないとすれば、結局この安全コストは消費者(乗客、利用者、患者等々)に転嫁せざるを得ないのは自明の理ではなかろうか。ところが日本では、採算を取る=利潤を上げる=金儲け=「悪」であるという考え方が根強くはびこっている。特に鉄道、航空、医療などのように人命を預かる機関が銭儲けを考えるとは何事だと言わんばかりだ。本来なら人命を預かるためにもっと利潤を上げて安全面に投資せよというべきではないのか。何もかも「越後屋、おぬしもワルよのう、フッフッフ」のレベルで判断されてはたまったものではない。
マスコミに出て来て勝手なことをコメントしていれば収入になるような気楽な人たちはそれで良い。だがそういう人たちによって形成された世論に乗っかって日本全体が安全コストへの投資をさらに軽視し続けていけば、我々の社会はどうなってしまうのか。さらなる大事故が頻発する前に、医療がメチャメチャになる前に、原子炉が爆発する前に、日本人は「安全への投資」を学ぶ必要があるのではないか。
マスコミさん、ちょっとヘンよ
私は右の頬を殴られたら、倍にして相手の左右の頬を往復ビンタしかねない、およそキリスト教とは縁遠い人間だが、ヨハネによる福音書の第8章の話だけは、ちょっと心に残っている。
オリブ山に行ったイエスの前に、律法学者やパリサイ人たちが姦淫した女を引っ張ってきて、どうすべきか問うた。モーセの律法によれば、姦淫を犯した女は石で打ち殺さなければならないのである。イエスは答えた。汝らのうち罪無き者、先ず女を石で打て。
自分だけは何の罪も無いと胸を張って言える者が果たしてこの世に何人いるか。結局、その場にいた者で女を石で打てる者は誰一人いなかった。イエスが、誰かお前を石で打ったかと訊くと、女は答えた、いいえ、誰もおりませんでした。イエスは言った、私もお前を罰しない、もう二度と罪を犯さないように。
なかなか深い話だと思う。そもそもキリスト教自体、処女懐妊で男児が生まれたなどと、世界中の人々を2000年以上にもわたって騙し続け(医学的にはイエスのY染色体はどこに由来するのか?)、聖母姦淫の罪を誤魔化し続けているのだから、世界には神を含めて誰一人として正しい者はいないということを、身をもって説いてくれる大変ありがたい宗教ではなかろうか。
それはともかく、世間を騒がす大事件が起きるたびに行なわれるマスコミの「記者会見」という名の行事と、その後に引き続く記事や報道ほど見苦しい見世物はない。イエスがいたら何と言うだろうか?
「汝らマスコミのうち罪無き社の記者、先ず関係者を罵倒せよ。」
先日のJR西日本の列車事故でも、何度か記者会見の様子が放映されたが、見るに耐えないほど醜悪なものだった。社会正義をかさに着た一部の記者たちの口から発せられる内容は、自分たちこそが正義を代表しているという傲慢な思い上がりが感じられて、不愉快この上もない。医者、政治家、官僚、銀行、交通機関、食品会社、等、等、次々と社会問題を起こしてくると(もちろん問題を起こす方に責任があって悪いに決まっているのだが)、それにハイエナのように群れ集まって正義漢ぶった記者会見を開き、お仕着せの糾弾記事や批判報道合戦を繰り広げるマスコミ関係者諸君。じゃあ、お前らマスコミは何の罪もないのかよ、と反対に吊るし上げてみたくもなる。
しかし彼らは他人の生命・財産を直接に預かるわけでもなく、無責任に良い子ぶったコメントを垂れ流していれば収益も上がるような仕事だから、なかなか尻尾を掴まれるような事件の責任者になることはない。しかし私は一つだけ絶対に許せないマスコミの犯罪を記憶しており、その後もマスコミが記者会見などと称して事件の責任者を吊るし上げる醜悪な場面を見るたびに、はらわたが煮えくり返る思いをしているのである。
そのマスコミの犯罪とは、平成6年6月27日夜間、松本市内でサリンが撒布されて7名の死者を出した、いわゆる「松本サリン事件」に引き続く一連の犯人探し報道である。サリン噴霧現場近くに住む会社員のKさんの自宅から化学薬品が見つかったことで、Kさんに事件の容疑がかかった。警察の捜査も杜撰と言わざるを得ないが、『真犯人特定』の特ダネを他社に先にスクープされては大変とばかりに、マスコミ各社が繰り広げた先陣争いは醜悪の一語に尽きる。
Kさんの奥さんがサリンガスで重体となったことから、奥さんを殺害しようとしたに違いないという予断と思い込みが、ハイエナのような記者たちをして、次々とある事ない事を織り混ぜたとんでもない報道を展開させた。
まあ、私もここまでの話なら、そんなにはらわたの煮えくり返る思いをすることもなかった。誰にでも思い違いはあるものだし、乱立する報道業界において、どこが一番記事を書くかというスクープ合戦は各社の命運を分けるほど熾烈なものであろう。その中でたまたまKさんの人権や名誉までを考慮する余裕がなかったとすれば、情状酌量の余地も無いではない。報道とて神ならぬ人間が行なうものだからである。いわば報道の「オーバーラン」であろうか。
ところがその後、Kさんへの容疑がまったくの冤罪であると判明してからのマスコミ業界の対応はまったくひどかった。身内業界の罪に対する追及が、各社横並びの「お詫び報道」のみで終わってしまったのだ!テレビ番組ならアナウンサーやキャスターのお詫びコメント数分間、新聞や雑誌ならせいぜい半ページ程度の記事1回。罪もない1人の一般市民の人権と名誉をここまで蹂躙してしまった原因についての追及や、将来の再発防止への具体的な制度改善の提言は何も無かったのである。
しかも松本サリン事件は、単にKさんの冤罪にとどまらない一面を持っているのだ。警察の杜撰な捜査に乗っかったまま、マスコミがウラを取らない無責任な報道を垂れ流したばかりに、松本サリン事件の真犯人であるオウム真理教は完全にノーマークになってしまった。松本市に支部を作ろうとしていたオウム真理教と裁判所の間にトラブルがあったという有力な状況証拠があったにもかかわらず…。
一応公安関係者はオウム真理教をマークしていたフシもあるが、こうして少なくとも一般国民は、サリン事件は「ちょっとヘンな会社員」の仕業ということで納得させられてしまい、結局、平成7年3月20日の東京地下鉄サリン事件を迎えることになる。ちょうどマスコミに誘導されてサリンへの警戒を解除してしまった形であるが、意地の悪い記者ならば、松本サリン事件の時のマスコミの不適切な対応が、地下鉄サリン事件を引き起こす要因の一つになったのではないか、と追及するところだ。
このようにマスコミは自分の身内・同族が引き起こした事故や事件に対する追及はきわめて甘いくせに、他の業界の事故や事件に対してはまるで自分が絶対無謬の神のごとく裁こうとする。先ほどからマスコミ記者をハイエナ呼ばわりしたのもそのためだ。ハイエナは他の動物の死体の肉はあさるが、同族の死体の肉をあさるイメージがないからである。(動物学的に正しいかどうかは知らない。)
もしマスコミ人が本当に松本サリン事件後の冤罪報道事件を真摯に反省する気があったのなら、Kさん犯人説を最初に記事にした報道機関はどこで、どの記者がどんな記事を書いて、どの編集者がチェックしたのかを明らかにしたうえで(出来たはずだ)、当人たちを呼んで「記者会見」をすべきだったのである。
「あなたの記事のお蔭で無実の市民が犯罪者呼ばわりされたんだぞ!どう思ってるんですか?責任は感じているのか?」
「記事を書いた根拠は何だ?あなたは正しいと思ったんでしょ?」
「地下鉄サリン事件にも責任が無いとは言わせないぞ!」
「新聞さえ売れればそれで良いのか!利益優先じゃないか!」
「お前じゃ話にならん。編集長をこの場に呼べ!」
さまざまな罵声が浴びせられただろうが、こういう記者会見は絶対に行なわれないから本当にマスコミとは気楽な商売だと思う。
無責任な報道やコメントを垂れ流すだけなら、インターネット時代の今日、既存の報道機関など不要である。各種ウェブサイトを検索してみれば、列車事故だけでなく、政治問題、外交問題、経済問題、医療問題、歴史問題、その他あらゆる領域の出来事に関して、私のような素人コメンテーターまでがいろいろな形で記事にしており、到底すべてに眼を通すこともできないほどの情報量である。また2チャンネル等を始めとする掲示板ではさまざまな人のコメントも読める。
インターネット上のコメントはそのほとんどが匿名であり、責任の所在が明確でないことが最大の欠陥だが、既存の報道機関が社会的に問題ある記事を書いても何の追及も制裁も無いとすれば、これはもうインターネット上の無責任な書き込みと同じことであり、そこから利益を上げている分だけプロのマスコミの罪は重いと言わざるを得ない。
プロのマスコミが果たすべき役割とは何だろうか。冒頭のオリブ山のイエスの話で言えば、最後にイエスが姦淫女を諭した言葉を実践することではないかと思っている。
「お前の罪を罰する資格のある者は誰もいないが、二度と罪を犯してはならない。」
正義漢ぶった声高な記者会見はマスコミ全体の品を落とす。あんな追及はインターネット上でいくらでも読める。ライブドアのフジテレビ買収の件は、ひとまず既存マスコミ側の勝利に終わったが、将来にわたって既存のマスコミが本当に存在意義を保持していきたいと思うなら、あの松本冤罪事件をもう一度検証して、当時の関係者の事情聴取なども行なったうえ、“プロ”の報道とは何かを真摯に考え直すしかないのではないか。
補遺
天下のマスコミ様にあんな事を書いて良いのか、と心配して下さった方々に心から御礼申し上げる。別に私は悪い事を書いたつもりもないし、まして恥じるような事もしていないと胸を張って言える。
私は尼崎列車事故に関して、ほんのささやかな私のホームページにささやかな私費を投じて、事故の分析と将来への警告を述べたに過ぎない。鉄道会社と同じく人命を預かる現場に奉職する人間としての私のコメントは、絶対に正しいとは言わないが、それなりに参考になる所見だとは思っている。念のために、掲示板(BBS)の方に書いたコメントはいずれ消去されてしまうので、再掲しておく。
この事故の最大の原因はJRの中堅職員不足だと思います。乗務経験が数年以上あれば、ダイヤの遅れにも、車体の不備にも、もう少し柔軟な対応が取れた可能性が大きいのではないでしょうか。中堅不足の体質はJR以外のほとんどすべての日本の企業・組織に当てはまります。経費節減のため新人採用を減らせば、一時はベテランと中堅だけで何とか無理をして機能を維持しながら人件費も節減できて、経営者から見れば、うまく行ったと思うでしょうが、次の世代ではベテランと新規採用の新人だけとなり、ベテランは新人を教育しながら組織全体の統括もしなければならず、十分に手が回らなくなります。そして次の世代では、十分な新人教育を受けられなかったかつての新人が中堅となって、新たな新人を教育しながら、なおかつ未熟なまま組織の統括までも求められ、さらにひどいことになります。
すでに日本の大部分の企業や組織は、経営改善のために「新規採用削減」という禁断の木の実を食べてしまいましたから、これから10年20年の間にどんな事が起こってくるか、恐ろしいです。
少なくとも大手マスコミが公共の電波を使って、延べ何十分間にもわたり垂れ流した、あのくだらない映像と比較しないで欲しい。
そのくだらない映像とは、事故当日、JR西日本の○○○車掌区の職員がボウリング大会を開き、その後で飲み会を開いたという店にレポーターが仰々しく押し掛けて、
「これがボウリング大会の後でJR職員が宴会を開いた店です!」
「あそこの席でビール○本、お銚子○本を注文しました!」
などと馬鹿げたレポートを何度も繰り返し放映した映像のことである。あれはいったい何なの?何か将来の日本に役に立つことあるの?
JR西日本はこんなにひどい会社ですよ、ということを、ことさらに強調するだけの効果しかないではないか。こういう報道をする方も、これを見て共感する視聴者の方も、「ああ、世間には俺よりもひどい奴がいるんだな」ということで安心するカタルシス作用だけは確かにある。(松本サリン後冤罪報道事件の後、当該マスコミ各社の長野支社や松本支局の記者や編集者たちは、ボウリングも飲み会も自粛したんだろうか?)
幼稚園や小学校の頃、ちょっと規則違反をした友達を見つけて、「わ〜るいな、わ〜るいな、○○ちゃんはわ〜るいな。せ〜んせいに言うたろ〜!」と皆を煽動して真っ先に囃し立てるガキが何人かは居たものだが、それと同じ精神構造ではなかろうか。本当に情けない報道だ。
ついでに言っておけば、事故列車に乗客として乗っていた同じJR西日本の2名の運転士が、救助作業に参加せずにそのまま出勤したことを、ほとんどのマスコミがまるで旧軍の「敵前逃亡」であるかのごとく報道し、「まるで他人事なんですね」などという“識者”のコメントまで付けたりもしていたが、では当該運転士が当日救助に没頭して出勤せず、本来乗務すべきだった別の路線の列車が運休でもした場合、マスコミや世論は、彼らを「責任を取って救助の先頭に立ったJR職員」として、称賛はしないまでも、その意気に感じて許しただろうか?
前年のイラク人質事件における「自己責任論」の時も感じたが、世論に迎合したスケープゴートを仕立て上げるマスコミ、またマスコミに先導されてスケープゴートをバッシングする世論、この悪循環に私は非常に危ういものを感じる。いつの日か、この国が大政翼賛政権の発足するような局面を迎えた場合、マスコミも世論もまったく国家の暴走を抑止する力にはなり得ないのではないかと。
ここは歴史独り旅の第2巻です。 第1巻に戻る 第3巻に進む
 トップページへ 歴史独り旅の目次へ
トップページへ 歴史独り旅の目次へ
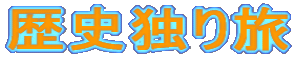
 しかし使用するミニチュアが大きくなれば、それだけ真に迫るかというと、なかなかそうは行かないところが洋上シーンの難しさである。戦艦大和を1/20で作ってみても、水と火は1/20にならないから、艦首が切り裂く波や、大砲発射の時の爆煙や、艦上に炸裂する炎などと比べると、絶対に本物のようには見えないのだ。特撮技術者たちの話によると、火と水だけはどうしても誤魔化せないというのが彼らの泣き所だそうである。だからこの1/20の大和も、白昼堂々と大海原を行くシーンは無かった。
しかし使用するミニチュアが大きくなれば、それだけ真に迫るかというと、なかなかそうは行かないところが洋上シーンの難しさである。戦艦大和を1/20で作ってみても、水と火は1/20にならないから、艦首が切り裂く波や、大砲発射の時の爆煙や、艦上に炸裂する炎などと比べると、絶対に本物のようには見えないのだ。特撮技術者たちの話によると、火と水だけはどうしても誤魔化せないというのが彼らの泣き所だそうである。だからこの1/20の大和も、白昼堂々と大海原を行くシーンは無かった。