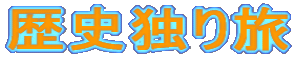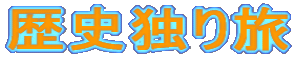
�o�C�o�C�A����Y
�@�ŋ߂���قǕ��ꂽ�V���L����ǂ��Ƃ͂Ȃ��B�悸��2006�N11���W���̖����V����������A�������ꂽ���������p����B
�@����Y�O�͂V���A�����}�u���{���Â��蓹��v�̂������ŁA��N�����I�����O�@�c��61���ɑ��āu�����Ƃ͎g���̂Ăɂ���邱�Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Â����Ⴞ�߂��v�Əq�ׂ��B
�@�����}���s�����i�߂�X�������g�̕��}��e�F���A���}�ɔ�������V�l�c���ɓ}�������������Ȃ��悤�N�M���h���������Ƃ݂���B
�@���́u�Q�@�I�ɕ����邼�v�ƌ��ȂǁA�������}�Ɉ٘_�������Ă��������ɐV�l�c���͏Ռ������l�q�B���������O�@�c���͋L�Ғc�Ɂu�g���̂Ăɂ���Ȃ��悤�Ɋ撣��v�ƌ�����B�y�đ��k��L�ҁz
�@2005�N�X��11���̂�����u�X�����U�v�ɔ������I���ŁA����i�����j�͗X�����c���ɔ������������҂Ɏ����}���F��^�����A�g�h�q���h�𗧂ĂĒǂ����Ƃ��������A�����}�������������Ƃ����r�Î����{�������̂́A���̂܂܂ł�2007�N�̎Q�@�I�ŎS�s�̉\��������̂ŁA�����}�Ƃ��Ă͊e�I����ɋ��͂Ȓn�Ղ��������c�����Ăю����}�Ɍ}���悤�Ɖ�Ă���B�����Ȃ�ƁA�h�q���Ƃ��ė��p����A�g�ɂ킩�����}�c���h�ɂȂ����V�l�c���͓}���ł̗��ꂪ�����Ȃ��Ă��܂��B
�@�h�q���Ƃ��ė���₵�ď����I���A�g����`���h�����h�Ȃǂƃ`���z������Ă��������V�l�c���̒��ɂ́A�����ƂƂ��Ă̎���������悤�ȊԂɍ��킹�I�Ȑl�ނ����Ȃ��Ȃ������̂ŁA��ʍ����Ƃ��Ă͔ނ炪�g�g���̂āh�ɂ���邩�ǂ����A���ɖʔ����O���ŋ��̌������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A�ނ���g���̂Ăɂ������{�l���炪�u�g���̂Ăɂ���邱�Ƃ��o�債��v�ȂǂƐ�����Ƃ����̂�����A����͂������ꂽ�ƌ������A�������ƌ������A�����������x�����͂邩�ɉz���āA�����ׂ����t��������Ȃ��Ƃ��������ł���B���Ƃ������E���i�Ȑl�i�c�B
�@���͗X�����c���Ƃ�������̐M�O�i��]�j�̂��߂ɁA2005�N�̑��I���ł͂Ȃ�ӂ�\�킸�����̎����}�����̂ĂĎh�q����������̂ł���B�X�����c���@�Ă��ʂ��Ă��܂��Ύh�q���̗L�ۖ��ۂ͎ז��҈����A2007�N�̎Q�@�I�̂��߂ɂ͎g���̂Ă��������B
�@����͂���Ŏ����}�Ƃ��Ă͋̒ʂ����헪�ł͂���B����ȓ}�̖{�������������A���p����邾�����p����������A���h�q��₪�g���̂Ăɂ���悤���A����͊e���҂̎��ȐӔC�Ƃ������̂ł���B�ʂɎh�q���Ƃ��ė������Ƃ����w���������悤�ȏł͂Ȃ������B
�@�������h�q���̐V�l���������̂�̖�]�̂��߂ɗ��p���邾�����p����������A�u�g���̂Ăɂ����̂��o�債��v�ƌ�������������Y�̕i�i�Ƃ͂����Ȃ���̂��B�䂪���{�����͂���܂ł��������i������Ȑl�Ԃ��ɑՂ��Ă����킯�ł���B
�@�����͂ǂ������ł��낤�Ƃ��A���̌�����o��ׂ����t�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������͂����B
�u��N�̑��I���ł́A���̎咣����X�����c���̂��߂ɑ����ɓ����Ă���Ă��肪�Ƃ��B���������̊��ɋy��ŗ��N�̎Q�@�I���T���������}�Ƃ��Ă͏��N�����̂Ă�悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂��~�ނȂ��ƂȂ��Ă��܂����B��ϐ\����Ȃ������B�s�я���A�S�����\���q�ׂ�Ƌ��ɁA���N�̍���̕��������F�肷��B�P���킢����A�[�ӂ��B�v
�@�Ō�̈ꕶ�͂������A���U���̐��݂̐e�ƌ���ꂽ�吼�뎟�Y�����̈⏑�̒��̌��t�ł��邪�A����Y�ɂ͑吼�����قǂ̗ǎ����疳�������B���́A�l���l���g���̂Ăɂ����Ƃ����悤�ȏ�����ƁA�ǂ����Ă����U���̂��Ƃ����ɕ�����ł��܂��B�l���g���̂Ăɂ����l�Ԏ��g�����̂��Ƃ𐳓������ċ�����p������ƁA�����A���{�l�Ƃ͍����̂��ς��ʂ��̂��ȂƒQ�����Ă��܂��B
�@�吼�����͓��U���̐��݂̐e�Ƃ���Ă��邪�A�{���ɓ��U���Ă��Đ��i�����̂͌��c���ȂǁA�����R�ߕ��ɂ����Q�d�����ł������B�������吼���������U�Ɏ^�����Ă������炱�����琄�i�����ďo���̂ł��낤���A�吼�Ƌ��ɓ��U���������ɐ[�ӂ��Ď��n���ׂ��l�Ԃ͑��ɂ��吨�����͂��ł���B�Ƃ��낪�ނ�͓��U���͓��{�l�Ƃ��ē��R�̈����S�̔��I�ł������Ǝ����̐ӔC��������ċ��������̂ł���B����̏���Y�Ɠ����ł���B
�@����Y���g���̂Ăɂ����̂́A����̐V�l�c�������ł͂Ȃ��B���{�����S�̂����g���̂Ăɂ��Ă���̂��B���̓��{���o�ϖ��i�𐋂����̂́A��Ђ��ƂɈ�r�ɐg������ĕ����������������̂��A�ł���B���̍��������̊��̏�ɒz����Ă����̂����̎����}���{�ł���B����Y��M���Ƃ��鎩���}�́A�����Ɏx����ꂽ�o�ϖ��i�̉��b���ČN�Ղ��Ă����Ȃ���A��Â╟���̖ʂł����g�o�ϐ�m�h�������̂āA�܂��Ɏg���̂Ă悤�Ƃ��Ă���̂ł���B����Y�͐�㔭�W���x�����o�ϐ�m�������̂āA�X�����c�����x�����V�l�c���������g���̂ĂāA����͂܂����͂̍��ɌN�Ղ������Ȃ̂ł��낤���B
�@�������̃T�C�g�̕ʂ̂Ƃ�����_�����U���ɂ��ď����Ă��邪�A���͑��������̗J���̎�����y�Ă���킯�ł͂Ȃ��B�l���g���̂Ăɂ��Ă����Ď���͐����c��A�����h�B���ɂ߂Ă����Ȃ���A������⑰�ɑ��Ĉꌾ�̎Ӎ߂��Ȃ��A����̜������Ȃ��A����̏���Y�̂悤�Ȕj���p�ȏ�w����ᔻ���Ă���̂ł���B���̃T�C�g��ǂ�ʼn��������啔���̕��X�͂����������̈ӂ�����ŁA�S�ʓI�Ȏ^�ӂ����[���ȂǂŊĉ������Ă���B
�@���́A�������g�����U�ɍs���Ȃ��悤�Ȑl�Ԃ����U�����^�����邱�Ƃ��I�ɋ����Ȃ��B�R�ߕ��Q�d���������c���́A��������悵�ē��U�����^�����Ȃ���A�������s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂȂ�ƁA���̏ꂩ�瓦���o�����l���ł���B���U�������R�Ǝ^������l�Ԃ͍ŋ߂܂������Ă��Ă��邪�A�ʂ����Ă��̉������������g�����U�ɍs�����Ƃ܂ŃC���[�W���Ă���̂��낤���B
�@���͎Ⴂ���͎��̐푈�Ŏ����������U�̐�w��邼�ƐS��l���Ă����B�K���ɂ��Đ푈�͋N���炸�����i�炦�Ă݂�ƁA���������n�������Ȑl�Ԃ���������������{�Ƃ������̍\���I�Ȍ��ׂ������Ă��܂����B���͂��̕������{�œ��U�������Ɏ^������l�Ԃ́A�������g�͓��U�ɍs���Ȃ��l�ԁA����A��������U�ɍs�����闧��̐l�Ԃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@����Y�Ƃ������l���͂��ē��U�������^�������B���̒j�͎������x���Ă��ꂽ�V�l�c�����g���̂Ăɂ����B���{�̌o�ϔ��W��S���Ă��ꂽ����̍��������E���ɂ����B����ȏ�̏؋������낤���B
��点�̃^�E���~�[�e�B���O�Ɠ����T�C�g
�@�����Ȋw�Ȃ̋�����v�^�E���~�[�e�B���O�ŁA����哱�́u��点����v���p�ӂ���Ă�����肪���サ���B���{�E�����}���ژ_�ދ�����v�Ɍ����Đ��_������Â��邽�߂ɁA��ʐl�����Ə̂���^�E���~�[�e�B���O����悵�A�����ł��炩���ߗp�ӂ��Ă��������҂ɐ��{�̈Ӑ}�ɉ����������������Ƃ������ɌƑ��ȁg��点�h�ł���B�����Ȋw�Ȃ͋ǒ�������������j�����������i�ǂ����`���ゾ�����낤���j�A����͖{���͂��̒��x�̑����ōςޖ��ł͂Ȃ��B
�@���̓��{�͖����`���ƂƂ������Ƃł��邩��A������Ӊ��B�ō���������t���邱�Ƃ͌����I�ɋ�����Ă��Ȃ��B�����Ń^�E���~�[�e�B���O�Ŗ��ӂ��U�������`�́u��点����v����ꂽ�ƌ���ׂ��ł��낤�B���ƌ��͑������낢��g�w�K�h���āA�������I���ɂȂ��Ă��Ă���B
�@���͍��ƌ��̖͂��ӋU���H��Ƃ��āA�����ŋߓ��ɋC�ɂȂ��Ă���̂��C���^�[�l�b�g��̓����T�C�g�ł���B���ӔC�ȓ��e�҂����鎖�Ȃ����D������Ĕ�排����������܂���f���̗ނ͂��̍ۖ��Ƃ��Ȃ��B�t�ɂ���Ȃ�ɗ��h�Ȉӌ����q�ׂ��Ă��铽���T�C�g�̒��ɂ́A���ƌ��͂̈ӂ��s�����댯�ȃT�C�g�������̂ł͂Ȃ����Ǝ��͋^���Ă���B
�@���͗c��������̊S�ŁA���l�l�̏������_�����U���Ɋւ���T�C�g�͂����Ή{�������Ē����Ă���B�ŋ߂ł͓��U���ɔے�I�Ȃ��̂��m��I�ȃT�C�g�̕����ڗ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��邪�A����Ȃ�ɐ���҂̗��h�Ȍ����ƒm�����q�ׂ����̂ł���ɂ�������炸�A�����������ł���B
�@���U��������������A���̈����̎�����^������A���̍l�����ɂ͎����܂��������ӂł���B���������U���āE�v��E���{���Ȃ��玩��͂��̐ӔC�����������w���ɑ���ᔻ�L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂����̎咣�ł���A����������̎��̃T�C�g�ɏڍׂɏq�ׂ��Ƃ���ł���B���U������w���̗��ꂩ�����I�Ɍ����E�^�����邾���ł́A�Ăѓ����ߌ����J��Ԃ����ł��낤�B
�@�ނ��덑�ƌ��͑��̐l�ԂƂ��ẮA�Ăѓ��{�l�𖽗߈ꉺ�A����̂��߂Ɋ��Ŏ���ł���鍑���ɍ��ς������Ɖ�Ă���͂��ł���B�����ł͂܂����u���U���Ɋւ���^�E���~�[�e�B���O�v�ȂNJJ�Âł���͂����Ȃ�����A���͑����g��点����h�̑���Ɋ�ނ͉̂����낤���A�l�������Ƃ͂���܂����B
�@�C���^�[�l�b�g�����y���A�����́g���U�v���h�ł����҂����̂قƂ�ǂ��p�\�R���𑀍삷��悤�Ȏ���ɂ����ẮA���U���������E�^������T�C�g�����J���āA���ꂪ���{�́g���Ӂh�Ȃ̂��ƍ��o������A����قǗL���Ȏ�i�͂Ȃ��B���������T�C�g�ɑ����̃T�N���������A�N�Z�X���āA�T�C�g�J�ݎ҂̈ӌ��ɉ������������݂�����A���ꂾ���Łu�����A����ς���{�����ɂ͓��U�Ȃ̂��v�Ǝv�킹�A�����𐌂킹����ʂ͐��ł���B
�@���U���Ɍ��炸�A������A�����S���A�O����E�E�E�A�ǂ��̒N�������Ă��邩����Ȃ��悤�ȏ��ɂ͏\���Ȍx�����K�v�ł���A���Ƃɂ���Ďd�g�܂ꂽ���̉\�����^���Ă݂�ׂ��ł���B���ɋ�����^�E���~�[�e�B���O�ł͕����Ȋw�Ȃ̒S���҂͌Ƒ��Ȏ�i��p���Ė��ӂ�U�����悤�Ƃ������_�����炩�ɂȂ����̂�����E�E�E�B
�@�܂������{���ɍ���J���Ĉӌ����q�ׂ����̕��ł���A�����Ǝ����𖾂炩�ɂ��Đ��X���X�Ǝ��_���q�ׂ�ׂ��ł���B�̂����Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ���A���ۂɎ��������̂悤�ɍs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ������ɃR�\�R�\������悤�Ȑl�ԂłȂ��Ƃ������Ƃ��A����ؖ�����̂��_�q�Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B
��\���I�̈Ӗ��F�l�ނ̖���
�@���͂悭�����_�Ƃ���A�D�g�t���[�Ƃ����l�́u��O�̔g�v�i�ʍ��ŏЉ��j�����p���邪�A����Ƃ͕ʂ�K�D�{�[���f�B���O�iKenneth E. Boulding�j�́u��\���I�̈Ӗ�
The Meaning of the Twentieth Century�v�Ƃ����{���Y���B�����I�����s�b�N���J�Â��ꂽ1964�N�ɏo�ł��ꂽ�{�ŁA���҂̓C�M���X���܂�̃A�����J�l�i�A���j�̌o�ϊw�҂������ł���B��g�V�����琴�������Y�ɂ��|�������B
�@�g�t���[�͐l�ނ̗��j��_�Ɗv���i���̔g�j�A�Y�Ɗv���i���̔g�j�A���v���i��O�̔g�j�̂R�ɕ��������A�{�[���f�B���O�͇@�����O�Љ��A�A�����Љ��A�B������Љ��ɕ����Ă���A�_�Ƃɂ���ė]��H�Ƃ̔��~���\�ɂȂ�܂ł̎����������O�Љ��A�_�ƂɌp���ōH�Ƃ��N�����ċZ�p�W�����Ă����̂������Љ��A�����Đ��E���ŕ��������قڊ������Ď��̕�����]�������z������̎����������Љ��ƒ�`���Ă���B
�@�����܂��Ɍ����g�t���[�̑��̔g�Ƒ��̔g�����킹���Z�p�v�V�̎��オ�{�[���f�B���O�̌��������Љ��ł���A�Q�l�Ƃ�20���I����21���I�ɂ����Đl�ޕ����͎��I�ȑ�]���𔗂��Ă���Ƃ����_�ł͈�v���Ă���B�������g�t���[�͂ǂ��炩�Ƃ����Ƒ�O�̔g�̓������y�ϓI�ɑ�����X��������̂ɑ��āA�{�[���f�B���O�̕��������Љ�����������Љ��ւ̈ڍs�͔��ɍ��������߂邾�낤�ƔߊϓI�\�������Ă���A�l�ނ����̑�]�������z�����ł̑傫�ȏ�ǂ���̓I�ɂS�����Ă���B
�@20���I���ɐl�ނ�҂��Ă���ł��낤�ƃ{�[���f�B���O���\��������̓I�ȏ�ǁ����Ƃ���(pitfall)�Ƃ͎��̂S�ł���B
A�j�푈�̗��Ƃ���
�@����͂��������猾���܂ł��Ȃ��B�푈�Ƃ́g�j�푈�h�̂��Ƃł���B�����͕ă\���卑�̊j�R�g�������l�ސ������������Ă����̂ł��邪�A�A�����J���\�A�����|���ĕ����߂����݁A�j�푈�̊�@�͋��������ƌ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�C�M���X�A�t�����X�A�����Ȃǂɑ����C���h�A�p�L�X�^�����j�����ɐ����A�k���N�A�C�����A�C�X���G���Ȃǂ��j����ۗL���ւ̖�S���ނ��o���ɂ��Ă���A�j����Ɋւ��鐢�E��͂���ɍ��ׂƂ��Ă����B�l�̃e�����X�g�ł������^�����������邱�Ƃ��\�ł���Ƃ��������Ă���̂��B
B)�l���̗��Ƃ���
�@�l�������̊�@�̂��Ƃł���B�o�����̒ቺ�킸�Ɏ�Ƃ��ē������S�������I�ɉ��P���ꂽ���Ƃɂ���Đl�ނ͐l�������̏d�ׂ�w�������ނ��ƂɂȂ����B�{�[���f�B���O�͐l�������ɂ���đ��������Ⴂ����ւ̋��炪�s�S�Ɋׂ�A�Љ�ւ̒m���̏W�ς��邱�Ƃ���ɋ���Ă����悤�����A���Ԃ͂���ɏd��ł���B�H�Ƃ␅�Ȃnĵ������Ă��������ɕK�v�s���Ȏ����̔z�����o���Ȃ��Ȃ�A���̐푈�͐A���n��Ζ����߂�����̂ł͂Ȃ��A�����␅��q�����ߎS�Ȑ킢�ɂȂ�Ƃ��������Ă���B
C)�Z�p�ɓ��݂��闎�Ƃ���
�@����̋Z�p�͂قƂ�ǂ��ׂĂ���Ƃ��ĐΖ��Ƃ������ΔR���Ɉˑ����Ă���A���ꂪ���̑�]���̑��g�ɂȂ��Ă���ƃ{�[���f�B���O�͎w�E����B�{�[���f�B���O�͒P�ɐΖ���ΒY�Ȃǂ̎����̌͊�����ԐS�z���Ă������A21���I�ɂȂ��Ă��܂������݁A���̗��Ƃ����͂���ɖ��Ȗ����܂�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�Ζ��̖����ʂ͓����\������Ă������������Ɛ��肳���悤�ɂȂ������A������R�₷���Ƃɂ���đ�C���ɕ��o������_���Y�f�ɂ��n�����g���������ł��Ȃ��Ȃ����̂ł���B�l�ނ̊������̂��̂��n�����ɏd��ȉe����^���A�l�ނ̐������̂��̂��������v���ƂȂ������A���������������ʃK�X�̔r�o���K�����悤�Ƃ��������₩�ȓw�́i���s�c�菑�j�������A�A�����J�A�����A�C���h�Ȃǂ̑卑�����ۂ��Ă��錻��������B���̂܂ܒn�����g�����i�߂A��ɂ�X�͂̕X���n���ĊC�ʂ��㏸���A�ُ�C�ۂ���`���ĕK�R�I�ɍk�n�ʐς̌����A�H�Ƃ̌��Y�A�H�����D�̂��߂̐푈�ւƑ������ꂪ����A�ȏ�R�̗��Ƃ����͕����I�Ȋ�@�ł�����̂��B
D)�l�Ԃ��̂��̂ɓ��݂��闎�Ƃ���
�@���ɐl�ނ����ׂĂ̊�@�����z���ĐV����������}�����Ƃ��Ă��A��������Z�p�I�ɂ����n���Ċ�@�̋��������ɂ����āA�l�ނ͂���܂łǂ��蔭�W�ւ̈ӗ~��ۂ������邱�Ƃ��o���邾�낤���B�v����Ƀn���O���[�łȂ��Ȃ����l�ނ͔��W��������đމ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����@�ł���B�{�[���f�B���O�͂�����w�̖@���ɏ������ăG���g���s�[�̗��Ƃ����Ƃ��Ă�ł���B�܂�M�͊w�I�Ɉ��艻�����n�ɂ����Ă͂��ׂĂ̔������~�܂�̂Ɏ��Ă���Ƃ������Ƃ��B����̓C�M���X��SF���H�DG�D�E�F���Y���u�^�C���}�V���v�̒��ŗ\�����Ă���B���{�ȂǖO�H�̐�i�����ɂ�����j�[�g(NEET)���́A���邢�͂��̗\�������m��Ȃ��B
�@�������čl���Ă݂�ƁA1960�N��Ƀ{�[���f�B���O�⑼�̑����̊w�҂������x�������l�ޕ����̊�@�͉��������ǂ��납�A����ɐ[�����A��s�����ĉ�X�ɓ˂������Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��낪�l�ނ͂���܂ň���ɉ����̂��߂ɗ͂����킹�悤�Ƃ͂��Ȃ��������A���݂����Ă��Ȃ��B���E�I�ȃ��x���ł̊j�R�k��������Ƃ͂Ȃ����A�����K�X�r�o�K����搂������s�c�菑�ɂ̓A�����J���Q�����悤�Ƃ������Ȃ��B���������l��������H���~�߂Ă��A���ꂪ�t�ɍГ�ł��邩�̂悤�ɑ�����������B�l�ނɂ͖{���ɖ��邢����������̂��낤���H
�@�������������������͂������ꍇ�A�Ō�̒��߂ɂ́u�l�ނ̉p�m�����W���ĉ]�X�v�Ƃ��u�����̉\����M���ĉ]�X�v�Ƃ��A��������̂Ȃ���]�I�A�y�ϓI�Ȍ��t�������Y����̂��A���ɓ��{�l�ɂƂ��Ă͈Öق̗����ɂȂ��Ă���t�V������B����͒P�Ȃ鎩�ȋ\�ԁA���������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ𐳒��ɔF�߂Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���H�����Ȃ��Ƃ��������ʒ��F�̋C�x�߂ɘf�킳��āA��@�ɗ����������ӎu�̕\�����x��邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�܂��܂���\���H
�@2006�N�̔N���͕��i�����]�v��TV�ɂ�������Ă�����i�̂́g�u���E���ǁh�ɂ�������ƕ\���������̂����A�ŋ߂�TV�͉t����ʂɂȂ��Ă��܂����j�A�܂����Ă��V������\���i��a���j���o�ꂵ���悤���B12��30�����f�́w�r�[�g�������̒��팻�ۃ}����t�@�C��2006�x�i�e���r�����j�ł���Ă����̂ŁA���������������Č��Ă��܂����B�������\���W�n�ł͂���B
�@��̃m�X�g���_���X�̑�\���ɂ��A1999�N�V���͋��|�̑剤���~���Ă��Đl�ނ͖ŖS����͂����������A��X�͉��Ƃ�21���I���}���Ă���B�ނ̗a�����̒��ɂ������g�}���X�h�Ƃ��g�A���S�����A�h�Ƃ������P����o���Ă���l�����Ȃ菭�Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����B
�@�����������͂��������ŖS��a���́A�����̎��Ƌ��ɐ��̒������ׂĖł�ł��܂��悢�Ƃ����l�Ԃ̃G�S�C�Y���𖣗����鈫���ȗ���唌�ɉ߂��Ȃ��Ǝv���Ă��邪�A����̃u���W���l�W���Z���[�m���̗a���́A�������ꏊ�����Ȃ��̓I�ł���Ƃ������Ƃŋ�����������ꂽ�B�v����Ƀm�X�g���_���X�̎��̂悤�ɒ��ۓI�ȒP�ꂪ����ł���킯�ł͂Ȃ������Ȃ̂��B
�@�Ⴆ�m�X�g���_���X�ł́u�|�`�̒��łQ�̑M�����P���v�Ƃ������t���A���{�ɗ��Ƃ��ꂽ�Q���̌�����\�����Ă����ȂǂƂ������ƂɂȂ�̂ŁA���ƂȂ��P���Ɋ�����ĈÎ��ɂ������Ă��܂��̂����A�W���Z���[�m���̗\���͐���N�ɂǂ��łǂ������������N����̂��𐳊m�Ɍ������Ă�̂��������B2001�N�̃j���[���[�N���������e�����A2004�N�̃C���h�m��Ôg���\�����I�m�ŁA���{�⎩���̂̊W�҂�������͂��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@�W���Z���[�m���͖����̏o�����Ō��邱�Ƃ��ł��āi�\�m���j�A���̍ЊQ�𖢑R�ɖh�����������߂Ɍx�����Ă���̂��Ƃ����B�m�X�g���_���X�̉���{�������Ĉ�ł��҂��܂���A�\�����O�ꂽ��͒m��������Ă���悤�ȗ~�[���l�Ԃ����Ƃ͐S��������Ă��邱�Ƃ͊m�����B
�@�ł�������Ƒ҂��Ă�B���������e���Ƃ��C���h�m��Ôg�Ȃǁg�ߋ��h�̎����������ɓI��������������āA�{���ɐM�p���Ă������̂����H�Ƃ����Ӓn���ȋ���������Ď��͔ԑg�����Ă����̂ł������B�ߋ��̑厖�����g�\���h�����Ə̂���l�Ԃ͐��E���ɉ���l������B
�@����������̃W���Z���[�m���̗a���Ɋւ��ẮA2007�N���ɐ^�U�̂قǂ����ł���d��Ȍ����ԑg�̒��ŏq�ׂ��Ă����B���������\���i�a���j�͊O��Ă��܂��Ɓu�����A�܂����v�ŏI����Ă��܂��āA�啔���̐l���Y��Ă��܂��X���ɂ���B�����Ŏ����N���N�n�̃q�}�ɂ܂����Ă��̃E�F�u�T�C�g�Ƀ����������c���Ă������Ǝv���������킯�ł���B
�@�W���Z���[�m���ɂ���2007�N�͑�ЊQ�̑����N���Ƃ����B�ނ�2007�N�ɋN���鎩�R�ЊQ���Q�����Ă����B
����̓g���R�Ȃǐ��A�W�A���ʂő�k�Ђ��N����B
��������͍��܂Ō������Ƃ��Ȃ��قǂ̑䕗���t�B���s�����P���B
���������ɂ��ׂ��\�������A�����ꂩ���O�ꂽ�ꍇ�i�����Ƃ��O��ė~�������j�A����ς�W���Z���[�m���̗\�����R����Ȃ����Ə�������Ƃ��ł���B���ЂP�N��̃E�F�u�X�V�ł͂��������������̂��B
�@�����������Ƃ��������Ă��܂����ꍇ�A���̌��̋@��͓��{�l�ɂƂ��Ď��ɐ؉H�l�����ƂȂ�B�W���Z���[�m����2008�N�X��13���i���̓��͓y�j���ł���j�ɃA�W�A�̂��鍑�ŁA�n�k�ƒÔg�̂��߂ɕS���l�P�ʂ̋]���҂��o��ƌ����Ă��邻���ł���I
�@�܂������K�X�r�o�K�����x���ƋC�����ێ�60�x���z���n�悪�o��Ƃ��i����͕ʂɗa���҂ɂ��Ȃ��Ă��{���ł���j�A�����2043�N�ɐl�ޖŖS�Ƃ��c�B�܂��A�O����\���I�̈Ӗ��ł��������Ƃ���A�ʂɗ\���ҁi�a���ҁj����������Ȃ�������20���I�㔼����21���I�ɂ����Ă̐l�ޕ����͍j�n��̘A���Ȃ̂ł���B�a�����O��Ă����ǂ͓������A�ł͉��ɂ��Ȃ�Ȃ��B
���j�ς̑��ΐ�
�@2006�N�͑����m�푈�ő�̌���ƌ���ꂽ�������U�h�����đo������`�����푈�f��삪���J����Ęb����ĂB�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h(Clint
Eastwood)�ēɂ��w���e�����̐������x�Ɓw����������̎莆�x�ŁA���͂܂��ǂ�����ςĂ��Ȃ��̂œ��e�ɂ��Ă͌���@�����Ώ������Ƃɂ��āA����͑o��������j��������Ӌ`�ɂ��čl���Ă݂��B
�@���́g��������h�͕č��̃C�[�X�g�E�b�h�ē����đo���̎��_����f��𐧍삵���̂ł����āA���{���̎��_�͓��{�l���ē����킯�ł͂Ȃ��B�����Ƃ��č��l�ē����삵���ɂ�������炸�A�ʏ�̕č���y�f��̎�@�̂悤�ɒP�Ȃ銩�P�����i���Ē����j�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ́A�e��̔�]��\���҉f���A�ςĂ����l�����̘b����قږ��炩�ł���B
�@�܂���{�R�𐬔s���ׂ����ʂƂ��ĕ`���Ă����Ȃ����A�����̕č��̂�������ΐ��`�Ƃ��Ă��`���Ă��Ȃ��B���̂悤�ɂP�l�̕č��l�����G�����̘g���āA�������U�h��̗��j��U��Ԃ낤�Ƃ����Ӌ`�͑傫���Ǝv�����A����͓��Ă݂̂Ȃ炸�A�����E���E�����E���I�i���\�j�E�����E�����Ȃǂ�����̍��ƊԂ̗��j�������邤���ł���ȑԓx�ł͂Ȃ��낤���B
�@����̃C�[�X�g�E�b�h�ē͂��܂��ܕč��l���������A�č��l�ɂ��������ԓx������������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���͂����������Ђ��āA�C�[�X�g�E�b�h�ēl�̗��j�I�ԓx���^�������Ǝv���B
�@�C�[�X�g�E�b�h�ē�1930�N���܂�A�������U�h��̍��͂����炭�����ȐN������}���Ă����B�ނ̖ڂɂ͑���{�鍑����{�R�͂ǂ��ʂ��Ă������낤���B�i�`�X�h�C�c�Ǝ�����сA�A�W�A�ɐi�o���ĉ��Ă̗�����W�Q���A�^��p���x�܂������������Ă������c�B�����čD�ӓI�Ɍ��邱�Ƃ͏o���Ȃ������͂��ł���B
�@�����������Q���z���ē��ČR�l�������ɒ��߂���悤�ɂȂ�A���邢�͌����ɒ��߂Ȃ�������Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�܂łɂ́A�����Ԃ����Ԃ��K�v�������̂ł͂Ȃ����B���\�N���̒������Ԃ������āA���Ď����̍��̐l�X�ƎE���������G���̐l�X���܂������l�Ԃł���A���ꂼ��̒u���ꂽ���Ƃ̎���ɂ���ĐS�Ȃ炸���s�K�ȗ��j������ł��܂����Ƃ����F�������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@��X���C�[�X�g�E�b�h�ē���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̗��j�I�ԓx�ł���B���{�͌��݁A������؍��Ƃ̊Ԃ̗��j�F���ɂ��Č����ėǍD�ȏɂ͂Ȃ��B�����̗��j�������闼���̋�����Ƃ��v�悳��Ă���Ƃ������A�����o���̌����҂ɃC�[�X�g�E�b�h�ē̗��j�I�ԓx���Ȃ���ΐ�ɂ��܂������Ȃ��B
�@�Ⴆ�Γ��{�����猩��ꍇ�A�����̒����l�̐g�ɂȂ��čl���Ă݂�ǂ��Ȃ邩�H�Ή�21�����ȂǂƂ����A���n�I�v����˂������A���{�R�ɒ����e�n�̗v�����̂���A�����@����P���d�|���Ă����c�A�����͓���������t�]���čl�����ꍇ�A���Ȃ킿�Γ��A���n�v����˂������A���{���y�������R�����W����A�܂Ŏ����j���������Ɖ��肵���ꍇ�A���{�l�͉ߋ��̒����������邾�낤���Ƃ������ƂɂȂ����Ă���B�i������������I�ɔj���ĐN�U���A�k���̓y�𗩂ߎ�����\�A����{�l�̑啔���͋����Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����B�j
�@���ĂƓ����̗��j�̖{���͈قȂ��Ă��邯��ǂ��A���荑�̍������܂������l�Ԃł���Ƃ����F��������A������̏ꍇ�ł��݂��̗��j�ɑ��Ăǂ������ɂ݂������邩�͂����ɗ����ł���͂��ł���B
�@�����đ��荑�̐l�Ԃ̐g�ɂȂ��čl���Ă����A�p���đ��荑���̔�����R�Ɍ����Ă���B�Ⴆ�Γ����ߑ�j���s�K�ɐ��ڂ����傫�Ȍ����͒����i�����j�̑Γ����́A�Γ������ɂ������Ǝ��͎v���Ă���B�ߋ��̉h���������ɒ��āA���荑�𐪕��ł���قǂ̋���ȌR�͂ŋ�����������A���Ƃ������Ƃ����ǂ��ǂ��������������邩�A�������̗��j�����҂ɂ������l�ԂƂ��čl���ė~�����B���̑Γ������̌����ʍ��ŏڂ����q�ׂĂ���B
�@���j�F���̑���ɂ��ẮA�݂��ɐ����Ɏ����̐��������咣�������A���̑傫�����������Ƃ��������ŗǂ��̂��H�����I�ɂ͂���Ō�����������̂����m��Ȃ����A����ł͗��j�͊w��ƂȂ蓾�Ȃ��B���j�͂����̐����̎�i�ł���Ƃ����Ȃ炻����\��Ȃ����A���ɂ͎���邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ł���B
�@�C�[�X�g�E�b�h�ēɂ�闰�����U�h��̉f���̓A�����J�ł������̕]���͎��悤�����A�ł͌����̉f�悪���l�Ȏ�@�Ő��삳�ꂽ�ꍇ�A�ǂ��������ƂɂȂ邾�낤���B�c�O�Ȃ���܂��A�����J�Љ�̓q���V�}�E�i�K�T�L�̗��j����đo���̎��_�ŕ`�����f��܂ł������ɂ͓����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�����푈��1970�N��ɎR�{�F�v�ēɂ���ĉf�扻���ꂽ�ܖ��쏃������́w�푈�Ɛl�ԁx�Ȃǂ͓����o���̎��_���ӎ��������ŁA�����������_���ɒ[�ɖڂ̋w�ɂ���l�����{�ł͂܂���������ǁA����Ȃ�ɂ�����Ƃ��������ȕ]����ۂ��Ă���B���Ȃ��Ƃ����y�ɊO���i���{�j�̌R���̒��������i�����⒩�N�j�����̗���������ɕ`�����Ƃ���ԓx�́A����̃C�[�X�g�E�b�h�ēƋ��ʂ���̂ł͂Ȃ����B�c�O�Ȃ��璆�������ɂ͂��������ԓx�͂��肻�����Ȃ��B�i�����ɂƂ��Ă͈���I�Ȗ��ߎ��̔�Q�҂ōςނ̂��Ƃ������ł���B�j
�@�ł͌��݂̖k���N�Ƃ̊W���A���\�N������Ό����Ɍ�����悤�ɂȂ�̂��낤���B����������������Ƒ������ƍِ����̉��Łg�c���h�ւ̈��ƒ����𐾂킹���A�\���ȍ��ۏ����^�����ʂ܂܂ɓ��{��č���؍����g�G�h�Ƌ������܂�A����P�����Ċ댯�C���ɕ������ꂽ��҂������A�����l�ԂƂ��Č����ɕ`������������ꗈ��̂��낤���B
 |
|
 |
�@����͉��l�`�̊C��ۈ����{�݂ɓW������Ă���k���N�̍H��D�i�s�R�D�j���B���{�̏����D�ƌ�킵�Ď���������A�����グ���Ē������ꂽ�D�̂ł���B��ɐ��ˍۊO����W�J���ċߗ����Ԃْ̋������߁A�O���l�f�v�▃�A�E�U�D�����Ȃǂ̔ƍߍs�ׂΌ��R�ƍs�Ȃ��A����͂��Ɋj�����܂ŋ��s�����k���N�ɑ��A��X�ŋ߂̓��{�l�͂ǂ����Ă��G�ӂ��Ɋ����Ă��܂��B
�@���������ƍِ����̉��Ő��]������čH����ƂȂ�A�ꂵ���P���̖������̉ʂĂɁA����ȑe���ȍH��D�ɏ���ē��{�C�ɏ��o���Đ������������k���N�̎�҂������A�D�ӓI�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�����l�ԂƂ��Č����Ɍ��邱�Ƃ̏o�������������͗��ė~�����Ǝv���B
�������㗤���̓�
�@���N2007�N�͗��������̂�����1945�N�Ɠ����j���ɂȂ�B�܂藰�����㗤���J�n���ꂽ�Q��19���͍��N�Ɠ��������j���������B�㗤���J�n�O��̓��j���A���ɂ����������{�R�������s���Ƌ��|�ɏP���Ă������낤���A�㗤���T�����A�����J�C�������̕s���Ƌ��|�������Ȃ��̂������̂ł͂Ȃ����B�A�����J���w�����Ƃ���A���j���ɏ\���ȋx��������ďT��������g�d���h�Ƃ����Z�i�ł������낤���A���ۂɓ��{�R�̏e�e�𗁂т镺�m�����́A�E�҉ʊ����G�ɕ`�����悤�ȊC����������ł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�����炭�����̎����̐������v���A�̋��̉Ƒ����v���A���̓��j�����i���ɑ����Ă��ꂽ�炢���Ɗ���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B���݂̉�X�̂悤�ȓG�e�����ŗ��Ȃ��E��ł����A�T�����̎d���n�߂͗J�T�ł���B
�@�Ƃ���œ����̗������̓��{�R�w�n�̍U���̓A�����J�C�����ȊO�ɂ͕s�\�������̂ł͂Ȃ��낤���B���������{�R��������ɂ��܂ʗE�҂ȌR���Ȃ�A�U�߂�A�����J�C�������܂�������ɂ��܂ʗE�҂��ɂ����Ă͓��{�R�ɏ���Ƃ����Ȃ����̂������B���������̃h�C�c��\�A���܂ރ��[���b�p�����̌R���ł���A���J�n�����Ԃ̑��Q�ɋ���œ��̒D���f�O�����ł��낤���A���������}�R�������������ɂ��Ă����������낤�B���̕��͕���������̖��a�@�ň��|�I�ȍ����}�R�ɕ�͂��ꂽ���A�G�͓��{�R�Ƃ̔����������čU�߂ė��Ȃ������Ƃ����B�������H�R�͂����ƗE�҂������炵�����A����͎w�������������c���ɕ��ׂēG�w�ɓ˓������A�����镺���͌�납��ˎE�����Ƃ�������A����ł͕����͑O�i�ނ�葼�Ɏd���Ȃ��ł͂Ȃ����B���������̐�@�ł͗������̓��{�R�w�n�͔����Ȃ��B
�@�v����ɉ��������������Ƃ����A��6800�l���̐펀�҂��o���Ă܂œ����̂���ӎu�ƗE�C�ƋZ�ʂ��������R���̓A�����J�C�����������đ��ɖ��������Ƃ������Ƃł���B�A�����J���R�i�C�����Ƃ͕ʑg�D�j�ł����P�Ƃŗ������ɐ������𗧂Ă�܂Ő�ӂ��ێ��ł������ǂ����B
�@�t�Ɍ����A�A�����J�ɂƂ��Ă����܂ł��ė�������D�悷��K�v���������̂��낤���B�����������㗤���̓�Ə������̂͂܂��ɂ��̓_�ł���B�o���U�C�ˌ����A�ʍӂ��A���U�����ƁA�l�������т̌y���ɚg���Ďg���̂Ăɂ�����{�R�Ƃ͈قȂ�A�A�����J�R�͈ꕺ���̐����ł����������Ė��ʂɂ͎��킹�Ȃ��̂ł͂Ȃ��������B
�@�A�����J�̑Γ���{�헪�́A�}�b�J�[�T�[���R�̃t�B���s���E���ꃉ�C���ƁA�j�~�b�c��̃}���A�i�E���}�����C���́A���v�Q�{�̖�œ��{�{�y�ɔ���Ƃ������̂������B�A�����J�R�͏\���ȗ]�T�������đΓ���ɗՂ�ł���A�}�b�J�[�T�[���R�̒S�����ɂ��Ă��A���{�R�̓�����_���������o�E��������Ɏc���ăt�B���s�����U�����Ă���B����͊J�퓖���A���{�R�̍U���Ƀt�B���s����ǂ�ꂽ�}�b�J�[�T�[�̈Ӓn���������ɈႢ�Ȃ����A�w��̃��o�E������u�����܂܃t�B���s�����U�߂�Ƃ����̂́A�ʏ�Ȃ畠�w�ɓG���ċ������ɂ����댯��`�����ƂɂȂ�B���������{�R�����o�E���Ɏc���Ă����Ă��\���h�������Ƃ������M���A�����J�R�ɂ͂��������炱���A�����Đl���Ղ��郉�o�E���㗤����������̂ł͂Ȃ����B
�@���{�R�͂������S���r�߂��Ă����ƌ����Ă悢�B�t�B���s���𗎂Ƃ�����͑�p��f�ʂ肵�ĉ�����U�߂邱�Ƃ����肳�ꂽ�̂�1944�N�X���A�܂��t�B���s����킪�{�i�I�Ɏn�܂��Ă��Ȃ��i�K�ł���B���Q���o���Ă܂ő�p�ɏ㗤�������s����K�v�͂Ȃ��A�������Ɖ�����̂��ē��{�{�y�ə����˂����悤�Ƃ����_���ł���B�s�v�ȏ㗤���ŕ����Ղ��邱�Ƃ͔�����Ƃ����A�����J�R�̊�{�p�����M����B
�@�ł͂Ȃ����������U�߂��̂��낤���B�������U�������肳�ꂽ�̂�1944�N�X���A�t�B���s���U����͑�p��f�ʂ肵�ĉ���ɏ㗤����Ƃ������j�����肳�ꂽ�̂Ɠ����ȏ�ł���B�����̃A�����J�R�̐�͂��l����A�}���A�i�����𑫏�ɂ��āA�������̓��z���ɓ��{�{�y�㗤�����s�\�ł͂Ȃ������B
�@��ʂɂ́A�}���A�i�������ї����ē��{�{�y��P���s�Ȃ��Ă���B29�����@�����������ꍇ�̕s������n���~���������A�܂�B29����q���čs��P51�퓬�@�̊�n���~���������A������K���ɗ����������ɍs�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B
�@�������������㗤���J�n�����Q��19���܂ŁA�}���A�i��n���璼�ړ��{�{�y��P���s�Ȃ����͓̂����A���É��A�_�˂Ȃǂv18��A����1602�@���o������71�@�r���Ƃ������x�ł��邩��i�u�ۃX�y�V���������m�푈�C���V���[�Y�v���j�A�m��ɕs�������Đ����͂��s���ɋ~������铋������������Ƃ��l������A����l���̊C���������]���ɂ��Ă܂ŗ�������D�悷��K�v���͊������Ȃ��BB29�̑r�����̓��[���b�p�ł̑h�C�c�헪�����̑��Q�������Ă����炵�����A�㗤���J�n�O�A���{�R������̐��͂P������l�Ɛ��肳��Ă�������A�����ɍ�킪���ڂ��Đl�����Q����{�R��1/10�ȉ��ƌ��ς������Ƃ��Ă���1000�l�̃A�����J�R���m����������̂ł���BB29�����@�̓�����̎��������������S�l�Ƃ͈�������Ȃ��B�������������㗤���̍�����A���{�{�y��P�͖�ԏĈΒe�U���ɕ��j�ύX���ꂽ�B���������Č�q�퓬�@�̕K�v���]�X�����܂�d�v�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@����ɗ�������s��̓��{�R�퓬�@��B29�����@��҂��������čU�����邱�Ƃ�����Ƃ͌����Ă��AB29�ґ��̒ʉߎ��Ԃɍ��킹�ė������Ɋ͖C�ˌ��������邩�A���͍̊ڋ@�����Ĉꎞ�������Ă����悢�̂ł���B�C�����̏㗤���ɔ������Q�ɔ�ׂ�Ε��̐��ł͂Ȃ��B
�@�ł͂Ȃ��㗤����A�C�����̑��Q�������̗\�z���͂邩�ɏ����Ă��Ă���̂ɁA�����ꎞ���~���Ȃ������̂��낤���B�����̐l����D�悷��A�����J�R���������ɗ͍U�߂������͔̂��ɕs�v�c�ł���B���o�E�����p�ɑ���㗤����]�T�ŃL�����Z�������A�����J�R�Ƃ͎v���Ȃ��B�����������͂ȗv�ǂ���������w��Ɏc���킯�ɂ͂����Ȃ������Ƃ����̂������ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�A�����J�R�͓����A�������Ȃǂ͂��������P�T�Ԃŗ��Ƃ���Ɨ\�z���Ă����̂ł��邵�A�������{�{�y�㗤��킪�J�n�����Η������Ȃǂ͕⋋�������ČǗ������A�d��ȋ��Ђɂ͂Ȃ蓾�Ȃ�����ł���B
�@���͂����ɃA�����J�Ƃ������Ƃ̐��ւ̈ӎu��������B�������㗤���̍s�Ȃ�ꂽ1945�N�̂Q������R�����A�A�����J�R�����ɗ\�肵�Ă����͉̂���㗤�Ɠ��{�{�y�㗤�ł���B�������㗤���������{�{�y�㗤�̗\�s���K�̈Ӗ��������Ă������Ƃ͊m�����낤���A�����ȌR���v�ǂւ̍U���͂��ꂪ�Ō�̃`�����X�Ȃ̂��B�A�����J�C�����̓K�_���J�i�����ȗ��A�����̉��ǂ���̎蒼���Ȃǂ��܂��܂Ȍo����ς�ł����A���̕��K�����Ă������������̂ł͂Ȃ����B
�@���̂��߂Ɂc�H����͂��̌�A���N�푈��x�g�i���푈�ł̃A�����J�C�����̔��ʘZ�]�̊��������Δ���B�C�����Ƃ́A�n�㕔���Ƃ�����x������͒���q��@����̂ƂȂ��āA�n���ア���Ȃ�n��ւ��}���ɓW�J�ł��闤�E�C�E����͂̃��j�b�g�ł���B�A�����J�ɂƂ��ẮA�������œ|��ɍT���Ă��鋤�Y��`���ƂƂ̐푈�𐋍s���邽�߂ɁA�ǂ����Ă��������Ƃ̏o���Ȃ��M�d�ȑ��݂������B
�@���͂���{��œ|���邽�߂ɂ͂���قǕK�v�ł��Ȃ������������B����͎��̉��z�G���A�\�A��M���Ƃ��鋤�Y�������Ɍ����Ă��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����̂����̌����ł���B���ꂪ�����̗\�z���͂邩�ɏ��鑹�Q���o���Ă��܂����B�A�����J�R��w�������͘T�������Ƃ���A�܂��ɂ��̓_�Ɋւ��Ăł���B�A�����J�R�ɂ��Ă͒������A�㗤����������2000�l�ȏオ�펀�����Ƃ����̂ɁA�P�T�Ԍ�̍��������ł͐펀��644�l�Ƃ������\���Ă��Ȃ��B��w���ɂƂ��Ă����ɏՌ��I���������B���ė����Ƃ̈Ӓn�ƃ����c�����̂��߂ɗ������ɓ|�ꂽ���R�����ɑ��āA���͓������܂��ւ����Ȃ��B
�����D�_
�@�ŋ߁A�S���e�n�Ń}���z�[���̊W���A�K�[�h���[�����A���h���̔������̋������i������̔�Q�ɑ����Ă���Ƃ����������B���݂͕ʂɉΎ��������Ă�������@���Ēm�点��Ƃ�������ł͂Ȃ����A��͂���h�̏ے��ł���L�O�i�̔����܂ł����܂��Ƃ����̂͗R�X�������Ԃł���B�����������𓐂ނ̂́A�������܂��Ɂg���h�ɂȂ邩��ł����āA���̂����Ƃ̑��g�A�X�̃V���b�^�[�A�d����p�C�v�A���]�ԂȂǂ���A���ԏ�ɒ�߂Ă����������Ԃ̕��i��S���̃��[���܂ŁA�����ł���Ή��ł�����ł��_���鎞�オ����͎̂��Ԃ̖�肾�B
�@�Ƃ���ōŋ߁A�l�ނ̈��W���関����\������悤�ȐV���L�����Ђ�����ƌf�ڂ���Ă����̂���L���̕��͂ǂꂭ�炢���������邾�낤���B2007�N�Q��16���̖����V���[���̊Y���L����S�����p���悤�B
�u��������2050�N�ɂ��͊��v
�@BRICs�����ƌĂ�钆����C���h�Ȃǂ̌o�ϐ��������݂̂܂ܑ����ƁA���A���A�����A���A��ȂǑ����̋���������2050�N�܂łɌ͊�����Ƃ̗\�����E�ޗ������@�\���܂Ƃ߂��B�S�┒���͔�r�I�L�x��100�N�ȏ�̌@�\�Ƃ��鎎�Z���ߋ��ɂ��������A�����50�N�܂łɗݐώg�p�ʂ��̖����ʂɒB����Ǝ��Z���ꂽ�B���@�\�́u���̂܂܂ł͒n���K�͂ł̌o�ϔ��W��d���Ȃ��v�ƌx�����Ă���B
�@���@�\�́A�ߋ�50�N�Ԃɓ��{���g�p����21��ނ̋����̎g�p�ʂƌo�ϐ������Ƃ̑��ւׂ��B������A��i���ƒ����A�C���h�A���V�A�A�u���W����BRICs�̌o�ϐ����\���ɓ��Ă͂߁A�e�������Ƃ�50�N�܂ł̗ݐώg�p�ʂ����Z�B���A���A�����A���A��A���A�j�b�P���Ȃ�12��ނ̗ݐώg�p�ʂ͌����_�̖̉����ʂ�����A�C���W�E����72�{�A���10�{�A���A���͖�U�{�ƂȂ����B
�@��r�I�L�x�Ƃ����Ă���S�┒�����A50�N�܂łɂ͉̖����ʂɕC�G����g�p�ʂɒB���邱�Ƃ��킩�����B�@�y���ˎ���q�L�ҁz
�Ƃ������Ƃ����A����͐l�ނɑ���]���鍐�ɂ��������̂ł͂Ȃ����B�l�ނ͌o�ϊ������~�߂āA�����玩�������̎�����ɋt�߂肷��킯�ɂ͂����Ȃ��B�o�ϊ����ɕK�v�Ȃ̂̓G�l���M�[�����������A�Ƃ�킯�����͏d�v�ȍޗ��ł���B���̋�������������50�N�����Ȃ������ɍ̂�s������Ă��܂��B�G�T�͂���50�N��������܂����Ƃ����鍐�ł���B
�@���đ��Â̎���A������A�����a�Ƃ��đ��H�������ɉh���A���H�������a�Ƃ�����H�������N�Ղ����B�A�����ɖ��₷���C�����̂��K���A���H���������H�������L�x�ȐH���̂������łǂ�ǂ�̂����剻���Ă������B�����Ēn���̋C��ϓ��ƂƂ��ɃG�T���Ȃ��Ȃ�A�����͐�ł����B
�@����Ɠ������Ƃ��Ԃ��Ȃ��l�ނɋN����B�ȂɁA50�N�̊Ԃɂ͋����̌@�Z�p���i�����邵�A���T�C�N���Z�p�����B���Đl�ނ��~�����낤�ȂǂƊy�ς��Ă��Ă͂����Ȃ��B�����̋Z�p�̐i���͂��邾�낤���A�l�ނ��g�p�ł���e������̗ʂ��ꋓ�ɂQ�{�ɂ��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B���ɂQ�{�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�l�ނ̗]����50�N����100�N�ɉ��т邾���ł���B
�@����܂ł͐Ζ��̖����ʂɌ��肪����Ƃ��A�Ζ���R�₹�Βn�������g������Ƃ��A�G�l���M�[�̖ʂ��������l�����Ă��Ȃ������t�V�����邪�A���x�͐l�ނ̌o�ϊ����̃G�T���̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��B�H�����s�����Ă���ΐl�Ԃ͑��l�̕��𓐂�łł��Q���������Ƃ��Đ�܂����s���ɑ���B������}���z�[���̊W�̐ޓ��͂�����������̗\���ł���B
�@�����l�ނɏ����铹���킸���ł�����Ƃ���A����͚M���ނⒹ�ނɊw�Ԃ��Ƃł���B�n����̐H�Ƃ��͊����ċ�����������ł��Ă��������A�M���ނⒹ�ނ����̓G�l���M�[�����̗ǂ������ȑ̌^�����Ă����B���ɒ��ނ͋�������i�������ƌ�����B�G�T���L�x�Ȏ���ł���A���̂��傫�������͂������Ď����������A�����ȓ������͐��������ɓK���Ă������낤���A�G�T���R�����Ȃ�ΐ}�̂��f�J�C�����̃��c�͎��ł��邵���Ȃ��̂ł���B
�@�A�����J�Ƃ�EU�Ƃ�BRICs�Ƃ����{�Ƃ��������������ł��Ă�������A���ނ̂悤�ɐ����c��鍑��n��͂ǂ����A�n�}�����J���ĒT���Ă݂���悩�낤�B���͂�o�ϐ�i���̐}�̂�����������p���Ȃ��ȏ�A�������������ȍ��X�܂ł�푈�≷�g���ŖŖS�̓��A��ɂ��Ȃ����Ƃ������A�l�ނƂ����푰�̊�]�𖢗��ɂȂ����@���Ǝv���B
���������H
�@2006�N�Ɉ��{�W�O�������a�����Ĉȗ��A�u���������v�Ƃ������t���悭���ɂ���B�����������肪���{�����̃L���b�`�t���[�Y�������ŁA���炪���҂ƂȂ��������̖{�������Ԕ��ꂽ�炵���B���������c�A�܂��X�������͌��\�ł������܂����c�B
�@���������Ƃ������ʂ����߂Č������A���̓A�����J�̂��Ƃ��Ǝv�����B���Ɠ�����̐l�����Ȃ�o���Ă�����Ǝv�����A1960�N�ォ��1970�N��ɂ����āA�����̕�����v����ёv�z�ɂ��Ԃꂽ�����w���^���Ƃ����̔��ē���������オ���Ă����B��w�̃L�����p�X�ɂ͊w���^���̏ے��ł��������ĊŔi�^�e�Łj���Y�����Ɨ������сA�A�����J�鍑��`��œ|����Ƃ����X���[�K�����Ɠ��̉������̂ʼn��菑������Ă������̂ł���B
�@�w���^���Ƃ����̒��ɂ͂��������^�e�łɁw�����鍑��`�œ|�x�Ƃ͏������ɁA�ނ�̐��q����ё̌̋������ɕ���āw�����鍑��`�œ|�x�Ə����҂����������B�����Ƃ͒�����ŃA�����J�̂��Ƃł���B�R���Ǝv���Ȃ�l�b�g�Łu�����v�Ɠ���Č�������A�A�����J�֘A�̒�����T�C�g��������������|�����Ă���B�b�̂��łɂ��������T�C�g����A�����J�̏B��������E���Ă݂����A�ǂ߂܂����H�ĈЈΏB�A�H�Վz���ߏB�A�m����B�A���[���B�A��������B�A�֑�\�B�A���z�f�z���B�A����B�A���f�z���B�A�Ŗ֓��B�A�Ўz�N���B�A���m�F�B�A�N��ཊi�B�c�B
�@���V�т͂��ꂭ�炢�ɂ��āA���{�̂������������Ƃ̓A�����J�̂��Ƃ��낤���B����O�Ɠ������A���̐l���A�����J�ׂ�����A�A�����J�ɂ����ی����ꂽ�炠�Ƃ͉��̍�����������Ȃ��Ƃ́A�k���N���łU�������c�̌o�߂Ȃ��Ă��Ă����炩�����A�܂��������������A�����J���̂��̂ł͂Ȃ��낤�B
�@�{���͍��̃g�b�v�ɗ������Ƃ������������ۓI�ȕ\���ō��̖�������邱�Ƃ͖]�܂����Ȃ��B��̓I�Ȓ�`�̗��Â����Ȃ����炾�B�u���������v�ƌ���ꂽ���ɓ��Ɏv���`���C���[�W�͐l���ꂼ��ɂ���Ă܂������قȂ��Ă���B�����Ăǂ������C���[�W��`�����Ƃ��Ă��A�u���������v�́u�X�����v�����ǂ��Ɍ��܂��Ă��邩��A�����Ƃ���u���Ȃ��͔��������ɔ��ł����H�v�ƕ������A�N�����āu����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�^���ł��v�Ɠ�������Ȃ��B
�@���ꂪ���Ɋ댯�Ȃ̂ł���B�Ⴆ�u���������́H�v�Ɩ��ꂽ�������A�R�������A�������Z�ȍ��y���v�������ׂāu���������v�̃X���[�K�����x�������Ƃ��Ă��A�����Ƃ̕��́A��w�����疽������Γ��U���Ƃ��āg�������h���ɂɍs���������吨���鍑���C���[�W���Ă���ꍇ�����蓾��B������v�ɂ����錾���Ȃnj��Ă���ƁA�����炭���{�̍��_�͂������낤�B
�@�����ƂƂ������̂͂��������_���̂���ւ����I�݂ɂ��̂ł���B���̍D�Ⴊ�u���R�v�Ƃ������t�ł���B�u���R�͗ǂ����Ƃ��A���̍��͎��R�Ȃv�ƌ����Ă��������A�����ɂ͎v�z�⌾�_��w��̎��R�Ȃǁg���_�I�Ȏ��R�h�̃o���F�̃C���[�W��U��܂��Ȃ���A���ۂɂ͋����҂��ア�҂����R�ɐH�����ɂ���g�o�ϓI�Ȏ��R�h�Ɋ�Â�����𐄂��i�߂Ă����ł͂Ȃ����B����g���_�I���R�h�Ɓg�o�ϓI���R�h�̈Ⴂ���A�@���ȂǏK��Ȃ������l�ł����{�����Ȃ�\���g�ɂ��݂Ďv���m�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�u���������v�Ɋւ���o���F�̃C���[�W�������ݒ��X�Ɛi�s���ł���B���y��ʏȂ̃E�F�u�T�C�g�Ȃnj���ƁA�܂��ɎR�������A�������Z�ȍ��y�̃C���[�W���U��߂��Ă���B�������N���_����͌����⒪���ߒ�h�Ȃǂ̉ߏ�Ȍ������ƂŎ��R�̐��Ԍn���Ă����̂��H�N���S���t��Ȃǂɑ�\����鍑�y�̗��J���������Ă����̂��H
�@�܂��u���������v���Ă����͔̂p�������ԕ��u��S�~�����Ȃǃ������̖����s�ׂł���Ƃ��āA��ʍ����̐S���������Ȃ����炾�ƌ�������̕\��������B�m���ɍ����̃��������r�p�������邱�Ƃ͎����ł��邪�A�ł͐����Ƃ͂ǂ��Ȃ̂��H���M������̋c����ق��������ɂ��Ă��Ȃ���A�N�Ԑ��S���~���������o��Ɍv�サ�Ă�����b���������B�m���ɂ��������g�������h�F��̃������͈�ʏ����ɂ͌����Ȃ��B
�@���̂Ƃ�����{���C����āu���������v�Ȃǂƌ��ɂ��Ă݂��Ƃ���ŁA�����̍������V�����đ���ɂ��Ă��Ȃ��悤�Ɍ����邱�Ƃ������~���ł���B�����͍����������Ƃ�����Ⴊ�삦���̂��A����Ƃ����{���ǂ����悤���Ȃ����Ԓm�炸�ō������o������Ȃ������Ȃ̂��B
���̏]�R�L�|�Γ�i�R���|
�@2002�N�W�����A�����|�ꂽ�ƕꂩ��A�����������B���̔N�̂R���ɂ͔����I��������@��߂Ĉ��ނ������肾�����̂ŁA���������̈�҂Ƃ��Ȃ�Ǝ����̎���������Đl���̌�Еt�������Ă�������̂��Ɗ��S�ɒ^��Ȃ�����ƂɌ������B���ւł͕�ƒ�v�w���A����ŕ��Ƃ̍����̕ʂ�Ƃ����悤�Ȕߑs�Ȋ�ŏo�}�����B�������Ō�̍F�{�Ŗ����̖�����点�ĖႨ���Ɗo�債�Ė����ɍs������A���Ƃ����̒E���ł������B�m���Ɉӎ��͞N�O�Ƃ��ĉ����͖����̂����A�������܂������o�Ă��Ȃ��B�A�t�̂P�{����������߂邾�낤�Ǝv���A���̋Ζ������w�a�@�ɓ��@�������B
�@���ǁA���̐f�f�͐������A�����V�ɏ�����邱�Ƃ͂Ȃ������̂����A�����ꂻ�������������邱�Ƃ����߂Ď���������ꂽ�o�����ł������B�����Ȃ�Ε��������ŕ��������Ղ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�����^����Ɏv�����̂͂��̂��Ƃ������B�������ɘR�ꂸ�䂪�Ƃł����q�ɂƂ��ĕ��e�͉��������݂ł͂��������A����ł܂����e�̑��Ղ�ǂ������Ă݂����Ƃ����v�������������̂ł���B�����푈���ɒ�������ɏ]�R�������Ƃ��A�������͗c���ȗ��A����̘b�̒[�X����M���m�邱�Ƃ͂ł����B��������͖k���̘b�ł�������A����̘b�ł�������A�g�q�]�̘b�ł������肵�Ă����ς�v�̂Ȃ��̂ł���B�����ʼn��Ƃ����̓��@�̋@��𗘗p���āA�����ʂ������Ղ������ł��������Ă�������͖������̂��낤���ƍl�����B
�@�������͂��܂蒆���ł̏]�R�̌��ɂ��ē��ӂɂȂ��Č�邱�Ƃ͂Ȃ������悤�Ɏv���B����͂������낤�A��������o���҂ł��A����ŕč��R�ƑΛ������l�����ɂ́A�A���R�̕��ʑ���ɂ悭�撣�����Ƃ����^��������B�r���}���ʂʼnp��R�Ƒΐ킵���l�����ɂ́A���d�ȍ��ő�ςł����˂Ƃ����˂��炢�̌��t������B�܂����B���ʂɂ����l�����ɂ́A���\�ȃ\�A�ɐ��������}������Ă���J�ł����Ƃ������t������B��������������ɍs�����l�����ɂ́A�N���҂Ƃ��Ē����l���������߂���Ȃ����Ƃ����₽���ڂ��������邱�Ƃ̕������̓��{�ł͑��������̂ł͂Ȃ����B��������Ƃ����Γ싞��s�E�Ƃ��V�R�P�����̐l�̎����Ƃ��A�����嗤�̓��{�R�ɂ̓i�`�X�h�C�c��̈����C���[�W���蒅���Ă��܂����B
�@����ł͕��Ɍ��炸�A�����������̋A�ҏ��������̑����͌����������Ȃ����낤�B�����������̋A�҂̊m���͓����r���}�Ȃǂ̌���n�ɔ�ׂ���Ȃ荂�������Ǝv���邪�A���ɂȂ��Ă���o�ł��ꂽ���R��L�̐��́A�A�҂����͂��̕������ɔ䂵�Ė��炩�ɏ��Ȃ������Ǝv����B��́A���a30�N��̏��N����T�����ɂ͐�͑�a�Ƃ����┹�Ƃ��̑��ɁA�}���[�����E�t�B���s���E�������Ȃǂ̗���L���f�ڂ��ꂽ���Ƃ������������A������L���f�ڂ���Ă����L���͂Ȃ��B����������������̔����ȕ��͋C�f���Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@�������肽����Ȃ���������̂��Ƃ��A���܂��Ċ�����킹�Đu�˂�̂����ƂȂ��C�p�����������A�܂����ɕ����V���ɓ����đ����͒���C�ɂȂ��Ă����Ƃ��Ă��A�ǂ���60�N���̘̂b������L�����B���ɂȂ��Ă��邾�낤�Ǝv���āA���͈�v���Ă����B�w�K�����ЁiGakken)����o�Ă���w���j�Q���x�Ƃ����G���ɑ嗤�Œʍ��i���̎Q�������ꍆ���j�̓��W�L�����������̂ŁA�����V��ł��ǂ߂�悤�Ɋg��R�s�[���ē��@���̕��̕a���ɓ͂����̂ł���B���Ƃ����畃���������������������̃R�s�[�̗]���◠�ʂɂł������~�߂Ă����Ă��ꂽ��A�ォ���j�Əƍ����ĕ��̑��Ղ����ǂ�S�ς���ł������B
�@�Ƃ��낪�����A��ӂ����ċL����ǂݏI�������́A�����͑��\���t�c�ɂ��Ă�����������Ƃ��A�r���ŕʖ����čŌ�܂Ŏt�c�ƈꏏ�ł͂Ȃ������Ƃ��A�|�c�|�c�b���o�����B�܂����傤�ǂ���Ƒ��O�サ�āA��͂���\���t�c�ɂ��ē������ɎQ���������Ȃ̓��������̐�L���o�ł��ꂽ�̂ŁA������������߂ĕ��ɓn������A�ǂ���炱�ꂪ�����h�������炵���B���̌ソ�܂Ɏ��ƂɊ���o���Ɖ���牜�̏��ւŃS�\�S�\����Ă���悤�Ȏ������炭�����Ă���Ǝv������A���̓��@�������炿�傤�ǂP�N�o����������A�u�h�肪�ł����v�ƌ����Č����Ă��ꂽ�̂��A�唻�̑�w�m�[�g106�y�[�W�ɂ킽���čׂ��������Ńr�b�V�������L���ꂽ��L�������̂ł���B�܂���ۂɎc������i�ɂ��ẮA�����ȃX�P�b�`�u�b�N�ɉ��M�ɂ��f�`���������Y�����Ă����B
�@���̐�L�͈�U�A�l���X�Ƃ����o�ŎЂ��玩��o�ł������A���̎��ɓǂ�ʼn����������l���̕�����̋^��ɓ�����`�ŁA����ɖc��Ȍ��e���lj�����A����͒����[�́w�ہx�Ƃ����G���̊������Ґ�L�Ƃ��āA2006�N�̂R�����ƂS�����ɂ킽��A�u����͘I���Γ�i�R���v�Ƒ肵�Čf�ڂ��Ē������B����ɂ͉ߕ��Ȍ��e���������āA�����炭���ɂƂ��Ă��̐��̍Ō�̉҂��i�N���≶���͕ʁj�ƂȂ�ł��낤���A��͂�c�O�Ȃ��ƂɎ��ʂ̐����A�R��Ƃ��Ă̈�w�I�Ȏ����ɂ��Ă͑啝�ɃJ�b�g���Ȃ���Ȃ炸�A�܂����M�`���̑f�`���ڂ���X�y�[�X�͂Ȃ������B
�@��ʌ����̌R���G���ł��邩��~�ނȂ����Ƃł��邪�A���͕��Ɠ��Ǝ҂Ƃ��������A��͂肿����Ɛɂ����Ǝv���Ă����Ƃ���A��L������ɓˑR�앶�ɖڊo�߂������n��̈�t��̉��ɏ]�R�L�𓊍e���͂��߂��̂ł���B������͓��ƎҌ����Ƃ������Ƃ�����A�܂����e�������Ă�������ȉ��������قǑ����Ȃ��G���ł��邩��A�O��R���ɂ킽���Ă��Ȃ���I�Ȏ������܂߂��L�����S���f�ڂ��ꂽ�B
�@�����Ŏ��́A�ŏ��̐�L���x�[�X�ɂ��āA����̈�t����̌��e���e��D��������V�K�̌��e���쐬���A���̃E�F�u�T�C�g�Ɍ��J���邱�Ƃ��v���������B�������f�`���ꏏ�ł���B�����Ȃ��R��ɂȂ������A������Ȃ����R���̐V���̌����o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A����ɕ��������������a�@�Ƃ͂ǂ������g�D���A�ȂǂƂ�����ÊW�̏ڍׂȋL���Ɋւ��ẮA���̃T�C�g�������J�ƂȂ�B
�@������������ɏ]�R�������������̃T�C�g�Ɍ��\���邱�ƂɊւ��ẮA���������S�O����Ƃ��낪�������B���ɂ����l�������̗F�l������B���̕����R���Œ����ɓn�����̂́A���{�̔s�F�Z���Ȃ������a18�N�̂��Ƃł���A�m���Ɍ��ݓ����ԂŖ��ɂȂ��Ă���싞��s�E�Ȃǂ̂������Ƃ���鎞���ł͂Ȃ����A��͂���Đ�Ȃǂɔ�ׂ�Ɣ����Ȗ����܂ޓ����푈�Ɏ��̐g�����Q�����Ă������ƂȂǁA�킴�킴����Ȃ��Ă��ǂ�����Ȃ����Ƃ����C�������������B
�@�������l�̐e���ƍ��ƊԂ̗��j�͈Ⴄ�B���Ƃ̗��j�Ɋւ��Ă͉B�����艓�������肷��ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���������B���̕��������̂قƂ�ǂ̓��{���m�������A�����D��œS�C�S���Œ����ɓn�����킯�ł͂Ȃ��B���R���鍑�ƊԂ̗��j�̒��ŁA�l�I�Ȉӎu�ɊW�Ȃ��A�퓬�s�ׂɎQ�������̂ł���B
�@���̗��j�̒��ʼn����������̂��B��������`����̂��̌��҂����̋`���ł���A�܂���������̌��҂��������Ȃ��Ȃ������݂ł́A���̌��t���p�����҂����������Č��`���Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���肠�鐶�����Ȃ��l�Ԃ��ȑ̌����㐢�ɓ`����ɂ͂���ȊO�ɂȂ��B������ł��邾�����̌��t�̂܂܂Łc�B
�@���������킯�ŕ��̐�L���Ăсw�Γ�i�R���x�Ƃ�������ł����ɏ����~�߂Ă������Ƃɂ����B�ŋ߂ł͂܂����{�͑���E���ŕ������̂̓A�����J�ɑ��Ăł����āA�����ɕ������킯�ł͂Ȃ����Ƃ��������肪�������悤�ɂȂ��Ă������A���̏]�R�L��ǂނƕK�������������Ȃ��Ǝv���Ă���B�m���ɒ����̓A�����J�Ȃǂ̘A�����̉����Ȃ����ē��{�R�ɏ����Ƃ͂ł��Ȃ����������m��Ȃ��B�������u�����ߍU�v�Ƃ������A���ʂ̓G��@�����߂ɂ́A�㐢�̓G�ƂȂ邩���m��ʃA�����J�Ƃ����сA�����̒��ł��鍑���}�Ƌ��Y�}�����g�ށA�����������������Ȑ헪�����������m��ʍ��ł��邱�Ƃ���������Ă���B
�@�܂��R��W�̐�L������܂ʼn������o�ł���Ă��邪�A�܂��Ⴄ���ꂩ��̈�w�I�l�@����n�����̋L�^�ȂǁA����̈�ÊW�҂Ƃ��Ă�����������B����ł͂����炩�炨����ɂȂ��ĉ������B�Γ�i�R��
�@�Ȃ����{�ꃏ�[�v���ɕϊ�����������̒n���Ɋւ��ẮA�~�ނ����̐F��ς��ăJ�i�����ɂ��Ă���B
�W�p���O����������
�@2007�N�R��18���A���j���̌ߌ�O��45�����A���̎����͋N�����B�����R�s�O���쒬�̔�ˑ�ߓ����ɕ��݂���Ă���勴�R���N�V�����ق���A�d��100�L���A�����Q���~�̋����D���ꂽ�̂ł���B�ߓ�������25���N���L�O����1989�N����W������Ă����Ƃ����B���̏ߓ����́A�����l���Ζ�����ɕa�@�̐E�����s�ŖK�ꂽ���Ƃ����邪�A���̎��͂܂�����̓W���͂Ȃ������B
�@���������A���j�̂������Ƃ����̂ɗ���q�͊F���ŁA����W����̈���̃t���A�ɏ����]�ƈ����Q�l���������������ŁA�S�l�g�̔Ɛl�͎蔖�Ȍx���̌������v����ċ���̑����j�ē���Ԃʼn^�ы������炵���B�܂�ʼnf��̂悤�ȁc�ƌ��������Ƃ��낾���A���Ƃ��Ԕ����Șb�ł���B
�@�����̃��f�B�A�ł́A�Q���~���̋����W������̂ɏ�݂̃K�[�h�}�����u�����A���܂�ɂ��x���̐������e���������Ǝw�E���鐺�������B�m���ɂ��̒ʂ肾���A���j�̒����̃S�[���f���^�C���ɓ���҂��قƂ�ǂ��Ȃ��悤�ȓW���قɁA�K�[�h�}���Ȃnjق��o�ϓI�]�T�ȂǂȂ������̂ł��낤�B�܂��R���◣��̂悤�Ȃ��Ƃ���翂т��y�n�ł́A�̂���D�_�����Ȃ������̂ʼnƂ̌����|����K�v���Ȃ��ƕ��������Ƃ����邪�A�����������l�̑P����M����y�n�������h���ȓW���̐��ɂȂ����������m��Ȃ��B
�@�����������u�Ԕ����Șb�v�Ƃ����̂́A���������蔖�Ȍx���̂��Ƃł͂Ȃ��B���ŏߓ����ɋ����W������̂��Ƃ������Ƃł���B�ߓ�������25���N�̃��j�������g�c�B���z����������č̌@���n�܂��Ă���25���N�Ƃ����Ȃ�b�͔���B����Ȃɋ����肪�����̂��B
�@�����Ŏv���N�����o�u���i�C�̐^��������1988�N����1989�N�ɂ����āA�����̒|���o�́u�ӂ邳�Ƒn���v�Ƃ��̂��āA�S��3200�]�̎s���������̂ɑ��Ĉꗥ�ɂP���~����T���A�e�����̂����������Ŏ��R�Ɏg���āu�ӂ邳�Ɓv�����Ǝw���������Ƃ��������B���݂���l����Ɖ��Ƃ����̂悤�ȃo�J�o�J�����o�u���Șb�ŁA������u�ӂ邳�Ƒn������v�Ƃ����B
�@�G���Ɉ��ŁA���ォ��P���~���̑���������ꂽ�e�����̂̎g�����́A����܂����Ƃ��o�J�o�J�������̂����������B���ł���͂菃�����݂̘b�͖ڗ����Ă��āA���Ɍ��Ö����ł͂P���~�̋�����ēW�������A�X�����Ύs�ł͏����̃R�P�V������ēW�������A���m�����y�����ł͏����̃J�c�I������ēW�������B�ǂ��̎����̂��������Y�ꂽ���A��͂�P���~�̋�����ĊC�ɒ��߂悤�Ƃ����b���o�ĕ��c���������A�������ɋ�����ł���Ǝv�������Ń��}���ł���A�V���������`�����ł���������B����ȃA�z�Ȃ��Ƃ��l����c�������I�ׂȂ������͕̂s�K�ł���B�������ɂ��̘b�͍�����݂ɂȂ����炵���A���̌�͘b��ɂ��Ȃ�Ȃ��悤�����c�B
�@���������y�����̋��̃J�c�I�͌������ɑ������A���Β��̋��̃R�P�V�ƒÖ����̋���͂�����������̂̍��������̂��ߔ��p�̘b���o�āA�Z���̊Ԃŋc�_�������N�����Ă���炵���B���Ƃ�����ΓI�o�ω��l�̗��Â��������Ɋ����Ă��������߂ɁA�����̊���P���~�͌��݂ł͂P�����疜�~�ɂȂ��Ă���炵�����A��͂���Ƃ������̂͐l�Ԃ̗~�]���������ĂāA�Ō�̓��N�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ��悤�ł���B
�@����ȋ��̉������������Ė������Ă���l�Ԃ̒��ł��ŋ߂̓��{�l�͓��ɊԔ����ł���B������������肪�������āA���Ċ�ѐG���Ċy����ł��邾���ŁA���Ɏg������m��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�W�����ċq�Ɏg���A�C�ɒ��߂ă��}�������Ȃǂƌ����o���Ԕ����Ȑl��B�o�u���i�C�̍��A�������i�X�ł͋����ň�����i����ŐH���悤�Ȑ����ǂ����ʐ^�T�����ɍڂ��Ęb����T�����B�Í������A���͉���M���ȂǓ����K�����Ɛ肵�Č��Ђ̏ے��Ƃ����̂��킾�������A�����܂Ŕn���Ȃ��Ƃ����������͂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����H
�@�\����Ȃ����A����̔�˂̋������ǂ�Ŋ����Ȃ����̂��������B���{�l�͖{���̋��̉��l��m��Ȃ��B���Ă͉����̍��W�p���O�Ə̂���A��������ߐ��̃��[���b�p�l�̓���̓I�A�R�����u�X���W�p���O�ڎw���ė��������ƌ����Ă���قǂ����A�]�ˎ��㖖���ɂ͓��{�̋��E��������[�g�����̃A�W�A�������������ǂ������̂ŁA�����̃��[���b�p���l�����̃J���ɂȂ��āA���ʂ̋����C�O�ɗ��o�����ƌ�����B���̍H�|�i����ɂ͗D�ꂽ�Z�p�������Ă������A���̌o�ω��l�Ɋւ��鍑�ۏ��ɂ͂��̍�����a�������B
�@�m���q���̍��ɓǂC�\�b�v�̋��b�������Ǝv�����A����Ȃ̂��������̂��o���Ă���B����~����Ȑe�ꂪ������ɖ��߂āA���Ӗ����Ɍ@��o���ẮA����߂Ċ��ł܂����߂Ă����B�Ƃ��낪����������C�\�b�v�������ʂ̏ꏊ�ɉB���đ���ɐ���߂Ă������B������@��o���Ėڂۗ̕{�����悤�Ƃ����e��́A������ɕς���Ă���̂����ĒQ���߂��ނ��A�C�\�b�v���킭�A
�u���̂悤�ɋ�����������߂Ă��邾���Ȃ����ł��������Ƃ��B���̋���͂����ƗL�v�ɖ𗧂Ă�l�̂Ƃ���֎����čs��������������B�v
�C�\�b�v�������Ԃ������ǂ����͊o���Ă��Ȃ����i��̃C�\�b�v����͐��E�e�n�Ō��`��������e���قȂ��Ă���̂ŁA���Ԃ���{�̎q�������̘b�ł͋���͕Ԃ����̂ł͂Ȃ��낤���j�A�Ƃɂ����C�\�b�v�͂��������ė~����e���@�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B
�@���������q������W�������ĐG���čK���ȋC���ɂȂ�̂�����A��������D����Ɛl�������ċ�������̂ł͂Ȃ����A����̋��D������������{���肵�ċ������Ă��܂����ꍇ�A���{�l�͂�������P�Ƃ��ĕs�K���̍K���Ƃ���ׂ��ł���B�g�}�X�E���A�����z�̐��E��`�����L���Ȓ���w���[�g�s�A�x�ɂ́A���[�g�s�A�l�����͋���ŏ��藧�Ăĕx�������т炩�������l������}���Ă���Ƃ������B����͒P�Ȃ鋕�h������ł���B���{�l���{���ɋ��̉��l�������o���閯���ɂȂ�邩�ǂ����A����̎�������ǂ��������P���邩�ɂ������Ă���B
�@����͋��i����j�Ɍ��炸�A��������i���ˁj�������Ă��Ă��A�L���ȂƂ���ɏo���ɂ��݁A�p���Čォ��呹�������n���Ȏ�K�z�����{�ɂ͑����̂ł͂Ȃ����B
���F
�@���̌�l�b�g�Œ��ׂ���A����߂Ă����C�\�b�v�̋��b�ň�ԑ����Љ��Ă���p�^�[���́A���̂悤�Ȃ��̂������B
�@��K�z������߂Ė��ӌ@��o���Ă͊y����ł����Ƃ���A�D�_�ɓ��܂�Ă��܂��B�Q���߂��ގ�K�z�e����Ԃ߂Č������Ƃɂ́A�u����Ȃɔ߂��܂Ȃ��Ă�������B�ǂ����������߂Ă��邾���ŗL���Ɏg��Ȃ��Ȃ�A����̑���ɐ���߂Ă�����������B�v
�@�����c�����ɓǂ̂����̃p�^�[�������������m��Ȃ����A�����끛�\�N���̂̂��Ƃ�����v���o���Ȃ��B����������̃��`�[�t�͑�̂ǂ�������ł���B���̃p�^�[�����Ƃ܂��ɍ���̔�ˑ�ߓ����̎������̂��̂ł͂Ȃ����B�C�\�b�v�Ȃ炱���������낤�B
�u�����܂ꂽ���Ă���Ȃɔ߂��܂Ȃ��Ă������ł���B�����W�����Ă����ėL���Ɏg��Ȃ��Ȃ�A����̑���ɏߓ��ł��W�����Ă�������ǂ��ł����ˁH�v
�@����A��������Ԃ��Ȃ������ꍇ�͑���ɐ�W�����āA���̃C�\�b�v�̋��b���Љ��R�[�i�[�ɍ��ς����炢���̂ł͂Ȃ��낤���B���i���ˁj��ׂ��邾���ׂ��Ă����Ȃ���A���S��ɏo���ɂ����߂ɒ��N�|���Ă����ڋq�̐M������C�Ɏ������n���Ȏ�K�z�ꑰ���o�c����V�܂̗m�َq���[�J�[���b��ɂȂ������肾�B���͂͗L���Ɏg��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ƃ������P��`���邽�߂ɍ���̎������������A���{�ɂ��܂��~��������Ƃ������̂ł���B
����k�F
�@���̎����A�R������̂U��19���ɓ��܂ꂽ����̈ꕔ����������j���R�l���ߕ߂��ꂽ�Ƃ������������B����͐蔄�肳�ꂽ�炵���A��2/3�̑傫���ɂȂ��Ă����炵�����A�܂��͌������߂��Ă��ėǂ������A�ǂ������c�B�������ڌ��肵�Ė߂��Ă���������ĂѓW�����邩�ǂ����A�쎟�n�Ƃ��Ă͋����̐s���Ȃ��Ƃ���ł͂���c�B
�����̏W�c�����Ƌ��ȏ�����
�@���t���獂�Z�Ŏg�p���鋳�ȏ��̓��e�Ɋւ���2006�N�x�̌��茋�ʂ������Ȋw�Ȃ�����\���ꂽ�B��͂肻�̒��œ��ɖ��ƂȂ�̂́A�����ɂ�����Z���̏W�c�����ɂ��āA�]���͓��{�R�ɂ�鋭����F�߂Ă������A�����▽�߂Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��ė��j���ȏ��̋L�q�̏C�������߂����Ƃł���B���̗��R�Ƃ��ẮA�W�c�����𖽗߂����Ƃ������{�R�̌��������A�ٔ��Ŗ��߂�ے肷��،����������Ƃ��������Ă���B
�@�m���Ƀ^�C���}�V����1945�N�̉����̌���ɖ߂��Ċm�F���Ȃ�����A�W�c�����̖��߂����������ǂ����Ȃǒf��ł��Ȃ����A�܂����Ɍ�����m�F�����Ƃ��Ă��A��̓I�ɉ���h�q�ɓ��������t�c���������A�������A�������Ƃ���������ӔC�҂��Z�����W�߂āu���ɏ}����v�ƌ����ĎE�Q�����莩�E���������Ȃǂ͂Ȃ����낤�B�������Ƃ��Ă��ǒn�I�Ȃ��̂ł���A���Ƌ@�ւƂ��Ă̌R�̐ӔC�ɂ܂ŋy�Ԃ悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������͂����B
�@����������ӌ��̗��R�Ƃ��Ė@��ɂ�����،���������ׂ��ł͂Ȃ��B���Ԗ����ŏW�c�����𖽗߂����Ƃ���錳�������A���߂̎����͂Ȃ������Ƒ��n�قŏ،������������Ȋw�Ȃ͏d�����Ă��邪�A�ٔ��ő���ꂽ�����ł���Η��_���L���ׂ��ł���̂ɁA���_���L�ł͌�������Ƃ��āu���{�R�ɂ�閽�߁v�̋L�q���폜�������炵���B���j�����ɑ��鐭�����͂ƌ����Ă悢���낤�B
�@����Ȃ��Ƃ������o���A���ȏ��ɕs���_�ȋL�ڂ����ꂽ�ߋ��̗��j��̐l�����ׂĂɂ��Ė��_�̂��߂̍Ē��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���̐��ł͖��q���G���D�c�M�����E�����͉̂�����Ȃ��A��炳�ꂽ�������Ƒi���Ă��邩���m��Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@����ł��M���͌��G�̌R���Ɉ͂܂ꂽ�{�\���ŗ��������킯�����i�{���͌����Ɍ������ꂾ���āg�����h�Ƃ��ĔF�肵�Ă悢���ǂ�������Ȃ��j�A�����ł͏Z�����W�c���������킯�ł���B�Í������̗��j������A�킢�ɕ��������̏Z�����A��̓I�Ȗ��߂��������ɂ��斳�������ɂ���A�W�c�Ŏ�������ȂǂƂ������Ƃ́A���ɋߐ��ȍ~�̗��j�ɂ����Ă͂��Ȃ�ُ�Ȃ��Ƃł���B���ُ̈�Ȃ��Ƃ����{�ŋN�������Ƃ����������������j�ł���B
�@�����Ȋw�Ȃ́A�Ɍ���Ԃɒu���ꂽ�Z�������܂��܂Ȏ���̗��݂ŏW�c���������Ƃ̎w�E������ȂǂƁA�܂�ŏW�c�q�X�e���[�łł����邩�̂��Ƃ��������q�ׂĂ��邪�A����͓��{��������M������̂ł͂Ȃ����B
�@�Ȃ��W�c�������N���������B����͌R�����a16�N�P���ɐ��肵����w�P�����������̔��[�ł͂Ȃ������̂��B�u�����ė����̐J�߂����v�Ƃ͌R�l�ɑ���s���K�͂Ƃ��Ē�߂�ꂽ���̂ł���A�m���ɏZ���̍s���܂ł���̂ł͂Ȃ������B���������a19�N�̃T�C�p�����ח��̍ہA���̖k�[�ɒǂ��l�߂�ꂽ�w���q���܂ޑ吨�̈�ʏZ���܂ł��f�R����g�𓊂���Ƃ����ߎS�ȏɑ��āi���ꂪ�o���U�C�E�N���t�̒n���ƂȂ����j�A�ԏ\���ȂǍ��ۋ@�ւ����{���{�Ɍ��n�̏Z���ی���Ăт�����悤�v���������A�������{���{����R�������������ƍl����̂��B�T�C�p�����ɂ�����Z���̏W�c���g���������ۋ@�ւ���m�炳�ꂽ�����̓��{���{�́A�䂪���ł͕w���q�܂ł����ɏ}����o������߂Ă���Ƃ��āA�������O�Ɍ����ď^�����̂ł���B
�@����ł͓����ɂȂ����Ȃ�A�����ĉ���ł͂܂��ɓ����ɂȂ����킯�ł��邪�A���{�R���ʍӂ�����͏Z�������ǂ��Ď��˂Ɩ��߂��������R�ł͂Ȃ����B�������W�c�����𖽗߂����̂͌��n�w�����ł͂Ȃ��A���{���Ƃ��̂��̂������̂��B���j���ȏ��ɂ͉����̋ǒn�I�Ő����������m��ʎ������L�ڂ�������A�����̓��{���Ƃ��R�l����łȂ����Ԑl�ɂ܂Ŏ��������v����w�i�������Ă������ƁA�����Ă��̐��_�I�y�����̉��������ӔC�҂����݂ł��g�_�h�Ƃ��Ė����_�Ђ��J���Ă��鎖���������L�ڂ���ׂ��ł͂Ȃ��̂��B
�@��w�P��ʂ��ĕ������玀�˂ƌR�l�ɖ��߂����͓̂����p�@���R��b�A�܂��T�C�p�����ŏZ���܂ł��f�R����g�𓊂����̂��^���āA��ʓ��{��������������Ɩ��߂����̂����������p�@����������{���Ƃ������B�����������Ƃ̈ӌ����ď]�e�Ǝ�����������Z���ɑ��āA�܂�ŏW�c�q�X�e���[�ł��������̂��Ƃ��������q�ׂāA�]���̋��ȏ��̋L�ڂ��폜�����������Ȋw�Ȃ̖�l�ǂ��ɂ͓{����ւ����Ȃ��B���ǂ͂��ꂪ�]�R�Ԉ��w���Ȃǂɑ��Ă������ԓx�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�����������ɂł��Ȃ����{���l���A�O���l���ɂ���킯���Ȃ��B
�@�l���Ă݂�Δ픚�҂ɑ��鉇����s�\�����������A�����a��C�^�C�C�^�C�a�Ȃǂ̌��Q�ɋꂵ�ޏZ�������ɂ���W�������B�܂��e����Ȃǂƌ����ĕČR�̔h��ȌR���s���ɂ͒ǐ����邭���ɁA�e���̋]���ɂȂ���������⑰�ɑ���x���Ȃǂ́A���Ċe���ɔ�ׂ��疳���ɓ������B
�@���j���ȏ��̋L�q�Ɍ���ӌ����t���ꂽ���Ǝ��̂͏����Ȏ����ɉ߂��Ȃ������m��Ȃ����A����ƋO����ɂ��邱�ꂾ���̔w�i�����邱�Ƃ���X�͌������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���a�̓�
�@2007�N�S��29���́u���a�̓��v�ƌĂ��ŏ��̏j���ƂȂ����B���a����ɂ́u�V�c�a�����v�ł���A�����ɂȂ��Ă��炵�炭�́u�݂ǂ�̓��v�ƌĂ�Ă������A2007�N����́u���a�̓��v�ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B
�@2007�N�x�̑�w�̐V�����̒��ɂ́A�����̑����܂�i�P�`�R�����܂�j�̐l���`���z��������B�����ʐڂ�����Ă��Ĝ��R�Ƃ������̂ł��邪�A�l���Ă݂�Α��̑命���̐V���������a62�N�E63�N���܂�ł��邩��A�ނ炪���S�������ɂ͂��łɐ��͕�������ɂȂ��Ă����B���Ԃ����̑O��̐��オ��w�ɐi�w�������ɂ́A���ɐ푈��m��Ȃ����オ��w���ɂȂ����ƌ����Ă������Ƃł��낤�B��������Ď���͈ڂ��Ă����̂ł���B
�@�ł͏��a�Ƃ͂ǂ��������ゾ�����̂ł��낤���B����͈���Ɍ����͓̂���B�Ⴆ�Ζ��������45�N�܂ł���A���a�Ɏ����Œ����������������A���ˑ̐������ł��ċߑ�I�������Ƃ���������Ɠ����ɁA�����������ď��O���Ƃ̌��Ղ��J�n���Ă���A�x����������̉��A�����E���I�푈�����������āA���E�̋����̍��ɓo��l�߂�܂ł̎���Ƃ��āA��r�I�܂Ƃ߂₷������ł��������B����������]�Ȑ܂͂��������A�������{�̏o���_�Ɠ��B�_�͗��j�I�ɖ��m�ł���B
�@���������a����͂����͍s���Ȃ��B���a�͑傫���O���ƌ���ɕ������A�����E�吳���{�̉h����w�����ďo�����Ă��疳�d�ȑ����m�푈�Ńh����ɓ˂����Ƃ����܂ł��O���i��O���a�j�ŁA���̃h���ꂩ�甇���オ���ē����I�����s�b�N�����ɂ߂��܂����o�ϖ��i�𐋂��A�o�u���o�ς̒��_�ɒB����܂ł�����i��㏺�a�j�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@��������������L�O���āu���a�̓��v�𐧒肵���ƌ����Ă��A�͂����ď��a����̉����L�O���Ă���̂��A�����ς�s���Ƃ��Ȃ����̂�����B���{���������a����̐^���Ƃ��Č㐢�ɋL�����Ă����ׂ����͉̂��Ȃ̂��H�R���I�ɓ˂������ē����푈����Εĉp�푈�ɓ˓����Ă����������̂��ƂȂ̂��A�p�Ђ̏Ă��Ղ��痧�������Ċ�Ղ̌o�ϔ��W�𐋂��Ă����������̂��ƂȂ̂��B
�@���̏��a�����ʂ��Ĉ�т��ċ��ʂ��Ă�����̂��Q����Ǝ��͍l���Ă���B��͓��{�����A������͏��a�V�c�ł���B
�@���{�����͂����炭���E�ł��L���̏]���ŋΕׂȍ����ł��낤�B���g��ɂ��܂����������ɁA�㋉�҂ɑ��Ă͂قƂ�Ǖ��������Ȃ��i�����Ȃ��j�B���ꂪ�R���̎���ɂ����Ă͐��E�ŋ��ƌ���ꂽ�����̈�y��ƂȂ����B���E�̃W���[�N�̒��ɂ���Ȃ̂�����F���E�ŋ��̌R���̓A�����J�l�̏��R�E�h�C�c�l�̎Q�d�E���{�l�̕����̑g�ݍ��킹�ł���B�i���Ȃ݂ɐ��E�Ŏ�̌R���͒����l�̏��R�E���{�l�̎Q�d�E�C�^���A�l�̕����Ƃ̂��Ɓc�B�j
�@�܂��`�a�c�����i���a�ł͂Ȃ����j�ŗ̌R���̒������������ŁA�����̕������ł�����������̓��V�A�R�Ɠ��{�R�������ŁA���̗��R�̓��V�A�R�͗��\������A���{�R�̓}�W���ɐ푈���邩�炾�����炵���B
�@�����������{�̍����͐푈�����A�ꉭ�ʍӂ������t�Ɉ�ʕ��m�������肩�A�s�������܂ł��T�C�p���E����E���{�{�y�ŕ�������킸�Ɏ���ł��������A���̍����C���͐����o�ϐ�m�Ƃ��Ďp����A���{�͊�Ղƌ���ꂽ��㕜���ƌo�ϖ��i�𐋂����B�����s�퍑���������h�C�c�ƌ�����ׂ�قǂ̕����Ɣ��W�́A���{�l�����Đl��ɗ��ʔ\�͂������Ă��邱�Ƃ��ؖ��������̂ŁA���Ă̖������{�̔��W�������ęF�����R�̎Y���ł͂Ȃ��������Ƃ����߂Đ��E�ɒm�炵�߂����̂ł���A����͓��{�l�Ƃ��Čւ�������Ă��悢�B
�@���������{�̌o�ϔ��W�ɋ������������Đl�́A���{�l���E�T�M�����ɏZ�ރG�R�m�~�b�N�E�A�j�}���ƌĂ�ŕ̂B����ƕ��͎̂���d�ł���B
�@����ɂ��̌R���E�o�ςɂ�����Q�x�̊�ՓI���W���A��������킸�ɍ��g�������{�l�̍��������̂��ˑ����Ă������̂ł������Ƃ���A������œ��ӂɂȂ��Ă���͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������������̌��Ɗ��̏�ɌӍ��������Ă������\�Ȍ��͎҂������Ă��܂����ƂɂȂ邩�炾�B
�@�����ŏ��a�̐�O�E����ʂ���������̋��ʍ��ł��鏺�a�V�c���d�v�ȈӖ��������Ă���B���a�V�c�͗����N�吧�̖{�`����낤�Ƃ��āA��O�̌R������Ƃ̐���ɑ��Ĕ������T�����Ă���ꂽ�ƍ������Ă�����B�Q�E�Q�U�����̎��ɔ����R�̒����𖽂��Ĉȗ��A�����m�푈�̏I��̌䐹�f�܂ł̊ԁA���a�V�c�͐����̒��Œ��ق����ʂ��ꂽ�B���������Đ푈�ɂ��S�Ђ͌����ď��a�V�c�̐ӔC�łȂ��A�L���Ӗ��ł̐푈�ӔC���珺�a�V�c�ɂ͂Ȃ������B
�@����ɂ�������炸�A���a�V�c�͐��i�����Ă����A���R������}�b�J�[�T�[�i�ߕ��Ɏ��畋���āA�����͂ǂ��Ȃ��Ă��悢������{�������~���Ă���ƃ}�b�J�[�T�[���R�ɒ��i���ꂽ�̂ł���B���a�V�c�͎�����푈�ӔC�҂Ƃ��ď��Y����Ƌ��d�Ɏ咣���鍑�����邱�Ƃ�m���Ă���ꂽ�B��������m�̏�Ŏ��獑�ۖ@��ɗ����A�i��Y�������Ȃ����獑���������Ă���ƍ��肳�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��̂ł���B���̎��A���a�V�c44�B
�@���������N�傪���E���̂ǂ��ɂ��邾�낤���B���̂��܂ǂɉ������̂����Ċ�ꂽ�Ƃ����Ñ�̌̎����K���������b�ł͂Ȃ����Ƃ��ؖ����Ă���Ƃ����Ă悢�B���a�V�c�̖K����i�ߕ��Ŏ��}�b�J�[�T�[���R���A�V�c���������悤�ɘ��R�ƕ���ŗ��L���Ȏʐ^�����邪�A�}�b�J�[�T�[����ɐl�Ɍ�����Ƃ���ɂ��ƁA���a�V�c�������̐�����ɗ������̂��Ƃ���v���Ă����Ƃ���A�����̑���ɓ��{�����������ė~�����ƍ��肳�ꂽ�̂Ō��l�ȋC�����ɑł��ꂽ�炵���B
�@�O���̓��{���m�����Ŏ��ʊԍۂɁu�V�c�É����v�Ƌ��Ԏ҂͈ӊO�ɏ��Ȃ������炵�����A��͂���̃}�b�J�[�T�[�i�ߕ���K���悤�ȌN���Ղ��Ă������Ƃ́A���a���{�̌ւ�ł������ƍl���Ă悢�Ǝv���B���̑啔���̎���A�Εׂŏ]���ȍ����̏�Ɏ����I�ɌN�Ղ��Ă��������}���{�̑�b�⍂���̒��ɁA���a�V�c�̔����ł������̂��Ƃ��l���Ă��Ă��ꂽ�҂͂ǂꂭ�炢�����̂��B�����I�Ɏ����̐ӔC�łȂ����Ƃ܂ł��A����̗���ɂ����Ĉ�g���Ȃ��ď������Ƃ����҂͂ǂꂭ�炢�����̂��B
�@���̂��ƂɎv����v�����Ƃ��āu���a�̓��v�𐧒肵���̂ł���ΗL�Ӌ`�Ȃ��Ƃ��Ǝ��͎v���B
���́A�N�̂��߂ɂ������ɂɂ����c�H
�@�w���́A�N�̂��߂ɂ������ɂɂ����x�Ƃ����f�悪2007�N�T��12���ɓ��f�n�ŕ���ꂽ�B�w�z�^���A��x�i�ԉH��q�A�Έ�G���j�ň���L���ɂȂ����m���̗��R���U����`�����f��ŁA���U����������{���̕�e�Ɠ����悤�Ɏ����݁A�S���炻�̎��𓉂��_�g������𒆐S�ɕ���͐i�ނ炵���B�������s�m���̐Ό��T���Y��������̎w�����Ƃ������Ƃł��b����܂������A���̉f��ɂ��₩���āw�z�^���A��x�̖{����������ď��X�ɕ��ς݂���A���U������U������W�����G���̕ʍ����W�͂��ɂȂ������B
�@���͂��̘b�͉��x�ł��������A�ǂ��l���Ă��ߑR�Ƃ��Ȃ��̂ł���B�m���ɍ��x�̉f����Ό��T���Y�����炪�C���^�r���[�Ō��Ƃ���̔���f��ł��낤���A����ɐԉH�E�Έ䎁�́w�z�^���A��x��A���U���̕ʍ����W���A���������̎���s�𗝂Ȃ��̂Ƃ��ē��ގ��_�����͈ꉞ�ۂ��Ă���悤�Ɍ�����B�����ē��R�̂��ƂȂ���A���{�l�͓��U���_���������܂��傤�Ƃ��A�꒩�����鎞�͉䂪�g���ڂ݂����ɏ}���܂��傤�ȂǂƎ咣����҂ȂǒN�����Ȃ��B
�@��������Ȃ�Ȃ�����������i��o�ŕ��̒��ɁA�u��������̂̂��߂Ɏ���ł������v�Ƃ��A�u���R�Ǝg�����ʂ������v�Ƃ��A�u���������̔M���v���v�ȂǂƂ������������肪�ڗ��̂��B�����������U���������̎����u�U�����v�ƕ\�����邱�Ǝ��́A�l�Ԃ����̉Ԃɂ��Ƃ��ē��{�l�̔��ӎ��ɑi�������Ƃ����Ӑ}�����������Ă���B
�@�����̓��U���������̋]���ɂ�������炸���{�͐푈�ɔs��Ă��܂����A�ł����U���������������ɂ������Ƃ����炠�܂�ɂ��C�̓łł���A���߂Ă��̎��ɕ��͖��ʂł͂Ȃ������A�����������������Ƃ��Ď]�������Ƃ����S���͂悭����B���ꂪ�u�U��v�Ƃ������t�ɑ����ꂽ��X���{�l�̐S��ł���
�@�������قƂ�ǂ̓��{�l�������܂łŎv�l��~���Ă���ԂɁA�䂪���͍ĂсA����ł͓��U�������͂��ߍ��ɏ}����ꂽ���X���]���Ȃ���A�������Öʂō����R�Ɛ�̂āA��O��A�̋�����v�E�R�����v���S�O�Ȃ������i�߂鐭���Ƃ���绂��鍑�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���̓��U���_�́A��������x�ł��������A���̂Ƃ���ł���B
�c������邽�߂ɐg���̂ĂēG�͂ɓ˓�������҂������������Ƃ͓��{�����̌ւ�ł���B�������R���E�R���E���̎��s����҂����ɂ����K�@�������Ď���͐����c��A���瓹�`�I�ӔC�����炸�ɐ��h�B�����w�������������Ƃ͓��{�����ő�̉��_�ł���A�p�J�ł�����B
�@�قƂ�ǂ̓��{�l�͂��̌㔼���𗝉����Ă��Ȃ��B�܂��ĐΌ��T���Y���̂悤�Ȏw���ґw���A�w�^����Ύ���̍s�Ղɂ���������Ă���悤�Ȍ㔼������������͂����Ȃ��B���āu�������U������҂����v�������Ƃ������Ƃ�����`���č��������������悤�Ƃ������_�������������Ƃ���A�����͂��������w���ґw�̈Ӑ}���������邭�炢�����Ȃ�Ȃ�������Ȃ��B
�@�����Ƃ����͂܂��Ό�������̂��̉f����ςĂ��Ȃ��̂ŁA�{���͂����������Ƃ������ŏ����Ă͂����Ȃ��̂����A�Ό����̓���̌��������Ă���A���Ƃ��Ώ��a20�N��̉f��w�_�Ȃ����ʂĂɁx�ɕ`���ꂽ�悤�Ȏw���҂ւ̑����ɋ߂��{��܂ŕ`����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B
�@����̉f��ɂ��₩���ďo�ł��ꂽ�ʍ����W�̒��ŁA�ʍ��w���ʍU�����|�����ĖY��Ă͂����Ȃ����j�̐^���I�x�͏����ِF�������B�X�j�N���i�w�~�����̌ܐl�x�̒��ҁj�͋L���̒��Ŏw���������Ƌ��e���A�吼�����P�l�ɐӔC���������ĐӔC����������w�����N���X����Ă���A����ɓ���l�Z�����w�z�^���A��x�ɂ��Ă��A�ԉH�E�Έ䗼���̂��܂�ɔ���������L�q�����؏r�N���́w���U��n�m���x�ƕ��ׂČ����ɏЉ�Ă���B�i���̌��Ɋւ��Ă͎������̃T�C�g�����֘A�L���u�z�^���̕ϑJ�v�������Ă���B�j
�@���̕ʍ��̒��ɒm���̕x�����َO��ڏ����̒��_���コ��̘b���o�Ă���B�x�����ق͐펞���̓g�����萷�肵�ē��U���������̌e���̏�ɂȂ��Ă����ꏊ�ł���B���̎O��ڂ̓g������̑��̂��ł������ŁA���コ��͍��ł��g������Ɠ��U���������̌�蕔�ɂȂ��Ă�����悤�����A�����炭�g������̌��Ȃ������ł��낤���t�������ŏ��ɏo�邻�����B
�u�`���Ԉ�����Ⴂ���Ȃ���B����q��̋��{�Ƃ��̍��̕��a�Ɣ��W�̂��߂Ɂc�B�v
�@�������{�ł́A���U�����������`���ԈႦ���Ă��Ȃ����낤���B��X�͖{���Ɉ�������̂̂��߂Ɏ��ɂɍs����̂��낤���B�N�ł������A���̐l�̂��߂Ɏ���ł������Ǝv����l�Ɏv�������ׂĂ݂邪�����B�����Ă��̐l�ƈꏏ�ɐ���������A���̐l�̂��߂Ɏ��ɂɍs���Ɩ������鎩����z�����Ă݂邪�����B���Ȃ��͖{���Ɏ��ɂɍs����̂��B
�@���������A�{���ɂ��̐l�̂��߂ɂȂ�̂Ȃ�A�Ə����t���Ŏ��ɂɍs���̂�����Ƃ��낤�B���������U���������ɂ͂��̏����t�����狖����Ȃ������̂��B�ނ�͈�������̂̂��߂Ɏ��A�Ȃǂƌy�X�������ɂł���l�Ԃ����͐�ɐM�p�ł��Ȃ��B���ꂩ��̓��{�͌o�ϓI�ɂ����I�ɂ��d��ȋǖʂ��}���邱�Ƃ��낤���A�{���̓y�d�ꂪ�������ɂ͂��������l�����͐^����Ɏ��ɂɍs�����Ƃ��ł���̂��낤���B
�@�����炭���_�g������͐풆������ɂ����āA���悾���ŗ��h�Ȃ��Ƃ������l�Ԃ��������Ă������Ƃ��낤�B���������l�Ԃ�������������߂ē��U�������^������̂̓C���ƌ����قǕ����Ă���͂����B���̂����łȂ��u�`���Ԉ�����Ⴂ���Ȃ���v�Ƒ��Ɍ���Ă����g������̐S�c�B�ʍ��ɍ��̘b���ڂ����̂́A���U�����Ȕ��k�Ɏd���ďグ���Ă�������̕����̐����A�S���g���������Ȃ��n���ŗJ���Ă��邩��ł͂Ȃ��̂��ƂӂƎv�����B
�܂�����j���ς���ꂽ
�@2007�N�T���ɕ���ꂽ���f�̉f��w���́A�N�̂��߂ɂ������ɂɂ����x���A���N��ɂȂ��Ă����DVD�Ŋς���悤�ɂȂ����B���x���̉f���DVD�Ŋӏ܂���@����̂ŁA�O��ᔻ�߂������Ƃ����̃E�F�u�ɂ���������O�A�ȒP�ɑ������Ă����B�O��̋L�������ǂ݂ɂȂ��Ă���������Ȃ����́A��������ɂ��ǂ݉������B
�@�܂��ꌾ�Ō����A��͂�v���Ă����Ƃ���̉f��ł������B�m���̓��U�����̕�ƌĂꂽ���_�g������ƎႫ���������Ƃ̐S�̌𗬂͔��ɂ悭�`����Ă���B�b�q������g�������������̂��߂Ɍ������ɔ��R�����ʂ́A���ۂ̃g������������������ł��낤�Ǝv�킹��قǂ��B�{���Ƀg������̐g�̂ɂ͌���������ӂ��ꂽ�\�͂̐Ղ��������Ƃ����B
�@�܂��m���̃V���{���ƂȂ����z�^���ɂȂ��ċA���ė��������̘b�A�o���O��ɃA���������̂��Ă��������N�����o�g�̑����̘b�A�V�ȂɐS���c���Ď��̎����������̘b�A�r���̓��ɕs�������čċN�����������̘b�A�����͂�������m���̓��U���������̈�b�Ɏc����̂ł��邪�A�ߓx�Ɋ����I�ɂȂ炸�A�W�X�Ǝ��ɂ݂��Ƃɉf��������Ă���Ǝv���B�����܂ł́A�������Ό��T���Y���Ə^�ł���̂����c�B
�@�Ό����͉f��̖`���Ŏ��̂悤�ȃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă���B
�u�Y�X���������������A���Ă̓��{�l�̎p��`���Ďc�������Ǝv���܂��v
�Ό��T���Y���̂悤�Ȑ����Ƃ͂Ȃ������܂ł�����������Ȃ��̂��H���U�����^�����A�����_�ЂɎQ�q���鐭���Ƃ͊F�������B
�@���U���Ɋւ�����j�́A�������̃T�C�g�̂��������ɏ����Ă���悤�ɁA�u�Y�X�����������������{�l�̎p�v������`���Ă��Ă͊��S�ł͂Ȃ��̂��B���������ɂ������𖽂��Ď����͐����c�����u���X�����X���������{�l�̎p�v�܂ł�`���Ȃ���A�䂪���ɂƂ��Č㐢�܂��ƂɗJ���ׂ����ԂƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����A���������ɂ݂ɑς������Ď��������͊Â��`���z�����u���X�����X�����{�̈א��҂̎p�v�́A�ŋ߂��j���[�X�ŃC���ƌ����قnj��邱�Ƃ��ł���B�i�g�Y�X�����h�g���X�����h�Ƃ����̌��t�͖��炩�Ȓj�����ڂ��Ǝv�����A�����ł͐Ό����Ɉًc�������邽�߂ɁA�����ė��j�I�p�@�̂܂g�킹�Ă��������B�j
�@���U�������ł��������l���������邱�Ƃ��ӎ������̂��A�Ό����͂��̉f��̒��Ŏ��ɋ����ق����ςȗ��j�̝s�����s�Ȃ��Ă���B�Ⴂ�l�����͂��������f����ςĂ��A���̝s���ɂ͋C�t���Ȃ��l���܂��啔�����낤�B
�@�w���́A�N�̂��߂ɂ������ɂɂ����x�̉f��́A�`���t�B���s���œ��{�ŏ��̓��U�������肳���Ƃ��납��n�܂�B�吼�뎟�Y�C�R�������֍s�j��т���U���w�̎w�����Ɏw������L���ȏ�ʂ����i�{���͑吼�̈ӂ����������֑�т��w���������ƂɂȂ��Ă���j�A����͂����܂��C�R�̓��U���̌��ł����āA�吼���������R�̓��U�܂ł𖽂����킯�ł͂Ȃ��B
�@�������f��ł́A�C�R�֑̊�т̏o�����q�ׂ���́A�m�������R���U���̃G�s�\�[�h�������玟�ւƕ`���������ŁA�I��̓��ɑ吼�C�R���������U�̐ӔC���Ƃ��Ď��n�����ʂ�}�����Ă���B����͉f�搧��҂������Ӑ}�������̂��A�ϋq�͂�����Ɨ������Ă����Ȃ�������Ȃ��B�i�J�ԓ`������L�^�ɂ��A�֑�т͒������I�[���o�b�N�ɂ������㕗�̍D���������Ƃ������A�f��֑̊�т͊ۊ��蓪�������B��������̈Ӑ}���������̂����m��Ȃ����A����͂Ƃ肠�����ǂ��ł��悢�B�j
�@�m���ɓ��{�ŏ��̓��U����Ґ���������w�����͑吼�C�R�����ł���A�ނ͏I��̓��ɕ������C�R���U���������ɘl�тĎ��n�����̂ł���B�吼�����R���U���������ɂ܂Řl�т�C�������������ƍl����̂͂��܂�ɍr�����m�ł���A���{�̊����g�D�̂������m��Ȃ��ӌ��ł���B���{�̕s�ˎ��̐ӔC������ē����s�m�������E����悤�Ȃ��̂��B
�@�����炭�Ό����͉f��̒��ł������������̂ł��낤�B�Ⴋ���U���������͎��������Ċ��R�ƔC�����ʂ��������A��w�����܂�������Ɨ��Ƃ��O�������̂��Ɓc�B
�@���������R�ɂ͎��������đ��������ɘl�т������w�����Ȃǂ��Ȃ������B�t�B���s�������R���U���w�������x�i���������́A���������̒n�Ŏ��ʂƍ��ꂵ�A�w���ӎ������M�ق��ӂ���đ������������n�ɑ��葱�������A�t�B���s����̍ŏI�i�K�ɂ��ĕa�C�𗝗R�Ɏ��C��\���A�����̋����Ȃ������ɏ���ɑ�p�֒E�o���āA�i�ߊ��̓G�O���S�Ƃ܂Ō���ꂽ�B�i�㐢�̈��{�W�O�ȂǂƂ����l�Ԃɂ悭���Ă���ł͂Ȃ����I�j���������R���U���w�������������咆�����I��̓��A�Ō�̓��U�@�ŏo�����ׂ��Ƃ��������̐i�������ۂ��A�I���������̋@����킵�ĕ���������掂���V����S�������B�i���������ȗ\�Z��H���ׂ��ăI�����s�b�N���v�Ɏ��s���Ă����Ȃ���A�ӔC����낤�Ƃ��Ȃ��Ό��T���Y�s�m���ȂǂƂ����l�Ԃ̓��ލ����H2009�N10���NjL�j
�@����ł͂������̐Ό������f��ɂ͕`���Ȃ��ł͂Ȃ����B�Ό����͂��̉f������ȏ�A���������Ƌ��ɏ�w�����܂��Y�X���������������̂��ƁA�R�ł���������咣����K�v���������B�����Ό����͌R�╔���̏�w������҂����ɂ������̏o���𖽂��Ă����āA���������͐ӔC����������j����m���Ă����B�����Ď��琧��w�������f��ł͂��̎������āA�����ɑ��Ă̂ݗY�X��������������Ƃ����v���p�K���_���s�Ȃ��ׂ��A�C�R�����R�̘b��s���̗ǂ��Ƃ��낾���p�����킹�āA�܂��������ȉf��������炦���̂��B���{�̎w���ґw�̈�l�ł���Ό����̂悤�Ȑl���A���������I���ȗ��j�̝s�����s�Ȃ��̂ɍ����͘f�킳��Ă͂����Ȃ��B
���@�m�炸�̓��{�l
�@2007�N�T���A�������[�@�Ă�����ʼn�����A���悢����{�����@�����̎葱���������o�����B��}�͂��̖@�Ắg���@�����h��_���^�}�̎v�f�ł���Ƃ��Ĕ����Ă���悤�����A�ނ�͌��@�����������Ă��Ȃ��B��́A���{�����@�����̎葱���Ɋւ��ẮA���{�����@���̂̒��ɖ��m�ɋK�肳��Ă��邱�Ƃ�����A�����̂��߂̎葱���@�Ă��̂��̂ɗǂ����������Ȃ��B�����ɓ��{�����@����낤�Ƃ����ӎu������Ή�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂����A���������@������]��ł���̂ł���A�����j�~���悤�Ƃ�����}�̔��͂��ꂱ�����@�����ł���B
�@�������Ȃ̂́A���{�̗^�}����}���������A�܂������ߑ㌛�@�Ƃ������̂𗝉����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���邱�Ƃł���B���{�����@�͐�̌R���牟���t����ꂽ���@������������܂��傤�Ƃ����̂����{�^�}�̉����_�҂����̌����������A����ȋc�_���Ȃ���Ă��邱�Ǝ��́A���{�Ƃ������͋ߑ㌛�@�̐��_��m��Ȃ��A�����Ă܂����̐����̗��j���m��Ȃ��A��{�I�l���̌�i���Ȃ̂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@�l�ނ�17���I���炢�܂ł͊�{�I�l���Ƃ͖����ŕ�炵�Ă����B������M���́g�̒n�h�ɏZ�ސl���́g�̖��h�ƌĂꂽ���Ƃł�����悤�ɁA���̓y�n�ɐ����Ă��鑐������Ă���b�ȂǂƓ����悤�ȁg���Y�h�̈�ł����Ȃ��������炾�B�܂��A����M�������̏Z���ɑ���Ď��⊱�����݂̍��Ƌ@�\�̂悤�Ɍ��i�Ȃ��̂ł͂Ȃ���������A���l�͉��l�A���O�͖��O�ŕ��i�͂��ꂼ�ꏟ��ɕ�炵�Ă����킯�ŁA����قǐ[���Ȗ��ł��Ȃ��������낤���c�B
�@�ł͍������y�n��l�����g�̗L�h���錠���͂ǂ��l�����Ă������Ƃ����ƁA�u�����_�����v�A���Ȃ킿�_����^����ꂽ�_���Ȃ��̂ŁA�N���������������̂ł͂Ȃ��Ƃ������̂������B
�@������1689�N�A�C�M���X�̖��_�v���Łu�����͓̏T�v�����F���ꂽ���A����͋c��̏��F�Ȃ������͖����Ƃ��ꂽ����I�Ȃ��̂ł���B���������́u�����͓̏T�v�������Ƌc��Ƃ������͑��̍��ӂɊ�Â��Ď{�s���ꂽ�����̂��̂ł���A�܂�������l��l�̐l���ی�Ƃ������ʂ܂ł͎������킹�Ă��Ȃ��B
�@�����i�l���E�s���j����̓I�Ɋ�{�I�l�����������̂́A1789�N�̃t�����X�v����҂��˂Ȃ�Ȃ������B�o�X�`�[���S���P���Ɏn�܂����t�����X�v���́A���̌�W�����h�}�ƃW���R�o���}�̓�����A�i�|���I���c��̏o���Ȃ����]�Ȑ܂��o�Ȃ���A���܃}���[�E�A���g���l�b�g��吨�̌��𗬂������ɂ���ƁA�����̑�����̊�{�I�l���v���Ƃ����A����̐�i���ł͎��ɓ��R�ȍl�������蒅�����B
�@���ƌ��͂͑���X��������A�����Ă����Όl�̐l����N�Q���邱�ƂɂȂ�B�����Ȃ�Ȃ��悤�ɍ��ƌ��͂���̂��u�ߑ㌛�@�v�ł���A���������Ċ�{�I�l���̑��d��搂��A���ƌ��͑����h�����߂̎O���������K�肵�����̂������ߑ㌛�@�Ȃ̂ł���B
�@������604�N�̉䂪���̏\�������@�́A�������q�̍�����̗��O��搂������̂ł͂��邪�A��{�I�l���̏������Ȃ��̂ŁA�c�O�Ȃ���ߑ㌛�@�̒��Ԃɂ͓���Ȃ��B
�@�ŋ߂̉䂪���̉����_�c�Ɍ����Ă���̂́A���@�Ƃ͍����̊�{�I�l������邽�߂ɍ��ƌ��͂���̂��Ƃ����ߑ㌛�@�̗��O�ł���B�����������͒����̓����ɂ���l�Ԏ��炪���@�����𐭎��̑��_�ɂ���Ȃǂƌ����o���́A�^���ڂ̗D�j���j���j�����Ȃ���u�V�������Ŏ����ĉ������v�ȂǂƑi���Ă���悤�Ȃ��̂ŋC�F�����BSM�V���[���Ⴀ��܂����A���ł��邱�Ƃ̂ł���C�J�T�}���ɕς��Ă������Ƃ������_�������Ȃ����Ɗ����肽���Ȃ�B
�@�䂪���ɂ�����ߑ㌛�@�̗��j�͂�������������ł��Ȃ������B�]�˖��{�̐���|���Đ�����D�悵���F���̖����V���{�́A�J�����ď��O���ƑΓ��ȍ���������ł������߂ɁA�ߑ㍑�Ƃ̏ے��Ƃ������錛�@�����ڎw�����B�����đ���{�鍑���@�����z���ꂽ�̂�1889�N�A���������̍ۂɎQ�l�Ƃ����̂��l����i���̃t�����X��C�M���X�������炻�̌�̓��{�̗��j���ς���Ă������낤���A���[���b�p�̒��ł͌�i���������h�C�c�̃v���C�Z�����@�������B�i���F�C�M���X�ɂ͐����̌��@�͂Ȃ��B�j
�@����{�鍑���@��R���ɂ́A�u�V�c�͐_���ɂ��ĐN���ׂ��炸�v�Ƃ��邪�A����͂܂��Ɍ����͓̏T�ȑO�̉����_�����̍l�����ł���B�������͖����V�c���]���Ƃł͂Ȃ��낤�B�����V���{�̎w���҂������V�c�𗘗p���ē������₷�����悤�Ɖ�����ʂɈႢ�Ȃ��B
�@��ɔ���s�Y���j���Y��e�N���鉉���̒��Łu�ʍ��i�V�c�̒n�ʁj���Ȃ��ċ��ǂƂȂ��A�ْ��i�V�c�̖��߁j���Ȃ��Ēe�ۂƂȂ��A�Ȃ��Đ��G��_��������̂Ȃ�v�Ɗ��j�������Ƃ��A���͎҂��V�c�𗘗p���邱�Ƃ���}�����̂ł���B���Ȃ킿����{�鍑���@�́A�����̊�{�I�l������邽�߂ł͂Ȃ��A���͎҂����獑�������₷���悤�ɍ��ꂽ���̂ł������B
�@���̑̐������ǂ͑����m�푈�̔j�ǂ���������ƂȂ����̂ł��邪�A����͌��ʘ_�B�����������҂������ɓs���̗ǂ��悤�Ɍ��@���߂č����ɉ����t���������͗�R�Ƃ��Ă���B����͖������{���������ɋߑ㌛�@�̗��O���܂������������Ă��Ȃ��������Ƃ��������̂��B
�@��������ł͑����m�푈�̔s����o�āA���{�l�͋ߑ㌛�@�̗��j�Ɨ��O���w���낤���B���ɂ͂����͎v���Ȃ��B���̓��{�l���܂��A�ߑ㌛�@����{�I�l���������̂��Ƃ������O��������������ɒm��Ȃ����炱���A�����̂悤�ȉ����_�c�������N����̂ł͂Ȃ����B
�@�u�����t����ꂽ���@�v�����āc�H����{�鍑���@�����ē����҂������ɉ����t�������̂��B���{�ɂ͖����̐̂������̍����A���@�Ƃ͓����҂�����̎{��̕X�̂��߂ɍ����̂��Ƃ������x�̔F�������Ȃ��̂��B�ꉞ�͍����̐l������邽�߂Ɍ��͂�Ƃ����̍ق����͐����Ă���悤�Ɍ����邪�A���ǂ�SM�V���[�̃C�J�T�}���c�BSM�V���[�Ƃ�����g�ɕi�������Ƃ����̂Ȃ�A��E�o�}�W�b�N�p�̍����B
�@�ꗬ�}�W�V�������悭���E�o�}�W�b�N�ł́A�}�W�V�����͕R�⍽�ŃO���O�������ɔ����Č��̊|���������ɕ����߂��A�Β��␅���ɓ�����ꂽ��ɂ���������Ƃ��Ȃ����R�ƍēo�ꂵ�Ă��邪�A���̍��Ȃǂ͔���ꂽ�͂��̃}�W�V���������ł��������Ƃ��ł���悤�Ȏd�|��������Ɍ��܂��Ă���B�����^�}����Ă��Ă��錛�@�������ĂȂǂ͂��̃}�W�b�N�̍��Ɠ������B���������蕳�ȃ}�W�V�����̂悤�Ɏd�|�������������Ă���̂ɁA�ϋq�̍����̕����ߑ㌛�@��m��Ȃ�����A���ꂪ�܂����������Ă��Ȃ��B�����琭���^�}�̉��蕳�ȃ}�W�b�N�̎d�|����\���Ă݂��悤�B
�@��̂Ȃ����R����}�͎��R�}���ォ�����т��Č��@������ڎw���Ă������B�ނ炪�ς������Ǝv���Ă���̂́A���ǂ͑�X���̈�_�ł͂Ȃ��̂��B���ɂ�������b���V�c�̍����s�ׂɖ����肽�V�����U�łȂ��Ƃ��A�O�c�@���U�����R�ɂł���悤�Ɍ��͂��W�����������Ƃ����悤�Ȑ����^�c�̋Z�I�I�ȉ����|�C���g�����邾�낤���A����͌��s���@���ł�2005�N���I���̑O�ɏ���O������Ă��邩��A���킴�킴��������K�v���Ȃ��B
�@���������@��X���̓C���N�h������W�c�I���q���Ƃ̗��݂ōŋ߂��낢�됭���̎x�Ⴊ�o�Ă��Ă���A�^�}�ɂƂ��Ă͖ڂ̏�̃^���R�u�ł��낤���A����Ƃ͕ʂɁA��͂�60�]�N�O�̂��̎��A��̌R�ɂ���ĉ���ꂽ�A���������ꂽ�A���������T�������v���������ւ��Ĉ�C�ɕ\�ʂɕ����o�����ς�����B���ꂪ������t�����@��Ƃ������t�ɍ��߂�ꂽ�v���ł��낤�B
�@���̍��X�Ȃ�Γ����s�퍑���Ԃ̃h�C�c��C�^���A�ł����R�������S�ɔے肳���悤�ȋɒ[�Ȑ�㐭��������t�����Ȃ������B���ʼn�X���{����������ȁg���J�h�𖡂�킳�ꂽ�̂��H���U���܂ŏo���Ď��ɕ������̒�R�������������H��������������͂��ߐ�����ɂ��܂ʓ��{�l�ɋ��|������ꂽ�������H
�@�����͂��ׂĎא��Ƃ������̂ł���B���̎��̐��E�͂����Ȃ�ɂ��������B��ꎟ���̎S�Ђ����P�Ƃ����x���T�C���̐���~���ĕ��a��������ɂ�������炸�A���ꂩ��30�N�ƌo���Ȃ��Ԃɐ��E�͂���ɔߎS�ȑ�푈��̌����Ă��܂����B�폟���Ƃ͂����]�T�ŏ������킯�ł͂Ȃ��B��퓬���̎��������Œ�̃A�����J�ł����A��O�̌Ǘ���`������Ă���Ύ��Ȃ����ɍς͂���30���l�߂���҂��]���ɂ����̂ł���B
�@�����푈�̓C�����Ƃ����v���͑S���E���ʂ̂��̂������͂����B���{�ɂ����푈����������Ď��������͍��������ɐ푈���悤�Ƃ����悤�ȃP�`�ȗ������������͂��͂Ȃ��B�����������������S�ɉ�ł����Ƃ͂����Ă��A����Ɏ��̑�푈�̗\���͂������B���Y�������Ǝ��R�������̑Η��ł���B���̗��w�c���S�ʐ푈�ɓ˓�����Α���E�����͂邩�ɏ���]���҂��o��͉̂�����������炩���B���Y��`�͒��X�Ƒ�����ł߂Ă���B�̐A���n�x�z��E�����r�㍑�͕n�����̂��߂ɋ��Y��`���Z�����₷���B�������܂����Y�}�������}��ǂ��l�ߎn�߂Ă���B�h�C�c�͓����ɕ������ꂽ�B���ꂪ1945�N����1946�N���̐��E�̏ł������B
�@�����l�ނ���x�Ɛ푈�����Ȃ��ōςނ悤�ȕ��a�̗��z���������������͂Ȃ����̂��B�����I�ɂ܂������ɂȂ������Ɂu�푈�����v��搂������@�𐧒肷��A���邢�͐푈�������Ȃ邩���m��Ȃ��B���{�����@�̑��Ă�������l�X�̊Ԃɂ́A���{�l�A�O���l���킸�A���������v���͋��������Ǝ��͎v���B��̌R�������t�����ƌ������A�ނ������R�̌R�l�Ȃ�A���{�ɍČR�������đ��Y���̍Ԃɂ��悤�Ƃ������z�̕������R�ł���B�����������͂Ȃ�Ȃ������B
�@��X���͂����炭1946�N�����̐��E�̐S����l�X�ɂƂ��āA���E���a�Ƃ����l�ދ��ʂ̗��z�̎����ꂾ�����B���������60�N�A���E�����{�����K���Đ푈��������Ȃ��������߂ɁA�����܂��܂Ȗ��������o���āA���{�l���g���g���E���a�h�ւ̎�����������悤�Ƃ��Ă���B
�@����͂���ō����̑������]�ނȂ�Ύd���Ȃ����Ƃ����A���E���������炭���ڂ���ł��낤��X���������Ɋւ��āA���蕳�ȒE�o�}�W�b�N��SM�V���[�̂悤�ȏ��H�����Ȃ��ŗ~�����B�푈�������Ă��܂�Ȃ��Ƃ������S���ی����̐V���@���ĂȂǏo���Ă��Ȃ��ŗ~�����B�ȉ���2005�N��10��29���̐V���ɕ��ꂽ���R����}�̑��Ă̂����A�ő�̑��_�ɂȂ�ł��낤��X���֘A�����ł���B
��Q�́@���S�ۏ�@�i����͌����@�ł́u�푈�̕����v�ƂȂ��Ă���j
��X���i���a��`�j
���{�����́A���`�ƒ�������Ƃ��鍑�ە��a�𐽎��Ɋ��A�����̔�������푈�ƁA���͂ɂ��Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ẮA�i�v�ɂ�����������B�i���̂P���͌����@�Ƃ܂����������ł���j
��X���̂Q�i���q�R�j
�䂪���̕��a�ƓƗ����тɍ��y�э����̈��S���m�ۂ��邽�߁A���t������b���ō��w�����Ƃ��鎩�q�R��ێ�����B
�A���q�R�́A�O���̋K��ɂ��C���𐋍s���邽�߂̊������s���ɂ��A�@���̒�߂�Ƃ���ɂ���A����̏��F���̑��̓����ɕ�����B
�B���q�R�́A��P���̋K��ɂ��C���𐋍s���邽�߂̊����̂ق��A�@���̒�߂�Ƃ���ɂ���A���ێЉ�̕��a�ƈ��S���m�ۂ��邽�߂ɍ��ۓI�ɋ������čs���銈���y�ыً}���Ԃɂ�������̒������ێ����A���͍����̐����Ⴕ���͎��R����邽�߂̊������s�����Ƃ��ł���B
�C�O�Q���ɒ�߂���̂̂ق��A���q�R�̑g�D�y�ѓ����Ɋւ��鎖���́A�@���Œ�߂��B�i�����͕M�ҁj
�@�����ƈȏ�ł��邪�A����������t�������������A�E�o�}�W�b�N�p�̍��Ɠ����d�|���ł���B���Ă�������l�X�̒��ɂ͖@�����U�����҂����������ł��낤�ɁA����Ȑٗ�ȓꔲ���̎d�|�����悭�}�X�R�~�ɖ\�I�������̂ł��邵�A����ɋ������̂́A���̑��Ă����ꂽ��A���̓_��˂����ᔻ�͊������������ǁA���Θ_�̎嗬�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃł���B�����}�̐���ɔ����闧��̐l�X�̒��ɂ��@�����U�����҂͑����͂������A����ȒP���ȃ^�l�����������ł����ƍ����ɃA�s�[�����Ȃ��̂��B��������@�𗝉����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���@�͌����܂ł��Ȃ����̍��̍ō��@�K�ł���i�ō��@�K���j�A���̌��@�̒�߂�葱���ɏ]���č����n���c���s���Ȓ��Ő��肳�ꂽ���ʂ̖@���A��߁A���߂ɐ�������ۏႷ����̂ł��邪�i�����K�͐��j�A���̕ۏ�͌����Ĕ����ϔC�ł͂Ȃ��A���@�Ɉᔽ�����@�����߂▽�߂͏o���Ȃ��̂ł���i�����K�͐��j�B���Ȃ킿���@�ɂ́A�@���Ȃǂł����܂Ō��߂Ă悢�A����ȏ�̂��Ƃ͌��߂Ă͂����Ȃ��Ƃ������m�ȋK�肪�܂܂�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邪�A��L�̉������͊��S�Ȕ����ϔC�ł���B
�@���q�R�̊����͂ǂ��܂ł���Ă悭�āA�ǂ������͂���Ă͂����Ȃ����A���ꂪ���@�����Ŕ��f�ł��Ȃ�������Ȃ��B��������L���Ăł́A���̎����̎��ɉ����č���ō�����@��������Ή������Ă��\��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B����^�c�͑������������ł��邩��A���̗^�}���l�����Ƃ���Ɏ��q�R�������Ƃ��\�ł���B����͍��ە��������ł͂Ȃ��A�����̐�������銈�����ƌ�������߂āA�������ł��j�����ł����o���ł����ł��ł���B�����������ɂȂ��Ă��\��Ȃ��Ƃ����������������߂�̂ł���A������R�N�ȍ~�ɗ\�z����錛�@�����̍������[�ő�X�����ϖe���Ă��܂��Ă��d�����Ȃ����c�B
�i���̂X����Ɋւ���ӌ����ʍ����Q�Ƃ��ĉ������B�j
�o�������Ȃ��b
�@�ǂ����Ă����o�J�o�J�������Ƃ�����̂��m��Ȃ����A�N���L�^�������Ă��܂����炵���B���������Ύ��̏��ɂ������X�N�P���P���t���Ŋ�b�N���ԍ��̒ʒm�����������Ƃ��������悤�ȋC�����ĒT���Ă݂���A�ʒm���ɕt������Ɖ�ɂ́A����܂ŔN�����x���ƂɕʁX�ɉ����L�^���Ǘ�����Ă������ƁA���������ꂩ��͍���̊�b�N���ԍ������Ƃɐ�������K�v������̂ŁA�����͂����肢����|�̕��͂��m���ɏ����Ă���B�������ŋ������鎞�ɂ́A�[�Ŏґ��̂�����܂őz�肵���ꍇ���g���ؒ��J�Ɂh���������q�𑗂�t���Ă��邭���ɁA���̔N���ԍ��̐��������Ɋւ��Ă͎��ɂ��e���Ȃ킸�����s�̕��͂ł����Ȃ��B���������m��Ȏ葱�̂��߂ɏ������N���L�^��5000�����Ƃ������B
�@�x�������}���������{�����͍Q�ĂāA�N�����t�̎�����P�p����@�Ă����s�ɉ��������A����͎Q�@�I�����ɂ�ł̂��Ƃł��낤�B�܂���}�͐R�c�s�\���Ƃ��Ă��̖@�Ăɔ����Ă������A���ꂾ���Ă���Ȗ@�Ăō����̂��@���������ĎQ�@�I���Ŏ����}�ɕ[���߂������ς��Ƃ������x�̔F���Ɍ��܂��Ă���B�v����ɐ����Ƃǂ��͎����̂��Ƃ����l���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@���{�W�O���C�F��Ŏ��̌�����b�̐����l�i���E����}�j�̂����ɂ���A�����l�̓m�����N�����Ǝ��̌�����b�̏���Y�̂����ɂ���B�܂����������Ƃǂ��̓D�d���͌��Ă��Ĕ��f���o�����ȂقǏX������܂�Ȃ��B
�@��́A���Ƃɂ�鍼�\���Ɩ��㉡�̂��Ɣᔻ�̑����N���L�^���ƍ�5000�����A�����S�z�����ɕԊ҂���ȂǂƁA�^�}����}���Q�@�I�ړ��ĂɌ�������̗ǂ����Ƃ��茾���Ă��邪�A������ƍl����Ώ펯�I�ɂ���Ȃ��Əo�������Ȃ��ł͂Ȃ����B�P���P�������y���ԏ�ŏ����ɏƍ����Ă��������đS���I���܂ł�13�N�ȏォ����B�ƍ���Ƃ̂��߂ɕK�v�Ȑl����E������͂����炭���S���~�ȏ�Őŋ�����̗]���ȏo��B����ɑS�z�⏞����ƂȂ���̍����͐����~�K�͂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B����Ȍo�ϓI�]�T�����̍��̂ǂ��Ɏc����Ă���̂��H
�@�����Ƃ��������A�ǂ��������͍����ɒ��߂����˂Ȃ�Ȃ��ƕ��̒��ōl���Ă���Ɍ��܂��Ă���B�V���̎Q�@�I�����I�����������{�����`���z���������Ă��邱�Ƃ��낤�B���ꂱ���܂��Ɏ�����������炱�̃T�C�g�ɏ����Ă�����U���Ɠ����\�}�Ȃ̂ł���B���̎w���҂ǂ��̔��f�̊Â��Ǝ���̃c�P�����������ׂĕ��킹���A��w���͏]���ȍ����̋]���̏�ɌӍ��������ĐӔC���������B
�@���U���̏ꍇ�A�{���Ȃ��҂����Ɏ��E�s�𖽂����w�����͑S�����ǂ��ďI�펞�Ɏ��n���ׂ��������̂ɁA�����������̂͑吼�뎟�Y�����P�l�������B�i�������U�̉F�_�Z�͊܂܂��B�j����A�����̍��Y���_�U�������������̐����Ƃ⊯���́A���ꂪ�S�z��������Ȃ���Ύ���̎��L���Y���ׂĂ𓊂��ĕٍςɓ��Ă�ׂ��ł��邪�A���̂��炢�̐ӔC���̂��鐭���Ƃ⊯���͓��{�ɂ͂������Ȃ��ł��낤�B
�@���{�����U���̎���Ɖ���ς���Ă��Ȃ����Ƃ���R�Ɣ��鎞���Ԃ��Ȃ�����B����ł����Ȃ����͂܂����U���̔ߌ��ɐ����Ă��肢�����Ȃ̂��B����Ƃ�������̍��Ƃɂ���ȏ�̕��S�������Ȃ����߂ɁA�N���̈ꕔ���������o��܂Ō��߂�ꂽ�̂��B
���F
�@�Љ�ی����̓m��ȍ�Ƃ̂��߁A�����̔N���L�^�����ɕ�������ԂɂȂ����g�����h�̐ӔC�ɂ��āA���������ʂ̊ϓ_����l���Ă݂悤�B�܂荑�Ƃ̊Ǘ��ӔC���A�����̎��ȐӔC���Ƃ����_�ɂ��Ăł���B
�@����A�N���L�^���������Ƃ͌����Ă��A�N���ی������x�������Ƃ����̎���������Ή������͂Ȃ��B���������\�N���O�̗̎����ȂǕۑ����Ă���킯�Ȃ�����Ȃ����Ƃ��������̕s���Ɖ����̌��������A���̂Ƃ���́i2007�N�U�����݁j�F�߂��Ă���悤�Ɍ�����B���������{���ٖ̕��̒��Ɂu�̎���������Ή]�X�v�Ƃ����������A���肰�Ȃ��U��߂��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��B�����炭�����}�����̂����ɎQ�@�I���I���A�܂��ɂ��̓_��˂��āA�̎��������������̎��ȐӔC�Ƃ����_�@�ŁA�N�����̖��������s�Ȃ���\�������邩�炾�B
�@�m���Ɏx���ɑ���Ή������܂ł͗̎�����ۊǂ��Ă����̂��A�����_���ł̏펯�����A�x���҂̎��ȐӔC�ƌ����Ă��d�����Ȃ��B�������N���ی����͍��Ƃ������͂�w�i�ɋ����I�ɒ����������̂ł���B�������V��̂��߂ɔC�ӂŌ_�����̂ł͂Ȃ��B���ԕی���Ђ��C�ӂ��_���N���ł���A��Ђ̓|�Y�Ȃǂɂ��߂��ė��Ȃ��Ȃ����ꍇ�A�̎������������Ă���Α����̋~�ς����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B�܂��Ɏ��ȐӔC�B
�@����A���Ƃ������I�������������ł���Ȃ�A���̋L�^�����������Ƃ������Ƃ́A�����̑��̗̎��������Ƃ������ȑO�ɁA���Ƒ��̊Ǘ��ӔC�������ׂ��ł���B����������ł́u���͊m���ɕ������v�ƌ�������l���o�Ă����ꍇ�i�����炭�{���ɕ������l���A�������Ǝv������ł邾���̐l���A����ɂ͐V��̍��\�t���܂߂Ėc��Ȑl�����\�����ĂĂ��邾�낤�j�A���Ƃ͌����l�ŔN�����̂��H�{���ɕ������̂ɗ̎��������Ă��܂����l�ł���Ύd�����Ȃ����A�����ĂȂ��̂ɉR�̐\���������l�ɂ܂ŔN�����x������̂ł���A���̑����͒N�����S����̂��H���ǂ͍����̌��ł�A����ɎႢ����̔N���ی�����H���ׂ��č��\�t�̉����₷����Ȃ̂��H
�@�����ł������\�L�̌o�ϊ�@�ɂ��钆�A���������W�����}�Ɋׂ錴������������̊�������Ɓi�A�����j�́A�K�v�ŏ����̐�������������Ȃ̑S���Y�����ɂɔ[�����āA���\�t�ɋz������镪�������肷�邭�炢�̊o��������Ɏ����ׂ��ł���B���Ď����̔��Ăɂ���ĎႫ���U���������̐�����D�����吼�뎟�Y�C�R�������I�풼��Ɏ��������悤�Ɂc�ł���B���������̎����Ɍ�����b����������Y�́A�����ő�b����̋��^�����߂�ꂽ�ۂɁu���ɂ͂���ȋ��͖����v�Ƌ��������������B���ꂪ���ē��U�����^�������O�̐����U�}�Ȃ̂��B
�u���������v�̐���
�@2007�N�V���S����NHK�̐l�C�ԑg�u���̎����j�͓������v�ŁA���̐����� ���X�R����W���Ă����B1956�N12���ɓ��t������b�ɏA�C�������A�a�Ă킸���R�����őޔC������Ȃ������ł���B
�@���X�R���̉��~�͎��̎��Ƃ̋߂��ɂ����āA�܂������c�t���⏬�w�Z��w�N�̍��A���̉��~�̑O��ʂ邽�тɁA�c�ꂪ�u���������X�R�̂��Ƃ�v�ƌ����Ă����̂��v���o���B�ǂ������ɂ��Ďv���Ƒc��͂킴�킴����肵�Đ��Ƃ̑O��ʂ��Ă����̂ł͂Ȃ��������B�����c�S�Ɂg�^���U���h�Ƃ������������O���]���ɏĂ������B���X�R�́g��˕��h�̐����Ƃ��Ƃ��c��͐���Ɍ����Ă�������A���Ԃ��̑c��̂悤�Ȑl�ԂɂƂ��Ă����X�R�͑��h�̃}�g�������ɈႢ�Ȃ��B
�@�g��˕��i���ǂւ��j�h�Ƃ͍����Ȑ����Ƃ��w�����t�ŁA�{���ɍ����̂��߂��v���Ď����̍��Y�����������Đ����ɐ�S����A�ƍ��Ƃ��Ă͈�˂ƕ������c��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B���݂̂悤�ɓy�n�����@�̑ΏۂɂȂ�悤�Ȓl�ł��̂��鎞��ł͂Ȃ��B�͓̂y�n�Ȃǂ͈����ł�����ł������āA���̓y�n�Ɍ����Ă���㕨�i������́j�̕����y���ɍ������l�������Ă����B���������ׂĔ�₵�Đ����ɑł��������ƂƂ������Ƃł���B�ŋ߂̋c���ǂ��ɂ͎��̒ɂ����Ƃł��낤�B
�@NHK�̔ԑg�ɂ��ƁA���X�R�͐�O�͌R���ɋt����ē��{�̃A�W�A�A���n����ɐ^��������ق������A���̓A�����J�̐��E�x�z�̐��ɔ����āA���Y���Ƃ��o�ϓI�Ɍ𗬂��铹���J�����Ƃœ����̗��\����Ŕj���悤�Ƃ������E�I�Ȑ����ƂƂ������Ƃł���B�ŏ��A�����J�͐��X�R���x�����ĖW�Q���悤�Ƃ��邪�A���̌�͌��ǐ��X�R�Ɠ��������P���ċ��Y�������Ƃ̐ڋ߂�}��悤�ɂȂ����Ɣԑg�ł͏q�ׂĂ����B���X�R�����^�ɔ��Ȑ挩�̖��̂���l�ł������B
�@�ɂ��ނ炭�͔]�[�ǂœ|��ĒZ�������ɏI����Ă��܂������A���̌�������ȂNj��Y�������Ƃ̊W���P�ɗ͂�s�������Ƃ����B���X�R�Ǝ̍��𑈂����R�n�͊ݐM��ł������B�X�R�̗E�ނŃ^�i�{�^�Ŏ̍��ɒ��������A���̐l�Ȃǂ͐����{�̐��E�ɂ��Ⴕ���o�Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��l���ł���B�����p�@���t�̏��H��b�Ƃ��ĊJ��Ɏ^�������i�����v�j�ӔC��Y��A���͈�]���đΕĈ�ӓ|�ŃA�����J���̐���𐄂��i�߂��B
�@��O�͌R���ɔ����A���̓A�����J�ɏ|�˂������X�R�Ƃ͂܂�Ő����̐l�����������A�����������ɒ[�̐l������������ł���ꂽ�̂����̎��R�}�|���R����}�̋����������̂��낤�B�������Ƃ������ݐM��̂悤�ɖڐ�̕���ǂ݂A�������ɛZ�тĂ̂��オ���Ă����̎��͂ǂ�����`�I�Ȃ��̂̂悤�ŁA�ݐM��̑����܂��A����Ƃ����������l�ԂɐK����U���Ď̍��ɓo��߂����A�����̓I�ȃr�W��������������u���������v�ȂǂƂ������ۓI�Ȍ��t��M��ł��肢��B
�@���Ď��͕����N�Ԃ̐���2007�N�A�N�����E�����������ȂǂŎx�����}���������{�W�O�A�V�����ɍT����Q�@�I�Ŕs�k�������̐ӔC�_��u�˂��āA�키�O���炻��Ȃ��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��Ɠ˂��ς˂��炵���B�ǂ��������Ƃ̐ӔC�_�ȂǁA�G���̏����Y���܂߂āA�I���ɕ��������̐g���ɑ���ӔC�ł����āA�����ɑ���ӔC�ł͂Ȃ����Ƃ��炢�������Ă����Ȃ�������Ȃ����A���̉�̐ȏ�A���{�͋�����v�@�Ă�i���@�����̂��߂́j�������[�@�Ă̐����������āA�u���������Â���Ɍ����Ē����ɓy�䂪�ł��Ă���v�Ǝ��т����������Ƃ����B
�@����܂Łu���������v�ȂǂƂ������ۓI�Ȍ��t�ŃP���Ɋ�����Ă�������ǁA����ł悤�₭���{�̌����u���������v�̋�̓I�ȃC���[�W���_�Ԍ������킯���B�܂茛�@���������ČR���𖾕������A�q�������Ɉ����S�������t����̂��A���{�̂����u���������v�Ȃ̂��B
�@�قƂ�ǎ��v�̂Ȃ��������ƂɌ��ł𓊓����č��y�𗐊J�����Ă����܂�Ȃ��B�����Ǝ��炪�݂𐳂��Đ��n�����H���A�������爤�����悤�ɓw�͂���K�v���Ȃ��B�g����h���E�������ƌ��������������ĉE�������A�����Ă��ꂪ�����S���Ǝv�����ނ悤�Ɏq�����������炷��B���ꂪ���{�̂����u���������v���B����͂������܂����悤���Ȃ��B�Q�@�I�S�s�̊�@���ɃJ�[�b�Ɠ��Ɍ�����������v�킸�k�炵���{���ł��낤�B���������ɓ���[���W�߂āA�^�}�ɉߔ����̋c�Ȃ�^����悤�ȍ�������ł���A���͂������̍��ɖ����͂Ȃ��B���X�R�̂悤�Ȑ����Ƃ͊��҂ł��Ȃ��̂��낤���B
���E�u���������v�̐���
�@2007�N�V��29���ɓ��[���s�Ȃ�ꂽ�Q�c�@�I���͎����}�́g���j�I��s�k�h�ɏI������B�Љ�ی����̔N���L�^�����ɕ����ď����Ă��܂������Ƃ��A�������E�ԏ�_�ѐ��Y��b�̎���������ɒ[���鐭���������ւ̕s�M�Ƃ��A�����}�ɑ��鋭��ȋt���������r��钆�ōs�Ȃ�ꂽ�I���ł���������A���R�̌��ʂƂ������悤���A�܂��������}�������܂ō������爤�z��s������Ă���Ƃ͎v���ʂقǂ̎S�s�ł������i���I121�c�Ȓ�64��37�c�ȁj�B
�@�����}�ƃ^�b�O��g�ޘA���^�}�̌����}�܂ł����n����I�ɋc�Ȃ����炷���肳�܁i12��9�c�ȁj�B���̓}���͓̂��{�̗R����������}�ł��������A�����~�����Ɏ����}�ƘA����g����ɁA���͂⍑���̐M������������̂ł͂Ȃ����B��͂�x����̂����͂Ȃ̂ŋ}���ɐ��ނ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���邪�A�����߂���Ƃ������Ă̎Љ�}�i���E�Ж��}�j�����Ɏ�������������}�Ƃ��Ă̐M�������߂��Ă��Ȃ��A���̓�̕���ł���̂͊m���ł���B
�@���������A����g��ł��ꂽ�����}�ɂ܂ő���f�������āA����قǂ́g���j�I�h�ȎS�s���i�����ɂ�������炸�A�����}���قł�����{�W�O�͑��X�Ǝ�����錾���A�}���O�ɐӔC�_�������Ԃ�̂��������āA��ސw����C�͂��炳�疳���炵���B�Q�@�I�ɑ�s�����͎̂Љ�ی����̓m��ȔN���Ǘ���A�������E�ԏ�_�ѐ��Y��b��̐��������^�p�ւ̕s�M���������Ȃ̂ł����āA�������f�����{����͍����Ɏx������Ă���͂��ł���Ƃ��������œƑP�I�ȗ������L�҉�Ȃǂŏq�ח��ĂĂ���̂����A�܂�������قǂ̔n���Ƃ͎v��Ȃ������B���ꂵ���ɂ��قǂ�����B
�@�����̊�{���x������Ă���Ǝ咣�������̂ł���A����Y���X�����c���̎��Ɍ��s�����悤�ɁA�O�c�@�����U��ɑ��I���ɑł��ďo�āg���Ӂh��₤�ׂ��Ȃ̂ł����āA����������Ɏ̍��ɋ����葱���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�@���{�W�O�͉������ł����̂�̎�Ō��@���������A������������A�g��ヌ�W�[���h�Ƃ���p�����āA�u���������v����肽���悤���B�����Ƃ��ŋ߂ł́u���������v�Ƃ������t�ɑ����a�������邱�ƂɋC�������̂��A���ɎQ�@�I�S�s��́u�V�������v�Ƃ������t���悭�g���Ă��邪�A���ǂ͓������Ƃł���B���������ƌ��������A�V�������ƌĂڂ����A�����̖ڎw��������̉��l�ς������ɃS���������Ă����B���ꂪ���{�̖�]�ł���B
�@����ł܂��܂����{�̂����u���������v�̏X�����Ԃ������Ă����̂ł͂Ȃ����B���������ƌ��������A�}���O�̐��G�����ƌ��������A�����ɂ͂܂����������X�����A���͂̍��ɌŎ�����B�����������Ƃ����Ƃ������c�A�ƍٍ��Ƃł���B���{�̂����u���������v�Ƃ͌��͎҂Ƃ��̈ꖡ�������ǂ��v��������ƍَ�`���Ƃ��������Ƃ��A��X�����̑O�ɖ��炩�ɂȂ����킯�ł���B
�@�Q�c�@�Ŗ���}�ɑ��}��D��ꂽ����̋L�҉�ň��{���g�A�u���ꂩ��͖�}�̌������Ƃ������Ȃ�������Ȃ��v�ȂǂƏq�ׂĂ������A����ł͂܂�ō��܂Ŗ�}�Ƌ��c����C�Ȃǖ��������ƌ����Ă�������R�ł���B
�@���������l�Ԃ��O�c�@�̋c��2/3�ɕ������킹�Ė\���������ʂ��A���@�����⋳����v�Ɍ����Ă̕z�ł���A���������}�̌������ƂɎ���݂����ɋ��s�̌��Ɏ������s�̌��œ˔j���Ă������̂���ł���B����Ŏ����̊�{���u���������v�ɂ͍����̗���������Ƌ������Ă���̂�����n���������B
�@�����������{�����s�̌��̓���Ɏg�����O�c�@��2/3�̋c�Ȃ́A2005�N�X���̑��I���ŗX�����c�������P�_����ꂽ����������Y�ɗ^�������̂ł����āA���{�́u���������v�Ȃǂ�M�������킯�ł͂Ȃ��B���̕ӂ̗���������ʐl�Ԃ������`�������Ƃ��鍑�Ƃ̎߂Ă���c�I���������̑傢�Ȃ�t���ɋC�t�����ɂ���ƁA�i�`�X�̑䓪�����������C�}�[�����@���̃h�C�c�����Ɠ������j��z���Ă������ƂɂȂ�B
�@�Ƃ���ō���̎Q�@�I�Ŏ����}�ɂƂ��čő�̒v�����ɂȂ����ƌ������������E�ԏ�_�ѐ��Y��b���݂̎���������ł��邪�A���{���ԏ���������Ⴀ���Ⴀ�Ɓu�@���ɏ]���ēK���ɏ������Ă���v�ƌJ��Ԃ�����ŁA�����Đ��������̗̎��������J���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@���͎Ҏ��g������ɓs���̗ǂ��@��������Ă����āA���̖@���ɑ����Ă���Ζ��͂Ȃ��̂��H���{�̂����u���������v�ł͖@���ɐG�ꂳ�����Ȃ���Ή������Ă��ǂ��̂��H�l�ԎЉ�ɂ͂��܂��܂ȋK�͂�����A�@���I�K�͂͂��̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�@���I�K�͎͂Љ�I�Ɍ���ΕK�v�Œ���̋K�͂ł����Ȃ��̂ł����āA�������ʂɂ͂����ƍ����ȓ����I�K�́E�ϗ��I�K�͂�����̂��B
�@�����I�K�́E�ϗ��I�K�͂ɂ͖@���I�ȏ����͂Ȃ�����ǁA�����Ƃ�����������������荂���̋K�͂ɏ]���čs�����鍑�������{���ɔ��������Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��H�����܂ł��Č��͂ɂ����݂����{�ȂǂƂ����������������̐l�ԂɁu���������v�Ƃ��u�V�������v�Ȃǂƌ�鎑�i���͂����Ă���̂��H
�����͗��j�Ƃ藷�̑�T���ł��B�@��S���ɖ߂� �@�@�@�@��U���ɐi��
�@�@�@�@ �g�b�v�y�[�W�֖߂��@�@�@�@���j�Ƃ藷�̖ڎ���
�g�b�v�y�[�W�֖߂��@�@�@�@���j�Ƃ藷�̖ڎ���