
時間蝿は矢を好む
これは昔から英文自動翻訳の難しさを象徴するフレーズとして、よく例に挙げられていたものである。
Time flies like an arrow.
言うまでもなく英語の諺で、日本では『光陰矢のごとし』に相当する。確かに文法も間違っていないし、逐語訳も間違っていない。でも時間蝿って何だよ?という疑問をコンピュータは感じないから、こういう変な和訳でも平気でアウトプットしてくる。
そもそも“flies”という単語は、“蝿(複数)”を指す場合よりも、“飛ぶ(三人称)”を意味することの方が圧倒的に多いから、たとえこの諺を知らなくても、通常は“時が飛ぶ”というところから解釈をスタートしなければいけない。
翻訳ソフトによるこの種の誤訳・迷訳はいまだに完全には解決されていないらしくて、つい2年ほど前も、“lead(導く)”を“鉛”と誤訳した文章を見せられたことがある。
ところで今回はそういう話ではなく、『光陰矢のごとし』は本当だろうかということである。確かに歳月はあっと言う間に過ぎ去って行くような気がする。まるで空中を飛んで行く矢のようだが、時として風に押し戻されてスローダウンすることもあるんじゃないだろうか。
実際に原子時計が時を刻む、あるいは光や音波がある速度をもってある距離を進む、その物理学的な時間は誰にとっても一定であるが(今は亜光速で旅をする相対性理論の話ではない)、ある個人が自覚する心理学的な時間は人によってまちまちである。
1年365日、それは1年後の幸せな結婚を待ちわびる恋人たちにとっては非常に長い時間だろうが、1年後の試験の準備をする受験生にとっては、まさに矢のように飛び去るに違いない。そういう心理学的時間は、概して年を取るにしたがって早く過ぎ去るようになる。年寄りほど心理学的時間の歩みが早いのは、若者や子供に比べて死が近いからだという説もあるが、私はそうは思わない。
私が現在の学科の専任教員を拝命してから間もなく5年の月日が過ぎようとしている。4年前に入学してきた第1期生たちも本日めでたく卒業式の日を迎えた。歌の文句に『思えばいと疾し…』と言うけれど、この4年間の歳月は私にとって決して『矢の如し』ではなかった。
5年前の春、先年亡くなられた先代の学長から、新学科の学生を教えてやってくれと言われた時には、そりゃ何かの間違いじゃないの、と心の中で思ったものだ。自分が学生に物を教えられるような器量でないことは自分が一番よく判っている。人に誇れるような業績を残したわけじゃなし、人が教えを乞いに来るほどの知識の体系を持っているわけじゃなし、はっきり言って困惑した。自分としては卒業以来、小児科・産科の周産期部門から病理診断部門と、常に病院の診療の一翼を担い続けてきて、それが自分の天命であり、天職であり、最も性分に合っていると思っていたからである。
しかし大学としては、病理学や細胞診を教えるためにもっと適切な人材を学外から雇ってくるつもりはさらさら無さそうだったので、仕方なく専任の教職をお引き受けした。昔から特攻隊の話などを感銘を受けながら読んでいたから、もし自分以外に引き受ける者がいないならば…と多少不本意ながらも引き受けてしまったのかも知れない。
だが一旦お引き受けした以上は、たとえ自分の希望と違う不本意な部署であっても、決して手を抜いてはいけないと思った。私が教えている学生の大部分は将来は臨床検査技師という職種に就く。この臨床検査技師の病院での職域はかなり広く、心電図や脳波などを検査する部門、超音波を使って体内を調べる部門、血球を検査する部門、血液や尿の化学成分を調べる部門、あるいは私がやっていた病理部門など、多岐にわたっており、学生たちが卒業後に病院に就職しても、必ずしも自分の希望する部署や適性のある部署に配属されるとは限らない。
超音波検査をやりたかった者が血液部門に配置されることもあるだろうし、細胞診をやりたかった者が生化学部門に配置されることもあるかも知れない。そんな時に、それで気持ちが萎えたり、ふてくされたりして仕事の手を抜くような惨めで情けない姿を、教員自ら学生の前に晒すわけにはいかなかった。
学生に講義をするのは別に今回が初めてではなく、これまでも医学部や看護学校や助産婦学校などで、オムニバス形式の講義の一部を分担していたが、一つの学科のある科目の全体を統括して教育するのはまったく初めての経験だった。カリキュラムの作成、試験問題の作成と採点、レポートの判定、研究の指導…、と何から何まで一から始めるようなものだった。
1期生に実施したことは2期生、3期生と順次手直しをしながら応用できるが、1期生は何もかも最初から手探り状態、まるで新雪の積もったゲレンデをラッセルして滑走面を整えるようなものだ。そうやって学科の第1期生を何とか卒業に漕ぎつけるまでの4年間、それは決して矢が飛ぶように早く過ぎ去った歳月ではなかった。
思えばこれまでも似たようなことは何回かあった。医師は卒業してどこかの医局に入局しても、定年まで1ヶ所の病院に勤続するということは少ない。私も若い頃は2年から3年の期間で幾つかの病院で働いたものだが、どこの病院でも就職後の最初の1年間が心理的にかなり長く感じられる。
各病院の仕事の手順や流れを把握し、他科の医師や看護師さんや事務員さんなどとの人間関係を築いて、その病院で円滑に働けるようになるまでの期間が大体1年間ということだ。その1年間は自分なりにいろいろ考えて職場に溶け込もうと努力するから、自然に“密度の濃い時間”を過ごすことになり、心理的な時間の経過も長く感じられる。
若者や子供の方が年配者よりも心理的時間が長いのも同様な理由だろう。大人になって生活も安定するようになると漫然と日々を過ごす、つまり昨日と同じように今日を過ごし、去年と同じように今年を過ごすから、あっと言う間に1年が過ぎていく。
新学科での私の場合、“密度の濃い時間”は最初の1年だけではなかった。1期生が卒業するまでの4年間は、毎年毎年新しい難題が次から次へと降りかかった。それらに対して手を抜かずに、学生たちと一緒になって乗り切ってきたこの4年間、今になってあれこれ思い返してみるととても長く感じる。専任教員という配置、最初はちょっと心外だったが、これが自分の職業人生の最後に与えられた舞台だったのだなと、しみじみ思う。
とてつもなく長い4年間をプレゼントして“長生き”させてくれた1期生、ありがとう、さようなら。
勝ち運、負け運…
上記のような次第(↑)で、私の学科の学生たち相手にいろいろ頭を悩ませることも多かったから、ここ長いことカミさんの演奏のステージを聴く機会もなかったが、先日、本当に久し振りで(たぶん1年半ぶり)コンチェルトの演奏を聴きに行った。特に最近数ヶ月は、第1期生たちの卒業試験から臨床検査技師の国家試験と、彼らの人生に関わる重大な試験の経過の中で、試験に強い者と弱い者、勝ちグセのある者と無い者、運の良い者と悪い者、悲喜交々見てきて、やはり手塩に掛けて育ててきた学生たちだけに他人事とも思えず、私も一つ一つの結果に一喜一憂してクタクタに疲れきっていたので、久々の生演奏で心が軽くなるような感じだった。
しかしステージの上のカミさんを見ているうちに、学生たちの勝負運の強さにも関連して、初めてカミさんと知り合った頃の可笑しくも不思議な出来事を思い出していた。私がある人の紹介でカミさんと知り合ったのは浜松の病院に小児科医として勤務していた時である。ちょうど小児科医が4人いたから、病棟に重症の患者さんが入院していない時など、よく全員揃って病院前の麻雀荘に出かけて「ポン」とか「チー」とか鳴いていたものだ。
私はそんなに麻雀が上手ではなかったが、東京でカミさんと初めて知り合った翌週、また浜松に戻って来た時から、連日にわたって物凄い勝ち方が続くようになった。役満こそなかったが、ただの「ツモ」のみの手が「リーチイッパツ」に裏ドラが乗って一気に倍満(しかも親)などということが半荘1回のうちに何度もあるという驚異的な勢い…(麻雀やらない人にはゴメンナサイ)。
俗に言う「上げ○○」というヤツなんだろうけれど、勝負運の強さには、そういうコンピュータなどでは予測できない“人との繋がり”みたいな事が確かに存在する。ある人とコンタクトすることによって、学問的に“大脳辺縁系”とか“深層心理”とか“潜在意識”とか呼ばれる部分が好ましい方向に刺激され、活性化されて人生の勝負勘が研ぎ澄まされてくるのだろうが、当然、逆もある。
もちろん試験などの人生の勝負に勝つためには、そのための努力と研鑽が必要なのは言うまでもないが、一生懸命コツコツ勉強しているのに試験が出来ない、勉強方法も間違っていないのに点が取れない、というのは、やはり自分の勝負運を高めてくれる人との出会いをつかめないということではないのか。そういう出会いをつかめない人の類型が2つほどあると思う。
一つはアピールが弱い人。誰かに出会った時、自分はどういう人間で、何を考え、何を望んでいるのか、それを出来るだけ正確に相手に伝えようという努力が乏しい。だから自分の勝負運をポジティブに高めてくれる可能性があった人にも素通りされてしまう。
もう一つは人との出会いの機会を自分自身でコントロールできない人。例えば仲間に無理やり誘われるまま、気が進まないのに飲み会などに付き合わされてしまう人は、せっかくそこで人に出会っても自分の気持ちが積極的になっていないので、逆にネガティブな波長に同調する人間を呼び込んでしまいやすい。
ところでカミさんから貰った私の勝負運ですが、浜松の雀荘ですっかり使い果たしてしまい、今のザマです(笑)。
友達の作り方
この前、別のコーナーで若い人たちに友達の作り方を教えなければいけない、と書いたが、それに関連して、ずいぶん昔に読んだサン・テグジュペリの童話『星の王子さま』を思い出した。有名なこの童話の中に、誰かと友達になるにはどうしたらよいか書いてある。もっとも中学生の頃にそれを読んだ時には、ずいぶん変なことを書いてあるなあ、と違和感を感じて読み飛ばしてしまった箇所であるが、今になって考えると最近の若い世代の人たちが知らずに成長してきたことのような気がする。
星の王子さまは故郷の星(小惑星B-612)に咲いていたバラの花と喧嘩して旅に出て、最後に地球にやってくる。そしてキツネと友達になるのだが、その時の会話が“友達のルール”について触れているのである。その部分を、日本で最も読まれている内藤濯氏の訳に基づいて、適宜わかりやすいように省略や改編を加えてご紹介しておく。(本物の訳は元の絵本を読んで下さい。)
「僕と遊ばないかい?僕、本当に悲しいんだから…」と王子さまはキツネに言いました。
「俺、あんたと遊べないよ。飼い慣らされちゃいないんだから」とキツネが言いました。
「<飼い慣らす>って、それ、何のことだい?」
「あんた、ここの人じゃないな。いったい、何を探してるのかい?」
「友だち探してるんだよ。<飼い慣らす>って、それ、何のことだい?」
「よく忘れられてることだがね。<仲良くなる>っていうことさ。」
「仲良くなる?」
「うん、そうだとも。俺の目から見ると、あんたはまだ今じゃ他の十万もの男の子と別に変わりない男の子なのさ。だから俺はあんたがいなくたっていいんだ。あんたもやっぱり俺がいなくたっていいんだ。あんたの目から見ると、俺は十万ものキツネと同じなんだ。だけとあんたが俺を飼い慣らすと、俺たちはもうお互いに離れちゃいられなくなるよ。あんたは俺にとってこの世でたった一人の人になるし、俺はあんたにとってかけがえのないものになるんだよ…」とキツネが言いました。
キツネは黙って長いこと王子さまの顔をじっと見ていました。
「何なら…俺と仲良くしておくれよ」とキツネが言いました。
「僕、とても仲良くなりたいんだよ。だけど僕、あんまりヒマがないんだ。友だちも見つけなけりゃならないし、それに知らなけりゃならないことがたくさんあるんでねえ。」
「自分のものにしてしまったことでなけりゃ、何にもわかりゃしないよ。人間てやつぁ今じゃもう何にもわかるヒマがないんだ。商人の店で出来合いの品物を買ってるんだがね。友だちを売ってる店なんてありゃしないんだから、人間のやつ、今じゃ友だちなんか持ってやしないんだ。あんたが友だちが欲しいなら、俺と仲良くするんだな」
「でもどうしたらいいの?」と王子さまが言いました。
キツネが答えました。
「辛抱が大事だよ。最初は俺から少し離れて草の中に座るんだ。俺はあんたをちょいちょい横目で見る。あんたは何にも言わない。それも言葉っていうやつが勘違いのもとだからだよ。1日1日とたっていくうちに、あんたは段々と近いところへ来て座れるようになるんだ…。」
あくる日、王子さまはまたやって来ました。するとキツネが言いました。
「いつも同じ時刻にやって来る方がいいんだ。もしあんたがいつでも構わずやって来るんだと、いつあんたを待つ気持ちになっていいか、てんでわかりっこないからなあ…決まりが要るんだよ」
「決まりって、それ何かい?」と王子さまが言いました。
「そいつがまた、とかくいい加減にされているやつだよ。そいつがあればこそ、一つの日が他の日と違うんだし、一つの時間が他の時間と違うわけさ。」
こうして王子さまはキツネと友だちになり、キツネの忠告に従って、地球に咲いているたくさんのバラの花を見に行く。そして故郷の星に咲いていた1輪のバラの花との違いについて、キツネから大切なことを教えて貰う。
「心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。かんじんな事は目に見えないんだよ」
「かんじんな事は目に見えない」と王子さまは忘れないように繰り返しました。
「あんたがあんたのバラの花をとても大切に思ってるのはね、そのバラの花のために時間をつぶしたからだよ。人間っていうものは、この大切なことを忘れてるんだよ。だけどあんたはこのことを忘れちゃいけない。面倒みた相手にはいつまでも責任があるんだ。守らなけりゃならないんだよ、バラの花との約束をね…」とキツネは言いました。
サン・テグジュペリがフランス語で書いた物語を日本語に翻訳する時に、元のニュアンスが少し崩れていると思われ、最初に読んだ時にはずいぶん違和感を覚えたものだった。そもそも最初のキツネとの会話にしたって、相手を“飼い慣らす”と友達になるって変なイメージ、これじゃ『星の王子さま』じゃなくて、『SMの女王さま』か…。
フランス語はよく判らないので、英語圏で翻訳された英文を見ると、やはり“tame”、飼い慣らすとか服従させるという意味の単語が使われている。
しかし全体の文脈を追って読んでいくと、サン・テグジュペリが良き人間関係について言いたかったのは次のようなことではなかったか。
“友だちになる”ということは自分一人でできることではなく、相手の都合を考え、相手と同じ基準に合わせて行動し、そうやって相手と少しでも近づこうと努力するために自分の時間を費やすことが大切である、そしてそうやってお互いに時間を共有した相手との約束は決して忘れてはいけないんだと…。
最近の若い人たちが好む漫画やRPG(role playing game)には、固い友情で結ばれた仲間同士で冒険に行くテーマが多いが、それらの中の仲間は勝手に自分で指定して、友情だと思い込むことのできる架空のものでしかない。まさに“店で売っている友だち”というところか。そんな友だちを現実の世界に手っ取り早く求めようとしても無理というもの、ちょっとでも自分と合わなくなったら、漫画やRPGみたいに買い換えるつもりなのか?
私も自分のことを思い返してみると、若い頃は恋愛に悩むより先に友情に悩んだ時期があった。若者にありがちな“仲良しグループ”と本当の友人は違うんじゃないかと疑問を持って、人間嫌いになった時期もあった。しかし社会人になった頃から、そんなことはどうでもよくなって、日常生活の中ですっかり忘れ去っていたら、先日ある学生さんから「先生は人間嫌いですね」と言われて驚いた。人間関係のバランス感覚が良い学生さんだから、私の本質的な部分まで見抜いたんだろうと思うが…。
確かにゴタゴタした人間関係に巻き込まれずに済んでいるのは、漫画やRPGみたいにあまりに完璧な人間関係を求めないせいかなと思うが、相手に求め過ぎないというのは友達を作る上で意外に大切なことかも知れない。自分だって相手の求めに完全に応じることはできない。それをお互いに理解することが、キツネの言っていた“決まり”なのではないか。キツネはいつでも構わず来てはいけないと言っている。自分の好き勝手な時だけ相手に“友だち”を求めてはいけないということだと思う。
バカになれ
あれは中学2年の夏休みのことだった。その年の春から新しく着任されていた数学の味八木先生は野球部の顧問であり、また私のクラス担任でもあったが、その先生が校内新聞に『バカになれ』という文章を書かれた。そしてその文章を読んだ音楽部の部長(主務、高校2年)がえらく感激して、夏休みの校内練習が終了した夕方、我々部員一同の前で、「我々もバカになろう、バカにならなくちゃダメだ」と盛んに“バカになれ”を連発して気勢を上げた。
私はいくらクラス担任の先生であってもそんな校内新聞の記事をいちいち読んでいなかったし、まだいかに人生を生きるべきかなどということを大袈裟に考える年齢にも達していなかったし、それに第一“バカ”という言葉は、「そんなバカなことをするな」とか「お前はバカか」とか親や小学校の教師に怒られた時にしか聞かないネガティブな単語だったから、呆気に取られながら部長の話を聞いていた。
味八木先生の文章を音楽部の部長が要約したところによると、利口な者は真夏の暑い盛りに(部活動の)苦しい練習などしない、家で冷たいものでも飲みながらゴロゴロして、2学期以降に備えて英気を養っているが、バカな者は将来何の役に立つか判らない、いや、もしかしたら何の役にも立たないかも知れない辛くて苦しい練習に汗水流している、我々の学校は(有数の進学校だったから)そういうバカが少なく、利口な者が多い、そんなことじゃダメだ、だからバカになろう…!
こうやって書くと、あまりにもバンカラでムチャクチャな論理だが、何となく当時の部員一同の胸に響く言葉だったのだろう、それから何年もの間、「バカになれ」は我が音楽部の合言葉になった。
音楽部は一応文化部だが(運動部のわけがない)、毎日練習後にそれこそ運動部顔負けのトレーニングをやっていた。1周2キロ近くある学校の敷地周囲を3周だ5周だ、週末には10周だという凄いランニングの後、懸垂、腕立て、うさぎ跳び(今はやってはいけない運動)などやっていて、味八木先生のところの野球部員なども「お前らは運動部か」と呆れる始末…。普通なら部員から文句が出るところだが、我々はとにかく「バカになれ、バカになれ」「バカになるとはこういうことか」と自問自答しながら頑張ったし、大学受験が目前に迫っても、バカになりきってしまった我々は最後まで楽器を離さなかった。
利口な者はすぐに目先の結果を考え、物事の効率を考え、苦しい道と苦しくない道があった時には迷わず苦しくない方を選ぶ。そして他人からどう見えるかも常に考えていて、苦しい方を選ばなかった理屈をクドクドこね回し、もっともらしい言い訳を並べ立てて弁解する。また自分だけ楽をするとカッコ悪いので、友達を道連れにして苦しくない方を選ぶ仲間を増やそうと画策する者もいる。“楽な道、皆で行けば怖くない”、というわけだ。
ところがバカな者は、他人から何を言われようが、どう見られようが、一度やろうと決めたことは泥の中を這いずり回って悪戦苦闘してでも最後までやり遂げようとする。あるいは力が及ばず仮にやり遂げられないことになったとしても、それで「ああ損した」とクヨクヨすることもない。時間や労力を無駄にしたとは考えない。
利口な者には物事の結末がよく見える。そんな事やるよりこっちをやった方が楽しいよ、それをやって何の意味があるの、こっちの方が得だよ、すぐそういうふうに考えてしまう。
ある一定の年配以上の方なら清酒大関のCMソングを覚えておられるだろう。
白い花なら百合の花 人は情けと男伊達
恋をするなら命がけ 酒は大関 心意気〜♪
というアレだが、あの3番だったか4番だったかは次のように続く。
夢は人には見せぬもの 勝負するときゃバカになれ
それでいいのさ男なら 酒は大関 心意気〜♪
思えば私も中学2年の頃までは利口者だった。利口で物事の逃げ道をすぐに探してしまうことが多かったから、前年の中学1年の時の体育祭でどうしようもない恥ずかしい思い出を残してしまうことになった。また書くと長いので、そっちを読んで下さい。
「バカになれ」
それは一つの哲学である。単なる処世術ではない。もし中学2年の夏休みにこの生き方に共感できなかったら、私のその後の人生はまた別の色合いに染まっていただろう。もちろん私は今の結果を見越してバカになる生き方を選んだわけではないが、やはり自分の学生さんには私から改めて言いたい。
「バカになれ」
はやぶさ君
人類初の小惑星軟着陸を果たして探査を終えた日本の探査機「はやぶさ」が、日本時間の2010年6月13日深夜にその使命を終え、小惑星で採取したサンプルの入っている可能性があるカプセルを分離した後、大気圏に突入して燃え尽きた。まさに“完全燃焼”であった。
探査機「はやぶさ」が打ち上げられたのは2003年5月9日だから、地球帰還までほぼ7年間の歳月である。7年前といえば、私のこのサイトが起ち上がった年だから、私がいろんな事をチャラチャラとこのサイトに書き流していた間ずっと「はやぶさ」は太陽系の虚空にあって、貴重な観測データを地球に送信し続けていたのである。
私のサイトはこの7年間に2度ほど送受信停止して復旧に多少苦労したが、「はやぶさ」も何度かトラブルに見舞われたらしい。もっとも私のパソコンは手元にあって機器の交換や回線の新設など自由にできたけれども、「はやぶさ」は地球を飛び立った時の装備のまま、しかも何億キロも離れた場所まで遠隔操作で修復しなければいけないのだから、私のサイトのトラブルなどと比較しては失礼というものであろうが…(笑)。
「はやぶさ」が探査した小惑星は、日本の宇宙ロケット開発の先駆者である故糸川英夫博士の名前を取ったイトカワ(ITOKAWA)であるが、日本の軍用機マニアであれば、糸川博士が旧陸軍の隼戦闘機の設計にも関与していたことは有名な話であり、宇宙空間での糸川博士と隼の邂逅にはちょっと胸が熱くなるものがあった。
胸が熱くなる、と言えば、「はやぶさ」のミッションが終わりに近づくにつれて、日本国民の関心は一気に高まり、探査機を擬人化して「はやぶさ君」などと呼んだりしていた。南アフリカでのサッカーWカップがなければ、その熱狂はもうしばらく続いたかも知れないが、普段は宇宙になど興味もなく、日食と月食の理由も分からない国民、惑星と衛星の違いも分からない国民が示したこの“素人の熱狂”はいったい何なのか?
これを機会に国民の科学や宇宙開発への関心が高まるというならそれも良いが、1998年に打ち上げられ、さまざまなトラブルによく対処しつつも2003年に最終的に火星周回軌道投入を断念した火星探査機「のぞみ」の時には、ちょうど国産ロケット、国産衛星の失敗が相次いでいた時期とも重なって、税金の無駄遣いという世論が強かったのである。
「のぞみ」の失敗の経験は今回の「はやぶさ」に生かされているはずだし、科学技術とは本来そういうものである。それを失敗した時は税金泥棒呼ばわりし、うまく行けば「はやぶさ君」などと機械に対して最高の敬称を付けて迎える…。もし「はやぶさ」のミッションが失敗していたら、日本の科学技術開発への予算はさらに大幅に削られて、我が国の宇宙開発は完全に息の根を止められていただろう。
案外、前の戦争も同じような国民の精神構造だったのではないか?勝ってる時は軍部に迎合したメディアの論調に乗せられて「バンザイ」「バンザイ」の提灯行列、それが一転敗戦となると手のひらを返したように、国に殉じた「軍神」が「国賊」になる世の中…。こういう熱しやすく醒めやすい国民性がいずれまた大きな過ちを犯さなければよいが…。
懐メロ…
今朝(2010年6月27日)の『題名のない音楽会』(テレビ朝日)で、歌手で俳優の加山雄三さんがデビュー50周年で出演しておられました。加山雄三といえば、私がまだ小学生の頃から、ゴジラやキングギドラなど東宝の特撮怪獣映画と抱き合わせの2本立てで公開されることの多かった“若大将シリーズ”の主役として、最初から押しも押されぬスターだった記憶しかなく、中学から高校の頃は、加山雄三の歌が得意だった美男子のクラスメートがヤケに羨ましかった思い出などもあり、とにかく私たちの世代から見て憧れの大スターでした。
その後、多額の借金などで苦労されたとも聞きましたが、テレビの画面で見る加山雄三さんは昔のままのオーラを放っており、やはり大スターのままでした。ちなみに私の世代からは、加山雄三が兄貴分とすれば、山口百恵が妹分でしょうか。妹分の方は三浦友和と結婚して芸能界を引退してからは、頑なにテレビや雑誌の取材も拒否して今や人々の記憶からも薄れようとしていますが、かつてレコードやカセットテープなど(DVDではありませんよ)を買って応援したファンに対しては、その印税にちょっと報いるくらいのことはして欲しいものです。
ところで今朝の番組では、カミさんも加山雄三さんの後ろでチャラチャラ伴奏などしており、よせばいいのに「結婚の見合いの相手は加山雄三さんみたいな人が良いって頼んだんです」などと余計なコメントをしておりましたが(加山雄三みたいじゃなくて悪う御座いましたm(_ _)m)、リハーサル中に加山さんの歌を聴きながら涙を流していたという気分は何となく分かります。
私も番組の中で加山さんが歌った『旅人よ』を聴いて、初めてあの歌を聞いた中学生の頃の思い出がよみがえってきて切ない気持ちになりました。自分が歩んできた道を振り返るような感じですね。過去の思い出を振り返る媒体としては他にもいろいろありますが、日記などはあまりに直接的で改めて読むのは気恥ずかしい(でも捨てるのも気が引ける…)、小説などの活字はまずその本や雑誌を書棚から取り出して気合いを入れなければ読めない(そもそも本や雑誌が手元になくなっていることもある)、映画はDVDで昔のままに再生できるけれども全部観るのに時間がかかる、ですから何気ない機会にふと耳に入ってくる歌や音楽というものは、最も簡単に自分を過去の思い出の中へ引き戻してくれるキーなんですね。
昔から“懐かしのメロディー”を省略して『懐メロ』という言葉はありました。私が子供の頃の代表的な懐メロは軍歌や戦時歌謡でしたが、やがて昭和30年代くらいにテレビやラジオから流れていた歌謡曲が加わり、ついに私が社会人になった昭和50年くらいのフォークやポップスも懐メロになり、最近では平成初期の歌も一部では懐メロ呼ばわりされています。
自分が今より若かった頃を思い出させてくれる歌は、月並みな言い方ですけれど、やはり力や元気を貰えますね。学生さんや若い職員と一緒にカラオケへ行くと、何だかよく分からないリズムとメロディーに乗りまくってますが、やがてあれが彼らの懐メロになるんでしょうか(笑)。
神の手

九州大学医学部構内の、附属病院の真ん前に『神の手(the Hand of God)』という名前の不思議な彫像がそびえ立っている。カール・ミレス(Carl Milles)というスウェーデン生まれの彫刻家の作品(1954年)で、箱根の彫刻の森にも同じ物があるようだが、どちらが本物でどちらがレプリカか、あるいはどちらもレプリカなのか、美術にそれほど縁がない私には判らない。
ただ大学病院という医学・医療の場に『神の手』という名前の彫刻が存在しているのが興味深くて、先年九州大学を訪れた時に写真だけ撮ってきておいた。この彫刻の躍動美に心和む患者さんや付き添いの家族の方もおられるようで、今後も病める方々を力強く支える神の手であり続けて欲しいと思うが、我々医療関係者から見ると、『神の手』という言葉にはまた別の意味も感じられる。
一つは物凄い名医という意味である。手塚治虫さん原作のブラックジャックのように、普通の医者には手の下しようのない病気を巧みなメスさばきで完治させてしまう名医、あるいはその卓越した治療技術を指し、最近医療界を扱った小説や漫画などで『神の手』と言った時は、ほとんどがこちらの好ましい方の意味である。我が国にも名医を指す『鬼手仏心』という言葉がある。鬼のごとき冷徹な技術と仏のごとき暖かい慈悲の心という意味だが、東洋の鬼は時として西洋の神と同じ存在として語られることがある。誰だって病気になったら入神の技術を持った医師に治療して貰いたいだろう。
ところが医療界にはこれと裏腹の意味の『神の手』がある。昭和50年代頃、ある漫画誌に『○○○』という人気連載漫画があった。美人女医を主人公にした漫画だったが、『神の手』という副題の付いたストーリーで、新生児仮死で重度の脳性麻痺になった子供の治療を打ち切る行為を神に例えたとして、人権団体や障害者団体から抗議が殺到、急遽連載打ち切りになったことがある。私も当時、小児科医として新生児医療に関わっており、新生児仮死や脳性麻痺の子供たちの治療に当たっていたから、いくら将来に望みを持てない重症だからといって、治療放棄することを神の手に例えるなど、何と不遜なことかと思った覚えがある。
(現在も、おそらく問題の部分だけカットしているだろうが、ネットなどで単行本を販売している作品であり、一応作品名などは伏せておく。)
最近(2010年7月)ドラマがスタートした『美丘』(石田衣良)も、描いている病気は必ず症状が悪化して死に至るクロイツフェルト・ヤコブ病で脳性麻痺とは状況が違うが、原作の最後の部分に主人公(医師ではない)自身の手で恋人の死期を早める行為が暗示されており、私は昔のあの漫画を思い出してしまった。
医療の側から見た『神の手』には表と裏がある。すなわち並みの医者では助けられないような命を救う神業の医療手技と、この病人を天に召すべきか否かという本来なら人間には許されていない寿命の判断である。
この表裏が一体となったのが臓器移植であり、現在では法制化されているとはいえ、まだ完全に万人が納得する形で施行されているとは言い難い。臓器移植が激しい論議の対象になっていた時代、医師にもまた賛否両論があった。概して言えば、必ずしも明確に区分できたわけではないが、我々医師仲間で言っていたことは、自分の受け持ち患者が誰かから臓器提供を受ければ救う望みのある心臓外科や肝臓外科などの医師は臓器移植に賛成、一方、自分の受け持ち患者が臓器提供者(ドナー)にしかなれない科の医師は臓器移植に反対であるということだった。
寿命の判断は神の領域であると言っても、医師が患者の寿命を延ばすのはごく当然の使命である。普通の医師であっても、天の寿命がここまでと決められていたはずの病人を何人も救っているはずである。私自身、私があの場にいなければあの子は死んでいたと確実に断言できる患者は1人や2人ではない。
一方で人の寿命を延ばしているんだから、もう一方でどうせ救いようのない患者の死期を早めて(心臓死から脳死)何が悪い、というのが身も蓋もなく端的に言った場合の脳死移植の論点であると私は今でも思っている。もちろんドナーの生還も前提としている骨髄移植や生体肝移植などはこの限りでない。
小児科の患者さんは重症の新生児仮死の後遺症や、重篤な先天異常など慢性疾患も多く、受け持ち患者がドナーにしかなれない科の医師として、私は脳死移植に反対だった。今までドナーカードを持ったことはないし、他人の臓器を頂く気もない。
ただし自分自身のことなら比較的簡単にそう思えるが、もし私に子供がいて、その子供が誰かから臓器を頂かなければ助からないと言われた場合、親として物凄い苦悩があるだろうなと思う。
病理医になって脳死状態の患者さんを何例も病理解剖させて頂いた。脳はドロドロに溶けていて原型をとどめていないことも多く、もちろんそんな例では、いくら他の臓器が健全でも救いようがない。こんな状態になるんだったら、私の臓器も脳死後にどなたかに役立てて頂いても良いかなと思ったこともあるが、ただ実際の脳死判定は脳がここまでメチャメチャになる前に行われるわけであり、万に一つの間違いも許されない寿命終結の判断を行なえるほど、現代の医療診断技術は神の領域に入ってきているのか、特に子供からの臓器提供までを容認する立場の人々は、病理解剖の脳所見と対比した判定基準を明示すべきであると思っている。
(脳がドロドロに溶けた状態というのは、もっと正確に言えば、脳死のまま長期間人工呼吸器を装着されて脳以外の部分だけが生きていた状態の終末期で、病理学的に人工呼吸器脳 respirator brain と呼ばれる)
本音社会…?
最近のニュース報道でショッキングだったのは、2年前の秋葉原無差別殺傷事件の被告が、インターネット上での自分の存在場所がなくなりそうだったから、誰でも知っているような場所で事件を起こしたかった、と述べていたことである。
ネットは本音社会、現実は建前社会、その本音社会で掲示板を荒らされ、別人によってなりすましの書き込みをされ、居場所がなくなりそうだったから、警告の意味で実社会で殺傷事件を起こした、ということらしいが、これは少なくとも私の世代の大部分の人間にとってはまったく理解不能な考え方である。
まあ、こういうマスコミに報道されるコメントは、被告側弁護士の入れ知恵もずいぶん入っているだろうから、必ずしも額面通りに受け取ることはできないが、この被告にとってはネット社会は自分の人生の中で無くてはならない場所だったのであろう。
私たちのように、大人になってある程度の歳月が過ぎるまではパソコンもインターネットも普及しなかった世代にとっては、ネット社会などは蜃気楼みたいな実体のない世界である。だから逆に実体のある現実社会で何か自分の存在を脅かされるようなことがあると、ネット社会に逃避してうさ晴らしする人間はかなりいた。
職場の上司がイヤな野郎で鼻持ちならないといった理由で、仮名でホームページを起ち上げて、その上司の悪口をある事ない事、次から次へと書きまくって、ちょっとした騒ぎになった私の同業者もいた。でもせいぜいこの程度の“事件”が、私たちの世代のネットトラブルである。
ところが今回の秋葉原事件の被告の場合、実と虚が我々の世代とは逆転しているのである。本音の言えるネット社会でイヤな思いをしたから、現実の社会で人を殺傷してうさ晴らしする、私にとっては身の毛もよだつ事件である。被告の頭の中にしかない架空世界での出来事のために、この現実社会で生きんとしていた人間が何人も生命を奪われたのだから…。
現実と空想の境界がわからない幼稚な人格の者が増えているとか、インターネット社会が現実社会をむしばんでいるとか、そういう通り一遍な解説だけで事件を納得するのは難しい。
鏡に映った姿が虚像だとばかり思っていたら、その虚像が邪悪な意志を持って実像の自分の行動や思想を支配するようになっていた、そんなホラー現象にしか思えない。
我々の世代の人間には、本音も建前も鏡のこちら側にしかなかった。本音も建前も自分の実像がコントロールしていた。鏡の中の影法師が言ったことにして、実像の自分は責任を取らずに本音を垂れ流しているうちに、こんな怪奇現象が現実に起こるようになってしまったのか。
エアコン壊れた…
この夏はかなり記録的な猛暑で、ビールなどもずいぶん売り上げを伸ばしたらしい。私の住む練馬区は東京都内でも最も気温の高い地区であり、本当に夏は例年とても過ごしにくいにもかかわらず、何と無情なことに、選りも選ってこの時期に我が家のエアコンが故障してしまった。もう耐用年数も過ぎており、本当は買い換えなければいけないのだが、私もカミさんも開き直って扇風機と団扇だけで、この7月と8月を乗り切ってきた。
昔は真夏に我慢比べ大会などというバカな企画をする者もいて、灼熱の太陽がギラギラ照りつける真夏の午後に、家の窓も全部閉め切り、マフラーやコートを着込んで、「寒い、寒い」と言いながら火鉢の炭火を囲んでスキ焼き鍋をつつき、最後まで我慢した者の優勝というようなことをやっていたらしい。
もちろん私は参加したこともないし、今年も別にカミさんと我慢比べをやっていたわけではないが、クーラー無しの家庭でひと夏を過ごしてみて、昔の夏の懐かしい“感触”が甦ってきた。
私が子供の頃は、どこの家庭ももちろん、かなり大きなオフィスやデパートや交通機関でも冷房などは無く、天井で扇風機がグルグル回っていたものである。東京都内の電車なども窓を開けて外から吹き込んでくる風が心地よく、駅に停車すると急にムッと蒸し暑くなった。
高校時代くらいまではクーラーの冷気を味わえる場所など無かったと言ってよい。部活動の後など、喫茶店の屋根の下に逃げ込んで食べたかき氷のうまさは、冷房完備の最近のレストランでは味わえないような気がする。
クーラーの冷気など想像するしかなかったから、戦争中の戦艦大和は冷暖房完備で“大和ホテル”と呼ばれていたなどという話を読むと、贅沢な軍艦だったんだなと羨ましく思ったものだ。
大学に通うようになった頃から、一部のデパートや喫茶店、バスや電車に冷房が装備されるようになったが、冷房付きのバスや電車もクーラーとは別に天井には扇風機が取り付けてあり、よほど暑い日以外は扇風機で車内に風を送っていた。また都内の交通機関でも最も冷房の普及が遅かったのは営団地下鉄(現メトロ)で、これはトンネル内では冷房は効かないという理由だったが、結局は設備投資の出し惜しみだったらしく、その後いろいろと反論されて、今では地下鉄も冷房完備した車両ばかりになっている。
要するに乗客や利用者など人間の体が、だんだん文明の利器の心地良さを知ってしまうと、もうそれらなしでは生活していけないというのが本当のところだろう。
しかしエアコン無しでひと夏を過ごしてみて、冷房は決して不可欠の機器ではないと改めて思った。むしろエアコン無しで眠った翌朝の方が体調が良い。実はこの夏も2泊だけカミさんと都内のホテルに宿泊したが、エアコンの効いた部屋で目覚めた日は1日中何だか体がだるかった。
昔のプロ野球で、国鉄スワローズ(現ヤクルト)と読売ジャイアンツで驚異的な400勝を上げた金田正一投手は、どんな真夏の暑い夜でも、腕を守るために絶対に扇風機すら消して寝たという。特に真夏の中日戦の名古屋遠征は辛かったらしい。やはりプロに徹した根性だったんですね。
最近の若い人たちは乳幼児の頃から冷暖房の中で育ってきたから、温度変化に弱いという研究もあったように記憶している。我々の世代に比べて皮膚表面の汗腺の発達も悪く、ホルモンによる体温調節機構もサボリがちになっているのだ。
もともと生物の体は外気温の変化に対応するために発汗の気化熱による冷却や、各種ホルモンによる代謝調節などのメカニズムが備わっているものだが、幼少時から人工的に気温の変化を最小限にとどめた環境下で養育されてきた若い人たちは、こういう生物としての能力が減退している可能性は高い。
実験や愛玩用に一定の環境下で飼育された動物は、同じ種の野生の動物よりも適応能力は低い。人類においても同じことが言えるだろう。ちょっと心配なことですね。
四季の移ろい
前項で書いたとおり、我が家はエアコンが壊れたため、この夏はかなり苦しい季節ではあったが、水分と塩分の補給に気を使いながら何とか乗り切ってきた。今年は東京でも熱帯夜の連続記録を更新したようで、今日はまだ9月初旬だが、まだまだ10月くらいまでは例年よりも気温が高い日が続くらしい。
まったくウンザリだが、一昨日の午後、空を見上げたら真っ青な夏空の中にウロコ雲が広がっており、大気の高層ではもう秋の変化が始まっていることが感じられた。家にエアコンがあったら、「早く帰ってクーラーつけよう」で終わっていたかも知れないが、今年は何とウロコ雲が頼もしく見えることよ。
「冬きたりなば春遠からじ」とはよく言うけれど、夏の中にもかなり早い時期から秋が兆しているし、秋になればすぐに空気が冷たくなって冬の気配が忍び寄って来ることだろう。
昔から日本人は季節の移ろいに敏感で、清少納言が『枕草子』の中で、春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は早朝(つとめて)と書いているのは有名だし、平安朝の女流作家の双璧である紫式部の『源氏物語』でも四季折々の気象の描写はかなり鮮やかである。
やはり私も自分自身がいつの間にか人工的な環境に慣らされて、四季の変化に気づきにくい体質になっていたことを思い知らされた。農林業に関わるわけでなく、船で海に乗り出すわけでもなく、エアコンの中でオフィスワークをすることの多い現代人に共通する弱点であろう。飛行機も最近のハイテク機はどうだか知らないが、かつての零戦乗りの坂井三郎さんは、コックピットの中にいても四季それぞれの空気の感触がまったく異なったと書いておられた。
医者をやっていると、特に臨床医で外来に出ていた頃は、そろそろ喘息の季節、とかインフルエンザの季節とか、そろそろ川崎病が来るな、などと病気の季節感があった。いくらエアコンや除湿器があっても、所詮は人間なんて自然の一部、良くも悪くも気候の影響から逃れることはできない。
しかも文明が発達して快適な環境を享受できるようになれば、人類という種族はその分だけ野生の適応能力を喪失する。つまり生物としては弱くなる。たぶん文明を維持するエネルギーの切れ目が、種族としての寿命の切れ目になるだろう。
四季は緯度がある程度高い地域ほど明確に感じることができると言われ、確かにタイでは1年の季節は雨期、乾期(冬)、暑期(夏)の3つだった。日本のように四季のある地域に生まれたならば、せめて季節の気配を嗅ぎ取るだけの感性は鋭敏に残しておきたいものである。
究極の食糧危機対策
『動物とは何か?植物とは何か?』
意外に難しい質問である。
人間は言うまでもなく動物である。動物であるから動くわけだが、動くことができる、あるいは動かなければいけないことは生物として幸福なのか?言い換えれば動物は植物よりも幸福なのか?
もし動物が動かなければどうなるか?餌を取ることができずに餓死するだろう。
ではなぜ動物は餌を食べなければならないのか?動物が動くのは筋肉の働きによるものであるが、筋肉が収縮するためには餌の中の炭水化物を酸化して得られるエネルギーが必要である。我々が動くためのエネルギーは、酸素を使って炭水化物を二酸化炭素と水にまで酸化する課程で得られるものである。
植物は餌を食べなくても生命維持のためのエネルギーを産生することができる。太陽の光の下で空気中の二酸化炭素と大地の水から炭水化物を作るからである。この炭酸同化作用とか光合成と呼ばれる還元反応のお陰で、地球の大気は酸素を含有するようになり、酸素を使った酸化反応がなければ生きていけない動物の繁殖を支えることになった。同時にまた動物は植物が蓄えた炭水化物を直接(草食)、間接(肉食)に餌として摂取しているのであるから、動物は植物なしには生存さえできないのである。植物サマサマである。
餌を食べるためにわざわざ動かなくても生きていける植物と、生きるためにしょっちゅう動き回って餌を探し求めなければならない動物とでは、どちらが生物として幸福なのか?
動物の細胞はミトコンドリアという細胞内小器官を持っており、これが炭水化物と酸素さえあれば物凄い効率でエネルギーを生み出してくれるから、動物は筋肉を収縮させて動き回ることができる。
一方、植物の細胞はクロロフィル(葉緑素)などの光合成色素を含む葉緑体(クロロプラスト)という細胞内小器官を持っており、これが二酸化炭素と水から炭水化物と酸素を作り出している。
実はこのミトコンドリアと葉緑体は共通した構造を有している。どちらも細胞の中にバクテリアのような微生物が取り込まれて共生しているような構造なのだ。
地球上に初めて発生した生物の原始細胞は、まだ動物とも植物ともつかぬ素性の知れぬものだった。それが太古の海を漂っているうちに、近くに微生物が泳いでいたので、餌のつもりでパクッと食ったら、その微生物は原始細胞の中で二酸化炭素と水と太陽光線を使ってせっせと炭水化物を作り始めた、こいつは便利で良いや、もう自分で餌を取らなくて済む、と原始細胞が思ったかどうかは定かでないが、とにかくそれ以後は原始細胞と微生物は仲睦まじく一緒に暮らすことになった、原始細胞は餌を作って貰い、微生物はその他の一切の面倒を見て貰い、言ってみれば典型的な専業主婦と関白亭主みたいなものだ。
主婦業を引き受けてくれるカミさんを貰った原始細胞の方が生存に有利なので、たちまちこの原始細胞は他の仲間たちを圧倒し、地球上を席巻して植物細胞となり、微生物の方は葉緑体と呼ばれるようになった。
植物細胞の子孫が増えてくると、光合成によって排出される大気中の酸素濃度が上昇する。するとこの酸素を利用して莫大なエネルギーを作ることのできる微生物が進化した。そして未だ植物になりきれず、太古の海の中で日陰者だった原始細胞が餌のつもりでこの微生物をパクッと食った、するとあら不思議、全身に力がみなぎってきたではないか、こうして地球上にまた新たなカップルが誕生した。原始細胞は動物細胞になって植物細胞と並び立つ王国を築き上げ、微生物の方はミトコンドリアと呼ばれるようになった。
しかしこちらのカミさんは貞淑な専業主婦というわけではなく、家の中で亭主にハッパ(葉っぱではない)をかけて、「もっと稼げ、もっと炭水化物を探して来い」と叱咤するので、亭主はカミさんのご機嫌を損ねないように餌を求めて彷徨う運命を背負ってしまった。
植物細胞と動物細胞、どちらが幸せかの判断は皆さんにお任せするが、遠い将来、世界の食糧危機を打開する夢物語がここにある。現在の細胞工学技術ではまだ無理であるが、もし仮に動物細胞がミトコンドリアと共に葉緑体を持っていたらどうなるか?
受精卵の段階で細胞質内に植物の葉緑体を移植する、するとこの受精卵から発生した動物は、本来のミトコンドリアの働きで莫大なエネルギーを産生して筋肉を動かすことができるだろうし、移植された葉緑体の働きでミトコンドリアの活動に必要な酸素と炭水化物の自給自足が可能になる。つまり動物は餌を食べる必要がなくなるし、場合によっては肺から酸素を取り込む必要さえなくなる。究極の食糧危機対策、環境危機対策である。
人間に応用しなくても家畜には使える。食肉用の牛や豚も見た目が全身緑色なのは薄気味悪いかも知れないが、飼料を与えなくてもスクスクと育ってくれるだろう。葉緑素を含んだ肉が美味かどうかは別の問題だが…。
まあ、亭主の細胞としては貞淑なカミさんとジャジャ馬のカミさんが2人いるようなもので、天国みたいなハーレム環境かも知れないけれど、家庭(細胞)内の平和は保てないかも知れませんね(笑)。意外な修羅場になったりして…。
補遺:
もし葉緑体を移植されたら光合成色素(クロロフィル)のために動物は全身緑色になる。人間ならば『ドラゴンボールZ』のピッコロさんみたいなものか(笑)。あのピッコロさんは飯を食べるんだろうか?
小児科医をやってた頃はそういうアニメのキャラクターにも詳しかったが、最近ではそんなもの見てるヒマもない。しかし今年の春(2010年3月)に卒業した私の学科の第1期生たちが残した卒業アルバムの中の「ピッコロさんは誰?」というコーナーで私を指名した者がいたので、ちょっと調べてみました。
女性専用車−どうでも良いこと
最近、首都圏の朝のラッシュ時の通勤・通学電車では当たり前の光景になったが、10両前後の編成の一部の車両を『女性専用車』に指定して、男性乗客の乗車を“拒絶”している。痴漢の被害にあって精神的にも傷を負った女性が多いということは聞いていたから、別に特に目くじら立てることもないと思っていたが(目くじら立てることは他にいくらでもある)、女性専用車に反対してわざわざ『女性専用車』に抗議乗車する団体があると聞いて笑ってしまった。その団体のホームページもあるが、私は別に趣旨に賛同しないからリンクは付けない。
そのホームページには“抗議乗車体験記”や、またその行動に対する賛否を書き込む掲示板などがあるので、興味のある方はぜひ検索してお読みになってみればよいが、ほとんどが賛成派と反対派の人格攻撃の応酬である。一見まともな社会的話題を議論するように見えて、実は醜い人格攻撃に堕してしまうのは、鉄道会社の責任逃れの体質に原因があるのではないかと思っている。
●痴漢被害にあって傷つく女性乗客を守らなければいなけい
●世の中の大部分の男性乗客は決して痴漢などしないから疑ってはいけない
この2つの対策は明らかに相反するものであるが、鉄道会社は『当社は女性を守っています』という姿勢をアピールして良い子になるために、一方的に大多数の男性乗客を“痴漢予備軍”と見なして『女性専用車』を導入したのではないか。
混雑する時間帯に10両編成のうち1両を『女性専用車』にすれば、女性の通勤には10両を提供しているのに、男性には9両しか提供しないことになる。それで男性の通勤定期券の割引率を引き上げて1両分を値引きするかと言えば、そういう“商道徳”に見合った当然の対応もしない。つまり自分のフトコロは全然痛めずに良い子ぶっているだけと言われても仕方がない。
こういう責任逃れの事なかれ主義の対応は別に鉄道会社に限ったものではない。何かの被害や不利益が起こった時に、管理責任が問われる側は、自分の払う犠牲や労力を最小限にして、「何かやってます」あるいは「何かやりました」というアリバイ的なアクションを示そうとする。医療分野に限らないだろうが、例えば病院や企業や銀行などで何か問題が起こった時の監督官庁の対応然り、学校などでイジメや暴力問題があった時の監督者や保護者の対応また然り…。
それに比べれば『女性専用車』など可愛いものだが、1つだけ利用される女性乗客の方にも考えて欲しいことがある。鉄道会社の例の事なかれ主義の言い分によると、女性専用車は優先席(昔のシルバーシート)と同じで、男性乗客は利用を控えるように“お願い”しているだけだそうだ。
だから他の車両が混んでいる時に“緊急避難的”に『女性専用車』に乗り込んできた男性乗客を非難する女性は、元気で健康であれば決して『優先席』に座らない人たちだと信じてもよろしいですね?あれも単に鉄道会社が元気な人は座らないで下さいと“お願い”しているだけの座席ではありますけれど…。
不思議の国のアリスに挑戦
旧約聖書によれば、人間が神に近づこうとして天空に届くような巨大なバベルの塔を建設しようとしたため、これに怒った神は二度と人間がこういう大それた考えを起こして力を合わせることが出来ないように、人々の言葉を乱したという。それ以後、国や地域の異なる人々は、互いに相手の喋る言葉が判らなくなり、共同作業に支障をきたすようになってしまった。(またスカイツリーなんか作って神様に怒られるかも・笑)
現生人類の祖先であるクロマニヨン人(新人)はネアンデルタール人(旧人)を圧倒して地球上に繁栄したが、それは解剖学的な発声器官がネアンデルタール人より発達していたため、言語による意思疎通をスムースに行なえたからだという説を読んだことがある。言語を使えるといっても、幾つもの閉鎖された地域で独自の社会を作り上げてきた現生人類の言語がバラバラであるのは当然であろう。
むしろ私が不思議に思うのは、なぜ人類は互いに外国語を理解する手段を獲得できたかということである。辞書があるじゃないか、と言うかも知れないが、私が言いたいのはその最初の辞書作りはどうして可能だったのかということである。
中国語と日本語のように、あるいは英語などヨーロッパ系の言語のように、一方が他方の母体だったり、共通の語源の多い言語同士なら何となく理解できる。しかし、例えば初めて日本にやって来たポルトガルの宣教師や、鎖国時代の日本からアメリカへ漂流したジョン万次郎みたいな人は、どうやって相手国の言語を操れるようになったのだろうか。
私とあなたとか、山とか川とか、空とか星とか、リンゴとかニンジンとか、そういう単語ならば身振り手振りで何とか互いに意味を共有できるだろうが、古代ギリシャ哲学のような抽象的な概念までが、各国の言語に翻訳されて現代まで伝えられることが可能だったは何故なのか、私にはいまだに謎のままである(笑)。
それはともかく、通訳とか翻訳という仕事は、相手国の言語を自国の人々も理解できるように置き換える作業であり、自分だけが判っていても仕方がないところが面白くもあり、また大変困難な点でもある。
私も小児科医になって2年ばかり経った頃、当時の東大小児科学教室の主任教授だった小林登先生から翻訳の仕事を任されたことがあった。Dynski-Kleinという人の書いた小児疾患の図譜で、写真が多い本ではあるが全部で400ページ近くもあり、なかなか読みごたえのある本だった。南江堂という会社から『小児疾患カラーアトラス』として出版され、私も当時の金で20万円という大金を得ることができたが、若手の小児科医の身ではあまりに忙しく、悲しいことにせっかくの金の使い途も知らない、それでお見合いしたばかりのカミさんと最高級のステーキを食べたりして道楽をやりまくり、あっという間に使い果たしてしまった。今でもカミさんは、あんな美味しい肉はあれっきり食べさせて貰えないとブツブツ言っている。(たぶんサミットで来日した各国首脳が食らうくらいの肉…)
そんなこともともかく、そのアトラスの翻訳に取りかかったはいいが、一番最初の文章の翻訳に意外に手こずって10日間ほど費やしてしまった。
A picture, it is said, is something between a thing and a thought.
直訳すれば、「写真は物と思考の間にある何かである」、ということだが、本の冒頭からそんな不自然な日本語に置き換えていては翻訳者の力量を疑われる。
「写真は物と思考の間にある」(ウーン、まだダメだ)
「写真は実体と思考をつなぐ」(イマイチだなあ)
と四苦八苦した末に、思い切って「写真を見れば一目瞭然」と訳してしまった。そもそも本の読者というものは原文と訳文を照らし合わせて、学校の英語の先生みたいに添削したり採点したりしないのだということに気付いた瞬間、元の文章の単語や構造を離れて、完全に自分自身の言葉に置き換えてしまうことが出来たのである。
こういう翻訳作業の最大の難物は相手の言語にのみ通じるギャグやダジャレの類であり、その最たるものの一つがルイス・キャロル(Lewis Carroll)の『不思議の国のアリス(Alice's Adventures in Wonderland)』であろう。この作品は英語という言語にのみ通じるギャグやダジャレがポンポン飛び出してきて、さぞ翻訳家泣かせであろうと推察している。
日本語訳は幾つかあるが、どうも日本人翻訳家は原文の英語を几帳面に訳そうとしすぎるのではないか。大多数の読者は元の文章など参照したりしないのだから、元の英文の単語を逐一日本語に置き換える必要はなく、英語圏の読者が感じるギャグやダジャレのセンス自体を日本語圏の読者に伝えることを重視しなければいけない。
そこで私も及ばずながら、『不思議の国のアリス』のギャグやダジャレの翻訳に挑戦しているが、やはり非常に困難な作業であると痛感している。この何年間かの私の成果をここにお目にかけることにするので、御批評いただければ幸いである。
お姉さんと一緒に土手の上にいたアリスは変なウサギを追いかけて不思議の国の冒険へと出かけるのだが、そこで木の上にいたネコと別れる場面:
"All right," said the Cat; and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time after rest of it had gone.
ネコが尻尾の先からゆっくり消えていき、笑い(grin)だけが最後まで残っていたということだが、
「初めはネコが笑っていましたが、もう一度見たら笑いがネコっているだけでした」
というのは(ちょっと苦しいが)いかがだろうか。この作品のギャグは、読者に元の英文を引き合いに出して訳注で解説を加えるよりも、一発芸的に軽く読み飛ばせるような日本語にした方が良いと思う。
同じようにウミガメの先生の登場する部分:
"We called him Tortoise because he taught us."
なぜ海ガメ先生なのに陸ガメ(tortoise)と呼ぶのかという問いの答えだが、彼は私たちに教えた(トータス)から陸ガメ(トータス)なんだよと訳しても、日本語の読者には何のことだか判らない。
「僕たちのこと、とってもよくカメってくれたからカメさんなんだよ」
これもかなり苦しいが、元の英語の単語を持ち出すよりは軽く読み飛ばせるのではないか。
この海ガメ先生の部分には学校の教科に関するダジャレが連発している。
Reading(読み)とWriting(書き)を、Reeling(よろめき)とWrithing(もだえ):
Latin(ラテン語)とGreek(ギリシャ語)を、Laughing(笑い)とGrief(悲しみ):
など、到底いちいち日本語に置き換えていられない。元の英単語は無視して、最初から日本語で科目名のダジャレを当てはめた方が良さそうだが、これがまた難しい。なかなか対にして並べられるダジャレが見つからないから、単発でも良いか。
エエ子の英語、物理プッツリ、家庭科は堅えか…、恥ずかしくなってきたからもう止めるが、算数の足し算(addition)引き算(subtraction)かけ算(multiplication)割り算(division)を、野心(ambition)逆上(distraction)醜悪(uglification)嘲笑(derision)と訳しても何が何だか…。
いっそのこと元の単語も文章の流れも全部無視して:
「先生は算数の時間に女の子とのつきあいのコツを教えてくれたよ、たしなみ、引き際、かけひき、割り勘」とか、
「算数の時間なのにご飯の話ばっかり、だし汁、ひき肉、かけそば、割り箸」
ハイ、お後がよろしいようで…。
明日がある
早いもので今年(2010年)もまた年末が巡ってきた。師走とは、教師が走り回るほど忙しいとされる12月のことだが、師走は教師になる前から何となく気ぜわしい時期だった。
特にあの年賀状というヤツ、ただでさえ忙しいのに何で日本人はあんな習慣を止められないのだろうか?最近の若い人たちは義理の年賀状などは出さず、親しい友人同士でメールを送りあうだけという人も増えているようで、そのうち年賀状などはだんだん廃れていくと思われるが、私たちの世代はまだ子供の頃からの習慣で、やはり暮れの忙しい時期の合間をぬって年賀状を書かないと何となく気持ちが落ち着かない。悲しい習性である。
子供の頃は年賀状を出すのが楽しみだった。自分の年賀状を受け取った友人たちが驚いたり喜んだりするところを想像しながら、11月くらいから版画を作り始めたり、奇抜な文面を考えたりして心が浮き立つようなこともあったが、社会人になってからは年末の重荷でしかなくなったし、年賀状を書くのが楽しみですなんていう奇特な人に出会ったこともない。
ほとんど離れ離れになって会うことも少なくなった人たちに1年に1回、近況を知らせる大切な儀式だという意見ももっともだと理解できるが、それが100人200人となるとちょっと…。
年賀状に「今年もよろしく」なんて書いておいて、その年は1回も会わず、また次の年の年賀状に「今年もよろしく」と書く、その後ろめたさといったらない。せめて「今年はよろしく」だろうと思ったりするが、さすがにそんな事は書けない(笑)。
ひどい時は、年賀状に「○○はどうなりましたか」と書いたら、翌年の年賀状に「○○はこうなりました」と返事がきて、さらに次の年賀状で「○○はそうだったんですか」と返事をして、1つの会話が3年越しで成立することさえある。それはそれで面白いことではあるが…。
こんな気が重い年賀状でも、書かなければいけないものならさっさと100枚でも200枚でも書いてしまって、クリスマスくらいになったらあとは悠々と年末を遊び暮らそうと、毎年11月くらいから思ってはいるのだけれど、1度としてそうできたことはない。
ん?これって何かに似てるな、と思ったら、小学校や中学校の頃の夏休みの宿題も同じだったっけ。7月下旬から1ヶ月以上も学校は休みになる、イヤな宿題などさっさと済ませてしまえば、夏休みの後半は悠々と遊べると判っているのだが、なかなかそれが出来ない。来年こそは宿題を早めに制覇するぞと誓うのだが、結局夏休みの後半を心ゆくまで遊んだことは1度もなく、明日から2学期という晩は必死の追い込みだった。
子供の頃の夏休みの宿題といい、大人になってからの気の重い年賀状といい、何で人間はいつまでたっても成長しないものなのだろうかと可笑しくて仕方がないが、これも明日があると信じられるからこそ、と思えば、まんざら悪いことでもなかろう。故遠藤周作さん(狐狸庵先生)が「明日できることを今日するな」と書いていたのを読んで、我が意を得たりという気になったのはもう30年近くも前のこと。
しかしイヤなことはいくら先延ばししても、必ずいつかはやらなければいけないのもまた真実、早くそのことに気付いた方が良い。などと言いながら、今年もまた年末は年賀状の末尾に「今年もよろしく」と書き続けているだろうなあ。
物の名前
最近、人の名前や地名を思い出すのに時間がかかるようになってしまった。タクシーに乗った時なども、自宅の近くの地名をドライバーに指示するだけなのに、
「この先の…アノー…エート…ナントカ橋、ホラ、地下鉄の駅の近くの…道が二股になって…エート…アノー…」
などと、しどろもどろになり、かつて一度覚えたことはほとんど忘れない記憶力を誇った私としては何とも情けない状態になることが時々ある。
一番困るのは学生さんたちの講義の最中に、ある事柄を何と表現するべきか言葉が出て来ない時で、また板書しようとしても漢字や英語のスペルを度忘れすることもある。
「先生、時々“ん〜”とか言って立ち往生してるよ」などと、学生さんたちも率直に指摘してくれるお陰で、自分の症状は何とか客観的に把握できているが、地名の指示にしろ、学生への講義にしろ、物事の本質が判らなくなっているわけではない。ただそれを何と表現するか、名前が浮かんでこなくなっているだけである。
物には名前がある、その名前を言葉として表現することによって他人とコミュニケーションができる、それは当たり前のことであるが、その当たり前のことを最近つくづく感じるようになった。
幼少時に視力と聴力を失ったヘレン・ケラー女史が家庭教師のアン・サリバンの導きで、世界中の物には名前があることに気付く場面は感動的でさえある。小学生の時に伝記を読んだ記憶では、サリバン先生がヘレンの手に水を掛けながら“ウォーター(water)”という単語を何度も手のひらに書いたというような場面だったと思うが、物には名前があることを知ってヘレンの世界が変わったらしい。
ところで物の名前が出てこなくなる現象は老化の症状の一つと思われがちだが、私はこれを単なる“物忘れ”とは区別して、“言葉忘れ”とでも命名した方が良いと思う。タクシーの運転士さんに指示する地名がすぐに出て来なくなっても、私はまだ道が判らなくなって迷子になるわけではないし、講義の最中に単語が浮かばなくても、学生さんにトンチンカンなことを教えているわけでもない。
私は自分に“言葉忘れ”の症状が出たことに気付いた頃から、この進行防止策を講じるようにしている。頭の中で考えているだけの内容に対しても、いちいち言葉を当てはめていく訓練がそれである。
我々は慣れた道を歩いている時など、わざわざ地名など意識しないで通り過ぎている。
「あそこをあっちへ曲がって、まっすぐ行ってこっちへ曲がる」
などと、それすらも言語の意識までは持って上がらず、無意識のうちに慣れた道順に沿って足が自然に動いていく。
私は気持ちに余裕がある時は、なるべくそれを心の中で言葉にしながら歩いてみる。“あそこ”ではなく、“○○町○丁目の十字路”、“あっち”ではなく、“△△屋を右”などである。
大通りを渡る時も、“ここは□□街道で、ここを右に行けば▽▽、左に行けば◇◇”などと、わざと心の中で言葉にしてみる。
学生さんの講義で立ち往生するのは、決まって予習の時に言葉にする作業をつい省いてしまった箇所であることが多い。
物事にはすべて名前があり、その名前を共有しあうことで人々は互いにコミュニケーションを取ることができる。しかし最近では新しい物が次々に出現してくるために、名前の共有が間に合わないことの方が多くなっているように思う。
その1例が、近頃よく公共の場所に設置されている“AED”というヤツ。正式には自動体外式除細動器といい、英語(Automated External Defibrillator)の頭文字をとってAEDだが、日本語で言われたって普通の人には何が何だか判らないだろう。一応は音声ガイド機能がついているので、一般の方々でも正しく使えるということであり、心臓が動く仕組みも心室細動という病気のことも何も知らなくても、AEDという物を使って心停止の人を助けることが可能なのだから、これはもう『物事』と『名前』の完全な解離状態と言ってもよい。
劇場や街角で誰かが心臓の発作を起こして倒れたとすると、たぶんその場に居合わせた人々同士は、「おい、アレを持って来い」だけで話が通じてしまうだろう。
物事の正しい名前を知らなくてもうまく生活していける世界がこれからどう変化していくのか、私にはちょっと興味がある。そう言えば昨年の秋(2010年9月30日)、TOブックスという会社から『正式名称大百科』という本が出版された。このAEDなど医学用語ばかりでなく、動物や植物、地理、建造物、生活用品などいろいろな分野の正式な名前を解説してくれているが、実はこの本の中に私のサイト中の写真を使って頂いている。確か昨年の夏頃だったと思うが、その写真をこの本の該当ページに使わせて下さいというご丁寧な申し出のメールがあり、承諾しておいたところ、確かに末尾の写真協力者の欄に私の氏名も入っていて、2センチ角ほどではあるが、私の撮影した写真も掲載されていた。
さて私のサイトのどの写真かお判りでしょうか?(笑)
入学試験の思い出
また今年も大学の入学試験の季節が巡ってきて、私の学科もずいぶん多くの受験生の方々に受験して頂いている。試験監督をしながら、私も自分が受験生だった昔の頃のことを思い出していた。
「大人は試験がなくて良いね」
というと、必ずどの大人も同じような返事をしたものだ。
「何を言っているか、試験があっても子供の頃が一番良いのだ。大人は試験勉強よりももっと苦しい思いをしているんだ」
その意味も今になってみると身に沁みてよく分かるが、学生時代を卒業するまでは、何と言われようともイヤなものは絶対にイヤ、早く試験の無い生活を送りたいと思うのである。
私の大学では、たぶんいろんな理由はあるのだろうけれど、医学部の教員は医学部志願者の入試監督などはやらないのである。すべて他学部の教員任せだから、私も医学部の助教授時代は自分が教えることになる未来の学生たちへの関心はまったく無かった。医学部の学生さんたちには申し訳なかったが、自分が受け持つ学生への愛着を感じるようになったのは、現在の学科に移ってからのことである。
やはり入試の試験場で、五角形の鉛筆(五角鉛筆→合格鉛筆)など持って、緊張しながら必死に受験している姿を見ているので、つい自分が若かった頃と重ね合わせてしまい、イヤでも思い入れが強くなるのかも知れない。
私は昭和45年に現役として3校受験して全敗、浪人した翌年の昭和46年に2校受験して1勝1敗だった。敗戦の方が多いわけです。で、不思議なことに、現役時代はどこか1つくらいは受かるだろうという妙な楽観があったが、浪人して受験勉強の怖さを知ると、今度はこれから先、何年浪人してもどこにも受かるような気がしなくなった。やはり敵を知り己を知ると、あらゆることに用心深くなるということだろう。
私たちの頃は、理系受験では数学の出来が死命を制すると言われていた。おそらく現在でもそうだろうが、数学は1問余計に正解できるかどうかで得点が大きく違ってくるからである。私が幸運にも大学に滑り込みセーフだったのにも、数学のあの1問、まさに『運命の1問』とでも呼びたいような問題があった。何十年経って忘れようにも忘れられない問題である。
『3人でジャンケンしてn回目に勝者が1人決まる確率を求めよ』
という出題だったが、これは直前まで3人引き分けが続き、最後に2人同時に敗退して最終勝者が決まる確率と、途中で1人敗退して2人残り、さらにもう1人が敗退して最終勝者が決まる確率の和であるから、これは面倒な計算になるなあ、と思った瞬間、頭がカア〜ッとパニックになった、あのホワイトアウト状態は今でも鮮明に思い出せる。
何しろその年度の数学の出題は6問あり、1問目は比較的余裕で解答できたものの、2問目は2つに分かれた問題のうち前半しか解答できず、3問目はまったくお手上げ、4問目も2つに分かれた前半しか解答できず、5問目も解答の糸口さえつかめない、つまり5問中2問分しか得点できていないのに、6問目がこのジャンケンの確率問題である。
「ああ、こりゃダメだ」
諦めて2浪を覚悟した。その時の私の身体状況も思い出せる。座席の椅子から腰が浮き上がって机に前のめりになった格好、しかも緊張で息が吐けず喘ぐような呼吸だった。本当に傍から見たら滑稽だったに違いない。
1年間の浪人中、難問揃いだから予習より復習に力を入れろと前年度の合格体験者も書いていた予備校の数学問題集を、意地でも予習で自分なりに解いていった思い出が頭に浮かんだ。
「もはやこれまで、あれだけやっても無駄だったか、やはり医学部は高望み、残念無念」
と戦国の落ち武者のような気分になり、こうなったら予備校の予習の続き、来年のための練習問題だと思い直したところ、見事なくらい未練が消え失せていた。
そして椅子に座り直してお尻に自分の体重を感じた瞬間、呼吸も楽になって本当に気持ちが落ち着いてきた。自宅の机で数学の予習をしているような錯覚も起こって、改めて問題を見直したところ、2問目と4問目の後半部は依然として難問だったが、最初お手上げだった3問目と5問目は解法が見つかり、6問目も(本当はもっとスマートな解法があったらしいが)k回目で1人敗退してn回目でもう1人敗退するという二重の数列を作って馬力勝負の無茶苦茶な計算に挑み、
(2n-1)/3n
という正解(この答えも何十年経っても覚えている)にたどり着いた途端、解答終了の合図があった。
あれが本番の試験場のプレッシャーであったか。椅子に座り直した時にお尻に感じた体重の感触は今でも私の体が覚えている。あの感触のお陰で私はプレッシャーから脱出できたと思う。今の私の学科の学生さんたちも国家試験では大変なプレッシャーを感じるだろうが、その対策を伝授するうえでも本当に貴重な体験だった。
ただし私がプレッシャーから抜け出せたのは、1年間の浪人中に、無理して予習しなくても復習だけで良いよと言われていた予備校の数学難問を、ほとんど自力で頑張って解いた、その自信があったからでもある。本当に浪人時代の自分だけは褒めてあげたいと思う。
蜘蛛の糸の意図
小学校や中学校の国語の教科書に必ず掲載されている芥川龍之介の名作『蜘蛛の糸』ほど作者の意図が分からない不思議な小説はない。芥川龍之介はあの小説の中で何を言いたかったのか、間もなく還暦を迎える年齢になっても未だに謎のままである。
『蜘蛛の糸』のあらすじは日本人ならほとんどの人がご存じだろう。御釈迦様が極楽の蓮池から地獄の血の池を覗き込むと、カンダタ(小中学校の教科書だから仮名書きだった)という大悪党が他の罪人たちと一緒に罰を受けて漂っている。御釈迦様はこの男が生前、小さな蜘蛛を踏み殺すのを思いとどまったことがあったので何とか救い出してやろうと考え、蓮池の淵から血の池のカンダタの所へ蜘蛛の糸を垂らしてやる。カンダタはこれを登って行けば地獄から抜け出せると信じて懸命に登り始めるが、自分の後から他の罪人たちも次から次へと登って来るのに気付いて、「この糸は俺の物だから、お前らは下りろ」と怒鳴る。するとその瞬間、蜘蛛の糸はプッツリ切れてカンダタも他の罪人たちも再び地獄へ逆戻りしてしまう。
小学生でも読めるくらいの短編であり、私も確か小学校の3年生か4年生で初めて読んだと思うが、とにかく不思議な小説であった。まず「カンダタ」という名前からして妙である。姓が「神田さん」だとすると、名前は「た」しか残らない。「た君」なんて変な名前…。
(註:カンダタは「カン・ダタ」であり、カンの字が非常に難しい。菅ではない・笑)
初めて読んだ時の感想は、まさにカンダタと同じだった。せっかく主人公が御釈迦様のお陰で地獄を脱出して助かりそうだったのに、何で他の罪人たちはカンダタの邪魔をしたのか。邪魔さえしなければカンダタは助かったのに…。それが私の初回の正直な感想だった。邪魔した他の罪人たちが憎らしくて仕方なかった。
もう少し大人になって読んだら、自分さえ助かれば良いというカンダタの利己的な心がいけなかったのだなと気付いたが、そうするとまた別の疑問が湧いてきた。御釈迦様が垂らした蜘蛛の糸は、そういう人間の心を読み取って切れたり切れなかったりするのか、非常に不思議な物理的性質を持った素材である。
もし御釈迦様がそういう素材の性質を知ったうえで蜘蛛の糸を垂らしたのなら、御釈迦様はいったい何を考えていたのだろうか。御釈迦様はカンダタだけを救済しようとしたのか。それとも血の池に放り込まれていたすべての罪人を救済しようとしていたのか。
カンダタが他の罪人も皆で助かろうと考える寛大な心の持ち主であったならば、蜘蛛の糸は切れなかった。ということはカンダタの後から登ってきた罪人たちもすべて極楽へ来ることになってしまうが、地獄の閻魔大王の了承を得ずにそんな勝手なことをすれば極楽の存在意義はなくなってしまう。
御釈迦様がカンダタを助けようと思った理由が、生前に小さな蜘蛛を踏み殺さなかったことだけだとすれば、血の池にいた多くの罪人たちの中にはもう少し善い事をした者も当然いたはずである。もしかしたら御釈迦様は、罪人たちの中で最も凶悪なカンダタという男、せいぜい蜘蛛しか助けようとしなかった極悪人の心を試すことによって、それよりはましな他の罪人たちもすべて極楽へ救い出そうとしていたのではなかったか。そう考えなければ御釈迦様の行動は説明がつかない。
この年齢になって『蜘蛛の糸』について思うのは、この小説は一見カンダタという男の心についての説話になっているように見せて、実は御釈迦様の行為自体を批判していたのではないかということである。
極楽という場所の管理責任を問われる身でありながら、閻魔大王の了承も得ぬままに地獄の罪人たちの心を試そうとした。極楽と地獄の秩序を乱す行為である。裁判で有罪と決まった人間を権力者が勝手に赦免するようなものだ。
御釈迦様の気まぐれのお陰で地獄の罪人たちはどうなっただろうか。作品には事の顛末は描かれていないが、地獄で生前の罪を償っていた罪人たちは不意に一縷の望みを見せられたばっかりに、却ってその心は千々に掻き乱されたのではなかろうか。しかもカンダタと他の罪人たちとの間には埋めることのできない深い溝ができてしまったに違いない。そんな風に罪人たちの心を翻弄しておいて、カンダタが再び地獄に落ちてしまったのを尻目に、また蓮池の散歩を続けたと書かれているから、ちょっと無責任じゃないのと言いたくなる。
国家試験を受けた頃
2011年2月23日は、今春私の学科を卒業する学生さんたちの国家試験の日だった。学生さんたちの大部分は臨床検査技師という医療の専門職に就くことを目指して私の学科に入学してきたわけだが、その職種にふさわしい技能と知識を習得していることを国家が検定して、合格者には資格を認定してくれるわけである。
私たち医師にも同じような国家試験がある。いや、医師や臨床検査技師ばかりでなく、看護師や薬剤師、栄養士などといった医療職から、法律関係、建築関係、交通関係、経済関係、技術関係、情報関係など、いい加減にやられちゃ国民が困るような職種はすべてと言ってよいほど、国家が認定する資格なしに仕事はできないことになっている。
私が医師国家試験を受けたのは昭和52年(1977年)の春のことだった。あの頃は医師の資格に関してはちょっと面白い(といっちゃ語弊もあるが)事件が時々起こった。無免許、つまり国家試験を受けて医師免許を取得していない“ニセ医者”がよく摘発されていたものである。
どういうニセ医者かと言うと、戦前の陸軍や海軍には軍医の補助をする衛生兵とか看護兵という兵種があった。看護兵というから女性かというと別に普通の兵隊なのだが、これが戦場で軍医の手伝いをする。軍医はもちろん医師免許を持っているが、その軍医からちょっとした医学知識くらいは耳学問で聞いていただろうし、とにかく怪我人、病人が大勢いて軍医の手が足りなければ、こういう衛生兵や看護兵が傷の縫合や簡単な手術くらいもやっただろう。この人たちの一部が戦後に医師を名乗って患者さんの診療を行なっていたのである。
しかし衛生兵あがりだからといって決して馬鹿にしてはいけない。とにかく修羅場のような戦場で修練を積んできたから、戦後に医学部を出たようなナマクラな医者よりはずっと腕が立つし、学歴を詐称しているという負い目があるから患者さんには非常に丁寧に接している、だから自然に患者さんの評判も上がって地元では“名医”で通るようになっている。
医療はとにかく実地での経験が物を言う職場だ。だから医学部を出てからずっと研究室で論文を書いてましたなんていうナマクラな医者がいくら医師免許をひけらかしたって、現場での実力は絶対に私にかなわない。まして弾丸飛び交う戦場で修練を積めば、正式な医学教育を受けていなくても、たちまち手術の腕なんかは上達することになる。
当時の日本はひどい国で、兵隊なんぞは1銭5厘でいくらでも狩り集められる(1銭5厘は召集令状を出す郵送費、現在ならば1人50円というところ)、人間の生命よりも軍馬や兵器の方が大切にされるようなこともあったくらいだから、負傷兵など死んで元々、もし治療に失敗しても医療訴訟になるわけがない、そういう現場で医療の腕を磨いたわけだ。現在の最先端病院で外科や整形外科の研修を受けたって、たぶん戦争中の衛生兵ほど腕は上がらないかも知れない。
ところで皆さんに質問だが、もし病気や怪我になった場合、物凄く腕の良いニセ医者に診療して貰いたいか、医師免許を持ったナマクラな医者に診療して貰いたいか?
こういうジレンマを描いた漫画が手塚治虫さんの『ブラックジャック』であろう。無免許の天才医師ブラックジャックは、正規の医者でも手に負えないような難しい手術も完璧にこなして、不治と思われた患者も治癒させてしまうスゴ腕の持ち主である。ストーリー自体は、手塚さんが医学部出身であるにもかかわらず、あまり医学的でないことも多かったが、もしブラックジャックが実在であったならば、私だって同僚に診て貰うよりは、無免許の天才医師に診て欲し〜い(笑)。ただし治療費が法外に高いので支払いきれるかどうか…。
と言うようなわけで、腕さえ確かなら、ブラックジャックであろうと、元衛生兵であろうと、医師免許など関係なさそうであるが、こういう無資格者の中には、もしかしたら天才もいるかも知れないけれど、やはり金欲しさに資格を詐称しているだけの人間の方が多いだろう。とてもじゃないが日本全国で安心して国民の健康を任せるわけにはいかない。
そこで医師の“品質”を保証するのが、国家の認定する医師の資格であり、その資格を与えるかどうか決めるのが医師国家試験である。しかし医師ばかりでなく、看護師や臨床検査技師など医療職の資格は、法曹界の司法試験などのように、勉強した人には誰でも門戸を開いているわけではない。医学書を買い込んで必死に勉強しても、医療職の国家試験の受験資格は与えられないのだ。きちんと法令の定める設備とスタッフを擁し、定められたカリキュラムで教育を行なっている専門の学校を卒業するか、それと同等の教育を受けていると認められて初めて国家試験を受けることが出来る。
ところが私たちより前の世代の医師たちが受けた国家試験は非常に簡単だったそうだ。先輩医師たちからの又聞きによると、簡単な筆記試験もあったらしいが、ほとんどの受験生は面接試験で救済されてしまったという。各大学医学部の教授連が持ち回りで面接官を担当したらしいが、受験生はレントゲン写真とか検査所見とか見せられて、面接官の教授とディスカッションをして終わりと聞いた。レントゲン写真が何だかちっとも判らなくても、誘導尋問的に正解に導いて貰って合格しちゃった、などという話はよくあったものだ。
まあ、昔は医学部の入学者選抜試験および学部教育自体の“品質”が保たれていたから、医学部を卒業してきた人間なら、安心して医師免許を与えても問題はないと判断できたのだろう。しかし全国に新設私立医大が続々と認可されるようになって状況は一変した。
私がまだ高校時代に医学部を受験すると言い出した時、進学相談に行った私の親に対して担任教師が、「お宅の息子さんが寄付金なしに入れる医学部なんてありません」と言った話はどこかに書いたと思うが、当時は新設私立医大→高額の寄付金→裏口入学という連想の図式が当たり前のように存在していた。
とにかく医学部教育は金がかかるものであるから、私大経営者はどんな形でもいいから金が欲しい、代議士や地方議員や地元医師会の有力者などは何とか各方面にコネを誇示したい、いろんな思惑が交錯したことだろう。
「○○医院の院長も体調が悪くて倅を早く跡継ぎにしたいらしいんで何とかよろしく」
日本人はきわめて情実に脆い。かなりの知識人であろうと、欧米留学経験が長い人であろうと、実に呆れるほど簡単に話に乗ってしまう。こういう情実の結果、日本の国家や社会がどうなってしまうかなどということを理性的に考える思考回路が欠如しているとしか思えない。
そんなこんなで医師免許試験を中途半端な面接などで済ましていては大変なことになるということになったに違いない。何しろ医大の入試と学部教育の“品質”への信頼性が崩れて、情実でも医学部に入れるということになってしまったわけだから…。
よく覚えていないが、私が受験する数年前くらいから、医師国家試験も当時いろいろな試験に導入されるようになっていたマルティプルチョイス方式に変わった。この方式もさまざまな問題があることは事実だが、知識を客観評価されてしまうから医学生も勉強しなければ医師免許を取れないというプレッシャーが加わることになった。
ところがこのマルティプルチョイスの試験は、回数を重ねるに従ってどんどん重箱の隅をつつくような傾向になる性質を持っている。受験生は過去問題を研究してくるから、前年と同じ問題を出せば、正解を覚えられてしまって評価ができなくなる。試験問題は全員が正解しても、逆に全員が不正解になっても困ったことになる。受験生に得点差をつけて選別するために、ある一定数の受験生を不正解にしなければいけないのだ。
それで国家試験問題は年々細かいことを訊く出題になっていって、私が受験した年は最も難しい問題になっていた。医学部を卒業したばかりの者が知っている必要もないような知識、あるいは大部分の医師が一生の間に遭遇することはないくらい希少な疾患を問う出題者もずいぶんいた。この点もたぶん問題視されたのだろう、私の受験した翌年からは、医師国家試験の出題のガイドラインが定められて、あまりの難問や奇問は出ないことになったようだ。
ここでまた情実が入るのだが、国家試験の出題者はいろいろな大学の教員である。それが自分の所の教え子に試験問題を漏洩するのだ。最近も歯科医師だか何だかの国家試験問題が漏洩したという報道もあったが、私が受験した頃は本当にひどかった。
私などまだウブで世間を知らなかったから、まさか医師国家試験問題の漏洩など無いと信じていたところ、受験当日の朝、○○医大情報と称して「▲▲症候群が出るらしい」という話が回ってきた。そんな稀な病気の問題など出ないだろうと半信半疑だったが、試験が始まってみたら本当に出た。私が世の中を信じなくなったのは、あの時からかも知れない。
まあ、いろいろ書いてきたが、私にとって国家試験ほど気が重いイヤな試験はなかった。何しろこれで自分が夢見てきた形で社会人になれるかどうか決まってしまうからだ。内科や外科の問題に難問や奇問が多く、自分の解答に自信を持てなかったから、私はてっきり落第したものと思い込んで、しばらくは布団をかぶって言い訳ばかり考えていた。自己採点などしてみる勇気が出たのは受験の1週間後のことである。問題をもう一度、教科書や参考書と照らし合わせてみたら、私が以後働くことになる小児科や産婦人科で意外にも得点を稼いでおり、ホッと胸を撫で下ろした次第であった。
人体の不思議展
以前別項でお約束した『人体の不思議展』について私の所感を述べる。その時は軍艦の写真など歴史的資料は速やかな公開が望ましいという趣旨の一文を書いたわけだが、医学的資料については個人情報や人間の尊厳が侵犯される恐れがあるため絶対に非公開にすべきであると書いた。今回はその続きである。
現在生きている患者さんのカルテや診断書などはプライバシーの問題があって、これを公開してはならないことは明白であろうが、ではもう亡くなってしまった人についてはどうなのか。これはもうある意味で“歴史的”資料なのではないか?
例えば歴史上の有名な人物の死因に関して定説を覆すような証拠が発見された時に、それを公表するべきかどうか。この種のものでは、イエスキリストは実は日本に来て死んだとか、上杉謙信は織田信長の手先に毒殺されたとか、あまりにも興味本位で荒唐無稽なものも多いが、近世から現代にかけてのまだ御遺族もいらっしゃるような人物についてはどうなのか。
これを歴史的資料として公開するか、医学的資料として秘匿するか、ここには場合によっては犯罪捜査の観点も絡んでくることがあってなかなか微妙な問題だと思うが、いやしくも人間の死を取り扱う以上、そこにはやはり厳粛なモラルの規制が加えられるべきである。ある人物の死因や健康状態を興味本位であれこれ詮索すべきではない。
さて、ここではそういう問題は別として、今度はもっと一般的な死体について考えてみたい。死体はもう魂の抜け殻であるから、単なる物体として科学啓蒙のために広く一般の人たちに公開しても構わないという立場の方は日本にも多いようだ。日本各地を巡回して、その度に大盛況を呈しているらしい『人体の不思議展』を主催しておられる方々は皆そういうお考えであろう。
私ももう10年以上も前に横浜で開催されていた『人体の不思議展』を見に行ったが、言葉にならないほどの不快な衝撃を感じた。「人間の死体をオモチャにしている」というのが私の率直な感想である。
私自身、献体して下さった方の御遺体を解剖させて頂いて医師になり、現在は解剖学や病理学を学生に教えている教員であり、実物の人体を観察することの意義は十分に分かっているけれども、あれは絶対にやってはいけない“展覧会”である。
こう書くといろいろ反論もあるだろうが、皆さんは自分の死後にあの『人体の不思議展』の“展示物”として自分の遺体を献体できるだろうか。医学生や医療系学生が将来病人を救うための教材として役立てて貰えるわけではない。
あなたが死んだ直後、その道の技術者が死後の枕元に押しかけてきて、あなたの死体に硬直が起こる前に“馬に乗るポーズ”や“弓を引くポーズ”や、その他さまざまなポーズに仕立て上げる、そうしなければあれだけいろいろな格好の“展示物”ができるはずはないのだが、この点を考えただけでも、仮に“篤志献体”であろうと、あまりに異常であると思えないだろうか。
なぜ死体にいろいろなポーズを取らせるかと言えば、そうすれば一般の人たちが喜んでくれ、“展覧会”に足を運んでくれ、主催者はお金が儲かるからである。純粋に医学の勉強のためならば、別に死体が弓を引いてくれる必要はない、むしろそんな変な格好に折り曲げられた死体など正式な解剖学の知識の邪魔になるだけだ。それでもあなたは『人体の不思議展』に献体しますか?
『人体の不思議展』に展示されている死体は、プラスティネ−ション(plastination)あるいはプラストミック(plastomic)と呼ばれる技術で処理されたものである。人体の水分と脂肪を抜いて、代わりにプラスチックに置換する技術で、1978年にドイツのハイデルベルグ大学のグンター・フォン・ハーゲンス(Gunther von Hagens)博士が開発したと言われる。
キリスト教の社会では、人は死んだ後は魂が神様の許へ召されて行くので現世に残った死体はただの抜け殻という意識が強く、東洋人の遺族のように故人の遺体に取りすがって号泣するケースは稀であると、西丸與一先生が『続・法医学教室の午後』の中で述べておられる。そういう社会的、宗教的背景があって初めてこういう死体処理技術も開発されたのであろう。しかしフランスなどのキリスト教国においてさえ、人体の不思議展に類する企画への批判がある。
まして日本では遺族が故人の遺体に対して抱く愛惜の念は法律をもって守るに値するという趣旨で、刑法に死体等損壊罪(190条)が規定されている。そんな日本で『人体の不思議展』などという死体をオモチャにした企画が長年にわたって好評を博している理由は何なのだろうか。
ただの興味本位、死体という非日常的なものを目の当たりにさせてくれる娯楽、そこに展示されている死体は、どこか自分とは関係ない所で調達されて加工されたもの、それがもし自分の愛する肉親だったら絶対にイヤだし、自分自身がそんな企画に献体する気はさらさらないけれども、どこの誰だか分からない人の死体なら目一杯楽しませて貰ったっていいや…。
そんな日本人の身勝手を見せつけられるようで本当に後味が悪い。このサイトの他の部分で書いたように、自分は祖国のために犠牲になるのはイヤだけれど、国のために死にに行かされた特攻隊員の物語には感動したい、それとまったく同じ精神的基盤ではないのか。
プラスチックで固められて展示された人がどんな生き方をし、どんな死に方をしたのか、それを考える気にはならないのか?『人体の不思議展』の主催者はあくまでも篤志献体だと言い張るが、肝心なところは相変わらず不明瞭なままだ。一説によれば獄中で変死した中国人の遺体も混じっているという。
証拠も無いから軽々しく断定するわけにはいかないが、私が10年前に横浜の展示で見た遺体の中に気になるものがあった。プラスティネーションで固められて数ミリメートルに薄切りされたかなり大柄の男性標本だったが、明らかな頭蓋内出血を示していた。普通の観覧者は気付かないだろうが、病理の医者はそんなところを見ているのである。外傷によるものであることは明らかだったが、それだけで死因になるような大きさでもない。その断面だけでは何とも言えないことは事実だが、こんな死に方をした人の死体が十分な死後の検索も受けないまま、息を引き取ると同時にプラスティネーションの技術者によって固められてしまった、そんな気がして、あの展示を見て以来ずっと気になっている。
このくらいのことを考えられるようになって初めて死体を観ることが許されるのであって、解剖学のイロハも知らない人に猟奇的な展示を提供するような企画はいかがなものか。決して興味本位で死体を眺めてはいけない。解剖学の初歩的な知識くらいは習得してから見なければ、標本になった方々の霊も浮かばれないのではないか。
ちなみに余談だが、先ほど“頭蓋内出血”と書いたが、「頭蓋」と書いて「ずがい」としか読めない人は解剖学の素人さんである。学問的には「ずがい」という読み方はなく、「とうがい」と読まなければいけない。頭蓋骨は「ずがいこつ」ではなく「とうがいこつ」である。私も講義で発音する時は、あえて誤解の生じないように「ずがいこつ」と読み替えることもあるが、医学の専門家が私の前で「ずがいこつ」などと発音したら、ハハア、こいつは解剖学を勉強してこなかったなと思っている。
花の季節

今年(2011年)は3月11日に東日本大震災とそれに引き続く原子力発電所事故があり、気分が滅入る日々を送っていたが、震災からちょうど1ヶ月後の日曜日の東京は穏やかな晴天に恵まれて、絶好の花見日和となった。いつまでも庶民が愚痴っていても撒き散らされた放射性物質が減るわけじゃないので、このサイトも気分一新するために花の話題でも一つ。
しかしこの1ヶ月の何と長く感じたことか。
「明日は電車は動くだろうか」とか、
「明日はパンを買えるだろうか」とか、
当たり前の日々であれば決して考えないようなことまで頭を悩ませていたから、心理学的時間の歩みは遅くなっていたのだろう。
今年は例年に比べて肌寒く感じる日が多く、4月になっても桜の蕾がなかなか膨らまなくて、こういう年は春も遅いのかなあと根拠もなく思っていたけれど、やはり季節はいつの間にか移り変わって、私の大学の近くの石神井川沿いの桜も見事に花開いた。例年に増して今年は特にホッとする思いである。
ニュース記事を見れば、震災からの復興も原発事故に足を引っ張られている感じだし、政府の対応も後手後手に回っているようにしか見えないし、誰も自分の責任を明言しようとしないし、週刊誌なども政府や電力会社の非を声高に非難するばかりだし(その方が売れるからだろう)、学者も今後の余震や放射能漏れの見通しについて、センセーショナルに素人の不安を煽るようなことを言う奴もいるし(これもやっぱりその方が売れるからに違いない)、いったいこの国はどうなっているのだろうか。
本来ならこういう災害に際して、政治家やマスコミが国民の先頭に立って希望を指し示し、庶民を鼓舞する役目を果たさなければいけないのに、日本では国民に勇気を与えてくれるのは、四季の風物とスポーツ選手だけなのだろうか。(イチローもアメリカでだいぶ頑張ってくれているようだ。)

ところで今年の春先、カミさんが友達から昔懐かしい水栽培の花を貰ってきた。小学校の頃に誰でも1度や2度は水栽培の花を育てたことはあるだろう。
上部がくびれたガラス容器に水を満たして植物の球根を乗せておくと、水中に根を張って花が咲く。普段我々は葉っぱの中に赤や黄色の美しい花弁をつける“花”しか見ていないが、本当は目に見えないところで根を張って養分を吸収しているからこそ花を咲かせられる、水栽培を眺めながらそんな当たり前なことを考えてしまう。
思えば日本人は経済成長が頂点に達して“バブル”を極めていた頃から、この当たり前なことを忘れていたのではないか。努力もせずに成果ばかり求めようとする。地味で辛い仕事は“3K”などと言って敬遠し、なるべく楽をしながら脚光を浴びる仕事の方を求めようとする。
今回の原発事故も似たようなものだ。電気を使って贅沢な生活を送りながら、危険と隣り合わせで発電所を受け入れてくれている地方があることは意識に上らなかった。果たしてここまで華美な電気の“花”が必要だったのかどうか。
この数十年間、日本列島に咲き誇った“花”のあり方を、この震災を機にもう一度考え直さなければいけない。
ワンピースを知っていますか
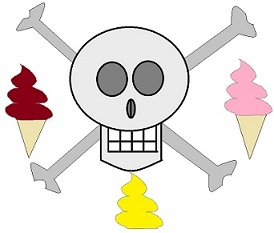
私も小児科医をやっていた頃は、いろいろな子供向け漫画のキャラクターたちのことにも相当詳しかったが、最近ほとんど少年漫画など読まなくなっていたところ、ある学生さんから「先生、ワンピースは読んだことある?」と聞かれました。
ん?ワンピースって女の人が着る上下ひとつなぎの服のこと?なんて言ってるようじゃ、最近の若い人の相手はできませんよ。ワンピース(ONE PIECE)とは、1997年から週刊少年ジャンプに長期連載中の少年漫画で、単行本も60巻を突破、しかもその単行本の累計売り上げ数が2億冊を越えたというチョー人気ぶりです。
いい年こいた大人がこんな所に少年漫画を取り上げて、もっともらしく解説など加えるのはヤボなので、興味のある方はウェブで調べてみて下さい。公式サイトからWikipediaからYouTubeから、やたらにたくさん検索に引っ掛かってくるはずです。
まあ、とにかく麦わら帽子がトレードマークの主人公モンキー・D・ルフィをリーダーとする仲間たちが海賊船に乗り組んで、他の海賊団や海軍や世界政府を相手に冒険を繰り広げていくという、こう書いてしまえば他愛もないストーリーなんですが、私も最初は「フン、どうせ“ドラクエ”的な少年漫画だろ」と多少バカにしながらも、学生さんから単行本を借りて読んでみたところ、いや完全にハマってしまいましたね。上のような海賊旗まで作る始末…。
アクション場面はほとんどおちゃらけたギャグが多いのですが、随所に泣かせる珠玉の名セリフが散りばめられている、こういう名セリフだけを集めた本も先日出版されました。
強くならなければ仲間を守れない、とか
人が死ぬのは皆から忘れられた時、とか
いざという時にリーダーを立てられない奴はダメ、とか
自分が選んだ人生は自分の責任、とか
たぶんこの漫画の読者が将来社会に出た時にハッと思い当たるようなセリフが、ストーリーの中にさりげなく表現されています。
願わくは、こういうセリフを漫画のキャラクターたちにだけ言わせて満足してしまうのではなく、読者の若者たち自身がこういうセリフの似合う大人になって欲しい。
あと何より作者の尾田栄一郎さんという人はストーリーの構成力が抜群なんですね。単行本で10巻以上も前の話が伏線になって現在の話につながり、さらに物語が新たな意表を突く展開になっていく、登場するキャラクターも1人として無駄な者はいない。ただの少年漫画として片付けてしまうには、あまりにも雄大な叙事詩です。
まあ、もっともらしい解説などはヤボと申し上げましたから、この辺でもう止めときますが、何年も連載を続けて読者の気を持たせておきながら平凡な結末に終わった『●●●』とか、局所的なストーリー展開に単行本10巻以上費やしながら大事な結末を1巻の半分足らずで尻切れトンボに終わらせた『▲▲▲』とか、章が変わるたびに前の章に出てきたキャラクターは完全に忘れ去って、また別のキャラクターと共に似たような話をダラダラ何年も描き続けている『■■■』とか、青年〜成人漫画も今のままでは海賊に食われちゃうよ。
ナマ肉…
2011年4月、富山県と神奈川県の焼き肉チェーン店で病原性大腸菌O111による食中毒によって何名も死者が発生し、食の安全に対する信頼が揺らいでいる。客に肉を提供した焼き肉店の責任か、店に生肉を卸した卸売業者の責任か、いずれに原因かあるのか、現在捜査が進んでいると思われるが、どちらにしても“生肉”という衛生的にきわめて微妙な食材の流通・販売に対する警戒が甘かったと言わざるを得ない。昨日までは客に売っても食わせても大丈夫だった、今日も大丈夫だろう、というのでは、津波に対する東電の原子炉と同じ体質である。
病原性大腸菌としては漫画『もやしもん』で人気キャラクターにもなったO157が有名だが、今回のO111を含め何種類かある。これらの細菌はベロ毒素(Vero toxin)を放出して腸管出血を起こすが、このベロ毒素はヒトの細胞に侵入して、リボソームという蛋白合成装置を破壊してしまうので、まず消化管粘膜が死滅、さらに腎臓や脳など全身にこの毒素が回ることによって生命の危険が切迫する。
下痢止めを服用するとベロ毒素が肛門から排泄されず、大腸から体内に吸収されてしまうので症状はさらに重篤となり、また抗生物質など服用すると大腸菌が死ぬ時にまるで“イタチの最後っ屁”みたいに毒素をドバッと放出するという説もあり、とにかく厄介な細菌であることは間違いない。
ところで今回の食中毒事件、舞台が焼き肉店であり、原因となったメニューはユッケらしいということで、私としても他人事ではなかった。私も職場の同僚や学生さんなどと焼き肉など食べに行くと、あのユッケは必ず注文していた。真っ赤な生肉の上に生卵をかけて出されるユッケは、最初はちょっと抵抗があったのだが、いったんクセになるととろけるような食感が何ともたまらない。
日本人が加熱していない生肉あるいは生焼けの肉を食らうようになったのはいつ頃からだろうか?私が子供の頃、すなわち1950年代から1960年代くらいまでは、牛肉ならばすき焼きが最高の贅沢、しゃぶしゃぶという食べ方もあまり馴染みはなかった。
一般の家庭でも薄切りのロース肉をフライパンでよく火を通したものを『ステーキ』と呼んでいたのではなかったか。“血のしたたるようなステーキ”という表現を、何か外国の文学か何かで最初に読んだ時の違和感は今も覚えている。
その後、本場のステーキとは、ミリメートル単位ではなくセンチメートル単位の厚さの肉を焼いた料理であることを知り、その焼き方にもウェルダン、ミディアム、レアの3通りあることを知り、それで肉は十分に火を通していなくても食べられることを知った。
私が初めて生で肉を食べた日のことはよく覚えている。しばらく前にこのコーナーの別の記事にも書いたことだが、英語の小児疾患アトラスを翻訳した報酬があまりに高額だったので使い途もわからず、お見合いしたばかりのカミさんを築地のスエヒロに案内して、最高級のステーキをご馳走した。
今では築地スエヒロ店は閉店してしまったが、最上階のステーキハウスのカウンターに座って店内を見渡すと、客は私たちだけしかいない。カウンターの向こう側にはシェフの方が2人いらして、私がメニューの一番上のコースを注文したらヘエッという顔をされた。
その後のバブルの時代ならば、ベンチャービジネスに成功した若造が豪遊することも珍しくなかっただろうが、まだ昭和50年代前半に30歳になるかならないかの男が“ハデな女(笑)”を連れて昼時にやって来た。そんな“にわか成金”の真似をした自分自身が、今思い出すと顔から火が出るほど恥ずかしいが、店のスタッフもさぞびっくり仰天したことだろう。
とにかくその時、シェフの方が厚さ3センチ以上の肉をサイコロ状に切り分けながら、
「これは私たちでさえ滅多に口にできない肉です。生でも食べられますよ。」
と言って、まったく加熱していない牛肉を私たちの目の前に並べたので、これにはカミさん共々(まだカミさんではなかったが)驚いてしまった。
それで恐る恐る生の肉を箸でつまんで口に運んだところ、これが旨いっ!何という美味っ!あれが私の生肉初体験だった。あの頃はまだ魚介類以外の肉を平気で生で食べられる日本人はそれほど多くなかったはずだ。
考えてみれば、昔のティラノザウルスも、今のライオンや虎も、捕らえた獲物の肉は生で食うのである。人類だって最初のうちは肉は生で食っていたに違いないから、加熱しなければ動物の肉は食えないという先入観があった昔の日本人の方がおかしいのだ。
今では肉食動物の本能に目覚めた日本人も生肉に対する心理的抵抗が減り、さらに韓国料理などの普及もあって、学生さんたちの世代のほとんどはユッケなど大好物みたいだ。中にはやっぱり赤い肉はダメです、なんていう子もいるにはいるが少数派である。
生で食らう肉は加熱した肉とはまた別の食感があり、現在の食文化に欠かせない食材になっているが、一世一代の仕事の報酬としてやっと食べることが出来たような時代ではなく、町のレストランや焼き肉店に行けば誰でも手頃な価格で食べられる時代になったわけだから、食の安全管理は厳しくやって貰わなければ困る。しかし大量に流通、販売されるようになれば、どうしても監視が手薄になるのは否めないから、消費者も常に目に見えない微生物から狙われているという意識だけは持っていなければいけないだろう。
ここは病理医の独り言の第7巻です 第6巻へ戻る 第8巻へ進む
 トップページへ戻る 病理医の独り言の目次へ
トップページへ戻る 病理医の独り言の目次へ