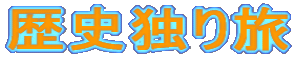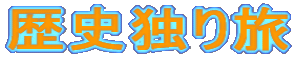
航空母艦加賀と赤城
別のコーナーで、私が最も長く通った板橋区 加賀という地名が加賀百万石の前田家に由来するという話を書きましたが、その旧国名である加賀、最近も海上自衛隊の大型護衛艦(ヘリ空母)にも命名されました。こちらは護衛艦かがと平仮名書きですが、旧帝国海軍には由緒正しく『加賀』と表記される大型航空母艦がありました。今回はその空母加賀の話。
加賀は戦前の大日本帝国海軍の空前の大建艦計画だった戦艦8隻・巡洋艦(巡洋戦艦)8隻より成る八八艦隊計画の1隻で、1922年のワシントン海軍軍縮条約で各国とも主力艦(当時は戦艦だった)の保有が制限されたため、日本では巡洋戦艦(普通の戦艦より速力がある)赤城と天城を空母に改装することになったが、翌年の関東大震災で天城の船体が大破したため、戦艦として計画されていた加賀が急遽この代役として空母に改装された、そんな話は護衛艦かがに関連してそちらの記事に書いておきました。しかしやっぱり平仮名書きの艦名はあまりピンと来ませんね。

そんなわけで空母赤城と加賀は厳密には生い立ちからして素性が異なっているのですが、同じ時期に同じような境遇から空母になったという意味で、赤城・加賀と準姉妹艦として扱われることも多いし、ミッドウェイ海戦で枕を並べて討ち死にするまでこの両艦は第一航空戦隊を構成して共に戦いました。
さてこの堂々たる(?)洋上模型、戦艦長門に先導されて進む赤城と加賀ですが、どちらが赤城でどちらが加賀かすぐに分かりますか。まあ、飛行甲板の艦尾に『ア』と書いてある左側が赤城で、『カ』と書いてある右側が加賀なのですが、これではもし関東大震災が起こらずに本来の天城が就役していたらどうするつもりだったんでしょうか(笑)。
しかし本当はそんな片仮名を見るまでもなく、両艦には決定的な違いがあります。この写真でも分かるとおり、赤城の艦橋は左舷にあり、加賀の艦橋は右舷にあります。煙突はどちらも右舷にあって、煤煙を舷側に向けて流す構造になっており、後の飛鷹型や大鳳、信濃が誕生するまで日本の主力空母の煙突の形態は変わりませんでした。これでは昔の蒸気機関車(SL)の旅と同じで、煤煙を吹きつけられる側にあった舷側の窓なんか換気もできずにさぞ大変だったことでしょう。
最近はこういう旧帝国海軍の艦艇についてネットで検索しようとすると、必ず『艦これ』とかいう余計なものを扱うサイトにヒットしてしまう、『艦隊これくしょん』というオンラインの艦隊育成シミュレーションゲームだそうで、一部のマニアには大変な人気だそうです。私の学生さんにも(女子を含む)この『艦これ』の“司令長官”になっているのが多いらしいが、まあ、きちんと本来の勉強もしてくれればそれでよい。
『艦これ』では旧帝国海軍の艦艇を美少女に擬人化しているのが人気の秘密かと思いますが、その美少女の最近の人気ランキングで空母加賀は駆逐艦島風に次いで堂々の第2位だそうです。美少女に擬人化するのも良いけれど、かつて精悍な艦影を誇ったこれらの艦艇も、戦後の飽食の時代ではたぶんこんなメタボな姿になっていると思いますけどね(笑)
 |
|
 |
ところで旧帝国海軍の関係者はなぜ赤城と加賀の艦橋の位置を別々にしたか。一説には作戦行動中の相互連絡が取りやすいようにするためだったそうですが、その話の前にまず新造時の赤城と加賀の特異な姿について…。
赤城も加賀もワシントン軍縮会議後に戦艦(巡洋戦艦)から生まれ変わった直後は飛行甲板が3段も積み重なった奇怪な姿をしていました。同時期にアメリカでも同じ事情で空母に改装されたレキシントンとサラトガは巨大な壁のような煙突が右舷に直立していて、やはりこれも奇怪な姿をしていた。それで世界の海軍関係者は奇怪な姿をしたこの日米の巨艦たちを“ビッグ4”と呼んでいたそうです。この4隻の奇怪な姿に興味がある方はぜひネット等で検索してみて下さい。
話を戻しますが、加賀は1934年から1935年にかけて、赤城は1935年から1938年にかけて大改装が行われ、奇怪な3段飛行甲板が廃止された後に、艦橋の位置はそれぞれ左と右に新設されましたが、こうしておけば赤城の左側を加賀が走ると、互いの艦橋が接近して手旗や発光による信号を交わしやすいと考えたらしいのですね。ですから実はこの写真の航行序列は左右逆なのです。
第一航空戦隊の赤城と加賀と同じく、第二航空戦隊の空母も飛龍は左舷、蒼龍は右舷に艦橋があった。同様に第五航空戦隊の瑞鶴と翔鶴でも当初の計画では翔鶴の艦橋を左舷に作るはずだったそうですが、いろいろ不具合が指摘されて両艦とも右舷艦橋になった。
ですから古今東西の世界の空母の中で左舷に艦橋があったのは赤城と飛龍だけと以前別の記事に書いたことがあります。にもかかわらず戦時中の“実写映像”と称して、例えば昭和19年のマリアナ沖海戦に出動した日本機動部隊とか言いつつ、平気で左舷に艦橋のある空母の遠景を掲載しているような商品の販売者の良識は信じられませんね。
それはともかく瑞鶴・翔鶴以降、なぜ日本でも空母の艦橋は右側に統一されるようになったのか。煙突と同じ側でないと煤煙が視界を遮るとか、気流が離着艦を阻害するとか、いろいろ言われてますが、私にはどれも決定的な理由には思えません。人間工学的な発想の欠如が根底にあったような気がします。
下の画像は15年以上も昔に坂井三郎さんの零戦をお借りして航空母艦瑞鶴から飛行した時のものですが、ちょっと懐かしいですね。もちろんフライトシミュレーターの画像ですが…(エッ、そんなの見りゃ分かるって?失礼しました)。その後に開発されたコンバットフライトシミュレーターではありません。フライトシミュレーターの基本ソフトに日本海軍ゆかりの航空機と古戦場のシーナリーを組み込んで作成しました。
まだ生きているWindows 95を起動してゲームを動かし、このサイトに掲載するための画像を保存しようと思ったら、まだJPEG画像が使えない機種、しかもUSBメモリー挿入口などあるはずもなく、CDドライブは壊れていた、仕方なく画面をデジカメで直接撮影しましたが、たかだか15年ばかりの間のパソコンの画像処理や外部記憶装置の技術の飛躍的な進歩に驚かされた次第です。
さて左上は空母瑞鶴の飛行甲板艦尾に待機中の零戦21型で、空母の左舷後方に秋月型防空駆逐艦が見えます。右側2枚が艦尾から艦首側を見た画像で、見れば分かるとおり、下のものは上の画像を左右反転しただけ、つまり上が実際の右舷艦橋の瑞鶴、下は左舷艦橋の仮想の空母“鶴瑞”です(笑)。
パイロットの視点から見て、どちらが離着艦しやすいか。当然パイロットの目には艦橋のでっぱりは障害物として映ります。これに衝突したら大変なことになりますからね。特に着艦の時は飛行機の舵の効き加減の狂いや、波浪による艦の動揺があるので、必ずしも離着艦ラインピッタリに降りて来れるとは限らない。ほとんどの場合は飛行機のお尻にあるフックを空母のワイヤーに引っ掛けて強引に停まりますが、もう一度着艦やり直しとなった時には、パイロットは艦橋から離れる方向に心持ち操縦桿を押さえ気味にしていくはずですし、実際にフライトシミュレーターのゲームでもそれは経験しました。
右側艦橋の空母では操縦桿を左へ、左側艦橋の空母では操縦桿を右へ、心持ち倒し気味にして艦橋をすり抜けるわけですが、この動作はどちらの空母の方がやりやすいか。パイロットは飛行機操縦教練の過程で、生来どんな左利きの者であっても主に右手で操縦桿を操作するように矯正されているはずですから、右側艦橋の空母では右手を内懐へ抱え込むように操作するのに対し、左側艦橋の空母では外へ払いのける操作になります。
抱え込む動作は腕の屈曲が主体で、これを行なう筋肉を屈筋群といい、逆に払いのける動作は腕の伸展が主体で、これを行なう筋肉を伸筋群といいます。私も神経生理学的なことまではまだよく勉強していませんが、たぶんヒトの場合、屈筋の方が伸筋より強くて精密に制御できる。
しかも操縦桿を握っている手の指は屈曲のまま、左側の艦橋を心持ち避ける時は前腕を伸展気味にしなければいけないのに対して、右側艦橋を避ける動作では手の指も前腕も屈曲になり、おそらくパイロットにとってはこの方が楽だったと思います。アメリカの空母はレキシントンもサラトガも、それに続くヨークタウンもエンタープライズもホーネットも、一貫して壁のような直立煙突と艦橋は右側に置いたままでしたが、たぶんパイロットの離着艦の操作性を第一に考えていたのではないでしょうか。
つまり日本海軍では空母の艦橋をどちらに置くかという課題を突きつけられた時に、パイロット目線ではなく、艦長や司令官が互いの信号を送りやすいとか、そういう上層部の使い勝手を優先したと思われますが、現場の感覚を大切にしない日本人上層部の欠陥が、こんなところにも表れていたと思います。
補遺
今回の話はここまでですが、空母の話を書いているうちにちょっと面白いことを思い出したので、艦橋の話題とは関係ありませんがついでに書いておきます。
世界の海軍艦艇情報を集めたジェーン海軍年鑑(Jane's Fighting Ships)という本がありますが、その1939年版の復刻版を見ると、1935年に改装が終わった加賀の新しい写真は編集にギリギリ間に合ったようですが、1938年に改装が終わっていたはずの赤城は3段飛行甲板時代の写真しかありません。ただし巻末の補足で赤城も加賀と同様の改装を終えた記載はあります。
ジェーン海軍年鑑編集部も仮想敵国だった日本海軍に関する情報の収集は困難を極めたと1939年版の前書きに書いていますが、例えば大型正規空母の翔鶴は「こうりゅう」というダミーの名前で建造されたため、中型空母である飛龍型の3番艦と誤認されていたようです。「ひりゅう」「そうりゅう」「しょうかく」とローマ字綴りが並べられていて、最初の2艦(飛龍と蒼龍)はドラゴンで、「しょうかく」は鶴の意味だから、もしかしたら新しいタイプの大型空母の可能性があると報じられていました。
さらに面白いのは、1939年版の巻末補足のページの最後にKADEKURU(かでくる)という正体不明の艦が1939年6月1日に横須賀海軍工廠で進水したとの報告があるという記載があります。翔鶴に関する情報の重複かと書いてありますが、進水日と進水場所はまさに翔鶴のものですから、確かに翔鶴を「かでくる」と誤解していたようです。この件は例の『艦これ』マニアの連中も知っていて、翔鶴→「かけつる」→「かでくる」となったと推測していますが、仮想敵国であった日本海軍の厳重な機密保持からよくこれだけの情報を知り得たものです。
『艦これ』マニアの多くは、アメリカは日本の軍艦の命名基準を知らなかったのかと揶揄していますが、そんなことはありません。上記のとおり、彼らも「しょうかく」は鶴の意味だから飛龍・蒼龍とは違うクラスではないかと正確に推理していますし、日本の空母は想像上の龍や鳥から命名されると知っていました。また一等駆逐艦は天然現象名から命名されることも知っていて、東雲、不知火、陽炎、子の日、五月雨、有明、狭霧などの意味もきちんとジェーン海軍年鑑に解説がありました。
核戦争の危機
2017年4月、核実験やミサイル発射実験など危険な国際的挑発行為を続ける金正恩体制下の北朝鮮に対し、トランプ新大統領のアメリカ軍は原子力空母を中心とする強力な打撃部隊を東アジアに派遣して、朝鮮半島の緊張が一気に高まっている。何かこの緊迫した国際情況って、多くの国民はあまり意識していないように見えるが、半世紀以上も昔に見たことがあるような…。
私は昭和26年のいわゆる“戦後”生まれだが、実は米ソ冷戦という時代の『戦争経験者』でもある。第二次世界大戦終結後、1950年代から1960年代初頭にかけての時期は、本当に人類がいつ核戦争で滅亡してもおかしくない時代だった。小学校に入学して、自分の身の回りのことから次第に世界のことにまで関心が広がっていく時期の私たちの目に映ったものは、人工衛星や有人宇宙飛行などの宇宙開発競争とともに米ソが進めている核弾頭や大陸間弾道ミサイル開発という軍備拡大競争だった。
宇宙開発だけなら科学バンザイで済むところだが、そういう人工衛星打ち上げ技術は大陸間弾道ミサイル技術と表裏一体であるという理屈まではまだよく分からなかったものの、これは相当ヤバイぞという危機感だけは、たぶん他のどの世代の日本人よりも強烈に感じていたのが私たちだったと思う。
第二次世界大戦で日本という国家自体の消滅の危機までを実際に身をもって体験した世代の人々は、今さら世界戦争が起こっても一体それが何なのと、妙に泰然とした雰囲気があったし、私たちより若い世代の人々は核ミサイルで抹消されるかも知れない自我もまだ発達していなかっただろうから、そんなに恐怖は感じずに済んだはずだ。
小学生からだんだん成長して大人になっていく過程、最近の世相では妙に達観している子どもたちも多いようだが、あの時代の少年少女にとって大人になるということは、少なくとも今の時代とは比べ物にならないくらい大きな夢であり、希望であった。早く大人になりたい、大人になったらあれをしたい、これもしたいという願いもあった。それが米ソの撃った核弾頭によって一瞬のうちに消えてしまう不条理は到底耐えられるものではなかった。
毎晩寝る前に、布団の中から天井板の木目や押し入れの襖の模様を必死に目に焼き付けようとした、それに何の意味があるかは漠然としていたが、これがこの世で目にする最後の物かも知れないという明確な恐怖に裏付けられた行為であったことは事実である。
そんな核戦争前夜の恐怖が頂点に達したのが1962年10月のキューバ危機、革命直後のキューバのカストロ首相が急速にソビエト連邦(ソ連)に接近、ソ連はその機に乗じてキューバに核ミサイル基地の建設を始めるがアメリカ合衆国の偵察機により探知され、米ソの対立は一挙に危険なレベルに達した、それがキューバ危機である。カリブ海という北アメリカ大陸の懐(ふところ)から核ミサイルを発射されてはアメリカも防ぎようがなくなるので、当時のケネディ大統領はカリブ海の海上封鎖を断行、基地建設資材や核ミサイルを運搬するソ連の貨物船に対してアメリカ軍は必死の妨害を行なった。
この間、アメリカ軍の強硬派によるキューバ空爆進言、ソ連潜水艦による核魚雷発射命令など、どれ一つとっても米ソ全面核戦争の引き金になったであろう危険な状況が頻発したにもかかわらず、現場にいた責任者の適切な判断や、アメリカのケネディ大統領とソ連のフルシチョフ首相の事態収束に向けての基本方針のお陰で未然に終わり、世界は滅亡まであと一歩の崖っぷちから生還して、皆さんも私が書いたこんなサイトの文章を読んでいられるのである。
あの時、米ソの誰か一人でも間違った判断を下していたら…、というより、もしあの時の国家の指導者がケネディとフルシチョフでなく、どちらかがトランプか金正恩だったら、人類の歴史は確実に1962年で終わっていたに違いない。東京オリンピックも大阪万博もなかったし、新幹線もジャンボジェット機もなかったし、人類の月面着陸もなかったし、パソコンもインターネットもなかったし、私は無念の想いを噛みしめる暇もなく絶命しただろうし、私の教え子たちなど生まれてもこなかった…。
今回の朝鮮半島危機、トランプと金正恩の危険なチキンゲームに1962年の時ほどの緊迫感がないのは、たぶんあの時はアメリカ合衆国とソビエト連邦という2大国の直接対決だったのに対し、今回は一方の北朝鮮など愚かな指導者がいくら粋がって突っ張ってみても、鎧袖一触でアメリカに吹き飛ばされ、まさか世界の滅亡にまでは至るまいと多くの人々が多寡をくくっているからだろう。
確かに北朝鮮のミサイル発射基地などは日米韓の偵察能力によって90%特定され、もしミサイルが発射されても日米韓の迎撃システムで90%撃墜され、弾道ミサイルを発射できる北朝鮮の潜水艦も90%以上は日米の潜水艦によって常時追尾されているだろう。万一米朝の“全面核戦争”になっても壊滅するのは北朝鮮だけ、アメリカおよびその同盟国に対する北朝鮮の攻撃は90%以上減殺されるはずだ。
…といって安心していられるのか。撃ち洩らした北朝鮮の核ミサイルが1発でも着弾(弾着)すれば広島・長崎を上回る未曾有の被害が出る。しかも狙われるのはアメリカ本土ではない。たぶん北朝鮮にはアメリカ本土を確実に攻撃できる能力はないし、あったとしてもその弾道ミサイルを探知・迎撃する時間的余裕はほぼ十分にあるだろうが、日本や韓国に対するミサイル攻撃は瞬時に対処しなければ国土は火の海になる。
キューバ危機の時のケネディ大統領もフルシチョフ首相も広島・長崎の被爆情況は熟知していた、というより核戦争の惨状については当時の世界中の指導者の共通認識だったと思う。あれを自国にやられたら大変なことになる…、だからケネディはアメリカ軍部の強硬論を退けてキューバを空爆しなかったし、フルシチョフも最終的にアメリカに譲歩してキューバのミサイル基地を撤去した。キューバのカストロ首相はいきり立ってソ連にアメリカへの核攻撃を進言する書簡を送ったというが、逆にそんな核戦争も辞さない若造と思われてフルシチョフからも距離を置かれるようになった。
今はそんな核戦争も辞さない若造が一方の国家の最高指導者になっており、もう一方の超大国もその名のとおりトランプゲームのような衝動で他国への空爆を決定するようなサイコパスとして、アメリカの精神科医たちが警告を発している人物、中国・ロシアの2大国とアメリカの同盟国首脳が適切に舵取りしなければ、北朝鮮の消滅と日本・韓国の国土の一部への核被害が現実のものとなる恐れがある。
キューバ危機のちょうど1年前の1961年、東宝から『世界大戦争』という映画が封切られた。私が小学校4年生の秋だった。世界は連邦軍(西側諸国)と同盟軍(東側諸国)の2大勢力が対立しており、さまざまな軍事的緊張や誤判断の末、ついに両陣営の大陸間弾道核ミサイルが発射され、ささやかな幸せを願って生きる一般の人々の切なる願いも空しく、全世界の大都市は次々と核爆発で消滅していくという、今考えても背筋が凍るような映画だった。
この映画は全世界に配給されたから、ケネディやフルシチョフとその側近たちも知っていたかも知れない、映画は観ていなくても広島や長崎の惨害を知っていたからこそ…としか思えない薄氷を踏むような和平への判断を選択できたのが1962年のキューバ危機、あれから半世紀以上を経て原爆の惨状は確実に風化しており、若造とサイコパスが核攻撃の権限を握って対峙している。
何事も起こらなければよい、明日も来週も来月も来年も同じように暮らせる世界が続いてくれればよい、政治にタッチできない一般国民にとってはそう願うことしかできない、その状況は『世界大戦争』の映画の当時と何ら変わっていない。
撤去された観音崎砲台レプリカ

先日あまりの好天に誘われてふと思い立ち、約1年半振りに横須賀から観音崎を訪れてみた。1年半前は海上自衛隊の観艦式から帰港する艦艇を陸上から眺めようと観音崎灯台に登ったのである。その時は海岸の遊歩道が一部工事中だったのを思い出したが、今回は工事も完了して突端の展望園地まで遊歩道沿いに行くことができた。
展望園地の緑地帯もすっかり整備されていたが、数年前までは“偉容(?)”を誇っていた右の写真のような大砲のレプリカが撤去されているのに気付いて、ちょっと感じるものがあった。この大砲は近づいて触ってみるまでもなく、チャチな木製の模造品なのだが、このモニュメントは観音崎の歴史、引いては我が国の国防の歴史を新たにさせる意義が大きいと思っていたので少々残念なことではある。ちなみにこの写真は5年前(2012年)に撮影したもの。
観音崎はその地形から考えて、東京湾に出入りする外国の艦船を監視する絶好の要衝であり、戦前までは一般国民の立ち入りも禁止されていた軍事要塞地帯であった。当然敵対する意志が明白な外国艦船を砲撃するための砲台は随所に設置されている。
現在展望園地になっているこの場所に実際に大砲があったかどうかは知らないが、それでも多くの観光客が訪れる場所に一見物々しい大砲のモニュメントを置くことで、国民に国防の在り方の歴史を多少なりとも意識して貰えていたと思う。江戸幕府もお台場に海上砲台を設置してペリー艦隊を城下の海面から退去させたが、明治時代以降は艦砲の発達により東京湾の入口である観音崎の防備を固めなければいけなくなった、しかし太平洋戦争後は航空機の発達により陸上砲台の重要性は薄くなった、それが国防の歴史であり、現在我々一般国民が気軽に観音崎に立ち入れる理由でもある。
かつて各国とも慣習的に海岸線から3海里(海里は地球の緯度1分相当の1852メートル)までを領海としていた時代があったが、これは当時の艦砲の射程距離を考慮したためと言われている。つまり3海里以内の水域に無断で入って来た艦船は海岸線の国土を砲撃できるので、自衛のためにこれを砲撃して撃沈してもよいということである。
そういう武器が絡む歴史を、とにかく軍国的といって頑なに教えようとしなかったのが我が国の戦後の戦争教育であった。兵器の進歩とともに当然世界各国の国防の考え方も変遷し、何とか不要な紛争を避けるためにさまざまな国際慣習もできる。国防の歴史とは、戦争するための歴史ではない、いかにして戦争を未然に防止するかという歴史の意味合いの方が強いと私は思っている。
戦争を知らない頭脳の持ち主は、戦争か否かという選択を迫られる局面に至った時には国家権力側に操作される情報に簡単に踊らされてしまう、私はそのように予言したが、現在の日本はまさにそのとおりに動いているように見える。いわゆるリベラル側の人々はさまざまな情報媒体を通じて自民党安倍政権を批判しているが、多くの国民がそんな人々に耳を傾けないようになった原因は、行き過ぎた反戦反軍教育によるところが大きいのではないか。
自衛隊は税金泥棒、敵が攻めて来たら白旗を上げりゃいい、鉄砲大砲ナンセンス、アメリカは帝国主義だからソ連と結べ、そんな幼稚な反戦原理で戦後の国民を“洗脳”してきた自称リベラル集団が、現在の安倍政権独走の精神的基盤を築いたと言ってよい。弾丸さえ撃たなきゃ世は平和…と洗脳され続けてきた国民の目の前に、頭越しにミサイルを撃つ奴がいる、島を奪いに来る奴がいる、戦後の反戦教育を受けた国民の思考は現在メチャクチャに混乱している。それでもいかにして戦争を避けて問題を解決するかというのが防衛問題のはずなのに、国民の中にはすぐに戦争に短絡する思考回路が整ったと思う。昭和16年の対米戦争の時もおそらくそうだったのではないか?
観音崎の大砲のレプリカは古くなって薄汚れてきたから、あるいは子供が登って危険だから撤去されたのかも知れないが、それなら代わりのモニュメントを設置すれば良い。この大砲が火を噴くような仮想の歴史の舞台とはどんなものだったのか、ここを訪れた人々がそれを学習できるような機会を奪ってはいけない。
友好親善のために外国の港を訪れる軍艦は港外で礼砲を発射することが多い。皇族が乗っている場合は21発とか弾丸数の規定もあるようだが、これは19世紀頃の大砲は筒先から次の弾丸を装填する先込め式だから、1発撃ってしまうと砲身をいったん艦内に引き入れないと次の弾丸を撃てない、だから港外で礼砲を撃つという行為は、現在では単なる儀礼と化しているが、もう我が艦は貴国を砲撃しませんよという意志表示であり、これに対して陸上の砲台も、我が国も貴艦とは戦闘しませんよという意味で大砲を発射してそれに応える。
そういう国際親善の意味も知らず、昭和39年の東京オリンピックの時、開会式で陸上自衛隊が国立競技場外で礼砲を撃ったのはけしからんと批判した無知な平和主義者が多かったのを思い出す。世界各国から選手を招く平和の祭典に、何で戦争放棄した我が国が戦争の真似事などするのかという実にナイーブな論調であったが、礼砲を撃たなければ、それは我が国の大砲はいつでも弾丸を込めてお前を狙っているそという威嚇の意味になる。何でもかんでも反戦反戦と叫んでいた戦後平和教育の無知ぶりを、私はあの時に垣間見た気がしている。
懲りない人たち
2017年7月6日、原子力規制委員会の田中俊一委員長(物理学者)が関西電力の原子力発電所がある福井県の高浜町を訪れて地元住民と意見交換会をした際、“不適切な失言”があったとの報道を読んだ。北朝鮮のミサイル攻撃について質問されて、「小さな原発にミサイルを落とす精度があるかどうか分からない、私なら東京の真ん中に落とした方が良いと思う」と述べたとされ、後で報道陣から不適切ではないかと指摘されて、発言を撤回したとのことであった。
北朝鮮から原発にミサイルを撃ち込まれたら大変なことになるから、きちんと対策ができているかどうかについて住民も質問したのであって、それに対して田中委員長は「たぶん北朝鮮には原発にミサイルを精密に誘導できる技術は無いだろうから安心して良い」と答弁したつもりなのであろう。それがちょっと調子に乗って余計なことに口を滑らせてしまったというのが実情と思われる。
彼は「もし自分が北朝鮮の司令官なら、原発を狙うよりも戦略的な要衝として東京を狙うよ」と冗談半分で発言してしまった。最近では政治家も次々と失言を繰り返して呆れてしまうが、元々理科系人間の委員長にとって自分の口から出た言葉が相手にどう受け止められるかという配慮が足りなかったのは致し方のないことである。
しかし私が“懲りない人たち”と言っているのは、田中委員長の“失言”を不適切ではないかとしか指摘できない報道陣の方であって、突っ込みどころはそこかよと何とも情けない思いである。皆さんも委員長が東京の真ん中にミサイルを落とすと発言したその言葉尻の一部だけを捉えて不謹慎だ、けしからんと憤慨しているだけでは、我が国は再び未曾有の被害を蒙る恐れがあるのではないか。
田中委員長の発言の要旨は、上にも赤字で強調したが、
たぶん北朝鮮にはミサイルの精密誘導技術はない→北朝鮮のミサイルは脅威ではない
という論理に基づいている。これが6年半前の未曾有の災害の時と同じであることを指摘して突っ込めない報道陣の情けなさ、東京にミサイルというセンセーショナルな言葉にだけ感情的・情緒的に反応しているだけだ。我が国の原子力行政はまたしても原発に対する北朝鮮のミサイル攻撃を“想定”していないではないか。
たぶん地震が起こってもそれほどの津波は来ない→原発にとって津波は脅威ではない
この独り善がりな判断によって我が国は2011年の3月に大きな痛手を受け、我が国ばかりか地球の環境に有害な放射性物質をいまだに垂れ流し続けているのである。原子力行政のトップを牛耳る人間たちの頭脳がいまだに6年半前と変わらぬことが暴露されたことも重大だが、それを追求するマスコミの能力不足も明らかになり、この国はこれからどこへ漂流していくのか不安は大きくなるばかりだ。
補遺:確かに田中委員長は大型航空機の敷地内墜落は想定しているから、ミサイル攻撃も同様に対処できると述べたらしいが、大型航空機の不慮の事故ではパイロットも原発上空から進路を外そうと最後まで努めるであろうと期待できるのに対し、最初から原発を破壊しようと超音速で突っ込んでくるミサイルも同じレベルで考えていることの危うさを同時に指摘しておきたい。
軍歌の時代
もう8年以上も前のことであるが、別のコーナーの記事で沖雅美さんが昭和40年代に歌ってヒットさせた『ポーリュシカ・ポーレ』という歌の原詩に関する資料を見つけたらご紹介するとお約束しながら、いまだに果たしていなかったことを思い出した。しばらく前に入手した辻田真佐憲さんが著した『世界軍歌全集』(社会評論社:2011年)という膨大な資料集の中に、この歌の原詩の翻訳も記載されていたのでちょっと代表的な部分を抜粋してみる。
その前に昭和46年に沖雅美さんが歌った歌詞をあるサイト上に見つけたので書き出しておく。
ポーリュシカ・ポーレ(作詞:橋本 淳)
緑もえる 草原をこえて
ぼくは行きたい
あなたの花咲く 窓辺へと
雲ながれる ロシアの大地に
二人の愛はめばえて
明日へとつづくのさ
忘れな草 胸に抱きしめて
別れをおしんだあなた
やさしく抱きしめたい
ポーリュシカ・ポーレ
それは愛のことば
二人だけの ちかいさ
永遠に 消えはしない
谷間をこえ 野原をよこぎり
あなたをめざして
ぼくは 今日こそ旅に出よう
夏の嵐 冬の木枯らしを
くぐりぬけたら
あなたの 笑顔が待っている
雲ながれる ロシアの大地に
若い二つの 生命が
寄りそうように もえる
ポーリュシカ・ポーレ
それは愛のことば
二人のこころのちかい
永遠に消えはしない
…とまあ非常に甘ったるい愛の歌であるが、辻田真佐憲さんの『世界軍歌全集』に紹介されたロシア語の原詩はまるで違う。確かにあの軽快なテンポのメロディーはロシア語の原詩にこそふさわしいと思われるが、ちょっと長いのでその翻訳を一部抜粋して書き出してみる。
ポーリュシカ・ポーレ(作詞:ヴィクトル グセフ)
平原よ、平原よ、
広茅(こうぼう)万里の大平原よ!
われらが大地を赤軍の
英雄たちは駆け抜ける。
乙女らは涙する、
今も悲しみに暮れて、
その上に大事な人は
軍隊へ行ってしまった。
乙女らよ、見てくれ。
見てくれ、われらが行く先を。
延延と遙かに続く、
この実に愉快な道のりを。
(省略)
この目に映るのは、
黒く濁った雲ばかり。
敵の憎悪は森影より
群雲なして押し寄せる。
乙女らよ、見てくれ、
敵を迎える備えはあるぞ。
われらの馬は駿足で、
われらの戦車も快速だ。
空なる黒雲を
峻厳な飛行士がが監視する。
潜水艦は疾駆して、
艦船が警戒態勢に着く。
(省略)
乙女らよ、見てくれ、
乙女らよ、涙を拭え。
一際高く歌って欲しい!
われらの戦闘歌を。
(第1節繰り返し)
何というギャップ。一部省略したが、元歌の意味は大体掴めたと思う。広茅とか延延とかはワープロ変換できない別の漢字で示されていたり、私が以前目にした赤軍合唱団のカセットテープに付いていた歌詞カードとは微妙に単語が異なったりしているが、沖雅美さんのヒット曲のような男性が恋人を求めて旅立つロマンスの歌ではない。男たちは恋人を故郷に残して戦いに赴く勇壮な歌なのである。
『世界軍歌全集』には日本を除く40ヶ国以上の国々から300曲もの愛国歌、国民歌、戦時歌謡など、いわゆる軍歌が掲載されているが、味方を讃えて士気を鼓舞し、敵を卑しめて憎悪を煽る内容のものが圧倒的に多い。これらを普通の言葉で演説すれば最近ではいわゆるヘイト・スピーチとして疑惑や嫌悪感を募らせる人も多いが、勇壮あるいは甘美なメロディーに乗せて国民に訴えれば、おそらく人々の潜在意識に作用して、それほど抵抗もなく国家のプロパガンダやスローガンを浸透させることができるのだ。
これも音楽の力なのだろう。300曲もの軍歌の歌詞をパラパラと眺めるだけでも、古今東西の各国の権力者たちが、いかに歌の力を利用して兵士や国民の士気を煽り立てようとしたか、その苦心の跡を偲ぶことができる。私も昔高校の吹奏楽部時代に演奏したマーチの名曲『旧友』にも『錨を上げて』にも士気を鼓舞する勇ましい歌詞が付いていた。
そういう勇壮な歌詞に混じって、『ポーリュシカ・ポーレ』のように恋人を故郷に残して戦いに出陣する男性兵士を歌ったものも見られる。最近では我が国にも婦人自衛官がいるように、各国とも戦争は必ずしも男の専売特許ではなくなったが、それでもやはり父を、夫を、恋人を、息子を戦場に送り出すのは女性であるという一般的な構造はそう大きくは変わらないだろう。
社会主義革命を成功させたソ連で特に顕著だったのだろうが、国外にナチスドイツという明白な敵がいるばかりか、他の資本主義諸国からも警戒され、国内情勢も不安定で国の存続さえ危ぶまれた時代には、そういう女性からの情緒的な反戦感情や厭戦気分は放置できなかったに違いない。『ポーリュシカ・ポーレ』だけでなく、あの有名な『カチューシャ』もリンゴの花ほころぶ岸辺に立つ娘の恋人は国境警備に出動しているのだし、『灯火』の娘の恋人の男性も海山遠く隔てた地で祖国の灯のために戦っているのである。我々はこれらの歌を単に“ロシア民謡”などと分類しているが、本当は“ロシア軍歌”と言った方がふさわしいかも知れない。
そして今、あの第二次世界大戦前夜のソ連と似たような状況が全世界を覆いつつあるのではないか。地球という星の環境が全人類の最大限の繁栄を約束できるものでないことが次第に明らかになってきた。もはや国内外に敵を抱えた革命後のロシアなんてものじゃない。いずれ国家同士が寸土を争い、食糧を奪い合う凄惨な時代が到来するのではないか。
そういう悲劇的な時代の予兆は先ず歌に示されるのではないかと思っている。祖国のために戦う兵士たち(特に男性)を送り出し、涙をこらえてその無事を祈るような歌が人々の口に上るようになった時、それは新たな大戦争の時代の序章となるであろう。
日本と北朝鮮、戦争の相似形
最近の記事でも書いたが、金正恩の北朝鮮は大陸間弾道ミサイル発射実験や核実験を繰り返して国際社会への挑発姿勢を強めており、今や“東アジアのならず者”として悪名を馳せている。我々現代日本人の多くは、最大限の経済制裁でも軍事基地への先制攻撃でも何でもやって、さっさと金正恩を抹殺してしまえ、アメリカの強大な軍事力と経済力で北朝鮮を潰してしまえ、何でロシアや中国の指導者どもはあんな“ならず者国家”を庇うのか、と極論に近い考え方にまで傾いているのではないか。
あといくら“ならず者”であっても、まさかあの強大なアメリカに喧嘩を売るような真似は金正恩にはできまい、さまざまな挑発も恐喝もせいぜい負け犬の遠吠えに過ぎないという楽観論も多くの日本人に共通していると思われるが、そういう楽観論に根拠はない。我々日本人の先祖もやった暴挙、国家の運命をまるごと賭けてアメリカに刃向かったのは大日本帝国の方が先輩格と言うべきだ。我々の先祖でさえやったことを、どうして北朝鮮の指導者がやらないと断言できるのか?
私はここに80年近い年月を隔てた歴史の相似形を見たような気がした。そしてその相似形を見た時、私にはさらに恐ろしい歴史の可能性が見えてきた。
あの1941年(昭和16年)の真珠湾攻撃、昔からアメリカのルーズベルト大統領の陰謀だったという説はあったし、最近ではアメリカの大統領経験者フーバー氏の回顧録もそれを裏付けるものとして邦訳が出版される運びになっているようである。狂人ルーズベルトが戦争したくてたまらず、1941年7月に日本に対する全面的な経済制裁を実施する、それはいかなる国も戦争せずには済まなくなるほどひどい内容だったとして、当時の大日本帝国の立場を結果的に擁護する内容であり、我々日本人の耳には心地よく響くものであろう。
1920年代の世界恐慌から立ち直るためには、ここらで一発戦争したい、とりあえずは日本を経済制裁で挑発して相手に最初の弾丸を撃たせ、こちらはそれを受ける形の理想的な口実の下に戦争状態を作り出そう、それはルーズベルトならずとも資本主義の元締めであれば誰でも考えそうなことであり、そういうことのできる政治的権力を持ったルーズベルト大統領がそれを最終的に実行したということである。
この推理が正しいか正しくないか、絶対的な歴史の真理は永遠に分からないものだが、日本人としては我々の先祖だけが悪かったわけではないということだから、こういう論説を受け入れたくなる気持ちは当然である。ではこのルーズベルト陰謀説を受け入れた場合、次に大日本帝国を北朝鮮、ルーズベルトをトランプと言い換えた時に見えてくる歴史の相似形は実に恐ろしいものである。
北朝鮮に最初の1発を撃たせておいて、アメリカはおもむろに反撃を開始、相手に弁明の機会さえ与えないようにしておいてから徹底的に叩き潰す、もし真珠湾陰謀説が正しければ、これが今度の対北朝鮮のアメリカの戦略となる可能性が高い。アメリカは日本に最初の弾丸を撃たせるためにはハワイにいた自国の艦隊でさえ囮の生贄として利用したのである。北朝鮮に最初の1発を撃たせるための生贄になるのは何だろうか?しかも北朝鮮に最初に撃たせるのは魚雷や爆弾ではない、正真正銘の核弾頭である。
北朝鮮の核弾頭など恐るるに足らず、と思っている人も多いだろうが、先の記事にも書いたとおり1発でも国土に落下すれば広島・長崎を上回る惨劇となるのは間違いない。アメリカの報復が恐いから日本や韓国に核弾頭を落とすはずがない、とか、どうせ北朝鮮には精密に核ミサイルを目標に誘導する技術がない、などと言って楽観できるものではない。我々日本人の先祖だって、世界中が予想もしなかった高性能の戦闘機を積んだ機動部隊をもって大国アメリカにパンチを食らわせたことを忘れてはいけない。
最近の北朝鮮の大陸間弾道弾(ICBM)実験に関連して、北朝鮮は核弾頭をEMP攻撃(電磁パルス攻撃)に使うかも知れないとの記事があった。これは高々度で核爆発を起こせば、発生したガンマ線が空気の分子から電子を叩き出して瞬間的に地表に向かう電磁波を作り出すことを利用した攻撃であり、敵国上空で核爆発を起こせば広大な国土全体にわたって送電システムや情報機器を破壊することができるので、精密誘導技術がなくても敵国に致命的な被害を与えることが可能である。
なあんだ、高々度での核爆発なら人は死なないじゃないかと思うかも知れないし、9月9日には我が国の小野寺防衛大臣も北朝鮮がほのめかしているEMP攻撃などあまりに唐突で現実化するとは思えないと能天気なコメントを出したらしいが、仮に北朝鮮が従来のミサイル実験と見せかけて核を搭載したミサイルを我が国上空を通過させ、そこで核爆発を起こせば、それがたった1回であっても日本は壊滅するのである。
1984年にストリーバー氏とクネトカ氏が発表した『ウォー・デイ(Warday)』という小説、翌年には邦訳も刊行されているが、この中にはEMP攻撃の恐ろしさが十分描かれている。この小説中では、1988年10月28日(発行時点では近未来)にアメリカとソ連の核戦争が勃発、それまでの予想とは裏腹に全米や同盟国の都市が次々と消滅していくような全面戦争に発展することなく、最初の数発の核ミサイルの撃ち合いだけで両国の国家機能が完全に崩壊してそれ以上の戦争継続が不可能となり、アメリカも核弾頭の直撃を受けた少数の都市だけが破壊されたものの、国土の大部分は核爆発による消滅を免れた、しかしソ連のEMP攻撃による送電システムや電子機器のさまざまな障害の結果、戦争当日に核爆発の犠牲になったアメリカ国民の10倍以上がその後数年間のうちに死亡した。そんなことが次から次へとドキュメンタリータッチで描かれている小説だった。
EMP攻撃による被害についても、全米の広範囲でコンピューターが破壊されたために自動車のエンジンがかからなくなった、もっと恐ろしいことに北米大陸を飛行中だった旅客機のほとんどが墜落した、送電が停止したために医療や交通や商品流通や食糧生産などが打撃を受けて、膨大な数の国民が死亡した、などと書かれている。
アメリカや韓国などは重要な国家機能を担うコンピューターには電磁遮蔽を施すなど、EMP攻撃の防御対策を進めているが、日本は遅れているらしい。別にそんなこと改めて言われるまでもなく、北朝鮮がEMP攻撃をほのめかすや、国民の動揺を防ごうと防衛大臣が気休めのコメントを発表するなど、我が国の戦争対策など今も昔も同じレベルなのかと溜め息が出る。
日本人の戦争は攻撃一本槍、防御に金を費やすよりは目に見える攻撃成果を上げることにばかり目が向いている。起こるか起こらないかさえ不確実な北朝鮮のEMP攻撃に備えるよりは、確実に金になる経済政策に投資した方が良いと思っているのだろう。津波対策に投資しなかった原子力発電所の二の舞である。第二次世界大戦中、運動性能と重武装ばかりを重視して、パイロットや燃料タンクの防御に手を抜いたために、そこに1発か2発被弾しただけで撃墜されたゼロ戦(零式艦上戦闘機)や一式陸攻(一式陸上攻撃機)の戦訓は生かされていない。
東京水害の記憶
近所にあった広大な空き地にこの春先から建設業者が入り、10数軒もの個人住宅が一斉に新築されている。最近は建築工法も進歩しており、どの住宅も秋頃には完成してしまうらしい。ついこの前まではだだっ広い更地だったのに、3ヶ月ばかりの間にもう立派な住宅街の様相を呈している。
未来の住宅街を歩きながら気付いたのは、その8割方の新築家屋の土台がコンクリートなどでかなり高く盛り上げられており、玄関を入るまでに数段以上の階段を昇らなければいけない構造になっていることだった。このバリアフリーの時代にこれでは高齢者は居住できないだろう、若夫婦だって歩き始めた子供が階段の手すりの隙間から転落して大怪我を負うことだってあるだろう、と心配になったが、おそらく住宅を設計した建築士たちは来たるべき災害対策を考えているのではないかと思い当たった。
私の小学校時代の社会科の教科書に『キャサリン台風』による水害の記載があったのを覚えている。昭和22年9月に関東地方を襲った大型台風で、利根川や江戸川の堤防が決壊、群馬県や栃木県で多数の死者を出した他、東京都内でも死者が出て、7万軒以上の住宅が床上まで浸水した大災害であった。現在では『カスリーン台風』と表記されるが、私たちの小学校の教科書には確かに『キャサリン台風』と書いてあった。
昭和22年といえば日本はまだ占領下にあり、台風にも女性の名前が付けられていたらしい。アメリカでは、最近は知らないが、台風(タイフーン)もハリケーンも女性の名前を持っていて、荒れ狂う暴風雨はまるで女性のようだと…(失礼)、カミさんの名前の付いた台風など来襲したら世の男性は恐くて逃げ回るしかないか…(笑)、日本に来るはずの台風にはどこか他の国に不倫して欲しいとか…(爆笑)。
冗談はともかく、社会科の教科書に『キャサリン台風』の水害と題して、バスの車体が半分まで水に漬かった写真が掲載されていた。当然小型乗用車などは完全に水没したであろう。思えばここ数十年以上も東京には道路が川になるような大規模水害は起こらず、九州や広島など全国各地で多数の犠牲者を出すような水害が毎年のように発生していたにもかかわらず、東京だけは水害とは無縁の都市のような幻想があった。まあ、この間の治水工事の成功のお陰だが…。
別の記事でも紹介したが、皆川典久さんの『東京スリバチ地形散歩』(洋泉社)という本によれば、東京はかつて何本もの川が武蔵野の洪積台地を浸食してできた意外に起伏の大きな土地、この本の第1巻と第2巻の随所に出ている地形図を見てまずギョッとするのは、東京山手線の東側、埼玉県から神奈川県にかけて京浜東北線が走っているあたりから海側には、海抜1メートル2メートルという低地が広がっていることだ。つまりここがかつての武蔵野台地が海に落ち込む“海岸線”であったということらしい。東京駅から皇居にかけてはかつての入り江だった。
こういう低地に水が溢れれば、現在の東京の都市機能は壊滅する。今では都内に網の目のように張り巡らされた地下鉄とか、人々で日夜混雑する迷路のような地下街とか、こういう地下空間を通って濁流は信じられないような場所にまで侵入するだろう。
こんな事態が起こるのは地震による津波だけではないそうだ。最近youtubeで話題になっている『荒川氾濫』という動画(国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所作成)を見たが(“荒川氾濫”と検索すればヒット)、埼玉県の荒川上流域に3日で500ミリ以上の雨が降ると荒川の堤防が決壊する恐れがあるらしい。もうすでに400ミリを越す雨量は実際に記録されており、このまま地球温暖化によって熱帯気候に近づいていけば、東京の堤防決壊は時間の問題ということだ。
この動画では深夜に堤防が決壊したことになっており、油断していた住民の犠牲が大きくなることを警告しているが、地下鉄や地下街の被害はゼロであったとやや楽観的な想定になっている。もし昼間に洪水が起きれば、今度は東京は安全と信じ切っている都会在住者や通勤通学者、それに言葉の通じない外人観光客などによってパニックが起こり、この動画での死者想定は千人単位であったが、その数十倍規模での犠牲者が出るに違いない。
震災ばかりでなく、首都圏に暮らす人はこれからは水害にも警戒しなければいけないと胆に銘じたが、最初の新築住宅の話、土台を高く作っていたのは荒川や利根川の水害が懸念される地域ではない、私が現在住んでいるのは武蔵野洪積台地の高台に当たる練馬区だが、ここらへんでも近年は思わぬ水害が発生している。今年(2017年)7月18日、練馬から池袋にかけて雹の混じった1時間100ミリほどのゲリラ豪雨が襲ったが、我が家の半地下式のガレージが水没してかなりの被害を受け、こんな高台でも土台を高くしなければ雨を防ぎきれない気候になってきているのを痛感した。個人住宅の半地下倉庫や地下室など論外、10年ほど前には私の実家近くの新宿区の落合で、豪雨の最中に住宅地下室の収納品を心配して降りてきた住人の方が水死されている。そもそもこの“落合(おちあい)”という地名、神田川と妙正寺川の2本の川が落ち合う場所という意味であり、高台でありながら洪水の起こりやすい地形であることを暗示している。
護憲派リベラルの過ち
2017年(平成29年)10月22日に行われた衆議院総選挙では、政策として憲法に自衛隊を明記する改正案を掲げた安倍自民党が公示前の284議席を堅持して圧勝、公明党の29議席を合わせて与党313議席を獲得するという結果にいわゆるリベラルと言われる護憲派の人々は相当の衝撃を隠せないようだが、こういう世界情勢の中でこういう選挙結果が出ることは、私はすでに半世紀も前から予想していたことである。
都知事選と都議会選で圧勝した小池百合子党首率いる希望の党から踏み絵を突きつけられて分裂させられた形の民主党など、野党の選挙協力の失敗を敗因に上げる人もいるが、私に言わせれば今回の野党敗北の原因はずっと以前にあった。今回の選挙で有権者が雪崩を打って安倍自民党に投票した原因はいったい何だったのか。戦後一貫して自衛隊を憲法違反として否定するだけの政策しか打ち出せなかった野党の国防方針が破綻したということではないのか。
ちなみに私の立場は護憲である。現憲法の第9条は一言一句変えてはいけないと12年前の記事に書いている。すでに自衛隊は現憲法下でも十分な国防方針を立てることができる“合法的”な軍事組織なのだから、憲法条文とのギャップもグレーゾーンとして折り合いをつけていけば良いのであって、今さら憲法に自衛隊を明記すれば、その明文化された条文をもとにさらなる新たな拡大解釈がなされるだろうとそちらの記事で危惧した。
しかし戦後の社会党も共産党も一貫して自衛隊を憲法違反の悪玉として否定し続けた。本当は自衛隊を完全否定するつもりは無かったはずなのに…である。
1994年自社さ連立政権(自民党+社会党+さきがけ)で首相となった社会党の村山富市党首は、海上自衛隊の観艦式でにこやかな笑顔を見せてご満悦だったし、共産党に至っては日本国憲法成立に当たって真っ先に憲法第9条に噛みついた。祖国を共産圏に売り渡す際に第二次対米戦争までを企図していたとしか思えないその偽善に関しては別の記事に書いた。
本気で自衛隊を否定する気もなかった社会党と共産党であったが、自衛隊は憲法違反です、自衛隊があると戦争になってしまいます、憲法を護りましょう、自衛隊は税金泥棒です、災害救助隊に組織替えしてしまいましょう、そういう口当たりの良いスローガンを叫んでいれば、戦争したくない有権者の支持を得られる、国民は誰だって戦争などしたくないに決まっているが、憲法護持=戦争反対・自衛隊反対という手っ取り早いスローガンで有権者の心情に訴えるしか能の無かったのが、戦後の社会党・共産党とその流れを汲む護憲派リベラル集団だったのだ。
昭和年代はまだ良かった。そんなことを言っていれば恒久平和が実現しそうな夢を見られる時代だった。しかし最近になって国際情勢が激変した。最近の記事でも書いたように、弾丸さえ撃たなきゃ世は平和…と護憲派リベラル集団に洗脳され続けた国民の頭越しにミサイル発射実験を強行する国がある、歴史的な領有権にケチをつけて我が国の領土を艦艇や航空機で脅かす国がある。昭和の時代であれば、根気よく話し合いで…とか、国際世論に訴えて…とか甘いことを言っていれば何となく丸く収まりそうな雰囲気もあったが、そんなことで解決できる国際問題でないことは誰の目にも明らかになってきた。
そんな情況で行われた今回の選挙戦、護憲派の党首がいくら「憲法無視する安倍政権を倒しましょう」と声を振り絞ったって勝てるわけがない。安倍政権による憲法破壊を危惧する有権者の多くは、もっと現実的な政策を期待できそうな立憲民主党に投票したようだ。議席数の変化がそれを物語っている。
立憲民主党は、希望の党の小池百合子党首から憲法改正の踏み絵を突きつけられて“排除”された旧民主党系らしいが、中国や北朝鮮の横暴があってもなお日本国憲法を護ろうという有権者はまだ多いのである。その人たちの票を集められなかったのが、社会党や共産党の流れを汲む旧護憲派だったのだ。
社会党や共産党が自衛隊を合憲とする国防方針に転換する最後のチャンスだったのが、ピースボートという市民団体のチャーターする客船がソマリア沖で海上自衛隊に護衛して貰ったという2009年の例の事件の時。このピースボートという団体は、社民党から民進党に鞍替えしたりする節操のないリベラル系議員であった辻本清美氏が学生時代に起ち上げたものである。当時はソマリア沖で武装海賊団による船舶襲撃事件が頻発していて、日本も国際協力で海上自衛隊の護衛艦を派遣していた。ところが辻本議員のピースボートは護衛艦派遣反対に名を連ねていたにもかかわらず、自分の身が危なければ守って欲しいと泣きつく、そんな身勝手な行動にしか見えない“事件”が起きた時も、社会党(社民党)も共産党も見て見ぬふりを押し通した。
思えばあの時に国家や国民の安全を護るために、自衛隊と憲法条文のすり合わせを行なっておくべきだったのではないか。それまでの自分たちの主張が現実に合わなくなっていることを率直に認め、国民の前で国防方針の転換を明らかにしておくべきだったのだ。その後、尖閣諸島近海がキナ臭くなり、頭上をミサイルが通過して行くような時代になって、いくら基本的人権尊重を謳った憲法の大切さを訴えたところで、多くの有権者が聞く耳を持たなくなってしまったのは致し方ないことであろう。
『学問のすすめ』のすすめ
先日九州へ出張で東海道・山陽新幹線を利用した折、持て余した時間で福沢諭吉の『学問のすすめ』など読んでみようと思い立った。東京~博多の所要時間は約5時間、私が小学校1年生だった昭和33年に国鉄最初の電車特急こだま号が東京~大阪間を6時間50分で結んだのが驚異的と賞賛された時代に比べて隔世の感があるが、それでもやはり5時間というのはかなりまとまった空き時間である。
それで『学問』でもしようかと…(笑)、最近ではこういう著作権の切れた書物だとか、著者の許諾を得た書物などの多くが、青空文庫というインターネット上の図書館に電子ファイルで収納されており、それこそ思い立ったらいつでもどこでもスマートフォンなどからアクセスして読みたい放題である。これもまた隔世の感であるが、高速鉄道にしろ、インターネット上の図書館にしろ、確かに明治時代に始まった文明開化の波が平成の世において到達した地点を示していると言ってもよいだろう。
しかし江戸時代末期の1835年に中津藩士として生まれて蘭学を修めた福沢諭吉の頭の中では、汽車が走ったり電信が通じたりする機械文明よりも、一般の人々が日本国民として成熟することの方を文明開化として捉えていたように思う。
「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」と言えり。
『学問のすすめ』冒頭のこの有名な一節は伝聞形で書かれているが、おそらく西欧流の人間平等の思想を啓蒙しようと意図したに違いない。江戸時代までは人々の身分は「士農工商」、すなわち武士・農民・職人・商人の4つに区分され、よほどのことが無ければ身分は固定されていて、人間は生まれた時の身分のまま一生を終えるのが当たり前であった。
受験戦争もなければ出世競争もない、まあ、ある意味で気楽と言ってしまえば気楽な時代であったが、近代国家として生まれ変わった日本では、その情況がガラリと変わった。明治時代以降の人々は「日本人」という国民として一括りにされる、努力次第で偉くもなれるし、もちろんその逆もある。だから努力して学問を修めなさい、というのがザックリ言った『学問のすすめ』の内容である。
江戸時代は武士が一番偉くて、次が農作物を作る農民、次が道具を造る職人、一番下が生産活動をしない商人というように、生まれながらに厳然と身分が固定されていたが、これからは日本国民は皆が同じ権利を認められた平等な人間として尊重される、その中で努力して学問した者は偉くなり、サボった者は落ちぶれる、偉くなった者は努力した結果なのだから恨んだり妬んだりするんじゃないよ…と、まるで現代の教育ママも真っ青な物の言い方である。まさか福沢諭吉がここまで書いていたとは思わなかった、
士農工商のいわゆる四民に分かれていた時代は、下の身分の者はとにかく武士階級の偉い人にはペコペコしておけば間違いなかった。どんなに理不尽でも、どんなに自分が正しくても、武士の方が偉いと一方的に決められていたのだから仕方がない。しかしこれからは武士も百姓も町人もない、人間はすべて平等な機会を与えられた対等な存在なのだから、国民1人1人が自立しなければいけない、国民が自立すれば国民の集合体である日本という国家の独立もまた確固たるものになる、というのが福沢諭吉の言わんとすることであった。
福沢諭吉の考え方が本来の人間平等の思想なのだろう。「平等」とは機会が平等なのであって、地位や身分が平等なのではない、学問をすればそれなりに重要な仕事にも就くようになるが、ただし重要な仕事に就いたからといって威張ってはいけないというようなことも書いている。職業の貴賎によらず、人間の生まれつきの価値に上下はないからだ。ただの立身出世主義ではない。
最近ではあおげば尊し2番の歌詞が歌われなくなって、21世紀に生きる我々は、学問によって自分を高めて重要な仕事に就くことを“立身出世主義”とか“学歴偏重主義”とかいって毛嫌いするようになったが、その反面、相変わらず士農工商時代のように身分や地位が上の人間にはペコペコ卑屈に振る舞っていれば大過ないと思っている人間が多くはないか。学問して重要な仕事に就いたことを鼻にかけ、自分の価値が上がって偉くなったと勘違いして威張り散らす人間も多いし、また「長い物には巻かれろ」とばかり、そういう輩を必要以上にヨイショする人間も多い。あの世で福沢諭吉がこれを見たら、何だ、日本の文明開化はまだまだ先じゃないかと落胆するに違いない。
福沢諭吉のもう一つの著書『福翁自伝』の中にこれに相当する例が挙げられている。一つは諭吉が鎌倉あたりで遊んだ時、道ですれ違った馬上の農民が士族であった諭吉を見て慌てて馬を下りたという。馬はもちろん農民自身のもの、農民の分際でお武家様の前で乗馬して申し訳ありません…とばかり馬を下りた農民を諭吉は咎めて、自分の馬に自分が乗って何が悪い、今は武士も農民もないのだから遠慮せずに乗っていけと言っても、恐縮してなかなか乗らなかったという。明治4年頃の話だそうだ。
もう一つはこれもやはり明治4年頃、有馬温泉を訪れて行き交う人々に道を尋ねた時、こちらが偉そうな態度で物を言うと相手は卑屈になって平身低頭せんばかりに丁寧な口調で答えてくれるが、逆に丁寧に礼を尽くして質問すると相手は横柄になって碌に物も教えてくれなかったという。これを何人にも試したが1人として例外はなかったそうだ。
相手が自分より上だと見れば謙虚に丁寧に卑屈にへりくだり、相手が自分より下だと思えば横柄に傲慢に振る舞う。水木しげるさんの妖怪漫画か何かで知った「見越し入道」という妖怪そっくり…(笑)。この妖怪は夜道を1人で歩いていると出現して、スーッと背丈が伸びていくので、それを見上げるとどんどん大きくなって後ろへ引っくり返ったところを殺されてしまう、この妖怪の対処法は「見越し入道 見越した」と唱えて上から見下ろすようにすると逆に小さくなってしまうらしい。
わざと不機嫌な表情を見せながら乱暴でぞんざいな言葉を使って相手を威嚇する、そうやって自分を偉そうに思わせて相手を支配しようとする見越し入道のような上司は今も日本全国にはびこっているようだ。明治初期に福沢諭吉に路傍で試された民衆たちの末裔というべきだろうが、2004年に樋口裕一さんという人が書かれた『頭がいい人、悪い人の話し方』(PHP新書)の中に、「自分を権威づけようとする」頭の悪い人のことがわざわざ1章設けて記載されている。
知的な人間ほど暴力的な言動に対してうまく対応できないものだから、それを利用してわざと最初に相手を怒鳴りつける無礼な人間がいる、最初に怒鳴ると相手は萎縮して黙って言うことを聞くようになり、さらにその後からなだめたりおだてたりすると相手は安心して慕ってくるようになるとのこと。
士農工商時代の武士のように、権威の力に頼って相手をコントロールしようとする輩は、福沢諭吉に言わせれば文明開化していない人間である。しかも武士ならばその身分は終生保証されていたわけであるし、戦前くらいまでならまだ元老とか華族とか言って死ぬまで大事にして貰えたかも知れないが、現代社会のしがない職場の上司風情が武士の真似をしてみても、地位を失って誰も自分の言うことを本当に聞いていたわけではないことを自覚する時がくるから、そうなる前に『学問のすすめ』とか『福翁自伝』とかお読みになることをお勧めする。
新幹線インシデントとカタストロフィー
東京オリンピックのあった1964年(昭和39年)の開業以来、事故らしい事故もなく営業運転を続けてきた新幹線で重大なインシデントがあったらしい。報道によれば、今年(2017年)12月11日、博多発東京行きのぞみ34号で、博多を発車した後から異臭や異音を感知し、岡山から乗り込んだ保守担当者が停車駅での点検を進言したが、列車はそのまま運転を続け、新大阪でJR西日本からJR東海への運行引き継ぎもおざなりにして、結局名古屋で車両点検したところ、13号車の台車に底面で16センチ、側面で14センチに及ぶ亀裂が見つかり、慌てて運転を中止したとのことである。
新幹線がこのまま走行すれば最悪の場合、名古屋~新横浜間で脱線転覆の可能性もあったという。ちょうどアメリカ合衆国のシアトル郊外でも12月18日、アムトラックの列車が脱線して陸橋から道路に転落する死傷事故も起こっており、もし新幹線が同様な事故を起こしていれば死傷者千名を超える大惨事になっていただろう。ジャンボジェット機の約3倍の乗客がシートベルトもせずに乗っているのだから、あの列車が時速200キロ超で線路から飛び出したらひとたまりもない。それに乗客だけでなく、線路際の住宅や高速道路などに突っ込んだら犠牲者がどのくらいになるか空恐ろしいものがある。
そういう大惨事と紙一重のところで運行している割に、異臭や異音の報告があってから3時間以上も運転を続けたことに対する衝撃が広がっている。またJR西日本か!とばかりマスコミの批判論調も一時はヒートアップしたが、あの時のような異常な取材が無かったのは、やっとマスコミも少しは自分の非に気付いたか。
マスコミの方は大人になってえげつない取材や報道を控えられるようになったが、少しのダイヤの遅れも許さずに現場に圧力を掛けるJR西日本の体質は、福知山線脱線事故以来ちっとも改善されていないという批判はたぶん当を得ているだろう。確かに秒単位の運行を誇る正確なダイヤが一種の世界的なブランドになってしまった日本の新幹線であるから、なるべく列車を停めたくない、列車を停めると会社の名誉に傷がつくというプレッシャーは現場を息苦しいものにしているだろう。しかし乗客乗員の安全あっての正確なダイヤであることを忘れてはいけない。
今回マスコミに掲載された批評の中で世論をミスリードする恐れのあったものが見受けられたので書きとめておく。それは新幹線の台車の亀裂が14センチ(側面)もあった、あと3センチで台車は吹っ飛んだ、まさに首の皮一枚で高速走行していた…という部分。
これをうっかり読み飛ばせば、今回のインシデントで台車の亀裂が見つかった時はすでに14センチにも達していた、ということは亀裂が5センチ、10センチとだんだん広がっていくのを日々の車両点検で見逃していたんではないかと考えた人も多かったのではないか?
もしそうだとすればまさに「たるんでる!」の一言だが、実際はおそらく博多駅を発車する直前に目視点検しても亀裂はほんの数ミリにも満たず、肉眼で発見することはできなかったのではないか。ああいう傷は長年かけて次第に材質が低下してきて、ある日突然バッと亀裂が開くものであろう。
もう30年以上も前になると思うが、『カタストロフィーの理論』というのが一世を風靡したことがあった。私は詳しく覚えてはいないが、カタストロフィー(破局)は目に見える同じような速さで進行するのではない。例えばポットの水を火に掛けると徐々に沸騰してくるのではなく、最初のうち水は肉眼的にはほとんど変化はなく、沸点に近づくにつれて急速に沸騰を始め、ある温度で突然吹きこぼれる…というのがカタストロフィー。
ハンドブレーキを引かずに緩斜面の坂道に停めた自動車も、最初はゆっくりゆっくり目に見えぬ速度で転がり始め、次第に加速してフットブレーキを踏んでもすぐには止まらぬスピードになってガードレールに激突する…のもカタストロフィー。友だちと仲違いするのも出会った最初の日から一定の割合で仲が悪くなっていくのではなくて、仲良く毎日暮らしながらも徐々に心に不満が溜まっていって耐えられなくなり、ある日突然絶交する…のもたぶんカタストロフィー。
新幹線の台車も新造時から何千キロ、何万キロと走行しているうちに、最初は材料の分子構造の緩みとして劣化が進んでいき、最後の運行日になって目に見える亀裂が突然入って台車が破壊される。だから始業時や終業時に一生懸命目視点検したって、今回のインシデントは防げなかっただろう。JR西日本の落ち度はあくまで異臭異音を無視して運転を強行したことである。
ある専門家が今回の新幹線台車の亀裂は典型的な金属疲労だとしてJR西日本の怠慢を責めていたが、ちょっとこの専門家も的外れで無責任ではないのか。典型的な金属疲労だというなら、同じ時期に納入された新幹線車両はすべて台車の亀裂を起こしうる危険な状態になっているということだろう。専門家としては、新幹線の車両も自動車の車検と同じような定期点検を施行して、台車やブレーキのような重要な部品は一定の走行キロ数ごとの交換を義務づけるよう提言するべきではなかったのか。
この専門家は、今回の台車の亀裂は“典型的な”金属疲労だと所見を述べた後に、何ですぐ列車を停めなかったのかと他の批評家と同じ結論にとどまった。今の日本、“専門家”と称する人間たちが本当に専門的な立場から意見を述べてくれていないのではないかと危惧した次第である。日本の諸事の“専門家”たちも徐々に劣化しているように見える。いずれどこかの分野でカタストロフィーが起こるかも知れない。
『不死身の特攻兵』
鴻上尚史さんという方が2017年に講談社現代新書で出版された『不死身の特攻兵』という本がある。副題が『軍神はなぜ上官に反抗したか』、さらに表紙には「死ななくてもいいと思います。死ぬまで何度でも行って、爆弾を命中させます」という主人公の言葉が表題と同じサイズの字体で書かれ、その下に小さく「1944年11月の第一回の特攻作戦から、9回の出撃。陸軍参謀に「必ず死んでこい!」と言われながら、命令に背き、生還を果たした特攻兵がいた。」と筆者の解説が記され、さらに裏表紙には『“いのち”を消費する日本型組織に立ち向かうには』という告発めいた文章もある。
私も神風特別攻撃隊については過去いろいろ書いてきたので、今さら新たに付け加えることもないのだが、この本の中に今も昔も変わらぬ日本という国家の正体を改めて垣間見る思いがする部分があったので、ご紹介しておきたい。憲法9条改正を支持する有権者も増え、中国や北朝鮮との一戦も辞さずという国民が多くなって、いずれ日本も戦争に巻き込まれる公算が高まったが、そうなった場合、国民がどのように取り扱われ、どのように後世に伝えられていくか、まざまざと見せつけてくれる内容である。
『不死身の特攻兵』は、陸軍最初の特攻隊だった万朶隊に選ばれて出撃し、そのたびに生還すること9回という佐々木友次伍長がいたことを知った鴻上さん(演出家・作家)が、まだ札幌で存命だった佐々木さんを訪ねてインタビューした内容をもとに執筆された本である。それも亡くなるまで数ヶ月という実にきわどいタイミングでインタビューできた貴重な証言でもある。
佐々木伍長は別に逃げ回って生き延びたわけではない。9回の出撃命令の中には離陸直前に敵襲を受けて飛び上がれなかったこともあるし、また離陸したうちの2回は敵艦船を爆撃し、しかも1回は命中させて撃沈している。陸軍はこれだけの技量を持ったパイロットをたった1度の体当たり攻撃で殺そうとしていたのだ。佐々木伍長は、別に体当たりしなくても敵艦船を撃沈すればいいと公言して憚らなくなり、その後も生還を繰り返した。腕利きのパイロットなら通常攻撃の最中に戦死するのは覚悟のうえ、1回だけの体当たりで死ぬのは御免だと誰もが思っていたという。
万朶隊は九九式双発軽爆撃機(九九双軽)という飛行機を特攻専用に改造した機体で編成された。パイロットが機内からは爆弾を落とせないように固定し、機首から長く突き出した信管が敵艦に触れた瞬間爆発するという非人道的な代物である。そういう非情な陸軍上層部への反発も現場指揮官や整備員の間にあって、これはいくら何でもひどいと思ったのだろう、自爆専用の九九双軽は命令違反も承知で、機内から爆弾を投下できるように密かに改造された。それが佐々木伍長が生き延びられた原因の1つ。
しかし何度も特攻隊として生還する佐々木伍長に業を煮やした参謀が、まるで見せしめの処刑としか思えない自殺同然の無謀な出撃を命じると、今度は護衛の戦闘機隊の隊員が佐々木伍長を死なすなとばかり反発して、敵艦隊上空まで達する前に適当に途中で反転し、佐々木伍長を基地に連れ戻してしまう。これも佐々木伍長が生き延びられた原因の1つ。
ここまで読んで、佐々木伍長は何で命令に従って立派に潔く散華しなかったのかと感じる日本人は今も多いであろう。特に自分は死なないで済む立場にあると思っている日本人に限れば、圧倒的多数がそう感じると思われる。日本という国家には、特攻のような非人道的な命令に従って従順な犠牲となるだけの崇高な価値があるのか。この本を読んで私が改めて憤激したのはこれから先である。
佐々木伍長がマラリアに冒されて入院していた昭和19年12月末、隣のベッドに出丸一男中尉もマラリアと下痢で入院していた。陸軍士官学校56期の正規陸軍士官で、靖国隊という特攻隊の指揮官だったが、2度の出撃とも不時着して帰ってきていた。名を問われて名乗った後、佐々木伍長が無理に死ぬことはないと言うと、出丸中尉も苦悩に満ちた表情で同意した。
ところがこの本によると12月31日、別の資料だと12月26日(佐々木伍長はマラリアの高熱で日付の記憶が曖昧という)、足音も荒々しく師団の参謀が入ってきた。
「出丸中尉どのはまだ動けませんよ」
と軍医が追いかけて止めるのも聞かず、参謀は出丸中尉の寝台の横に立ちはだかり、今から出撃せよと命令した。髭も伸びてやつれた出丸中尉が黙って仰向けに寝ていると、参謀はいきなりその胸元を掴んで引き起こし、すぐに飛行場へ行けと言った。
「よし、死んでやるぞ!」
泣くような必死の声で叫んだ出丸中尉は飛行服に着替えると、力の入らない足で部屋を出て行った。しばらくして飛行場から隼戦闘機がただ1機、護衛の戦闘機もなく、編隊を組む僚機もなく、まっすぐ離陸して行った。これは特攻飛行ではなく、処刑飛行だと佐々木伍長は思ったそうだ。
以上が『不死身の特攻兵』に書いてある事の顛末であるが、不条理な話はここからである。私の手元に『特別攻撃隊の記録〈陸軍編〉』という2005年に光人社から出版された本がある。著者の押尾一彦氏は日大農獣医学部を出て特に太平洋戦争関係の航空史を研究しているという異色の経歴の方だが、100人以上の方々から提供を受けた写真や資料を丹念にまとめて、陸軍航空史研究の集大成と銘打って出版されている。この本、というより資料集の中に出丸中尉の八紘第三隊
靖国隊のことも書いてある。
ざっと追っていくと、11月9日に立川航空廠で隼戦闘機を受領後、19日にフィリピンのルソン島に進出、11月20日にマニラで靖国隊と命名、21日にネグロス島に前進待機、11月24日の18時に夜間飛行可能な出丸隊長以下3機が出撃したが、部下の1機だけが大型艦船に突入して炎上させた。ついで26日には出丸隊長ともう1機がレイテ湾に突入、29日には6機がレイテ湾に突入、12月7日に最後の1機が単機オルモック湾に突入して靖国隊は消滅した、と書いてある。日付の表記だけは正確に書き写したが、11月とは書いていないものの、この記載の順番に従えば、出丸中尉は11月26日に戦死したことになっている。これはどういうことか。佐々木伍長のインタビューでは、出丸中尉は12月も押し迫ってから単機出撃させられたのではなかったか。
現在92歳になられておられた佐々木伍長に、マラリアの高熱に冒されていた時点の正確な記憶を思い出して貰う方が無理だ、佐々木伍長の思い違いに決まっているという方が大多数であろう。ところが『特別攻撃隊の記録〈陸軍編〉』の巻末には、膨大な陸軍特別攻撃隊員の名簿が資料として掲載してあって、八紘第三隊 靖国隊(一式戦)の項目には、出丸中尉を除く9名が12月7日までに特攻戦死したことになっており、さらに出丸中尉は12月26日にミンドロ島付近で戦死したとある。佐々木伍長の証言を裏付ける記載である。
しかも12月7日に靖国隊が消滅したとの記載のある本文中には、出丸中尉が隼戦闘機をバックに写った写真が掲載されており、写真説明の略歴の最後に「12月26日、レイテ湾の敵大型艦船に突入して散華」と書かれている。ミンドロ島とレイテ湾は直線距離で500~600キロはある。これはいったいどういうことなのか。しかも佐々木伍長の記憶によれば、出丸中尉は単機離陸したのである。大型艦船に突入などという戦果を誰が見届けたのか。佐々木伍長の証言を待つまでもなく、出丸中尉出撃に関する記述は破綻しているのである。本文と写真説明と巻末資料が3つとも違うことを書いているのだから…。
日本はこういう国なのだということを改めて嘆かわしく思う。国の命令を受け、しかも尋常ならざる作戦で戦死した1人の人間の最期が極端な欺瞞と粉飾にまみれたまま、歴史の集大成として公刊される国。特攻隊員に生き残られては命令した上層部の世間体が悪くなる、そんな時に上層部の方を守る国、それが日本なのか。フィリピン戦が終熄して飛行機も無くなった佐々木伍長たちはフィリピンの山中に身を隠して飢えと闘いながら自給していたが、特攻隊員に生き残られては困る司令部から佐々木伍長を射殺する命令も出ていたという。それが日本なのか。
下の人間よりも上のメンツを守る国、子より親、部下より上司、学生より教員、国民より政治家のメンツが大切に守られ、下の者は口を閉ざして年月を送る、今後もし中国や北朝鮮と戦争するつもりならば、二度と同じようなことを起こしてはならないし、震災や水害、原発事故や航空機事故の犠牲者や遺族が口を閉ざさざるを得ないような、立場の弱い者を肥料にして上層部が肥え太るような国の在り方は改めなければいけない。
なまけ者の知恵
かつて高校時代に読んだショートショートストーリーでこんなのがありました。タイトルも作者も忘れてしまいましたが、たぶんこういう発想は星新一さんか筒井康隆さんだと思います。失念してしまって申し訳ありません。
昔々人間が身を粉にして働かなければ生きていけなかった時代、食物は自給自足、それで足りない分は隣村へ行って物々交換しなければ手に入らない。ところがある村にとんでもない怠け者がいて、何とか働かずに必需品を手に入れようと知恵を絞った。それで身近に落ちていた石を拾って器用に丸い形に磨き上げ、それを持って隣村を訪れた。その怠け者は穀物を作っていた隣村の男に、その丸い石と穀物を交換するよう要求したが、もちろん男は疑心暗鬼、ところが怠け者が男に向かって言うには、お前はまだ何にも知らないのか、今ではどこの村でも物々交換で品物を持ち歩くのが大変だから、こういう丸い石で代用することが流行しているんだぜ、この丸い石を持って行けば、大抵どこの村でも欲しい物と交換してくれるはずだ、もし交換してくれなければ俺が今お前に説明したことを教えてやればいい。怠け者の弁舌にコロリと騙された男は、その丸い石と引き換えに自分が収穫した穀物をわけてやった。怠け者は味をしめ、それからは石を磨き上げるだけで、労せずしてあっちの村、こっちの村から必要な物を手に入れて回りましたとさ、めでたし、めでたし…ではなくて、今ではその丸い石はお金という物に姿を変えて、世界中の人たちを騙し続けているのです。
何だか遠い昔に読んだショートショートストーリーを思い出させるような事件が起こって、思わず笑ってしまいました。ビットコインとか呼ばれるコンピューター上の仮想の通貨を取り引きする会社組織があって、その中の1つである『コインチェック』という会社から今年(2018年)の1月26日、580億円相当の仮想通貨が流出、匿名サイトを通じてどうやらロシアあたりで売買されてしまっているらしいという事件です。580億円ですよ、昭和43年に起こった三億円強奪事件の180倍以上の被害額ですよ。いくら貨幣価値が当時とは比べ物にならないと言っても580億円ですよ。あの時の3億円は現ナマだったけど、今度のは仮想なんだろと言っても580億円ですよ。そんな金が被害にあった割には、今回は国民の皆さんはずいぶん冷静じゃありませんか。事件後まだ1ヶ月も経っていないというのに、もう平昌冬期オリンピックの男子フィギュアスケート羽生結弦選手の金メダルにしか目が向いていないですよね。
私も仮想通貨には興味はなかったし、コインチェックという会社の通貨管理体制に問題があったという最大の突っ込みどころに食いつく気もありません。政府や銀行などという強大な権威を持った機関の介入なしに、パソコンやスマホの端末を介してユーザー同士が価値を決めていく仮想通貨のシステム自体に、私は石を磨いてあちこちの村から品物を手に入れたあの痛快な稀代の怠け者の影を見る思いが残るだけです。
お金というものは正当な労働の対価として手に入れるべきものである、そういう観念に囚われている私は古風な人間なのかも知れませんが、1ヶ月もしないうちにあの事件が忘れられてしまう現状は、やはり日本国民の大多数が同じように考えている証拠ではないのでしょうか。事件後も相変わらず仮想通貨への投資が減らないとも伝えられていますが、世の人々はそれで大儲けして楽をしようとかいうつもりはなくて、競馬やパチンコのような単なるゲーム感覚でお小遣い稼ぎを楽しんでいるだけでしょう。
何の裏付けもないように見える仮想通貨などは多くの日本人にとってその程度のものだから、何百億円盗まれようが、事件は羽生結弦選手の金メダル1つに雲散霧消してしまう。お金というものは裏付けになる実体が伴ってこそ価値が保証されるという固定観念に縛られているのでしょうが、ここらでちょっと考えてみましょう。
昔は通貨の裏付けとして金塊(gold)を担保にする金本位制で世界経済は動いていたものですが、通貨の流通量を担保するには金塊量が十分ではなくなったので、20世紀後半頃までに各国の中央銀行が通貨発行量を規制する管理通貨制度に移行した、しかしその後コンピューター化の時代を迎えて電子媒体上にある通貨の量は無制限に増え始めた。そもそも私たちの世代が社会に出て働き始めた頃は、毎月の給料やボーナスは袋詰めされた現金で支給されたものです。給料日や、特にボーナス支給日は本当に嬉しかったですね。
ところが例の三億円事件は社員に手渡すボーナスを運ぶ現金輸送車が襲われたことなどもあり、次第に現金を扱う機会がどんどん減っていって、今では銀行振り込みになってしまいましたが、私たちはあの給与明細書とかいうペラペラの紙1枚に印字された数字を有り難がっています。しかしよく考えてみれば、あんな紙切れ1枚に書かれた金額、金塊どころか紙幣の裏付けさえないわけですね。それでも国家から家庭に至るまで我々の経済は支障なく動いています。
この延長線上に仮想通貨があると考えるととても恐ろしい。現行通貨は国家や銀行の後ろ盾があるから辛うじて信用とメンツを保っているものの、その国家や銀行の能力やモラルに対する信頼が薄れていけば、ユーザー間のパソコン端末同士で取り引きされる仮想通貨が取って代わるのは時間の問題です。お金は正当な労働の対価として頂くべきだなどとバカ正直なお念仏を唱えている人間が食い物にされる時代の予兆を感じます。
ここは歴史独り旅の第13巻です 第12巻に戻る 第14巻に進む
 トップページに戻る 歴史独り旅の目次に戻る
トップページに戻る 歴史独り旅の目次に戻る